日本書記 斉明天皇四年(658年)秋田と能代の話が出て来る。
この年、阿倍比羅夫が
船軍百八十艘を率いて蝦夷を討った。秋田・能代二郡の蝦夷は、遠くから眺めただけで降伏を乞うた。そこで軍を整え、船を齶田浦(秋田湾)につらねた。秋田の蝦夷の恩荷は、進み出て誓っていった。「官軍と戦うために、弓矢をもっているのではありません。ただ手前どもは肉食の習慣がありますので、弓矢を持っています。もし官軍に対して弓矢を用いたら、秋田浦の神がおとがめになるでしょう。清く明らかな心をもって、帝にお仕え致します」と。恩荷に小乙上の位を授け、能代・津軽二郡の郡領に定められた。有間の浜に渡嶋の蝦夷どもを召し集めて、大いに饗応して帰らせられた。
とある。その後三か月後には
蝦夷が二百人あまり、朝廷に参上し物をたてまつった。常にも増して饗応され、種々の物を与えられた。柵養の蝦夷二人に、冠位一階を授けられた。渟代郡(能代郡)の大領沙尼具那に小乙下、少領宇婆佐には建武、勇壮な者二人に位一階、特に沙尼具那らに蛸旗(旗の頭が蛸に似ている)二十頭・鼓二箇・弓矢二具・鎧二領を賜った。別に馬武らに蛸旗二十頭・鼓二箇・弓矢二具・鎧二領を賜った。都岐沙羅の柵造には位二階を授けられた。判官には位一階、渟足の柵造大伴君稲積には小乙下を授けられた。渟代郡の大領沙尼具那に詔して、蝦夷の戸口と捕虜の戸口を調査させた。
とある。
縄文の生活様式の蝦夷たちのとって、弓矢は食料確保の手段で鳥獣に向けて射つもの、「官軍(人間)に対して弓矢を用いたら地に住み神がとがめる」といっているように、縄文ではない考えをもつ人たちは理解しがたいのではなかったか?
百八十艘の船も、何してんだろうなとか思っているうちに集められ饗応されて、争わずによかったのかもしれない。三か月後に渟代郡(能代)の皆さんが位を賜ったようなので、良かったのでしょう。
しかし、蛸旗とか、鎧とか、鼓とかもらって、ありがたみがあったんだろうか、狩猟生活をしてたら必要ないものばかり
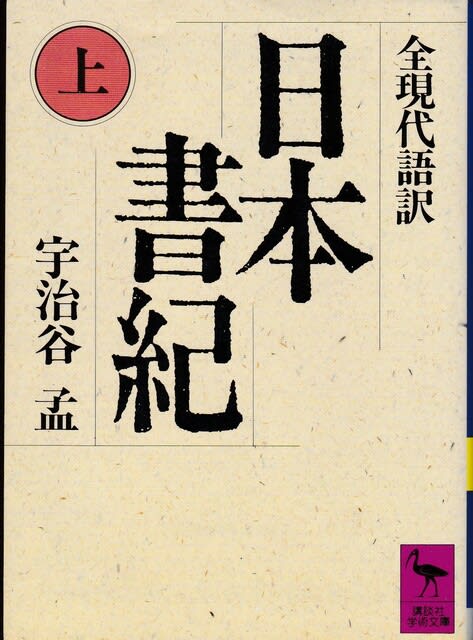
この年、阿倍比羅夫が
船軍百八十艘を率いて蝦夷を討った。秋田・能代二郡の蝦夷は、遠くから眺めただけで降伏を乞うた。そこで軍を整え、船を齶田浦(秋田湾)につらねた。秋田の蝦夷の恩荷は、進み出て誓っていった。「官軍と戦うために、弓矢をもっているのではありません。ただ手前どもは肉食の習慣がありますので、弓矢を持っています。もし官軍に対して弓矢を用いたら、秋田浦の神がおとがめになるでしょう。清く明らかな心をもって、帝にお仕え致します」と。恩荷に小乙上の位を授け、能代・津軽二郡の郡領に定められた。有間の浜に渡嶋の蝦夷どもを召し集めて、大いに饗応して帰らせられた。
とある。その後三か月後には
蝦夷が二百人あまり、朝廷に参上し物をたてまつった。常にも増して饗応され、種々の物を与えられた。柵養の蝦夷二人に、冠位一階を授けられた。渟代郡(能代郡)の大領沙尼具那に小乙下、少領宇婆佐には建武、勇壮な者二人に位一階、特に沙尼具那らに蛸旗(旗の頭が蛸に似ている)二十頭・鼓二箇・弓矢二具・鎧二領を賜った。別に馬武らに蛸旗二十頭・鼓二箇・弓矢二具・鎧二領を賜った。都岐沙羅の柵造には位二階を授けられた。判官には位一階、渟足の柵造大伴君稲積には小乙下を授けられた。渟代郡の大領沙尼具那に詔して、蝦夷の戸口と捕虜の戸口を調査させた。
とある。
縄文の生活様式の蝦夷たちのとって、弓矢は食料確保の手段で鳥獣に向けて射つもの、「官軍(人間)に対して弓矢を用いたら地に住み神がとがめる」といっているように、縄文ではない考えをもつ人たちは理解しがたいのではなかったか?
百八十艘の船も、何してんだろうなとか思っているうちに集められ饗応されて、争わずによかったのかもしれない。三か月後に渟代郡(能代)の皆さんが位を賜ったようなので、良かったのでしょう。
しかし、蛸旗とか、鎧とか、鼓とかもらって、ありがたみがあったんだろうか、狩猟生活をしてたら必要ないものばかり
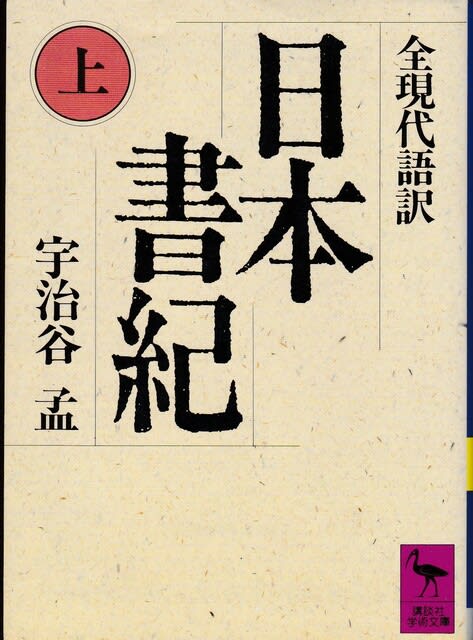




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます