A.エリクソンのアイデンティティ
そういえば昔、ぼくは山から落ちて骨を折り、半年ほど入院していた20歳の頃、病院で時間だけはたっぷりあったのでいろんな本を読んだなかに、エリク・H・エリクソンの“Identity”の出たばかりの邦訳『主体性』(岩瀬庸理訳)があった。ぼくがベッドでそれを読んでいると、回診にきた東大出の若い医者が、ほう・とぼくの本の表紙を見てこう言ったことを思い出した。「主体性?アイデンティティは「主体性」というのとちょっと違うな」それは確かに当っていた。まだアイデンティティという言葉が日本では定着していなかったころのことだ。まもなく「自己同一性」という訳語が使われて、しだいにエリクソンという名前も定着していったと思う。
エリクソン(Erik Homburger Erikson, 1902年6月15日 - 1994年5月12日)は、オーストリアからアメリカ合衆国に渡った発達心理学者で、精神分析家。「アイデンティティ」の概念ほか、社会心理的な説明理論を提唱し、米国で最も影響力のあった精神分析家の一人とされる。エリクソンはウィーンでフロイトの娘アンナから精神分析の手ほどきを受け、ウィーン精神分析研究所の分析家の資格を取得する(当時のウィーン精神分析所で取得した資格は、同時に国際資格になる制度であった)。その後、エリクソンはウィーンでカナダ人の舞踏家、ジョアン・セルソンと知り合い結婚することになる。
「ハルトマンとエリク・H・エリクソンの経歴を比べてみる場合、人はたいていそのいくつかの対照的な点から出発しないわけにはいかない。ただ一度大きな場面の変化があっただけで平静な秩序正しい生活を送ったハルトマンに対し、しばしば移動し冒険趣味のあったエリクソンの生活、また、自分の地位と才能に確信を抱いている前者の自己末梢的態度に対し、内気な振舞と目ざましい振舞との奇妙な交代にあらわれる地位・才能いずれにも長く不安につきまとわれていた後者の対比。若い頃のハルトマンにおいてすでに将来の精神分析運動の指導者を見分けることは可能であったが、エリクソンの場合、背の高い頑健な若い「ヴァイキング」はただ漸次変貌をとげて、文字通りカリスマを発揮し「聖者の役割」をも期待させる白髪の威厳ある人物となっていったのである。一方は同年輩の協力者たちと緊密に難なく仕事をしてプライヴァシーを守ったが、他方の尋常ならぬ人生航路はかれを同年輩の仲間たちから切り離して、公共の舞台へ、若い人びととの師弟関係に赴かせることになった。ハルトマンの影響はそれと気づかれぬような仕方で精神分析の理論と実際に充満し変形させていったが、エリクソンの仕事は運動の周辺部にとどまっていたのが突然、大方は予期しないような仕方で礼賛の中心となったのである。
ハルトマンよりはわずか八歳しか年下でないのだが、エリクソンは半世代もあとの人のように見えた。かれはその最初の重要な論文を公刊するのに四〇歳まで待っていた。かれの生涯のヨーロッパ時代は、ふりかえってみると準備期間であった。かれの成熟時代はすべてアメリカという舞台で過ごされたのである。のみならず、エリクソンのもっとも活溌な活動はハルトマンが自分の理論的体系に仕上げをしたちょうどその時にはじめられている。それゆえ、それぞれの著作における言及が若いエリクソンの方により多く見られることは当然のことである。ハルトマンはエリクソンについては行きずりに書きとめているにすぎない。エリクソンはアンナ・フロイトに第一に多くを負うていることを認めているが、ともに自我心理学の創始者たるハルトマンに何を負うているかを詳細に記述しようと試みている。1956年のフロイト生誕100年祭の講演ではかれは「環境の精神分析理論への橋」をつくり上げたことをハルトマンの功に帰し、対応する線に沿うてのかれ自身の経験的研究は「理論的に展開されていない」と特徴づけていた。12年後、講演やあれこれの論文を集めた第二巻を刊行したときには、エリクソンは自分とハルトマンがなにを共有しているかをもっとはっきりと書く準備がようやくにして整ったと感じた。ほとんどもっぱら臨床的、歴史的ないし論証的な文章の中にあっては珍しいのだが、「理論的間奏曲」という一文においてかれは、「自我(エゴ)」という専門用語は自己性(セルフフッド)という意味から明確に区別されねばならぬとするハルトマンの主張に同調している。この自己(セルフ)――もっとふつうには自己(アイデンティティ)同一性――への力説こそ、エリクソンが四半世紀にわたって表現しようと努めてきたものの核心であった。
1902年の誕生の日からエリクソンの生活はまことに非常套的な形で展開されてきた。かれの名前そのものがかれの出自の混淆、複雑な家族関係を明示している。デンマーク人の両親から生まれたかれは「バーデン州カールスルーエで小児科医テーオドル・ホンブルガー博士の息子として育てられた」。ホンブルガー博士と妻はその子のために善かれと願って、「母親が以前に結婚したことがあり」、実際にはかれはかれの生れる前に「その母親を棄てたデンマーク人の息子」であるという事実を秘密にしておいた。しかも、この国籍と父親の混乱だけではまだ足りないかのように、かれはさらに宗教上の同定という問題と闘わねばならなかった。「ブロンドで青い目の」若いエリクはその「義理の父の教会堂」で「“ゴイ”というニックネームをつけられた」。学校の仲間たちにとっては彼は「ユダヤ人であった」。
もちろん、結局はその少年は真実を見出すことになる。けれども、その結果は義理の父に対する明瞭な敵対ということにはならなかった。かれはこの義父の明らかにユダヤ的な名前を「感謝の念から……しかもまた逃避と見られることを避けるために」かれ自身のミドル・ネームとして残している。そしてかれは「医学校に行かずに近づけるだけ近く子供たちの医者という役割に接近した」。そうすることによってかれは、「小児科医たる義父」との「アンビヴァレントな同一化」と呼んだものと「かれ自身の神話的な父親」を「探すこと」とを「混合」したのである。しかし、この内的緊張の解消は、何年ものちにかれを「ほんとうに驚かしたフロイト・サークルによる採用」が精神分析の「当時すでに神話的な創始者」であったフロイトにおいて代理の父を与え、一方義理の息子という地位が不利であると同時に有利でもあることをかれに知らしめるにいたったときまで、あらわれはしなかった。それは、かれが自分の「まったく属していないところで受け入れられる」ことを「当然のことと考え」させ、「既成の諸領域の間で」またかれが「通常の信任状など持ちあわせてはいない制度的文脈のなかで」働くことへの確信を与えたのである。
そもそものはじめから、かれの母親と義理の父はかれに自分の道を「急がずに」見出させるという「辛抱強さ」をもっていた。かれらは大学で勉強することをやめて「放浪の芸術家となるべく……出発する」というかれの決心に反対しなかった。このようにして豊かな個人的経験を通じて、かれはのちにかれのキー概念となるものの一つ――人生の仕事にとりかかる前にくる社会的・情緒的「モラトリアム」――に出くわしてのである。この自由で「ロマンティック」な七年の生活ののちに、とうとうかれは心にかなった定職を見出した。かれはウィーンの小さな実験学校の教師として契約したのである。そしてここで幸運にもかれはアンナ・フロイトに出会った。彼女の精神分析による幼児の研究はまだ当時手をつけられたばかりであった。この精神分析創始者の娘による教育分析をこのあと受け、ハルトマンその人のごとき輝かしい新進の学者たちによる臨床上の正式の訓練もともに行われた。エリクソンは進むべき道も定かではない若者として1927年にウィーンに来たのだが、1933年にウィーンを去るときにはもう十分に羽の生えそろった素人分析家となっており、すでに結婚もして二人の小さな息子をもうけ、他の人びとの子供たちについての豊富な観察を蓄えていたのである。
このオーストリアの首都をかれが去ったのは、フロイト一家やハルトマンの場合のようにナチの占領によって追い出されたというわけではない。その五年前にかれは自分の意志でウィーン去ったのである。「……複雑な諸条件のもとで……強烈な訓練を受けた……のちに、別のところへ行って独立に働こうという考えが……心をはずましてくれるもの……のように思われた。」エリクソンは明らかに、創始者の継承者たちがすでに進んだ地位を要求している、精神分析の才能のうようよしているウィーンでは、かれのような非理論的精神の持主は囲い込まれてしまった感じを抱くことになるだろうと考えたのである。最初に、ごく短期間、かれは母国のデンマークで自立しようと試みた。次いで、こんどは決定的に、アメリカ合衆国へと移住した。かれの妻がアメリカ生まれであったことによって、また幼児分析は新しい分野で、行くところどこででも関心を喚起しえたという事実によって、そのアメリカ移住はスムーズに行われた。1934年から35年までかれはハーヴァードの医学校に、つづく三年間はイェールにいた。フロイトが死に第二次世界大戦が勃発した年に、かれはもう一度、こんどはバークリーのカリフォルニア大学に移った。ここでかれはその生涯の決定的な10年間を過ごすことになる。
実際エリクソンのアメリカ在住の主要段階はきっちり10年ずつに分けられる。1940年代はカリフォルニア、1950年代はバークシャー、1960年代はハーヴァードである。それぞれの時期に特徴的な性格と焦点があった。けれども、終始かわらずかれの臨床的な仕事と著作の根拠地は幼児の研究にあった。幼児の遊びのうちに(ヴィトゲンシュタインと同様に!)かれはフロイトが夢の世界に発見した理解への王道を見出したのである。エリクソンは子供のことを話すときにはいつもいちばん説得的であった。そこから遠く離れていけばいくほど、かれの思想は動揺し不明確になっていった。
エリクソンのカリフォルニア――といってもサンフランシスコ湾であって、多くのドイツ語を喋る亡命者たちが集まることになったロサンジェルス地域ではない――への移住は、もしもかれが東部に留まっていたら得られなかったような、アメリカ人の生活へのある感じを与えることになった。ハルトマンがコスモポリタン的な、ヨーロッパ志向的ニューヨークに移住したのとは異なり、エリクソンの西部行きの決心はかれら両人が育った文化的伝統からはるかに明確な断絶をもたらすことになる。ほとんどその土地で生まれた人たちとばかり付き合っていてエリクソンは、そこに「成年者の一風変った青年期スタイル」が認められる国民というものに関心をそそられた。手探り的に注意深くかれはアメリカの「国民性」を研究しはじめた。同時に、これはまた別の幸運なめぐり会いによって、かれは二つのまったく違った種族のアメリカ・インディアンの慣習と信仰とをじかに観察する機会に恵まれた。かれがまだイェールにいたとき、一人の人類学者の友人に南ダコタのシウ族保護地域に連れていかれたことがあった。またバークリーではアメリカ人類学の先達であるアルフレッド・L・クローバーに出会い、この人が北カリフォルニア海岸のユロク族へと案内してくれたのである。この点でもハルトマンとは対照的に、「エリクソンはまず精神分析と人類学あるいは歴史との概念的関係について考えめぐらすということをしなかった。その代わりにかれは特殊的なさまざまな環境下に生活している特殊な人びとの直接の観察……をあれこれ行ったのであった」。
1940年代のはじめに、アメリカ合衆国の土着民ならびに白人たちに関するエリクソンの暫定的な結論は一連の論文や草稿として形をとりはじめ、これがごくゆっくりと一冊の本にまで展開されていく。この本にはまた、かれが一般に注目されることになった最初の論文――1942年、戦争の高潮期に発表された「ヒトラーの心像とドイツの青年」――の改訂も含まれることになった。ハルトマンの共同研究者であるルドルフ・M・レーヴェンシュタインはその論文を「ユニークで記憶さるべき寄与」と呼んでいる。四年後、エリクソンは偶発的な形で論文を発表するのを止めた。一週間に一日必ず臨床研究や私的な業務を休んで、腰を据えてその本の完成に務めたのである。これが1950年に『幼児期と社会』Childhood and Societyとして世に出された。
構成はいかにも組織立ってはいないが、この『幼児期と社会』は実際には一見そう思われる以上に野心的な労作であった。諸事例の記述的研究にはじまるその本はシウ族、ユロク族をへて自我とアイデンティティに関する著者の中心的考察に進み、最後に現代アメリカおよびヒトラーの幼年期にまで及ぶ。しかしながら、このルースな試論タイプの構成の背後にはしっかりとしたドラマティックな意図が秘められている。エリクソンはこう説明する――かれの確信するところによれば、精神分析の方法は「本質的に歴史的な方法」であり、「人類の歴史」は「個々人のライフ・サイクルの巨大な物質代謝」である。したがって、かれの目標は「自我と社会との関係についての精神分析の書物」を書くことにある。これは、ハルトマンがこのような規模で、またこのように豊かな臨床的詳細さで企てることのなかったものである。」スチュアート・ヒューズ『大変貌 社会思想の大移動 1930-1965』荒川幾男・生松敬三訳、みすず書房、1978.pp.165-168.
ドイツ語圏からアメリカ合衆国に移住したユダヤ系知識人のうちでも、エリク・H・エリクソンはもっとも成功と名誉をかち得た人だったろう。かれの経歴はとてもユニークというか、波乱に満ちた人生で、いわゆるアカデミックな常識人とは一味も二味も違う人物だった。人間の運命の偶然性はまことに予測を超えたものだと感じるが、エリクソンの場合、生まれつきのコスモポリタンだったことと、おのれに与えられた自由を生かすすべを心得ていたといえる。

B.人工知能の社会的進化
新井紀子という人のことをぼくはこれまで知らなかったが、数学(数理論理学)というしごく抽象的かつ観念的な仕事をしながら、それが現代のヴィヴィッドな問題に直結していることを分かっている優秀な頭脳らしいと、初めて知ってなかなか面白い人だと思う。フランス・パリに呼ばれて大統領の前で「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトについて講演したという。「東大に入る」という日本的文脈はともかく、AIの最先端をぼくたちに理解できる形で説くのは、有意義である。
「仏のAI立国宣言 何のための人工知能か 日本も示せ:新井紀子のメディア私評
日本ではほとんど報じられていないが、人工知能(AI)分野で、地政学的な変化がおきようとしている。フランスの動向だ。マクロン大統領は3月末、世界中からAI分野の有識者を招き意見交換会とシンポジウムを開催。フランスを「AI立国」とすると宣言した。2022年までに15億ユーロをAI分野に投資し、規制緩和を進める。
招待された中には、フェイスブックのAI研究を統括するヤン・ルカンやアルファ碁の開発者として名高いディープマインド(DM)社のデミス・ハサビスらが含まれた。DMは今回パリに研究拠点を置くことを決めた。
これだけ読むと、「フランスもついに重い腰を上げたか」という感想を持つ読者も少なくないだろう。ドイツは早々に「インダストリー4.0」を開始した。ビッグデータやAIを活用することで製造業の革新を目指す国家プロジェクトだ。日本でも各省が競ってAI関連のプロジェクトに着手。それでも、米国や中国との距離は縮まるどころかますます水をあけられている。いまさらフランスが参入しても手遅れなのでは、と私も思っていた。
◎ ◎ ◎
ところが、である。意見交換会が開かれるエリゼ宮に到着して驚いた。出席者の約半数が女性。女性研究者は1割程度と言われるAIの会合では極めて異例だ。そこには、「破壊兵器としての数学 ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」の著者キャシー・オニールや、データの匿名化に精通したハーバード大学のラタニア・スウィーニーが含まれていた。マクロン大統領はこう言った。「AIの影響を受ける人々は『私』のような人(白人男性で40代)だけではない。すべての人だ。AIがどうあるべきかの議論には多様性が不可欠だ」と。
大統領から求められ、「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトを始めた意図を話した。「人々に広告をクリックさせるために」様々なサービスを無償で提供しているグーグルやフェイスブックのような巨大IT産業が、今回のAIブームを牽引することは2010年の段階で明らかだった。だが、日本はモノづくりの国である。99%の精度を、「100のうち99回正しい」ではなく「100に1回間違える」と認識すべき国だ。無償サービスの効率化のために開発された技術を、モノづくりに本格的に取り入れるべきか吟味すべきだ。AIの限界を探り、労働市場への影響を正確に見積もる必要があった、と。大統領は自ら詳しくメモを取りながら耳を傾けてくれた。
一方、「新技術が登場する時には心配する人は必ずいる。電話やテレビが登場した時もそうだが、何の問題もなかった。AIも同じだ」と楽観論を展開するヤン・ルカンに、大統領は厳しく指摘した。「これまでの技術は国民国家という枠の中で管理できた。AIとビッグデータは違う。圧倒的な寡占状況があり、富の再分配が行われていない。フランスが育成した有能な人材がシリコンバレーに流出しても、フランスに税金は支払われない」と。
◎ ◎ ◎
アメリカと中国でブームになると、日本は慌ててAIに手を出した。だが、「何のため」かはっきりしない。夏目漱石そっくりのロボットを作ってみたり、小説を書かせてみたり、よく言えば百花繚乱、悪く言えば迷走気味である。メディアも、AIと聞けば何でも飛びつく状況だ。フランスは違う。AIというグローバルゲームのルールを変えるために乗り出してきたのだ。
最後発のフランスにルールを変えられるのか。大統領のAIアドバイザーを務めるのは数学者のセドリック・ビラニだ。法学者や哲学者も連携して、アルゴリズムによる判断によって引き起こされ得る深刻な人権侵害、AIの誤認識による自己の責任の所在、世界中から最高の頭脳を吸引するシリコンバレーの「教育ただ乗り」問題を鋭く指摘。巨大なIT企業の急所を握る。そして、「データとアルゴリズムの透明性と正当な利用のための共有」という錦の御旗を掲げながら、同時に投資を呼び込む作戦だ。最初の一手は、5月に施行されるEU一般データ保護規則になることだろう。
ヨーロッパでは哲学も倫理学も黴の生えた教養ではない。自らが望む民主主義と資本主義のルールを通すための現役バリバリの武器なのである。
振り返って、我が国はどうか。「人間の研究者が『人工知能カント』に向かっていろいろ質問をして、その答えを分析することがカント研究者の仕事になるとわたしは予想する」(「AIは哲学できるか」森岡正博寄稿、本紙1月22日)。
これでは、日本の哲学者の仕事は風前の灯と言わざるを得ない。(敬称略)」朝日新聞2018年4月18日朝刊、17面オピニオン欄。
新井紀子さん:1962年生まれ。国立情報学研究所教授(数理論理学、人工知能)。近著に「AIvs.教科書が読めない子どもたち」。
日本の大手メディアだけでなく、政官財を含む大方の「お偉いさん」な人びとの、AIとビッグデータに関する理解はきわめて皮相で軽薄なレベルではないかと、ぼくはつねづね思っている。そうなってしまうのは、結局むかしの経済成長神話をいまだに信じ込んでいる冷戦ガラパゴス感覚と、新しい技術がややこしい課題すべてを解決してくれるという根拠薄弱な願望に捉われて、物事が見えなくなっているのだと思う。いまやAI、ロボット、ビッグデータは、行き詰った世界の救世主として期待を集めているのだが、これが人類の未来にとってほんとうに幸福な可能性を拓くかどうかは、人工知能にではなく人間の教養・叡智にかかっている、ということをフランス大統領は理解しているが、日本の首相はそんなことを考えたこともないのだろう。
そういえば昔、ぼくは山から落ちて骨を折り、半年ほど入院していた20歳の頃、病院で時間だけはたっぷりあったのでいろんな本を読んだなかに、エリク・H・エリクソンの“Identity”の出たばかりの邦訳『主体性』(岩瀬庸理訳)があった。ぼくがベッドでそれを読んでいると、回診にきた東大出の若い医者が、ほう・とぼくの本の表紙を見てこう言ったことを思い出した。「主体性?アイデンティティは「主体性」というのとちょっと違うな」それは確かに当っていた。まだアイデンティティという言葉が日本では定着していなかったころのことだ。まもなく「自己同一性」という訳語が使われて、しだいにエリクソンという名前も定着していったと思う。
エリクソン(Erik Homburger Erikson, 1902年6月15日 - 1994年5月12日)は、オーストリアからアメリカ合衆国に渡った発達心理学者で、精神分析家。「アイデンティティ」の概念ほか、社会心理的な説明理論を提唱し、米国で最も影響力のあった精神分析家の一人とされる。エリクソンはウィーンでフロイトの娘アンナから精神分析の手ほどきを受け、ウィーン精神分析研究所の分析家の資格を取得する(当時のウィーン精神分析所で取得した資格は、同時に国際資格になる制度であった)。その後、エリクソンはウィーンでカナダ人の舞踏家、ジョアン・セルソンと知り合い結婚することになる。
「ハルトマンとエリク・H・エリクソンの経歴を比べてみる場合、人はたいていそのいくつかの対照的な点から出発しないわけにはいかない。ただ一度大きな場面の変化があっただけで平静な秩序正しい生活を送ったハルトマンに対し、しばしば移動し冒険趣味のあったエリクソンの生活、また、自分の地位と才能に確信を抱いている前者の自己末梢的態度に対し、内気な振舞と目ざましい振舞との奇妙な交代にあらわれる地位・才能いずれにも長く不安につきまとわれていた後者の対比。若い頃のハルトマンにおいてすでに将来の精神分析運動の指導者を見分けることは可能であったが、エリクソンの場合、背の高い頑健な若い「ヴァイキング」はただ漸次変貌をとげて、文字通りカリスマを発揮し「聖者の役割」をも期待させる白髪の威厳ある人物となっていったのである。一方は同年輩の協力者たちと緊密に難なく仕事をしてプライヴァシーを守ったが、他方の尋常ならぬ人生航路はかれを同年輩の仲間たちから切り離して、公共の舞台へ、若い人びととの師弟関係に赴かせることになった。ハルトマンの影響はそれと気づかれぬような仕方で精神分析の理論と実際に充満し変形させていったが、エリクソンの仕事は運動の周辺部にとどまっていたのが突然、大方は予期しないような仕方で礼賛の中心となったのである。
ハルトマンよりはわずか八歳しか年下でないのだが、エリクソンは半世代もあとの人のように見えた。かれはその最初の重要な論文を公刊するのに四〇歳まで待っていた。かれの生涯のヨーロッパ時代は、ふりかえってみると準備期間であった。かれの成熟時代はすべてアメリカという舞台で過ごされたのである。のみならず、エリクソンのもっとも活溌な活動はハルトマンが自分の理論的体系に仕上げをしたちょうどその時にはじめられている。それゆえ、それぞれの著作における言及が若いエリクソンの方により多く見られることは当然のことである。ハルトマンはエリクソンについては行きずりに書きとめているにすぎない。エリクソンはアンナ・フロイトに第一に多くを負うていることを認めているが、ともに自我心理学の創始者たるハルトマンに何を負うているかを詳細に記述しようと試みている。1956年のフロイト生誕100年祭の講演ではかれは「環境の精神分析理論への橋」をつくり上げたことをハルトマンの功に帰し、対応する線に沿うてのかれ自身の経験的研究は「理論的に展開されていない」と特徴づけていた。12年後、講演やあれこれの論文を集めた第二巻を刊行したときには、エリクソンは自分とハルトマンがなにを共有しているかをもっとはっきりと書く準備がようやくにして整ったと感じた。ほとんどもっぱら臨床的、歴史的ないし論証的な文章の中にあっては珍しいのだが、「理論的間奏曲」という一文においてかれは、「自我(エゴ)」という専門用語は自己性(セルフフッド)という意味から明確に区別されねばならぬとするハルトマンの主張に同調している。この自己(セルフ)――もっとふつうには自己(アイデンティティ)同一性――への力説こそ、エリクソンが四半世紀にわたって表現しようと努めてきたものの核心であった。
1902年の誕生の日からエリクソンの生活はまことに非常套的な形で展開されてきた。かれの名前そのものがかれの出自の混淆、複雑な家族関係を明示している。デンマーク人の両親から生まれたかれは「バーデン州カールスルーエで小児科医テーオドル・ホンブルガー博士の息子として育てられた」。ホンブルガー博士と妻はその子のために善かれと願って、「母親が以前に結婚したことがあり」、実際にはかれはかれの生れる前に「その母親を棄てたデンマーク人の息子」であるという事実を秘密にしておいた。しかも、この国籍と父親の混乱だけではまだ足りないかのように、かれはさらに宗教上の同定という問題と闘わねばならなかった。「ブロンドで青い目の」若いエリクはその「義理の父の教会堂」で「“ゴイ”というニックネームをつけられた」。学校の仲間たちにとっては彼は「ユダヤ人であった」。
もちろん、結局はその少年は真実を見出すことになる。けれども、その結果は義理の父に対する明瞭な敵対ということにはならなかった。かれはこの義父の明らかにユダヤ的な名前を「感謝の念から……しかもまた逃避と見られることを避けるために」かれ自身のミドル・ネームとして残している。そしてかれは「医学校に行かずに近づけるだけ近く子供たちの医者という役割に接近した」。そうすることによってかれは、「小児科医たる義父」との「アンビヴァレントな同一化」と呼んだものと「かれ自身の神話的な父親」を「探すこと」とを「混合」したのである。しかし、この内的緊張の解消は、何年ものちにかれを「ほんとうに驚かしたフロイト・サークルによる採用」が精神分析の「当時すでに神話的な創始者」であったフロイトにおいて代理の父を与え、一方義理の息子という地位が不利であると同時に有利でもあることをかれに知らしめるにいたったときまで、あらわれはしなかった。それは、かれが自分の「まったく属していないところで受け入れられる」ことを「当然のことと考え」させ、「既成の諸領域の間で」またかれが「通常の信任状など持ちあわせてはいない制度的文脈のなかで」働くことへの確信を与えたのである。
そもそものはじめから、かれの母親と義理の父はかれに自分の道を「急がずに」見出させるという「辛抱強さ」をもっていた。かれらは大学で勉強することをやめて「放浪の芸術家となるべく……出発する」というかれの決心に反対しなかった。このようにして豊かな個人的経験を通じて、かれはのちにかれのキー概念となるものの一つ――人生の仕事にとりかかる前にくる社会的・情緒的「モラトリアム」――に出くわしてのである。この自由で「ロマンティック」な七年の生活ののちに、とうとうかれは心にかなった定職を見出した。かれはウィーンの小さな実験学校の教師として契約したのである。そしてここで幸運にもかれはアンナ・フロイトに出会った。彼女の精神分析による幼児の研究はまだ当時手をつけられたばかりであった。この精神分析創始者の娘による教育分析をこのあと受け、ハルトマンその人のごとき輝かしい新進の学者たちによる臨床上の正式の訓練もともに行われた。エリクソンは進むべき道も定かではない若者として1927年にウィーンに来たのだが、1933年にウィーンを去るときにはもう十分に羽の生えそろった素人分析家となっており、すでに結婚もして二人の小さな息子をもうけ、他の人びとの子供たちについての豊富な観察を蓄えていたのである。
このオーストリアの首都をかれが去ったのは、フロイト一家やハルトマンの場合のようにナチの占領によって追い出されたというわけではない。その五年前にかれは自分の意志でウィーン去ったのである。「……複雑な諸条件のもとで……強烈な訓練を受けた……のちに、別のところへ行って独立に働こうという考えが……心をはずましてくれるもの……のように思われた。」エリクソンは明らかに、創始者の継承者たちがすでに進んだ地位を要求している、精神分析の才能のうようよしているウィーンでは、かれのような非理論的精神の持主は囲い込まれてしまった感じを抱くことになるだろうと考えたのである。最初に、ごく短期間、かれは母国のデンマークで自立しようと試みた。次いで、こんどは決定的に、アメリカ合衆国へと移住した。かれの妻がアメリカ生まれであったことによって、また幼児分析は新しい分野で、行くところどこででも関心を喚起しえたという事実によって、そのアメリカ移住はスムーズに行われた。1934年から35年までかれはハーヴァードの医学校に、つづく三年間はイェールにいた。フロイトが死に第二次世界大戦が勃発した年に、かれはもう一度、こんどはバークリーのカリフォルニア大学に移った。ここでかれはその生涯の決定的な10年間を過ごすことになる。
実際エリクソンのアメリカ在住の主要段階はきっちり10年ずつに分けられる。1940年代はカリフォルニア、1950年代はバークシャー、1960年代はハーヴァードである。それぞれの時期に特徴的な性格と焦点があった。けれども、終始かわらずかれの臨床的な仕事と著作の根拠地は幼児の研究にあった。幼児の遊びのうちに(ヴィトゲンシュタインと同様に!)かれはフロイトが夢の世界に発見した理解への王道を見出したのである。エリクソンは子供のことを話すときにはいつもいちばん説得的であった。そこから遠く離れていけばいくほど、かれの思想は動揺し不明確になっていった。
エリクソンのカリフォルニア――といってもサンフランシスコ湾であって、多くのドイツ語を喋る亡命者たちが集まることになったロサンジェルス地域ではない――への移住は、もしもかれが東部に留まっていたら得られなかったような、アメリカ人の生活へのある感じを与えることになった。ハルトマンがコスモポリタン的な、ヨーロッパ志向的ニューヨークに移住したのとは異なり、エリクソンの西部行きの決心はかれら両人が育った文化的伝統からはるかに明確な断絶をもたらすことになる。ほとんどその土地で生まれた人たちとばかり付き合っていてエリクソンは、そこに「成年者の一風変った青年期スタイル」が認められる国民というものに関心をそそられた。手探り的に注意深くかれはアメリカの「国民性」を研究しはじめた。同時に、これはまた別の幸運なめぐり会いによって、かれは二つのまったく違った種族のアメリカ・インディアンの慣習と信仰とをじかに観察する機会に恵まれた。かれがまだイェールにいたとき、一人の人類学者の友人に南ダコタのシウ族保護地域に連れていかれたことがあった。またバークリーではアメリカ人類学の先達であるアルフレッド・L・クローバーに出会い、この人が北カリフォルニア海岸のユロク族へと案内してくれたのである。この点でもハルトマンとは対照的に、「エリクソンはまず精神分析と人類学あるいは歴史との概念的関係について考えめぐらすということをしなかった。その代わりにかれは特殊的なさまざまな環境下に生活している特殊な人びとの直接の観察……をあれこれ行ったのであった」。
1940年代のはじめに、アメリカ合衆国の土着民ならびに白人たちに関するエリクソンの暫定的な結論は一連の論文や草稿として形をとりはじめ、これがごくゆっくりと一冊の本にまで展開されていく。この本にはまた、かれが一般に注目されることになった最初の論文――1942年、戦争の高潮期に発表された「ヒトラーの心像とドイツの青年」――の改訂も含まれることになった。ハルトマンの共同研究者であるルドルフ・M・レーヴェンシュタインはその論文を「ユニークで記憶さるべき寄与」と呼んでいる。四年後、エリクソンは偶発的な形で論文を発表するのを止めた。一週間に一日必ず臨床研究や私的な業務を休んで、腰を据えてその本の完成に務めたのである。これが1950年に『幼児期と社会』Childhood and Societyとして世に出された。
構成はいかにも組織立ってはいないが、この『幼児期と社会』は実際には一見そう思われる以上に野心的な労作であった。諸事例の記述的研究にはじまるその本はシウ族、ユロク族をへて自我とアイデンティティに関する著者の中心的考察に進み、最後に現代アメリカおよびヒトラーの幼年期にまで及ぶ。しかしながら、このルースな試論タイプの構成の背後にはしっかりとしたドラマティックな意図が秘められている。エリクソンはこう説明する――かれの確信するところによれば、精神分析の方法は「本質的に歴史的な方法」であり、「人類の歴史」は「個々人のライフ・サイクルの巨大な物質代謝」である。したがって、かれの目標は「自我と社会との関係についての精神分析の書物」を書くことにある。これは、ハルトマンがこのような規模で、またこのように豊かな臨床的詳細さで企てることのなかったものである。」スチュアート・ヒューズ『大変貌 社会思想の大移動 1930-1965』荒川幾男・生松敬三訳、みすず書房、1978.pp.165-168.
ドイツ語圏からアメリカ合衆国に移住したユダヤ系知識人のうちでも、エリク・H・エリクソンはもっとも成功と名誉をかち得た人だったろう。かれの経歴はとてもユニークというか、波乱に満ちた人生で、いわゆるアカデミックな常識人とは一味も二味も違う人物だった。人間の運命の偶然性はまことに予測を超えたものだと感じるが、エリクソンの場合、生まれつきのコスモポリタンだったことと、おのれに与えられた自由を生かすすべを心得ていたといえる。

B.人工知能の社会的進化
新井紀子という人のことをぼくはこれまで知らなかったが、数学(数理論理学)というしごく抽象的かつ観念的な仕事をしながら、それが現代のヴィヴィッドな問題に直結していることを分かっている優秀な頭脳らしいと、初めて知ってなかなか面白い人だと思う。フランス・パリに呼ばれて大統領の前で「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトについて講演したという。「東大に入る」という日本的文脈はともかく、AIの最先端をぼくたちに理解できる形で説くのは、有意義である。
「仏のAI立国宣言 何のための人工知能か 日本も示せ:新井紀子のメディア私評
日本ではほとんど報じられていないが、人工知能(AI)分野で、地政学的な変化がおきようとしている。フランスの動向だ。マクロン大統領は3月末、世界中からAI分野の有識者を招き意見交換会とシンポジウムを開催。フランスを「AI立国」とすると宣言した。2022年までに15億ユーロをAI分野に投資し、規制緩和を進める。
招待された中には、フェイスブックのAI研究を統括するヤン・ルカンやアルファ碁の開発者として名高いディープマインド(DM)社のデミス・ハサビスらが含まれた。DMは今回パリに研究拠点を置くことを決めた。
これだけ読むと、「フランスもついに重い腰を上げたか」という感想を持つ読者も少なくないだろう。ドイツは早々に「インダストリー4.0」を開始した。ビッグデータやAIを活用することで製造業の革新を目指す国家プロジェクトだ。日本でも各省が競ってAI関連のプロジェクトに着手。それでも、米国や中国との距離は縮まるどころかますます水をあけられている。いまさらフランスが参入しても手遅れなのでは、と私も思っていた。
◎ ◎ ◎
ところが、である。意見交換会が開かれるエリゼ宮に到着して驚いた。出席者の約半数が女性。女性研究者は1割程度と言われるAIの会合では極めて異例だ。そこには、「破壊兵器としての数学 ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」の著者キャシー・オニールや、データの匿名化に精通したハーバード大学のラタニア・スウィーニーが含まれていた。マクロン大統領はこう言った。「AIの影響を受ける人々は『私』のような人(白人男性で40代)だけではない。すべての人だ。AIがどうあるべきかの議論には多様性が不可欠だ」と。
大統領から求められ、「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトを始めた意図を話した。「人々に広告をクリックさせるために」様々なサービスを無償で提供しているグーグルやフェイスブックのような巨大IT産業が、今回のAIブームを牽引することは2010年の段階で明らかだった。だが、日本はモノづくりの国である。99%の精度を、「100のうち99回正しい」ではなく「100に1回間違える」と認識すべき国だ。無償サービスの効率化のために開発された技術を、モノづくりに本格的に取り入れるべきか吟味すべきだ。AIの限界を探り、労働市場への影響を正確に見積もる必要があった、と。大統領は自ら詳しくメモを取りながら耳を傾けてくれた。
一方、「新技術が登場する時には心配する人は必ずいる。電話やテレビが登場した時もそうだが、何の問題もなかった。AIも同じだ」と楽観論を展開するヤン・ルカンに、大統領は厳しく指摘した。「これまでの技術は国民国家という枠の中で管理できた。AIとビッグデータは違う。圧倒的な寡占状況があり、富の再分配が行われていない。フランスが育成した有能な人材がシリコンバレーに流出しても、フランスに税金は支払われない」と。
◎ ◎ ◎
アメリカと中国でブームになると、日本は慌ててAIに手を出した。だが、「何のため」かはっきりしない。夏目漱石そっくりのロボットを作ってみたり、小説を書かせてみたり、よく言えば百花繚乱、悪く言えば迷走気味である。メディアも、AIと聞けば何でも飛びつく状況だ。フランスは違う。AIというグローバルゲームのルールを変えるために乗り出してきたのだ。
最後発のフランスにルールを変えられるのか。大統領のAIアドバイザーを務めるのは数学者のセドリック・ビラニだ。法学者や哲学者も連携して、アルゴリズムによる判断によって引き起こされ得る深刻な人権侵害、AIの誤認識による自己の責任の所在、世界中から最高の頭脳を吸引するシリコンバレーの「教育ただ乗り」問題を鋭く指摘。巨大なIT企業の急所を握る。そして、「データとアルゴリズムの透明性と正当な利用のための共有」という錦の御旗を掲げながら、同時に投資を呼び込む作戦だ。最初の一手は、5月に施行されるEU一般データ保護規則になることだろう。
ヨーロッパでは哲学も倫理学も黴の生えた教養ではない。自らが望む民主主義と資本主義のルールを通すための現役バリバリの武器なのである。
振り返って、我が国はどうか。「人間の研究者が『人工知能カント』に向かっていろいろ質問をして、その答えを分析することがカント研究者の仕事になるとわたしは予想する」(「AIは哲学できるか」森岡正博寄稿、本紙1月22日)。
これでは、日本の哲学者の仕事は風前の灯と言わざるを得ない。(敬称略)」朝日新聞2018年4月18日朝刊、17面オピニオン欄。
新井紀子さん:1962年生まれ。国立情報学研究所教授(数理論理学、人工知能)。近著に「AIvs.教科書が読めない子どもたち」。
日本の大手メディアだけでなく、政官財を含む大方の「お偉いさん」な人びとの、AIとビッグデータに関する理解はきわめて皮相で軽薄なレベルではないかと、ぼくはつねづね思っている。そうなってしまうのは、結局むかしの経済成長神話をいまだに信じ込んでいる冷戦ガラパゴス感覚と、新しい技術がややこしい課題すべてを解決してくれるという根拠薄弱な願望に捉われて、物事が見えなくなっているのだと思う。いまやAI、ロボット、ビッグデータは、行き詰った世界の救世主として期待を集めているのだが、これが人類の未来にとってほんとうに幸福な可能性を拓くかどうかは、人工知能にではなく人間の教養・叡智にかかっている、ということをフランス大統領は理解しているが、日本の首相はそんなことを考えたこともないのだろう。















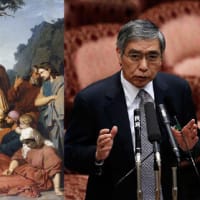










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます