A. 役に立つ「わざ」die Technikに集中するか?それとも、役に立たない「おもひ」das Denkenを巡らすか?
英語が自由に話せて読めて書ける能力が日本人に乏しい、という言い古された言説。そして、それは読み書き・文法偏重の日本の学校での英語教育に欠陥があるという俗説は、今も英語が得意そうでない政治家や財界人が気軽に口にするところだ。でも、それは粗雑なだけでなく誤った議論だと思う。中学高校の英語教育は、とっくに実用会話重視に切り替わっているし、英語を流暢に話し書ける能力が高い若者は確実に増えている。日本の未来にとって、外国語を学ぶということのもつ問題はそんなところにはないと思う。
小学校から英語を教えろ、英会話を必修化し、大学入試はTOEFLにしろ、といった類の教育論はしょせん浅薄な技術論である。そのおおもとの思想は、教育とは役に立つ「わざ」を子どもたちに身につけさせればいいので、学校は無駄なく効率よく「わざ」を教え込んだかどうかで評価されるべきだと考える。試験、点数評価、教育技術の数値化が語学においても標準モデルとなる。役に立たない「おもひ」、ものを考える能力はそれにともなって養われるだろうか?外国語を学ぶということは、たんに会話で意思疎通する道具を磨く、文章を書いて交渉や契約をする、外国の情報を収集する、という程度の道具・技法の習得でしかない、と思っている人は、学校で数年間みっちり教え込めばよいと考えるだろう。
子どもの能力はさまざまであるから、当然そこで期待通り良い成績を上げる子もいれば、うまく点数に反映しない子もいる。学校という教育機会を与えてあるのだから、そこで技術をマスターした人間にはふさわしい場とご褒美をあげるが、脱落した人間は役に立たない、使えない人間としてそれなりの処遇をする、という思想がどうも強まっている。考えてみると、そもそも何かを学ぶという行為が、役に立つ技術習得に偏っていくという傾向は、日本の場合昔から、もしかすると江戸時代からあった、かもしれない。
われわれがふだん生きている日常生活世界は、ネットで世界中の情報や画像が見られるようになった現在でも、さほど広いものではない。日本は特に国土が海に囲まれ、はるか海の向こうに異国があって異人が住んでいる、というイメージを強く持ってきたと思う。国際化だ、グローバル化だといいながら、「ガイジン」という言葉は今も使われている。19世紀なかばの幕末から明治への大転換は、文明の中心が日本にではなく西洋にあって、その西洋が極東の島国をも併呑するかもしれない武力や政治力をもって迫っている、と意識したときから、必死で西洋を学び始め、日本人は変革を成功させたといわれる。
でも、それが可能だったとすれば、日本人が全体として勤勉で有能だったから、というよりは、ごく少数の先駆的な人々がじゅうぶんな下馴らしの仕事を奇跡的に達成していたからだ、と考えた方がよい。異国の言葉を学ぶ、ということは動機が実用技術のためであっても、本格的に学んでいけば必ず、その言葉の生まれてきた土壌の文化そのものを理解することになる。会話というレベルでそれを深めるには、ネイティヴ外国人と日常的に接触するのが一番だが、読解と作文というレベルでは、とにかく原書をたくさん読むのが一番である。会話能力を高めればいいという話は、外国に行っても楽しく「ガイジン」とお話することができるようになるというにすぎない。それは確かに必要かもしれないが、グローバル化する世界で経済にしろ政治にしろ重要な仕事をするには学習の最優先事項ではない。かつて大学が国家の指導層予備軍養成という使命を掲げていた時代、そこで選ばれた学生たちは、翻訳のない膨大な洋書を原語で読まなければならず、その言葉の意味をいちいち考えて理解するものすごい努力をした。そこではたんなる翻訳ではなく、ひとつひとつの単語の概念に対応するわれわれ自身の生活と概念を考え新しい言葉を作り出す必要があった。
いわばわれわれはそのおかげで、西洋近代の科学も技術も思想も文学も、日本語のリテラシーがあればかなりの程度理解できるのである。もし、日本人が優れていた、と言うのならば、こんな役に立ちそうもない「おもひ」を、気の遠くなるような努力と困難を費やしてライフワークにしようと考えた、数人の奇妙な人が優れていた、というべきだろう。

B. 「おらんだ・まなび・ひがしにおよぶ・ことはじめ」
少し「蘭学」、つまり江戸時代中期18世紀後半の日本で、少数の若い医家たちがほそぼそ始めたオランダ医学の学習、そしてそこから幕末までに西洋文明への脅威と関心の高まりの中で急速に広がっていった「蘭学」を考えてみる。とりあえず文字通り『蘭学事始』である。
杉田玄白(1733~1817)が82歳の文化11(1814)年に書きあげたとされる『蘭学事始』上下二巻は、玄白の弟子大槻玄沢が師の命で原稿に推敲・修正を施し完成した文書である。高齢の玄白が、自分がライフワークとして築いてきた「蘭方医術」の歩みを、子孫や弟子に語り残しておきたいと考えて書かれたものである。いわば私的な随筆に近く、江戸時代には出版はされず、杉田家と大槻家に一部づつ所持されただけの毛筆文書(世界で2部しかない!)であった。明治2年になって福沢諭吉がこれを見つけ初めて出版された。日本の江戸時代の「蘭学」や「西洋医学」の出発点の苦労を生々しく伝える文書として、一級の資料とされ、歴史教科書などでもここに出てくる翻訳のエピソードなどは、しばしばとりあげらている。
玄白や前野良沢という初期の蘭方医が、オランダ伝来の医学書を苦労して読み始めた明和年間(1764~1772)には、まだ「蘭学」という言葉もなく、日本でオランダ語を読める人間も長崎の出島で通訳をする通詞(阿蘭陀通詞は大通詞四人、小通詞四人、稽古通詞若干名が基本定員と組織だったという:片桐注49)十人ほどしかいなかった。80歳を過ぎた玄白が、『蘭学事始』では、未知のオランダ医学への情熱を燃やしていた半世紀も前の30代の若い自分と仲間たちの仕事を振り返っている。(題名自体が「蘭東事始」「和蘭事始」など完成時に確定していなかった)
遠い外国、しかも鎖国政策の内にあって外国旅行は愚か外国人に会うことも不可能に近い状況で、外国語で書かれた書物を読もうとすることがどれほど困難であるか、まずは語学が入口なのに、彼らはいきなり大通詞から「やめたほうがいい」と言われる。
「一 翁かねて良沢は和蘭の事に志ありや否は知らず、久しき事にて年月は忘れたり。明和の初年の事なりしか、ある年の春、恒例のごとく拝礼として蘭人江戸へ来りし時、良沢、翁が宅へ訪ひ来れり。これより何かたへ行給ふと問ひしに、今日は蘭人の客屋に罷り、通詞に逢ふて和蘭の事をきき、模様により蘭語なとも問い尋ねんがためなりといへり。翁、其頃未だ年若く、客気甚しく、何事もうつり易き頃なれば、願くは我も同道し給われ、共々尋試たしと申ければ、いと易き事なりとて、同道して彼客屋へ罷たり。其年大通詞は西善三郎といふ者参たり。良沢引合にてしかじかのよし申述たるに、善三郎聞て、それは必ず御無用なり。夫は何故となれば、彼辞を習ひて理会するといふは至て難き事なり。たとへは湯水又酒を呑といふかを問んとするに、最初は手真似にて問より外の仕かたはなし。酒をのむといふ事を問んとするには、先茶碗にても持添注ぐ真似をして口につけて、これハと問へハうなづきて、デリンキ、と教ゆ。これ即ち呑む事なり。扨、上戸と下戸とを問うには、手真似にて問へき仕かたはなし。これは数々のむと数少なく呑にて差別わかる事なり。されども多く呑ても酒を不好人(このまざるひと)あるべし、又少く呑ても好人(このむひと)あり。是は情の上の事なれば、為すべきやうなし。扨其好き嗜むといふ事ハ「ア〻ンテレッケン」といふなり。我身通詞の家に生れ、幼より其事に馴居りながら、其辞の意何にの訳といふ事を知らず。年五十に及んで此度の道中にて其意を始て解得たり。ア〻ンとは元と向ふという事、テレッケンとは引事なり。其向ひひくといふは、向ふの者を手前へ引寄るなり。酒好む上戸といふも、むかふの物を手前へ引度(ひきたく)思ふなり。即ち好むの意なり。又故郷を思ふも斯くいふ。これ亦故郷を手もとへ引きよせ度と思ふ意あれハなり。彼言語をさらに習得んとするには、ヶ様に面倒なるものにして、我輩常に阿蘭陀人に朝夕してすら容易に納得しがたし。中〻江戸なとに居られ学んと思ひ給ふは不叶事なり。夫故野呂・青木両君など、御用にて年々此の客舘へ相越れ、一かたならず御出精なれども、はか〻敷御合点参らぬなり。其元にも御無用のかた然へし(しかるべし)と異見したり。良沢は如何承りしか、翁は性急のむまれ故其説を尤ときき、そのことく面倒なる事を為しとぐる気根はなし、徒に日月を費すは無益なる事と思ひ、敢えて学ぶ心はなくして帰りぬ。」杉田玄白『蘭学事始』(片桐一男訳注)講談社学術文庫、2000.pp.96-98.
デリンキはdrink、アーンテレッケンはaantrekkenというオランダ語動詞である。この話は、杉田玄白と前野良沢が江戸参府中のオランダ商館長(カピタン)一行の宿泊する長崎屋を訪ね、大通詞西善三郎に面会した折のことで、明和三年(1766)の春だったと推定されている。通詞の家に生まれ長崎で蘭人に日常接している西善三郎でさえ、まだオランダ語に習熟したとはいえないことばかりなのだから、幕府から蘭語習得を命じられたエリート学者でさえ、手こずってものになっていませんよ。江戸にいるあなたたちがオランダ語を習得するなど到底無理であることを具体的に説明された。玄白は、なるほどそうか、こりゃ諦めて他の事に時間を使うべきだな、と納得する。なかなか印象的な場面である。
しかし、結局やがて玄白と良沢は、オランダの解剖学書を翻訳し『解体新書』を完成させることになる。この情熱のもとは何だろう?身分制社会の中で、代々の医者の息子といっても明和年間に西洋医学を学ぶ動機は、立身出世や金銭や世間の評価ではありえない。横文字を読もうとすること自体が、きわめて特殊で異常なことだった。後の蘭学者たちのように場合によっては、異国かぶれの国賊と見られて逮捕されたり殺されたりはしないが、西洋医学の医療実践はまだまだ実用の域にはとても達していない。何しろ彼らは洋書を片手に解剖をして、はじめて内蔵器の区別と機能を目にするほど、技術者としても初心だったのだから。
英語が自由に話せて読めて書ける能力が日本人に乏しい、という言い古された言説。そして、それは読み書き・文法偏重の日本の学校での英語教育に欠陥があるという俗説は、今も英語が得意そうでない政治家や財界人が気軽に口にするところだ。でも、それは粗雑なだけでなく誤った議論だと思う。中学高校の英語教育は、とっくに実用会話重視に切り替わっているし、英語を流暢に話し書ける能力が高い若者は確実に増えている。日本の未来にとって、外国語を学ぶということのもつ問題はそんなところにはないと思う。
小学校から英語を教えろ、英会話を必修化し、大学入試はTOEFLにしろ、といった類の教育論はしょせん浅薄な技術論である。そのおおもとの思想は、教育とは役に立つ「わざ」を子どもたちに身につけさせればいいので、学校は無駄なく効率よく「わざ」を教え込んだかどうかで評価されるべきだと考える。試験、点数評価、教育技術の数値化が語学においても標準モデルとなる。役に立たない「おもひ」、ものを考える能力はそれにともなって養われるだろうか?外国語を学ぶということは、たんに会話で意思疎通する道具を磨く、文章を書いて交渉や契約をする、外国の情報を収集する、という程度の道具・技法の習得でしかない、と思っている人は、学校で数年間みっちり教え込めばよいと考えるだろう。
子どもの能力はさまざまであるから、当然そこで期待通り良い成績を上げる子もいれば、うまく点数に反映しない子もいる。学校という教育機会を与えてあるのだから、そこで技術をマスターした人間にはふさわしい場とご褒美をあげるが、脱落した人間は役に立たない、使えない人間としてそれなりの処遇をする、という思想がどうも強まっている。考えてみると、そもそも何かを学ぶという行為が、役に立つ技術習得に偏っていくという傾向は、日本の場合昔から、もしかすると江戸時代からあった、かもしれない。
われわれがふだん生きている日常生活世界は、ネットで世界中の情報や画像が見られるようになった現在でも、さほど広いものではない。日本は特に国土が海に囲まれ、はるか海の向こうに異国があって異人が住んでいる、というイメージを強く持ってきたと思う。国際化だ、グローバル化だといいながら、「ガイジン」という言葉は今も使われている。19世紀なかばの幕末から明治への大転換は、文明の中心が日本にではなく西洋にあって、その西洋が極東の島国をも併呑するかもしれない武力や政治力をもって迫っている、と意識したときから、必死で西洋を学び始め、日本人は変革を成功させたといわれる。
でも、それが可能だったとすれば、日本人が全体として勤勉で有能だったから、というよりは、ごく少数の先駆的な人々がじゅうぶんな下馴らしの仕事を奇跡的に達成していたからだ、と考えた方がよい。異国の言葉を学ぶ、ということは動機が実用技術のためであっても、本格的に学んでいけば必ず、その言葉の生まれてきた土壌の文化そのものを理解することになる。会話というレベルでそれを深めるには、ネイティヴ外国人と日常的に接触するのが一番だが、読解と作文というレベルでは、とにかく原書をたくさん読むのが一番である。会話能力を高めればいいという話は、外国に行っても楽しく「ガイジン」とお話することができるようになるというにすぎない。それは確かに必要かもしれないが、グローバル化する世界で経済にしろ政治にしろ重要な仕事をするには学習の最優先事項ではない。かつて大学が国家の指導層予備軍養成という使命を掲げていた時代、そこで選ばれた学生たちは、翻訳のない膨大な洋書を原語で読まなければならず、その言葉の意味をいちいち考えて理解するものすごい努力をした。そこではたんなる翻訳ではなく、ひとつひとつの単語の概念に対応するわれわれ自身の生活と概念を考え新しい言葉を作り出す必要があった。
いわばわれわれはそのおかげで、西洋近代の科学も技術も思想も文学も、日本語のリテラシーがあればかなりの程度理解できるのである。もし、日本人が優れていた、と言うのならば、こんな役に立ちそうもない「おもひ」を、気の遠くなるような努力と困難を費やしてライフワークにしようと考えた、数人の奇妙な人が優れていた、というべきだろう。

B. 「おらんだ・まなび・ひがしにおよぶ・ことはじめ」
少し「蘭学」、つまり江戸時代中期18世紀後半の日本で、少数の若い医家たちがほそぼそ始めたオランダ医学の学習、そしてそこから幕末までに西洋文明への脅威と関心の高まりの中で急速に広がっていった「蘭学」を考えてみる。とりあえず文字通り『蘭学事始』である。
杉田玄白(1733~1817)が82歳の文化11(1814)年に書きあげたとされる『蘭学事始』上下二巻は、玄白の弟子大槻玄沢が師の命で原稿に推敲・修正を施し完成した文書である。高齢の玄白が、自分がライフワークとして築いてきた「蘭方医術」の歩みを、子孫や弟子に語り残しておきたいと考えて書かれたものである。いわば私的な随筆に近く、江戸時代には出版はされず、杉田家と大槻家に一部づつ所持されただけの毛筆文書(世界で2部しかない!)であった。明治2年になって福沢諭吉がこれを見つけ初めて出版された。日本の江戸時代の「蘭学」や「西洋医学」の出発点の苦労を生々しく伝える文書として、一級の資料とされ、歴史教科書などでもここに出てくる翻訳のエピソードなどは、しばしばとりあげらている。
玄白や前野良沢という初期の蘭方医が、オランダ伝来の医学書を苦労して読み始めた明和年間(1764~1772)には、まだ「蘭学」という言葉もなく、日本でオランダ語を読める人間も長崎の出島で通訳をする通詞(阿蘭陀通詞は大通詞四人、小通詞四人、稽古通詞若干名が基本定員と組織だったという:片桐注49)十人ほどしかいなかった。80歳を過ぎた玄白が、『蘭学事始』では、未知のオランダ医学への情熱を燃やしていた半世紀も前の30代の若い自分と仲間たちの仕事を振り返っている。(題名自体が「蘭東事始」「和蘭事始」など完成時に確定していなかった)
遠い外国、しかも鎖国政策の内にあって外国旅行は愚か外国人に会うことも不可能に近い状況で、外国語で書かれた書物を読もうとすることがどれほど困難であるか、まずは語学が入口なのに、彼らはいきなり大通詞から「やめたほうがいい」と言われる。
「一 翁かねて良沢は和蘭の事に志ありや否は知らず、久しき事にて年月は忘れたり。明和の初年の事なりしか、ある年の春、恒例のごとく拝礼として蘭人江戸へ来りし時、良沢、翁が宅へ訪ひ来れり。これより何かたへ行給ふと問ひしに、今日は蘭人の客屋に罷り、通詞に逢ふて和蘭の事をきき、模様により蘭語なとも問い尋ねんがためなりといへり。翁、其頃未だ年若く、客気甚しく、何事もうつり易き頃なれば、願くは我も同道し給われ、共々尋試たしと申ければ、いと易き事なりとて、同道して彼客屋へ罷たり。其年大通詞は西善三郎といふ者参たり。良沢引合にてしかじかのよし申述たるに、善三郎聞て、それは必ず御無用なり。夫は何故となれば、彼辞を習ひて理会するといふは至て難き事なり。たとへは湯水又酒を呑といふかを問んとするに、最初は手真似にて問より外の仕かたはなし。酒をのむといふ事を問んとするには、先茶碗にても持添注ぐ真似をして口につけて、これハと問へハうなづきて、デリンキ、と教ゆ。これ即ち呑む事なり。扨、上戸と下戸とを問うには、手真似にて問へき仕かたはなし。これは数々のむと数少なく呑にて差別わかる事なり。されども多く呑ても酒を不好人(このまざるひと)あるべし、又少く呑ても好人(このむひと)あり。是は情の上の事なれば、為すべきやうなし。扨其好き嗜むといふ事ハ「ア〻ンテレッケン」といふなり。我身通詞の家に生れ、幼より其事に馴居りながら、其辞の意何にの訳といふ事を知らず。年五十に及んで此度の道中にて其意を始て解得たり。ア〻ンとは元と向ふという事、テレッケンとは引事なり。其向ひひくといふは、向ふの者を手前へ引寄るなり。酒好む上戸といふも、むかふの物を手前へ引度(ひきたく)思ふなり。即ち好むの意なり。又故郷を思ふも斯くいふ。これ亦故郷を手もとへ引きよせ度と思ふ意あれハなり。彼言語をさらに習得んとするには、ヶ様に面倒なるものにして、我輩常に阿蘭陀人に朝夕してすら容易に納得しがたし。中〻江戸なとに居られ学んと思ひ給ふは不叶事なり。夫故野呂・青木両君など、御用にて年々此の客舘へ相越れ、一かたならず御出精なれども、はか〻敷御合点参らぬなり。其元にも御無用のかた然へし(しかるべし)と異見したり。良沢は如何承りしか、翁は性急のむまれ故其説を尤ときき、そのことく面倒なる事を為しとぐる気根はなし、徒に日月を費すは無益なる事と思ひ、敢えて学ぶ心はなくして帰りぬ。」杉田玄白『蘭学事始』(片桐一男訳注)講談社学術文庫、2000.pp.96-98.
デリンキはdrink、アーンテレッケンはaantrekkenというオランダ語動詞である。この話は、杉田玄白と前野良沢が江戸参府中のオランダ商館長(カピタン)一行の宿泊する長崎屋を訪ね、大通詞西善三郎に面会した折のことで、明和三年(1766)の春だったと推定されている。通詞の家に生まれ長崎で蘭人に日常接している西善三郎でさえ、まだオランダ語に習熟したとはいえないことばかりなのだから、幕府から蘭語習得を命じられたエリート学者でさえ、手こずってものになっていませんよ。江戸にいるあなたたちがオランダ語を習得するなど到底無理であることを具体的に説明された。玄白は、なるほどそうか、こりゃ諦めて他の事に時間を使うべきだな、と納得する。なかなか印象的な場面である。
しかし、結局やがて玄白と良沢は、オランダの解剖学書を翻訳し『解体新書』を完成させることになる。この情熱のもとは何だろう?身分制社会の中で、代々の医者の息子といっても明和年間に西洋医学を学ぶ動機は、立身出世や金銭や世間の評価ではありえない。横文字を読もうとすること自体が、きわめて特殊で異常なことだった。後の蘭学者たちのように場合によっては、異国かぶれの国賊と見られて逮捕されたり殺されたりはしないが、西洋医学の医療実践はまだまだ実用の域にはとても達していない。何しろ彼らは洋書を片手に解剖をして、はじめて内蔵器の区別と機能を目にするほど、技術者としても初心だったのだから。















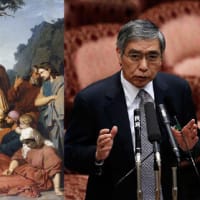










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます