A.ジャスパー・ジョーンズのアート
1952年12月~1953年5月の間、ジャスパー・ジョ-ンズは、朝鮮戦争のため仙台に駐屯した。特別任務を課され、映画の宣伝ポスターや、対性病教育用ポスターをつくる。仙台駐屯の間、彼は東京にも行き、ダダイスト、シュルレアリストに触発された日本のアーティストたちの展覧会を訪ねたという。「それはとても面白かった。ある作品を覚えている。台から女物の手袋が下がっていて、象の足が、その手袋の指の一本の上に乗ってこれを固定しているというものだった」東野芳明は後に、ジョーンズは日本に滞在していたとき「地方の喫茶店で、1枚の[エドガー・ヴァレーズ]のレコードを見つけ、すり減るまで聴いていた」と書いている。(東野芳明「東京のジャスパー・ジョーンズ」『美術手帖』1964年8月号。日本から戻ると、彼は上等兵を最後にフォート・ジャクソンの軍を除隊する。23歳の若者はまだ画家ではなかった。
「ジョーンズの作品にまず貼られたレッテルのひとつは「ネオ・ダダ」だったが、パフォーマンス的な不条理さも政治的な破壊志向も――1950年代後半から1960年代前半にかけてダダ以外の芸術に跳びうつり開花したダダイズムの精髄――ジョーンズの活動には些かの関わりももっていない。ジョーンズと縁があったのはとりわけデュシャンであり、その結びつきには独創性と換骨奪胎の趣がある。もしジョーンズが彼自身による「翻訳」を提供しなかったとすれば、1960年代以降のアメリカ美術にデュシャンがこれほど広範な影響を及ぼすことはなかったのではなかろうか。たとえばナウマンは過去をふりかえり、ジョーンズは「デュシャンへの扉」を開いてくれたが、それは「フォークナーを読むことによってフロイトを学ぶようなもの――目の前にあることに変わりはなくとも、実地に適用されていた」と語っている。ジョーンズがときに行うデュシャンへの明確な言及や、デュシャンのことばの引用は1980年代に登場した無数の「アプロプリエーション」に見出されるが、それより重要なのは、ジョーンズがデュシャンの作品をこしらえないという流儀を、作品の作り方に転じたことである。ジョーンズは思想の禁欲的な優雅さを、もの造りの実践に切り替え、巧みなウィットを暗澹とした不穏な心理作用に仕立てなおした。そこには1940年代に生じたヨーロッパからアメリカへの移行過程での変化、つまりマックス・エルンストやアンドレ・マッソンらがパリで旗揚げしたシュルレアリスムを、ニューヨーク・スクールの年若い画家たちがその洗練された趣を除去し、カンヴァス上に無意識をねじふせる生真面目で、切実な方策につくり直した経緯の反映をみることもできる。そのころ台頭し、ラウシェンバーグによって受け継がれた「アクション・ペインティング」の壮健で伸び伸びとした、ホイットマン風のひろがりに対抗して、ジョーンズは、思慮深くイーキンズを思わせる粘り強さで、ものの支配する有形の世界を思想の届く範囲に押さえこもうとする、風刺のきいた即物主義を主張したのだった。
ジョーンズの1960年代作《塗られたブロンズ(エール罐)》をデュシャンの《自転車の車輪》などのレディメイド作品と較べてみれば、ジョーンズが丹念に手作りでこしらえた実物紛いの作品のいかにもアメリカ的な特質が浮き彫りになるだろう。こうした手業の要素が、とりわけ絵画制作について、ゲルハルト・リヒターの世代のヨーロッパのアーティストたちの目にジョーンズをセザンヌに端を発する絵画の伝統、かれらが抑圧的と感じる伝統に深入りしすぎているとの印象を与えたのは、皮肉というしかない。ヨーロッパではジョーンズよりアンディ・ウォーホルのほうが幅広い影響をおよぼしたのは、こうした見方のせいもある――アメリカの魅力は工業的で人間味を感じさせない、粗野なところにあるというヨーロッパ人の考えには、ウォーホルの平板なスクリーンプリントがうまくあてはまった(一方、イギリスと日本では1960年代初めにすでに、ジョーンズの影響の広まりがはっきり認められるようになる)。ところがデビューしたてのころのジョーンズに(あるいは少なくともジョーンズが手にした成功と名声に)誰よりも夢中になったのはウォーホルだったのである。
ジョーンズは実際にしばしば「ポップの父」とみなされるけれども、本人の言葉にもある通り、「もしチューインガムを作っても、みながそれを糊代わりに使うようになれば、作り手は糊の作者として認められることになる」。ジョーンズとラウシェンバーグがポップの誘因になったことを否定しては、観察力の鈍さを示すことになりそうだ。ステラはこんな比喩を使う。デュシャンができあいのものを台座に載せたのに対して、このふたりは付随的な事柄と日常の世界を作品にもちこんで目ざましいまでの切実さを感じさせ、もの同士の間に新しい関係を見い出し、予期せぬ調和を力づくで得心させることによって、作品に有効性を与えた。またボックナーの証言にもあるように、ジョーンズが文化の象徴の本命である星条旗を用いたことが、無数のアーティストを文化とその批評という大きな問題に向かわせるきっかけになったのはたしかだろう。ありきたりなオブジェ――ビールの罐、懐中電灯、電球など――を題材にしたジョーンズの彫刻が、ポップ・アーティストの注意を商品に向ける呼び水になったのもまちがいなさそうだ。ところがポップの台頭と同時に、ジョーンズはそうしたオブジェの制作を止めてしまう。今から振り返ってみれば、作業現場に散らかった作品――汚れた床板、使いさしの絵筆、裸電球、アルコールやカフェインの名残り(1962年作《愚者の家》の箒とカップも忘れられない)—―から連想されるうらぶれたボヘミアン風のスタジオの様子は、大量生産や商業広告をにこやかに受け入れたウォーホールの「ファクトリー」やオルデンバーグの「ストア」とは好対照をなしていることがわかる。
ジョーンズは当初どうやらアメリカの社会生活のなかで、いつまでも中立的で変わることのないシンボルをいくつか求めようとしたらしい。ところがときはまさに国内の政治情勢、またとくに消費生活の変化が一段と速度を増す時期にあたっていた。星条旗の星の数は増え、商品のレッテルやロゴのデザインが変わり、息の長いブランド・ネームにも廃れたり改称されるものが現れた。不変と思われたものが次々と姿を消してゆくというこの感覚は、社会に流通している事物を拾いあげて、「ありふれた品々」の私的なイメージ構成をこしらえようという企図をジョーンズが断念する際にも一定の役割を果たしていたように思われるが、ポップ・アートに深い郷愁—―50年もレッテルのデザインの変わらない罐スープ、罐コーラ全盛時代のコカ・コーラの瓶、マディソン街の広告業界が雑誌のカラーページの隆盛に沸いた時代に生み出されたちっぽけで幼稚な宣伝の紙つぶてなど、かつてはありふれていたのに、今まさに消え去ろうとしているものに対する甲高く悲痛な哀歌――を呼び覚ます一因ともなった。一方、厳密に実寸を守るジョーンズのオブジェには無口で引っ込み思案な性質があり、これは美術の論理を敷衍しようとするポップの傾向とは水と油であったし、商品のイメージの作品化はただの二度(バランタイン・エールとサヴァラン・コーヒー)きりで終わらせているせいもあって、ジョーンズはポップ・アーティストの好む皮肉と感傷の安手の混淆からは超然とした位置を保っている。ポップのオブジェは取引を物語るのに対して、ジョーンズの作品は所有に関わる重要性を維持した。
ジョーンズがポップの父であることは、彼がミニマリズムの生みの親とされることとつねに対をなしている。魅了された対象が《旗》のイメージそのものか、あるいはイメージのあつかい方によって後継者たちの進路はふたてに分かれた。前者は客体そのものとみなす。かれらの目には、イメージを前面に打ち出しカンヴァスを隅から隅までうめつくしてしまうのは、通常の再現性を打ち消すことに等しいと映った。モリスが1969年に記したように、「ジョーンズほど絵画を非・描写の状態に近づけたひとはほかにいない。旗は描写よりむしろ複写に近い…ジョーンズは背景を絵画から追い出し、絵画をものとして抜き出した。背景は壁になる。それまで中立の立場を守っていたものが能動的になり、それまでのイメージがものになった」。
切迫したこの存在感、イリュージョンの空間との関連抜きに自立する全体性が、じつに多種多様なひとびとに鮮烈な刺戟を与えた。《旗》の縞からステラの1959年作のブラック・ペインティングへの受渡しが、直接的な点では最も顕著だとしても、ジョーンズは1960年代初めに登場したドナルド・ジャッドやダン・フレヴィンなど、内部の構成的な関係を排除し周囲の空間をじかに活性化させる道を探っていた彫刻家たちにも等しく影響を及ぼしている。ポップがジョーンズのとりあげた平凡な品物の身近で、些細な代用品から出発して、めまぐるしい世間のけばけばしさにのめりこんでいったように、もう一方のアーティストたちも認識の曖昧さに関わるジョーンズの作品を跳びこして、経験的な手応えのあるものへと突き進んだ。自分の描いた縞について、「目に見えるものが目に見えるもの」と述べたステラの名高い主張は、仲間のアーティストが言うように、ジョーンズを「見事に誤解」したもので、ジョーンズの作品が探ろうとした目と精神の間の微妙な緊張関係を、自信たっぷりに一掃したことになる。
こうした厳密なミニマリズム的な意味合いで、ジョーンズは明晰な思考に基づいて作品制作の過程から神秘的な要素をとりのぞくように促したとみることができる――ただし、もっと詳しく調べてみれば、表向きには素直な手ごたえを感じさせるジョーンズの作品にも、皮肉や疑念がまとわりついている。」カーク・ヴァーネドー「火――ジョーンズの作品はアメリカ人アーティストの目にどのように映り、用いられたか」(ニューヨーク近代美術館『ジャスパー・ジョーンズ展』カタログ)日本語版、読売新聞社発行、1996.pp.096-099.
アメリカの20世紀後半の美術シーンをふり返るとき、ジャスパー・ジョーンズという人の立ち位置は、「ポップの父」と呼ばれて当然ではあるが、それだけなら1960年代に終わったはずだ。ジョーンズより2歳年上のアンディ・ウォーホルは1987年2月に58歳で亡くなってしまったが、ジョーンズは87歳で今も生きている。20代はイラストレーターで働いていたウォ―ホルより美術界デビューはジョーンズの方が早かった。画家は短命な人もいれば、長生きする人もいるが、老齢まで現役で制作を続けたトップランナーは、ピカソそしてジョーンズではないか。それだけでも凄いな。

B.国家が強くなること
衆議院選挙の結果はほぼ自民党の圧勝、単独過半数達成という結果に終わりそうだ。加計・森友問題と都議選敗北でぐらついた基盤をリセットしたい安倍晋三の思惑通りの結果といえるだろう。これが日本の今後にどういう形で深く影響してくるか、やはり歴史に学ぶ必要があると思う。
戦前の日本には政党もあり選挙もあったが、政党以外にも貴族院やら元老院やらそして軍部という別個の権力があり、選挙権は国民の半分(女性)にはなかった。だから、一般の国民が敗ける戦争に突き進んでいったことへの責任は、国民大多数ではなく一部の権力をもっていた人々に責任が帰せられる、というのもある程度認められる議論だとは思う。もちろん鬼畜米英との戦争に喜んで協力したのも国民大衆の心情的支持があったからということも忘れてはいけない。
今を去る77年前の1940(昭和15)年10月大政翼賛会が発足した。前年1月に第1次内閣を総辞職した近衛文麿だったが、ヨーロッパで第2次世界大戦が始まり、東アジアの日中戦争も泥沼化するなかで、日本は強力な指導体制を形成する必要があるとする新体制運動が盛り上がり、その盟主として国民に人気のある近衛の再登板に期待が高まった。既成政党側でも近衛に対抗するよりもみずから新体制に率先して参加することで有利な立場を占めるべきだという意見が高まり、民政党総裁町田忠治と政友会正統派の鳩山一郎が秘かに協議して両党が合同する「反近衛新党」構想を画策したものの、民政党では永井柳太郎が解党論を唱え、政友会正統派の総裁久原房之助も親英米派の米内光政(海軍大将・前海軍大臣)を首班とし新体制運動に消極的な米内内閣の倒閣に参加して近衛の首相再登板を公言した。そのために合同構想は失敗に終わり、民政党・政友会両派(正統派・革新派)ともに一気に解党へと向かうことになった。右翼政党の東方会も解党し、思想団体「振東社」となった。近衛も米内内閣の後の第2次近衛内閣成立後にこの期待に応えるべく新体制の担い手となる一国一党組織の構想に着手する。なお、その際、近衛のブレーンであった後藤隆之助が主宰し、近衛も参加していた政策研究団体昭和研究会が東亜協同体論や新体制運動促進などをうたっていた。こうした動きの結果、大政翼賛会が発足し国民動員体制の中核組織となる。ようやく定着するかに見えた立憲君主制と二大政党政治が、ここであえなく崩壊した。日本の敗北崩壊まであと5年もなかったのだが、そのときは日本人の大多数はそんな未来は想像もしていなかった。
「安倍晋三首相(自民党総裁)は小雨が降る東京都千代田区の秋葉原駅前で最後の演説を行った。7月の東京都議選で「辞めろ」コールが起きた「トラウマ」の場所だが、連勝した直近4回の国政選挙で最後に街頭に立ってきた「験担ぎ」を優先。「アキバ」で人気のある麻生太郎副総理兼財務相が駆け付けたことも安心材料となったようだ。
「看板を変えたからって国民を欺くこと、だますことはできない」。首相は冒頭から、民主党政権で閣僚だった立憲民主党の公認候補を名指しで批判。その後も野党批判を軸に演説を続けた。解散に踏み切った理由として北朝鮮問題への対応と少子高齢化対策を挙げ、「将来に夢をもつことができる日本をつくる。日本を守り抜き、日本の未来を切り開くことができるのは私たち自民党だ」と訴えた。
麻生氏は株高や雇用増に触れ、「アベノミクスが正しかった。この政策に自信を持って続けていきたい」と主張した。
駅前は厳重警備で、夕方から日の丸の小旗や「安倍首相を応援しよう」などと書いたプラカードを手にした支持者らが集まった。自民関係者が支援者だけを前方に陣取らせるよう整理。一方で、「安倍9条改憲NO!」などのプラカードを掲げる聴衆は後方に多く、「うそつきな総理はいらない」とのヤジも飛んだ。」朝日新聞2017年10月22日朝刊2面総合欄。
安倍晋三は近衛文麿になるのか?そして、戦前日本に戻すような指向を滲ませた憲法を変えるという革命が、もうじき実現するのか?事態は往々にして思わぬ方向に展開してしまう。果たして近々に戦争が極東で起こるのかどうかは予断を許さないが、それよりもたぶん国内に深刻な亀裂が走るような気がする。安倍一強体制でなんでも通ってしまう政治が選挙で太鼓判を押されたとみんなが思えば、体制翼賛化がすすむのは避けられない。
いずれにしても、安倍晋三が目標とする「強い国家」とは何だろう?国家が強くなることは、ぼくたち国民にとってどういう意味をもつのか?それは単純にひとりひとりの幸福が増すことなのか?それとも「強い国家」のために国民は犠牲を払う価値などないのか?安倍自民党に強い指示を与えた投票有権者の多数は、「強い国家が自分たちを守ってくれる」と思ったのだろうが、この選挙への後世の人びとへの責任を自覚しているとはとてもいえない。
隣の国でも、「強い国家」を自慢し、世界への威力を誇示したい権力者が大きな声を出している。
「【北京=張勇祥】中国共産党の第19回党大会が18日午前9時(日本時間午前10時)、北京の人民大会堂で開幕した。習近平総書記(国家主席)に続き、江沢民元総書記、胡錦濤前総書記が入場した。李克強首相が開幕を宣言した。2012年に総書記に就任した習近平氏が、1期目である5年間の総括と今後の基本方針について演説した。党内の規律強化や脱貧困政策などの成果を誇示し、権力基盤の確立を国内外に強調する。最高指導機関である党大会の会期は24日まで。指導幹部である約200人の中央委員の選出や、党規約の改正などが主要議題となる。
焦点の党首脳人事については、中央委員が25日にも中央委員会第1回全体会議(1中全会)を開いて政治局員(現在は24人)を選び、そこから最高指導部である政治局常務委員(同7人)を決める。最高責任者である総書記は常務委員から選ぶ。党規約の改正については、習氏が掲げてきた政治思想や理念を明記して権威を高める見通し。「習近平思想」のように自身の名を冠した名称になれば、毛沢東氏や鄧小平氏に並ぶ権威を得ることになる。強力な権限を持つ毛沢東時代のポスト「党主席」を復活させる案も出ている。すでに別格の指導者を意味する「核心」の地位を手に入れている習氏が、さらなる権力集中を進められるか。習氏が望むとされる「3期続投」に向けた地ならしが進むかも注目点になる。
▼中国共産党大会 党の指導体制や基本方針を決める最高指導機関。5年に1度開き、指導幹部となる約200人の中央委員の選出や党規約の改正、重要な政策課題を討議する。第19回の今回は約8900万人の党員から選ばれた2280人の代表が出席する。大会冒頭で党トップの総書記が、過去5年間の中国を振り返り将来を展望する活動報告を読み上げ国家運営の基本方針を示す。大会閉幕直後に中央委員会第1回全体会議(1中全会)を開き政治局員(現在は24人)を選定。その中から最高指導部の政治局常務委員(同7人)を決め、常務委員の中から総書記を選ぶ。」日経新聞オンライン。
国家の強さは経済力と軍事力で他を圧倒しているかどうかで決まると習近平は考えている。そしていまや中国は、経済力にも軍事力にも主観的にはきわめて強い自信を持っているようだ。少なくとも経済力の乏しい弱小国家である北朝鮮が核兵器で大国アメリカに対抗しようとしている捨て身の冒険に比べれば、中国は実力をともなって世界への影響力を発揮し、日本など問題外とみなしているようだ。中国はぼろぼろの20世紀を否定して、栄光の中華思想を復活させたいのだろう。
あらためてぼくは思うのだが、国家と自分の関係をよく考えてみると、ぼくは確かにこの国に生まれて国籍ももっているのだが、国が強くなることも弱くなることもぼくとは何の関係もない。外国に行ってみると、確かに円が強いとちょっと買い物に有利だし、日本人だからと唾を吐かれたり罵倒されたりはしない。でも、そんなことはぼくという人間にはど~でもいいことだし、人間の質を見てくれる外国人にはぼくが日本人かどうかなんて、これもど~でもいいことだ。だから、日本という国家が経済力で衰弱しようが軍事力でもの足りなかろうが、そんなことは人間の生活にはど~でもいいことなのに、ど~してそんなに「強い国家」が必要だなんて思うのだろうか不思議だ。
確かにこの日本という国家が明治維新でできたとき、指導者は19世紀世界の情勢を見極めて、新しい国家が立ちゆくための知恵を絞った。その結果、ぼくたちは外国の植民地になることも内戦で分裂することも、経済破綻で崩壊することもなく、富国強兵を達成したけれども、昭和戦前期にあまりにも自己過信と軍事的妄想に溺れて、多大な犠牲と外国の占領という破滅を経験した。だからぼくはこう思う。ぼくらの前には今二つの別れ道がある。ひとつは昭和15年と同じことをくりかえす道で、「強い国家」ファーストの安倍自民党はそれを目指している。もうひとつの道は、「賢い国家」によってぼくたちの生命と生活の基礎を固めることを第一とする道だ。それは経済力と軍事力の強化を優先して世界に威張りまくる国にするのではなく、当たり前の人生を自分の意思で歩めるような社会を用意する国なのだ。
1952年12月~1953年5月の間、ジャスパー・ジョ-ンズは、朝鮮戦争のため仙台に駐屯した。特別任務を課され、映画の宣伝ポスターや、対性病教育用ポスターをつくる。仙台駐屯の間、彼は東京にも行き、ダダイスト、シュルレアリストに触発された日本のアーティストたちの展覧会を訪ねたという。「それはとても面白かった。ある作品を覚えている。台から女物の手袋が下がっていて、象の足が、その手袋の指の一本の上に乗ってこれを固定しているというものだった」東野芳明は後に、ジョーンズは日本に滞在していたとき「地方の喫茶店で、1枚の[エドガー・ヴァレーズ]のレコードを見つけ、すり減るまで聴いていた」と書いている。(東野芳明「東京のジャスパー・ジョーンズ」『美術手帖』1964年8月号。日本から戻ると、彼は上等兵を最後にフォート・ジャクソンの軍を除隊する。23歳の若者はまだ画家ではなかった。
「ジョーンズの作品にまず貼られたレッテルのひとつは「ネオ・ダダ」だったが、パフォーマンス的な不条理さも政治的な破壊志向も――1950年代後半から1960年代前半にかけてダダ以外の芸術に跳びうつり開花したダダイズムの精髄――ジョーンズの活動には些かの関わりももっていない。ジョーンズと縁があったのはとりわけデュシャンであり、その結びつきには独創性と換骨奪胎の趣がある。もしジョーンズが彼自身による「翻訳」を提供しなかったとすれば、1960年代以降のアメリカ美術にデュシャンがこれほど広範な影響を及ぼすことはなかったのではなかろうか。たとえばナウマンは過去をふりかえり、ジョーンズは「デュシャンへの扉」を開いてくれたが、それは「フォークナーを読むことによってフロイトを学ぶようなもの――目の前にあることに変わりはなくとも、実地に適用されていた」と語っている。ジョーンズがときに行うデュシャンへの明確な言及や、デュシャンのことばの引用は1980年代に登場した無数の「アプロプリエーション」に見出されるが、それより重要なのは、ジョーンズがデュシャンの作品をこしらえないという流儀を、作品の作り方に転じたことである。ジョーンズは思想の禁欲的な優雅さを、もの造りの実践に切り替え、巧みなウィットを暗澹とした不穏な心理作用に仕立てなおした。そこには1940年代に生じたヨーロッパからアメリカへの移行過程での変化、つまりマックス・エルンストやアンドレ・マッソンらがパリで旗揚げしたシュルレアリスムを、ニューヨーク・スクールの年若い画家たちがその洗練された趣を除去し、カンヴァス上に無意識をねじふせる生真面目で、切実な方策につくり直した経緯の反映をみることもできる。そのころ台頭し、ラウシェンバーグによって受け継がれた「アクション・ペインティング」の壮健で伸び伸びとした、ホイットマン風のひろがりに対抗して、ジョーンズは、思慮深くイーキンズを思わせる粘り強さで、ものの支配する有形の世界を思想の届く範囲に押さえこもうとする、風刺のきいた即物主義を主張したのだった。
ジョーンズの1960年代作《塗られたブロンズ(エール罐)》をデュシャンの《自転車の車輪》などのレディメイド作品と較べてみれば、ジョーンズが丹念に手作りでこしらえた実物紛いの作品のいかにもアメリカ的な特質が浮き彫りになるだろう。こうした手業の要素が、とりわけ絵画制作について、ゲルハルト・リヒターの世代のヨーロッパのアーティストたちの目にジョーンズをセザンヌに端を発する絵画の伝統、かれらが抑圧的と感じる伝統に深入りしすぎているとの印象を与えたのは、皮肉というしかない。ヨーロッパではジョーンズよりアンディ・ウォーホルのほうが幅広い影響をおよぼしたのは、こうした見方のせいもある――アメリカの魅力は工業的で人間味を感じさせない、粗野なところにあるというヨーロッパ人の考えには、ウォーホルの平板なスクリーンプリントがうまくあてはまった(一方、イギリスと日本では1960年代初めにすでに、ジョーンズの影響の広まりがはっきり認められるようになる)。ところがデビューしたてのころのジョーンズに(あるいは少なくともジョーンズが手にした成功と名声に)誰よりも夢中になったのはウォーホルだったのである。
ジョーンズは実際にしばしば「ポップの父」とみなされるけれども、本人の言葉にもある通り、「もしチューインガムを作っても、みながそれを糊代わりに使うようになれば、作り手は糊の作者として認められることになる」。ジョーンズとラウシェンバーグがポップの誘因になったことを否定しては、観察力の鈍さを示すことになりそうだ。ステラはこんな比喩を使う。デュシャンができあいのものを台座に載せたのに対して、このふたりは付随的な事柄と日常の世界を作品にもちこんで目ざましいまでの切実さを感じさせ、もの同士の間に新しい関係を見い出し、予期せぬ調和を力づくで得心させることによって、作品に有効性を与えた。またボックナーの証言にもあるように、ジョーンズが文化の象徴の本命である星条旗を用いたことが、無数のアーティストを文化とその批評という大きな問題に向かわせるきっかけになったのはたしかだろう。ありきたりなオブジェ――ビールの罐、懐中電灯、電球など――を題材にしたジョーンズの彫刻が、ポップ・アーティストの注意を商品に向ける呼び水になったのもまちがいなさそうだ。ところがポップの台頭と同時に、ジョーンズはそうしたオブジェの制作を止めてしまう。今から振り返ってみれば、作業現場に散らかった作品――汚れた床板、使いさしの絵筆、裸電球、アルコールやカフェインの名残り(1962年作《愚者の家》の箒とカップも忘れられない)—―から連想されるうらぶれたボヘミアン風のスタジオの様子は、大量生産や商業広告をにこやかに受け入れたウォーホールの「ファクトリー」やオルデンバーグの「ストア」とは好対照をなしていることがわかる。
ジョーンズは当初どうやらアメリカの社会生活のなかで、いつまでも中立的で変わることのないシンボルをいくつか求めようとしたらしい。ところがときはまさに国内の政治情勢、またとくに消費生活の変化が一段と速度を増す時期にあたっていた。星条旗の星の数は増え、商品のレッテルやロゴのデザインが変わり、息の長いブランド・ネームにも廃れたり改称されるものが現れた。不変と思われたものが次々と姿を消してゆくというこの感覚は、社会に流通している事物を拾いあげて、「ありふれた品々」の私的なイメージ構成をこしらえようという企図をジョーンズが断念する際にも一定の役割を果たしていたように思われるが、ポップ・アートに深い郷愁—―50年もレッテルのデザインの変わらない罐スープ、罐コーラ全盛時代のコカ・コーラの瓶、マディソン街の広告業界が雑誌のカラーページの隆盛に沸いた時代に生み出されたちっぽけで幼稚な宣伝の紙つぶてなど、かつてはありふれていたのに、今まさに消え去ろうとしているものに対する甲高く悲痛な哀歌――を呼び覚ます一因ともなった。一方、厳密に実寸を守るジョーンズのオブジェには無口で引っ込み思案な性質があり、これは美術の論理を敷衍しようとするポップの傾向とは水と油であったし、商品のイメージの作品化はただの二度(バランタイン・エールとサヴァラン・コーヒー)きりで終わらせているせいもあって、ジョーンズはポップ・アーティストの好む皮肉と感傷の安手の混淆からは超然とした位置を保っている。ポップのオブジェは取引を物語るのに対して、ジョーンズの作品は所有に関わる重要性を維持した。
ジョーンズがポップの父であることは、彼がミニマリズムの生みの親とされることとつねに対をなしている。魅了された対象が《旗》のイメージそのものか、あるいはイメージのあつかい方によって後継者たちの進路はふたてに分かれた。前者は客体そのものとみなす。かれらの目には、イメージを前面に打ち出しカンヴァスを隅から隅までうめつくしてしまうのは、通常の再現性を打ち消すことに等しいと映った。モリスが1969年に記したように、「ジョーンズほど絵画を非・描写の状態に近づけたひとはほかにいない。旗は描写よりむしろ複写に近い…ジョーンズは背景を絵画から追い出し、絵画をものとして抜き出した。背景は壁になる。それまで中立の立場を守っていたものが能動的になり、それまでのイメージがものになった」。
切迫したこの存在感、イリュージョンの空間との関連抜きに自立する全体性が、じつに多種多様なひとびとに鮮烈な刺戟を与えた。《旗》の縞からステラの1959年作のブラック・ペインティングへの受渡しが、直接的な点では最も顕著だとしても、ジョーンズは1960年代初めに登場したドナルド・ジャッドやダン・フレヴィンなど、内部の構成的な関係を排除し周囲の空間をじかに活性化させる道を探っていた彫刻家たちにも等しく影響を及ぼしている。ポップがジョーンズのとりあげた平凡な品物の身近で、些細な代用品から出発して、めまぐるしい世間のけばけばしさにのめりこんでいったように、もう一方のアーティストたちも認識の曖昧さに関わるジョーンズの作品を跳びこして、経験的な手応えのあるものへと突き進んだ。自分の描いた縞について、「目に見えるものが目に見えるもの」と述べたステラの名高い主張は、仲間のアーティストが言うように、ジョーンズを「見事に誤解」したもので、ジョーンズの作品が探ろうとした目と精神の間の微妙な緊張関係を、自信たっぷりに一掃したことになる。
こうした厳密なミニマリズム的な意味合いで、ジョーンズは明晰な思考に基づいて作品制作の過程から神秘的な要素をとりのぞくように促したとみることができる――ただし、もっと詳しく調べてみれば、表向きには素直な手ごたえを感じさせるジョーンズの作品にも、皮肉や疑念がまとわりついている。」カーク・ヴァーネドー「火――ジョーンズの作品はアメリカ人アーティストの目にどのように映り、用いられたか」(ニューヨーク近代美術館『ジャスパー・ジョーンズ展』カタログ)日本語版、読売新聞社発行、1996.pp.096-099.
アメリカの20世紀後半の美術シーンをふり返るとき、ジャスパー・ジョーンズという人の立ち位置は、「ポップの父」と呼ばれて当然ではあるが、それだけなら1960年代に終わったはずだ。ジョーンズより2歳年上のアンディ・ウォーホルは1987年2月に58歳で亡くなってしまったが、ジョーンズは87歳で今も生きている。20代はイラストレーターで働いていたウォ―ホルより美術界デビューはジョーンズの方が早かった。画家は短命な人もいれば、長生きする人もいるが、老齢まで現役で制作を続けたトップランナーは、ピカソそしてジョーンズではないか。それだけでも凄いな。

B.国家が強くなること
衆議院選挙の結果はほぼ自民党の圧勝、単独過半数達成という結果に終わりそうだ。加計・森友問題と都議選敗北でぐらついた基盤をリセットしたい安倍晋三の思惑通りの結果といえるだろう。これが日本の今後にどういう形で深く影響してくるか、やはり歴史に学ぶ必要があると思う。
戦前の日本には政党もあり選挙もあったが、政党以外にも貴族院やら元老院やらそして軍部という別個の権力があり、選挙権は国民の半分(女性)にはなかった。だから、一般の国民が敗ける戦争に突き進んでいったことへの責任は、国民大多数ではなく一部の権力をもっていた人々に責任が帰せられる、というのもある程度認められる議論だとは思う。もちろん鬼畜米英との戦争に喜んで協力したのも国民大衆の心情的支持があったからということも忘れてはいけない。
今を去る77年前の1940(昭和15)年10月大政翼賛会が発足した。前年1月に第1次内閣を総辞職した近衛文麿だったが、ヨーロッパで第2次世界大戦が始まり、東アジアの日中戦争も泥沼化するなかで、日本は強力な指導体制を形成する必要があるとする新体制運動が盛り上がり、その盟主として国民に人気のある近衛の再登板に期待が高まった。既成政党側でも近衛に対抗するよりもみずから新体制に率先して参加することで有利な立場を占めるべきだという意見が高まり、民政党総裁町田忠治と政友会正統派の鳩山一郎が秘かに協議して両党が合同する「反近衛新党」構想を画策したものの、民政党では永井柳太郎が解党論を唱え、政友会正統派の総裁久原房之助も親英米派の米内光政(海軍大将・前海軍大臣)を首班とし新体制運動に消極的な米内内閣の倒閣に参加して近衛の首相再登板を公言した。そのために合同構想は失敗に終わり、民政党・政友会両派(正統派・革新派)ともに一気に解党へと向かうことになった。右翼政党の東方会も解党し、思想団体「振東社」となった。近衛も米内内閣の後の第2次近衛内閣成立後にこの期待に応えるべく新体制の担い手となる一国一党組織の構想に着手する。なお、その際、近衛のブレーンであった後藤隆之助が主宰し、近衛も参加していた政策研究団体昭和研究会が東亜協同体論や新体制運動促進などをうたっていた。こうした動きの結果、大政翼賛会が発足し国民動員体制の中核組織となる。ようやく定着するかに見えた立憲君主制と二大政党政治が、ここであえなく崩壊した。日本の敗北崩壊まであと5年もなかったのだが、そのときは日本人の大多数はそんな未来は想像もしていなかった。
「安倍晋三首相(自民党総裁)は小雨が降る東京都千代田区の秋葉原駅前で最後の演説を行った。7月の東京都議選で「辞めろ」コールが起きた「トラウマ」の場所だが、連勝した直近4回の国政選挙で最後に街頭に立ってきた「験担ぎ」を優先。「アキバ」で人気のある麻生太郎副総理兼財務相が駆け付けたことも安心材料となったようだ。
「看板を変えたからって国民を欺くこと、だますことはできない」。首相は冒頭から、民主党政権で閣僚だった立憲民主党の公認候補を名指しで批判。その後も野党批判を軸に演説を続けた。解散に踏み切った理由として北朝鮮問題への対応と少子高齢化対策を挙げ、「将来に夢をもつことができる日本をつくる。日本を守り抜き、日本の未来を切り開くことができるのは私たち自民党だ」と訴えた。
麻生氏は株高や雇用増に触れ、「アベノミクスが正しかった。この政策に自信を持って続けていきたい」と主張した。
駅前は厳重警備で、夕方から日の丸の小旗や「安倍首相を応援しよう」などと書いたプラカードを手にした支持者らが集まった。自民関係者が支援者だけを前方に陣取らせるよう整理。一方で、「安倍9条改憲NO!」などのプラカードを掲げる聴衆は後方に多く、「うそつきな総理はいらない」とのヤジも飛んだ。」朝日新聞2017年10月22日朝刊2面総合欄。
安倍晋三は近衛文麿になるのか?そして、戦前日本に戻すような指向を滲ませた憲法を変えるという革命が、もうじき実現するのか?事態は往々にして思わぬ方向に展開してしまう。果たして近々に戦争が極東で起こるのかどうかは予断を許さないが、それよりもたぶん国内に深刻な亀裂が走るような気がする。安倍一強体制でなんでも通ってしまう政治が選挙で太鼓判を押されたとみんなが思えば、体制翼賛化がすすむのは避けられない。
いずれにしても、安倍晋三が目標とする「強い国家」とは何だろう?国家が強くなることは、ぼくたち国民にとってどういう意味をもつのか?それは単純にひとりひとりの幸福が増すことなのか?それとも「強い国家」のために国民は犠牲を払う価値などないのか?安倍自民党に強い指示を与えた投票有権者の多数は、「強い国家が自分たちを守ってくれる」と思ったのだろうが、この選挙への後世の人びとへの責任を自覚しているとはとてもいえない。
隣の国でも、「強い国家」を自慢し、世界への威力を誇示したい権力者が大きな声を出している。
「【北京=張勇祥】中国共産党の第19回党大会が18日午前9時(日本時間午前10時)、北京の人民大会堂で開幕した。習近平総書記(国家主席)に続き、江沢民元総書記、胡錦濤前総書記が入場した。李克強首相が開幕を宣言した。2012年に総書記に就任した習近平氏が、1期目である5年間の総括と今後の基本方針について演説した。党内の規律強化や脱貧困政策などの成果を誇示し、権力基盤の確立を国内外に強調する。最高指導機関である党大会の会期は24日まで。指導幹部である約200人の中央委員の選出や、党規約の改正などが主要議題となる。
焦点の党首脳人事については、中央委員が25日にも中央委員会第1回全体会議(1中全会)を開いて政治局員(現在は24人)を選び、そこから最高指導部である政治局常務委員(同7人)を決める。最高責任者である総書記は常務委員から選ぶ。党規約の改正については、習氏が掲げてきた政治思想や理念を明記して権威を高める見通し。「習近平思想」のように自身の名を冠した名称になれば、毛沢東氏や鄧小平氏に並ぶ権威を得ることになる。強力な権限を持つ毛沢東時代のポスト「党主席」を復活させる案も出ている。すでに別格の指導者を意味する「核心」の地位を手に入れている習氏が、さらなる権力集中を進められるか。習氏が望むとされる「3期続投」に向けた地ならしが進むかも注目点になる。
▼中国共産党大会 党の指導体制や基本方針を決める最高指導機関。5年に1度開き、指導幹部となる約200人の中央委員の選出や党規約の改正、重要な政策課題を討議する。第19回の今回は約8900万人の党員から選ばれた2280人の代表が出席する。大会冒頭で党トップの総書記が、過去5年間の中国を振り返り将来を展望する活動報告を読み上げ国家運営の基本方針を示す。大会閉幕直後に中央委員会第1回全体会議(1中全会)を開き政治局員(現在は24人)を選定。その中から最高指導部の政治局常務委員(同7人)を決め、常務委員の中から総書記を選ぶ。」日経新聞オンライン。
国家の強さは経済力と軍事力で他を圧倒しているかどうかで決まると習近平は考えている。そしていまや中国は、経済力にも軍事力にも主観的にはきわめて強い自信を持っているようだ。少なくとも経済力の乏しい弱小国家である北朝鮮が核兵器で大国アメリカに対抗しようとしている捨て身の冒険に比べれば、中国は実力をともなって世界への影響力を発揮し、日本など問題外とみなしているようだ。中国はぼろぼろの20世紀を否定して、栄光の中華思想を復活させたいのだろう。
あらためてぼくは思うのだが、国家と自分の関係をよく考えてみると、ぼくは確かにこの国に生まれて国籍ももっているのだが、国が強くなることも弱くなることもぼくとは何の関係もない。外国に行ってみると、確かに円が強いとちょっと買い物に有利だし、日本人だからと唾を吐かれたり罵倒されたりはしない。でも、そんなことはぼくという人間にはど~でもいいことだし、人間の質を見てくれる外国人にはぼくが日本人かどうかなんて、これもど~でもいいことだ。だから、日本という国家が経済力で衰弱しようが軍事力でもの足りなかろうが、そんなことは人間の生活にはど~でもいいことなのに、ど~してそんなに「強い国家」が必要だなんて思うのだろうか不思議だ。
確かにこの日本という国家が明治維新でできたとき、指導者は19世紀世界の情勢を見極めて、新しい国家が立ちゆくための知恵を絞った。その結果、ぼくたちは外国の植民地になることも内戦で分裂することも、経済破綻で崩壊することもなく、富国強兵を達成したけれども、昭和戦前期にあまりにも自己過信と軍事的妄想に溺れて、多大な犠牲と外国の占領という破滅を経験した。だからぼくはこう思う。ぼくらの前には今二つの別れ道がある。ひとつは昭和15年と同じことをくりかえす道で、「強い国家」ファーストの安倍自民党はそれを目指している。もうひとつの道は、「賢い国家」によってぼくたちの生命と生活の基礎を固めることを第一とする道だ。それは経済力と軍事力の強化を優先して世界に威張りまくる国にするのではなく、当たり前の人生を自分の意思で歩めるような社会を用意する国なのだ。















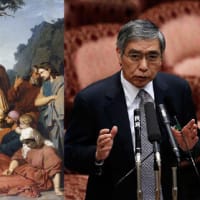










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます