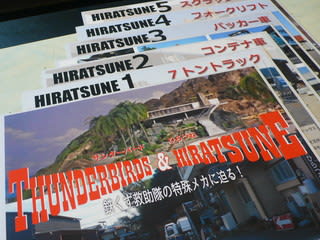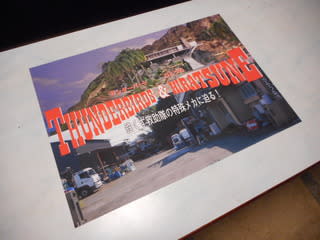こんばんは、室長です。
去る3月19日、山あげ会館にて開催された烏山マルシェに弊社が初出店しました♪

このマルシェは
昨年の同じ時期に開催されたマルシェの第2回目でして、今年もコンセプトにこだわっての開催です。参考までに、そのコンセプトを以下に書き出してみます。
あっさり捨てる消費の毎日から
質の良いものを選んで永く使う生活へ
今、身の回りにあるものや
日々、口に入れるものって
どんなものかよく考えてみる
何を選んで何に囲まれて生きていく?
烏山の暮らしをたのしくするマルシェ
そんな狙いにひらつねが相応しいのか若干自信がないものの、「質の良いもの→よく考えられたもの→廃棄時も考慮されたもの」と解釈して、生活を組成している素材とその資源リサイクルの現状を知ってもらう場を提供しようと、展示を中心とした出店を試みてみました!
とは言え、単なる展示だけだといかにも教科書的で堅苦しい気がしたので、少しばかり考えを巡らせてみました。
そこで、主役である①リサイクル図鑑をでーんとセンターに鎮座せしめ、奥では滞留の仕掛けとして②淹れ方にこだわった日本茶(緑茶)の販売をし、お客さんの目を引き付けるために③ちょっと変わった古物販売を前面に配するという、メインコンテンツ3本柱の構えでマルシェに臨みました。
まずは、これがその全景。

①リサイクル図鑑の様子。

素材は、鉄/アルミ/銅/紙/プラスチック/木/ガラス/繊維の8種類を選びました。
そして、各素材について
・資源名(実物展示)
・主な用途
・主原料と産出国
・自給率
・リサイクルの方法
・リサイクルの環境効率
・リサイクルされる比率
・リサイクル後の用途
・廃棄時点での価値
の内容を、テキストや写真、グラフ等で極シンプルに表現しました。
この順番は、
先のエントリーでも予告した、「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」に対応していまして、上記の項目は
・何者か:資源名(実物展示)/主な用途
・どこから来たのか:主原料と産出国/自給率
・どこへ行くのか:リサイクルの方法/リサイクル後の用途
とカテゴライズされています。
そしてデザインにも配慮した結果、一つ一つをカルタのような正方形のカード状に切り分け、トランプの「七並べ」のようにボード上に整然と並べてみました。
一覧性を持たせることで、タテ方向に見ればその素材(資源)の一生をたどることができ、ヨコ方向に見れば素材ごとの比較ができるという便利な(!)図鑑のようなものになりました♪
調べる過程で、それぞれの素材に深いストーリーがあるのですが、今回はデザイン上の要求から極限までそぎ落とす必要があったため、「リサイクル図鑑(抄)」というネーミングになった次第。
②続いて、日本茶の販売の様子。

ひらつねの筆頭茶師が腕を振るってくれました(笑)
二種類のお茶のうちいずれか一品について、3煎目まで堪能することができるというかなりお得なメニュー。
若い女性も喜んで味わってくれていたのは、意外ながらも嬉しい出来事でした♪
③そして、ちょっと変わった古物販売の様子。

古河のトロマル仕込み(にわか知識ですがw)の販売方式を導入してみたところ、やはり芝生と木と古物の相性は抜群!これで芝生が青ければ更に古物が映えたことでしょう~

手に取って見ていく人多数、実際に購入していく人少数ながらも、商工会祭りで出店している資源ライブラリー以上の反応の良さに、やはりマルシェ的なものとの相性の良さを再確認して得心した次第。
中には「ピタゴラスイッチ!」と喜んで手に取る子どもの姿も見られ、古物販売とは別のアクティビティへの活用へのヒントも得ることができました。
当日は天気にも恵まれ、会場全体も思った以上に賑わいを見せて、春の到来を思わせるマルシェでした。

動けば何か得られる——そんな感触を改めて得ることができたマルシェになりました。
お越しくださいましたお客さま、誘ってくださいました主催者の方、ありがとうございました!