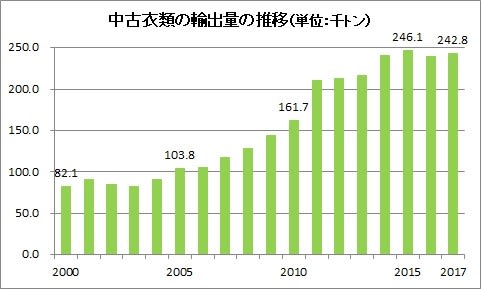こんにちは、室長です。
屑辞苑の第3回目に取り上げるのは「RPF」について。
なにかと便利なプラスチック製品。その手軽さと安さゆえ、用済み後はすぐに廃棄されがちですが、原油に由来することから都市油田にも見立てられることがある等、再生資源として見逃せない存在です。今回はその一つ、「RPF(固形燃料)」にスポットを当ててみます。
なお、産業廃棄物を原料とする固形燃料のことを業界では「RPF」(アール・ピー・エフ:Refuse Paper & Plastic Fuelの略)と呼んでいます。一般的にはあまり馴染みはありませんが、化石燃料の代替品として地味ながら活躍しています。
【RPF(固形燃料)】
――・とリサイクル
2015年、国内で一年間に廃棄される廃プラスチックの総量は915万トン(うち産業廃棄物の廃プラは480万トン)にものぼります。
そうした廃プラを処理・リサイクルする方法は、主に以下の4つに分類されます。
①マテリアルリサイクル
フレーク状や粒状に破砕して工業用品(パレット、建築資材等)の原料に再生利用する。
②ケミカルリサイクル
高温で熱分解して、合成ガスや分解油など化学製品の原料として再利用する。
③サーマルリサイクル
焼却して熱エネルギーを回収し、熱源や発電に活用する。または固形燃料の原料にする。
④未利用
熱回収されることもなく単純に焼却または埋立される。一番モッタイナイ!
RPFは製紙会社のボイラー燃料や発電用の燃料に主に利用されています。したがって、③サーマルリサイクルの一手法に整理されます。
――・の位置づけ
産業廃棄物由来の廃プラの処理実績を下表にまとめてみました。(データは『リサイクルデータブック2017』(一社)産業環境管理協会をもとに作成)
なお、比較用に一般廃棄物の処理実績も併載します。
〇産業廃棄物の廃プラリサイクル(2015年)

※参考:一般廃棄物の廃プラリサイクル(2015年)

廃プラ(産業廃棄物)のうち未利用は思いのほか少なく約13%にとどまり、大半がリサイクル=有効利用されていることが分かります。
注目すべき点として、再生利用(マテリアルリサイクル)が突出してスタンダードなリサイクル方法ではないということが挙げられます。むしろ発電・発熱の用に供するサーマルリサイクルが過半を占めているのです。
実は、選別や洗浄、輸送に多くのエネルギーとコストを費やして再生利用するより、シンプルに焼却して熱回収する方がトータルで環境負荷の低減につながるケースが多いということなのです。
スウェーデンは、年間約80万トンものごみを近隣諸国から輸入するという非常に珍しい国ですが、こちらも目的はズバリ「ごみ発電」のためなのだとか。
――・の勢力
上表の産業廃棄物のリサイクル実績のグラフは、国会の議席配分をなんとなく彷彿とさせるのでそれを例にとれば、リサイクル(マテリアル+ケミカル+サーマル)は連立政権与党、未利用は野党にたとえられます。
そして、中心与党たるサーマルリサイクルの最大派閥の領袖がRPFという図式とみると、その存在感が浮き彫りになるのではなかろうかと思います…(笑)
――・の特色
手持ちの画像がないのですが、実物は手のひらサイズのコロコロした形状で、道端に落ちているあるモノを連想させる独特の風貌をしています、、
産業廃棄物に由来することから、材質・品質が一定程度安定しているため、工業製品として大量生産されています。
元来が石油製品なので、石炭やコークスと同程度の熱量(カロリー)がある一方、CO2排出量が石炭に比して2/3に抑えられ、しかも安価という点が最大の利点として挙げられるでしょう。
――・の製造方法
細かい製造工程は割愛しますが、主原料となる軟質の廃プラや紙くず、木くずを破砕機で細かく切断し、それを成形機にかけて円筒形の固形燃料ができあがります。圧縮・成形の過程で熱を加えることでプラスチックが溶けて接着剤の役割を果たすのがミソのようです。
日本では約30年前に実用化されたこの技術。当時、急速に出回り始めたラミネート加工紙(プラ+紙)を単に焼却処分せずに有効にリサイクルできないかという悩みが、RPFという新燃料の開発につながったとされています。
その製造システムは開発者がドイツを訪れた際に目にした、“干し肉から鉛筆状のドッグフードを製造する装置”にヒントを得たそうです。この形状を見るにつけ「さもありなん」と思わされます(笑)
そのあたりの開発秘話はこちらが詳しいです。
――・の課題
いいことづくめのような技術ですが、塩素や油分、金属はNGで、とりわけ塩素はRPFを焼却する際にダイオキシンを発生させたり装置を腐食させたりするので、その選別が最大の課題とされています。
その辺の技術的な課題についてはこちらのNEDOの記事を参照ください。
いずれにせよ、「捨てればゴミ、生かせば資源」を体現している廃プラスチックのリサイクル。今後の更なる技術革新を要チェックですね!
[室長のまとめ]
RPFとは江戸時代の金肥(きんぴ)である。
※解説:近世(江戸時代)、農家が購入する肥料の代表として干鰯や酒粕がありましたが、都市部の長屋などから出るし尿も肥料として有価で取引される商品だったようです。その形(なり)や性質(廃棄物ながらもうまく加工すれば価値を持つ)はまさにRPFとそっくりではないかと思った次第。まぁ、その素朴な姿がやはりインスピレーションの源泉なのですが、、
屑辞苑の第3回目に取り上げるのは「RPF」について。
なにかと便利なプラスチック製品。その手軽さと安さゆえ、用済み後はすぐに廃棄されがちですが、原油に由来することから都市油田にも見立てられることがある等、再生資源として見逃せない存在です。今回はその一つ、「RPF(固形燃料)」にスポットを当ててみます。
なお、産業廃棄物を原料とする固形燃料のことを業界では「RPF」(アール・ピー・エフ:Refuse Paper & Plastic Fuelの略)と呼んでいます。一般的にはあまり馴染みはありませんが、化石燃料の代替品として地味ながら活躍しています。
【RPF(固形燃料)】
――・とリサイクル
2015年、国内で一年間に廃棄される廃プラスチックの総量は915万トン(うち産業廃棄物の廃プラは480万トン)にものぼります。
そうした廃プラを処理・リサイクルする方法は、主に以下の4つに分類されます。
①マテリアルリサイクル
フレーク状や粒状に破砕して工業用品(パレット、建築資材等)の原料に再生利用する。
②ケミカルリサイクル
高温で熱分解して、合成ガスや分解油など化学製品の原料として再利用する。
③サーマルリサイクル
焼却して熱エネルギーを回収し、熱源や発電に活用する。または固形燃料の原料にする。
④未利用
熱回収されることもなく単純に焼却または埋立される。一番モッタイナイ!
RPFは製紙会社のボイラー燃料や発電用の燃料に主に利用されています。したがって、③サーマルリサイクルの一手法に整理されます。
――・の位置づけ
産業廃棄物由来の廃プラの処理実績を下表にまとめてみました。(データは『リサイクルデータブック2017』(一社)産業環境管理協会をもとに作成)
なお、比較用に一般廃棄物の処理実績も併載します。
〇産業廃棄物の廃プラリサイクル(2015年)

※参考:一般廃棄物の廃プラリサイクル(2015年)

廃プラ(産業廃棄物)のうち未利用は思いのほか少なく約13%にとどまり、大半がリサイクル=有効利用されていることが分かります。
注目すべき点として、再生利用(マテリアルリサイクル)が突出してスタンダードなリサイクル方法ではないということが挙げられます。むしろ発電・発熱の用に供するサーマルリサイクルが過半を占めているのです。
実は、選別や洗浄、輸送に多くのエネルギーとコストを費やして再生利用するより、シンプルに焼却して熱回収する方がトータルで環境負荷の低減につながるケースが多いということなのです。
スウェーデンは、年間約80万トンものごみを近隣諸国から輸入するという非常に珍しい国ですが、こちらも目的はズバリ「ごみ発電」のためなのだとか。
――・の勢力
上表の産業廃棄物のリサイクル実績のグラフは、国会の議席配分をなんとなく彷彿とさせるのでそれを例にとれば、リサイクル(マテリアル+ケミカル+サーマル)は連立政権与党、未利用は野党にたとえられます。
そして、中心与党たるサーマルリサイクルの最大派閥の領袖がRPFという図式とみると、その存在感が浮き彫りになるのではなかろうかと思います…(笑)
――・の特色
手持ちの画像がないのですが、実物は手のひらサイズのコロコロした形状で、道端に落ちているあるモノを連想させる独特の風貌をしています、、
産業廃棄物に由来することから、材質・品質が一定程度安定しているため、工業製品として大量生産されています。
元来が石油製品なので、石炭やコークスと同程度の熱量(カロリー)がある一方、CO2排出量が石炭に比して2/3に抑えられ、しかも安価という点が最大の利点として挙げられるでしょう。
――・の製造方法
細かい製造工程は割愛しますが、主原料となる軟質の廃プラや紙くず、木くずを破砕機で細かく切断し、それを成形機にかけて円筒形の固形燃料ができあがります。圧縮・成形の過程で熱を加えることでプラスチックが溶けて接着剤の役割を果たすのがミソのようです。
日本では約30年前に実用化されたこの技術。当時、急速に出回り始めたラミネート加工紙(プラ+紙)を単に焼却処分せずに有効にリサイクルできないかという悩みが、RPFという新燃料の開発につながったとされています。
その製造システムは開発者がドイツを訪れた際に目にした、“干し肉から鉛筆状のドッグフードを製造する装置”にヒントを得たそうです。この形状を見るにつけ「さもありなん」と思わされます(笑)
そのあたりの開発秘話はこちらが詳しいです。
――・の課題
いいことづくめのような技術ですが、塩素や油分、金属はNGで、とりわけ塩素はRPFを焼却する際にダイオキシンを発生させたり装置を腐食させたりするので、その選別が最大の課題とされています。
その辺の技術的な課題についてはこちらのNEDOの記事を参照ください。
いずれにせよ、「捨てればゴミ、生かせば資源」を体現している廃プラスチックのリサイクル。今後の更なる技術革新を要チェックですね!
[室長のまとめ]
RPFとは江戸時代の金肥(きんぴ)である。
※解説:近世(江戸時代)、農家が購入する肥料の代表として干鰯や酒粕がありましたが、都市部の長屋などから出るし尿も肥料として有価で取引される商品だったようです。その形(なり)や性質(廃棄物ながらもうまく加工すれば価値を持つ)はまさにRPFとそっくりではないかと思った次第。まぁ、その素朴な姿がやはりインスピレーションの源泉なのですが、、