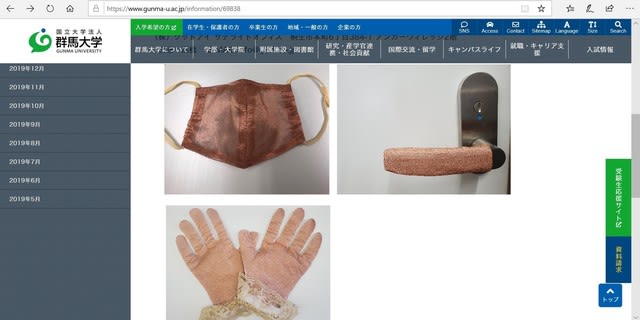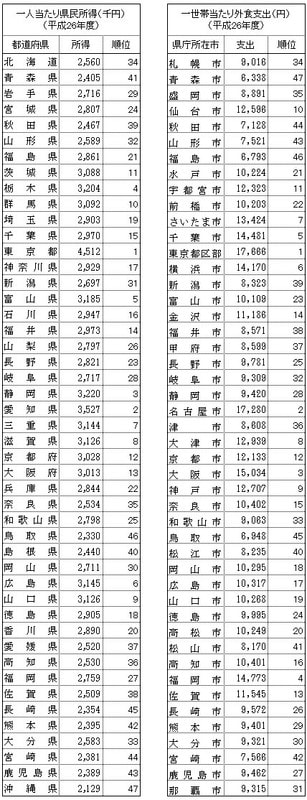室長です。
エントリーがかなり遅くなってしまいましたが、前回の続きです。最近気になるものづくり事例がいくつかあったのでそのまとめ。
①
大田ゲートウェイ(東京都大田区)
大田区は昔から関西の東大阪と並び、日本のものづくりの一大集積地です。
そんな「大田の技術・モノづくりのノウハウを集積し、次なる価値(NEXT VALUE)へ繋ぐ創造商社」というコンセプトのもと作られたのがこの大田ゲートウェイという会社。
とりわけ気になったのが「第一次産業との連携(工業による農漁業の効率化)により、生産性を劇的に向上させる」という企画の考え方です。
地方創生は前回のエントリーでも述べたように、農林水産業の成長産業化が大きな柱になっています。TPP締結という風も吹いており、農林水産業の一段の効率化は必須となっていくことでしょう。米国での農業はかなり大規模化・IT化されているようですし、ドイツや北欧の林業でも労働装備率(従業員一人あたりの設備額)は日本のそれを大きく上回っているらしいこと等を考えると、日本の農林水産業においても機械化を進めて作業効率を高めるという方向性は今以上に求められることでしょう。
そうした課題を先取りして、製品の企画・試作・製造を大田区の製造業の持つノウハウにてワンストップで対応可能な入口=ゲートウェイとして、総合商社ならぬ“創造商社”を機能させ始めているというのはなんとも良いではないですか!
今のところ開発した商品は漁業で用いる「船上さかな体重計」や「投縄機」のようですが、農業分野での開発も期待されるところですね~
②浜野製作所の
浜野プロジェクト(東京都墨田区)
同じく都内で大田区にひけをとらない小零細製造業の集積地である墨田区。
最近、地元・烏山の製造業者の方とお話していた際に教えてもらったのが浜野製作所というプレス屋さんでした。隣家で発生した火事のもらい火により同社の工場は全焼してしまったのですが、燃えゆく工場を見ながら社長は急いで不動産屋に駆け込んで代わりの工場を借りる手続きをして取引先の信頼を守り続け、その後見事に復活したという話にはとても驚いたものです。
気になったのでその後調べてみると、非常に面白い取り組みをしている会社でした(笑)
それが同社の掲げる「浜野プロジェクト」なるもの。
同プロジェクトのページでは、「浜野製作所では、産学官連携による新しい事業への進出、地域の工場資源を活用した環境・社会貢献活動、将来のものづくりを担う子供たちへの体験学習、デザイナーとの異業種コラボレーションなど、従来の下請け仕事をこなす町工場のイメージを超えた様々なプロジェクトを展開しています。」とのこと。
具体的には以下の取り組みをしています。
○Garage Sumida(ガレージスミダ)
これは同社が運営するものづくりの総合支援施設で、3Dプリンターやレーザーカッター、CNC加工機といった最新のデジタル工作機器を備え、町工場の設計や製造に携わる熟練した職人が個人から企業に至るまでの製品開発や加工を支援するものだそう。
モノづくりで起業したい、町工場の職人からアドバイスを受けたい、試作・開発のための工作機械を使いたい、作業としてのガレージスペースが必要…といった需要にこたえるための新しいものづくりの創出拠点となりそうです。
いかにものづくり(製造業)を身近に感じてもらい、いかにスタートアップのハードルを下げることができるか。そうした喫緊の課題に向き合って出した一つの解という気がします。
非常に刺激を受ける取り組みです。
○
配財プロジェクト
墨田区には、約2500ものモノづくり企業があるそうです。どの製造現場でもそうですが、それらの企業の製造工程では、様々な素材(皮革、木工、ウレタン、メッキ、紙、ガラス、繊維、ゴム、プラスチック、金属など)が扱われ、様々な加工がなされて様々な製商品が生まれています。
そんな中で「これらモノづくり企業に共通の課題が、どの業種でも必ず製造過程で発生してしまう「廃材」の廃棄です。産業廃棄物として廃棄するだけの「廃材」を、もっとECOで楽しくポジティブに活かしてゆくことはできないか!?」という問題意識のもと、若手後継者を中心に、“配財プロジェクト”が結成された経緯があるそうです。
これなんかは弊社の事業領域とモロにかぶる分野でして、個人的にこうした方向性のアイデアは温めているところなので非常に参考になります。むしろ先にやられてしまっているではないかと少々悔しい思いもあったりします。
同プロジェクトのサイトによれば、廃材を使って製作した万華鏡などのものづくり体験ワークショップ、墨田区の工場を巡るスミファ、その他にも展示会企画や商品企画・デザイン、企業のCSR サポートなど、配財を通して様々な事業に取り組んでいるようです。
中でもスミファ(すみだファクトリーめぐり)なんかは、少し前の
当ブログ(燕三条の「工場の祭典」に関するもの)でも触れたような「工場を見せる」取り組みでして、とても面白そうなプロジェクトです。
時間と距離さえ気にしなければ是非とも参加したいものです♪
他にも、電気自動「HOKUSAI」の開発や深海探査艇「江戸っ子1号」の開発等も行なっており、主業の他によくこれだけのプロジェクトを広げられるものだなと感心してしまいます。。火事の際の対処同様、経営者のパワフルさには脱帽です!真似できそうにありませんが…
③諏訪市の
DTF(長野県諏訪市)
とある工作をしている最中、塗装の際に下に敷いていた新聞紙(日本経済新聞)の記事が目に留まりました。2015年9月7日付の一面の特集記事で「新・産業創世記 消える垣根」という記事です。
GEやセンサーといった単語から「あぁ、またIoTがらみのネタか」と思ったものの、「工場は机の上」という大きな文字が気になりよく読んでみたところ、デスクトップファクトリー(DTF:Desk Top Factory)という日本の製造業のユニークな取り組みを取り上げていました。
新聞の記事とは表現が異なりますが、
ウェブ版に同じような内容がアップされていたので全掲してしまいます。
---------------------------------
○机の上に「工場」 変幻自在のカスタマイズ対応
ものづくりの世界は大量生産を前提としたメカニズムが働いてきた。IoT(モノのインターネット化)によってもたらされるのは「マスカスタマイゼーション(個別型大量生産)」。色やサイズ、性能などすべてを顧客の望み通りにかなえ、たった1個の受注生産でも利益を稼ぐ。設備や投資力が十分でなくても、競争力が高い製品を生み出せるチャンスがある。アイデアや技術力次第で、零細の組織であっても産業の脇役から主役になれる時代が到来する。
高い技術力を誇る中小メーカーが集積する長野県・諏訪地域で、そうしたIoT規格の生産ラインが完成に近づく。精密部品加工の高島産業(長野県茅野市)や精密板金加工の平出精密(長野県岡谷市)などの中小企業が中心となりプロジェクトを進める。
「デスクトップファクトリー(Desk Top Factory=DTF)」と名づけ、卓上サイズの小型の設備機械の開発に取り組む。「手のひらほどの大きさの部品で、数千万円もする巨大な工作機械を使うのはもったいない」(高島産業常務の遠藤千昭=61)。デスクトップファクトリーは消費電力が10分1程度ですみ、生産コストを圧縮できる。
これまで独ボッシュ、デンソー、セイコーエプソン、YKKなど国内外の大手企業がメンバーになり、理想ラインのアイデアを出してきた。「超小型、超軽量ラインこそ、IoT時代に対応できる」(同上)
ブロック玩具「レゴ」のように組み合わせ自由にした。「切削」「研磨」「加工」「組み立て」や「検査」など異なる機能を持つ設備を合体させる。これらの5台のマシンを並べたとしても3メートルほどと短い。1個の部品をつくる場合には「組み立て」マシンだけを使い、「研磨」「加工」が必要になれば3台をセットするといったように変幻自在。30分あれば異なる部品を製造できるラインに早変わりし、受注量が増減しても低コストでこなす。
○海外で人だかり 「3メートルライン」の実力
2014年秋にフランスで開かれたナノテクノロジー関連の展示会に出展し、海外で3メートルラインの実力を初披露した。金属を削ってメッキ加工して「コマ」のかたちにし、表面に微細な文字を刻印するデモを公開した。1分ほどで直径1センチの円に「DTF Suwa Nagano Japan」と刻む離れ業に、現地のエンジニアらの人だかりができた。
高島産業の遠藤は「IoTはソフト面ばかり注目されがちだが、現状では生産設備のハード面でまったく追いついてない」と商機を見いだす。DIY(日曜大工)の延長のようなスケールのラインだが、産業構造を様変わりさせる可能性を持つ。
---------------------------------
このDTFが開発されているエリアもやはり、かつて“東洋のスイス”などと言われた精密工業の集積地です。
そんな土壌で生き抜いてきた企業群が共同でDTFを開発し、机の上に乗るくらい小さな機械や工場で
1.小さなものを、小さな機械や工場で合理的に生産する。
2.短い納期と低コストですばやく形にする。
3.大量生産ではなく多品種変量の生産を行う
4.小さな工場や機械を実現し、最適な場所で生産することで、ユーザーとの連携を高め豊かで創造的な価値を生み出す。
ことによって、日本の「新しいものづくりのやり方」を拓いていこうとしていることに大きなヒントを感じずにはいられません。
ものづくりに関するこれら3つの先行事例から様々なサジェスチョンが得られ、同時に雑多なアイデアがモヤモヤと生まれてきました。
そこでモヤモヤの簡単なまとめ。
・今後の成長分野と製造業との親和性及び伸びしろを探る必要性がある。
・ニーズやシーズを探ることが重要。つまり企画開発の分野。
・その際、個社では対応不可能な場合「ゲートウェイ」的な共通の入口=商社機能が有効か。
・一方、製造業の集積地では、ものづくり分野における起業者の確保も重要。(後継者、優秀な人材確保、多様性etc)
・そのための側面支援にもやはり上記のゲートウェイ的機能を持つ受け皿が欲しいところ。
・日本のこれからのものづくりのカギを「マスカスタマイゼーション(個別型大量生産)」に求めるとすると、そのためのハードウェアの整備が必要。
・逆に言えば、DTF的な技術であれば、創業時のハードルはぐんと下げられる。
⇒マスカスタマイゼーション×起業者の誘致×商社機能(情報収集や企画開発)
意味不明ですが、とりあえずモヤモヤのまましばらく寝かせておくことにしたいと思います。
それにしてもこれらの事例を実際に見てみたいものです。