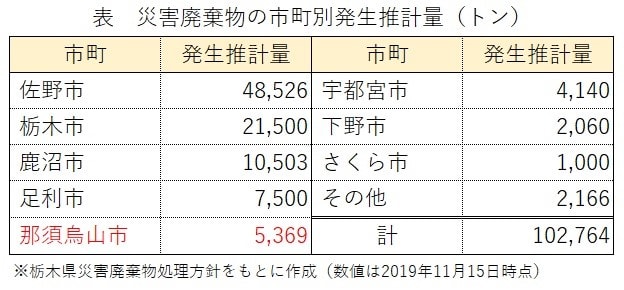室長です。
前回のエントリーでオンラインのウェビナー受講について話題にしました。そのウェビナーというのは、栃木県のコンサル会社「サクシード」による「ポストコロナを生き抜く術!【実践】強い会社の「人を大切にする経営」出版記念講演」というセミナーでした。
「ポストコロナで中小企業の価値が高まる」という文言に誘われ、思い切って参加してみた次第です。
途中、アクシデントで最後まで参加できませんでしたが、備忘録的に概要やキーワードを以下に記したいと思います。
〇ポストコロナで中小企業の価値が高まる
“社会のあらゆる場所に潜む見えない敵”が意識されるようになった
→小回りの利く中小企業が有利な環境と言える
〇デービッド・アトキンソンの生産性にまつわる言説について、規模だけが全ての解決策ではない
〇心の生産性(=心理的安全性)
〇錦の御旗となるべき経営理念の存在
〇全国一律のオペレーションは過去のものになる
〇ビジネスモデルの再構築
→ヒトとカネ…人を大切にする経営理念が重要
〇今後の人を大切にする経営のキーワード
・自立型、研究開発型(=市場創造型)
・腹八分目経営
・価格競争をしない
・製販一体にする→付加価値を高める
・多品種少量への対応
・情報の活かし方…収集+分析+加工+発信
・家族的経営
・社会課題を担う存在
〇デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した超優良企業の存在
・ふらここ(ひな人形)
→現代のニーズに沿った商品開発、ウェブでの販促
・マコセエージェンシー(会葬礼状)
→分業による即納体制、ITを使った作業の見える化
・カンセイ工業(区画線施工)
→AIによる自動配車
・スーパーまるおか(スーパー)
→こだわりの商品だけしか扱わない(6,000アイテムのうちナショナルブランドなし)
・アドバンティク・レヒュース(産廃収集運搬)
・セリオ(岡山県)のMEBO(Management and Employee Buyout)
・ばんどう太郎
〇子どもの数は「人を大切にする経営」で増やすことができる
90分のセミナーはあっという間で、普通の講演を聞いているのとさほど変わらない感覚でした。ただ、カメラオンでの参加でしたので、自分自身の姿やしぐさが画面を通して目に入り、鬱陶しかった感はありますが(苦笑)
特に印象に残ったキーワードは下線を引いた箇所。
錦の御旗となるべき経営理念が重要とのことで、これは今年2月の商工会青年部のセミナー時に取り組んだ「100年企業を見据えた自社のミッションを言語化する」という課題意識に沿うもので、課題設定の方向性はやはり正しかったのだなと再認識することができ、心強く感じました。
また、「腹八分目経営」は、室長的な言葉で言い換えれば「バッファ経営」(経営上、“余白・余裕”を意図的に設けること)と重なるところが多分にあると思われます。
情報の収集、分析、加工、発信の4段階は今後の営業戦略に是非とも使いたいところ。
久しぶりにセミナー的なものに参加しましたが、やはり有意義ですね♪
ちなみに、コロナが落ち着いたら、高崎にあるスーパーまるおかには是非とも買物に行ってみたいものです!
前回のエントリーでオンラインのウェビナー受講について話題にしました。そのウェビナーというのは、栃木県のコンサル会社「サクシード」による「ポストコロナを生き抜く術!【実践】強い会社の「人を大切にする経営」出版記念講演」というセミナーでした。
「ポストコロナで中小企業の価値が高まる」という文言に誘われ、思い切って参加してみた次第です。
途中、アクシデントで最後まで参加できませんでしたが、備忘録的に概要やキーワードを以下に記したいと思います。
〇ポストコロナで中小企業の価値が高まる
“社会のあらゆる場所に潜む見えない敵”が意識されるようになった
→小回りの利く中小企業が有利な環境と言える
〇デービッド・アトキンソンの生産性にまつわる言説について、規模だけが全ての解決策ではない
〇心の生産性(=心理的安全性)
〇錦の御旗となるべき経営理念の存在
〇全国一律のオペレーションは過去のものになる
〇ビジネスモデルの再構築
→ヒトとカネ…人を大切にする経営理念が重要
〇今後の人を大切にする経営のキーワード
・自立型、研究開発型(=市場創造型)
・腹八分目経営
・価格競争をしない
・製販一体にする→付加価値を高める
・多品種少量への対応
・情報の活かし方…収集+分析+加工+発信
・家族的経営
・社会課題を担う存在
〇デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した超優良企業の存在
・ふらここ(ひな人形)
→現代のニーズに沿った商品開発、ウェブでの販促
・マコセエージェンシー(会葬礼状)
→分業による即納体制、ITを使った作業の見える化
・カンセイ工業(区画線施工)
→AIによる自動配車
・スーパーまるおか(スーパー)
→こだわりの商品だけしか扱わない(6,000アイテムのうちナショナルブランドなし)
・アドバンティク・レヒュース(産廃収集運搬)
・セリオ(岡山県)のMEBO(Management and Employee Buyout)
・ばんどう太郎
〇子どもの数は「人を大切にする経営」で増やすことができる
90分のセミナーはあっという間で、普通の講演を聞いているのとさほど変わらない感覚でした。ただ、カメラオンでの参加でしたので、自分自身の姿やしぐさが画面を通して目に入り、鬱陶しかった感はありますが(苦笑)
特に印象に残ったキーワードは下線を引いた箇所。
錦の御旗となるべき経営理念が重要とのことで、これは今年2月の商工会青年部のセミナー時に取り組んだ「100年企業を見据えた自社のミッションを言語化する」という課題意識に沿うもので、課題設定の方向性はやはり正しかったのだなと再認識することができ、心強く感じました。
また、「腹八分目経営」は、室長的な言葉で言い換えれば「バッファ経営」(経営上、“余白・余裕”を意図的に設けること)と重なるところが多分にあると思われます。
情報の収集、分析、加工、発信の4段階は今後の営業戦略に是非とも使いたいところ。
久しぶりにセミナー的なものに参加しましたが、やはり有意義ですね♪
ちなみに、コロナが落ち着いたら、高崎にあるスーパーまるおかには是非とも買物に行ってみたいものです!