
50年間もろう運動を続けてこられた水上氏の叙勲の祝賀会があった。
現在の聴覚障害者の福祉、難聴者の福祉も含めてこうした活動の上にあることを実感した。祝賀と感謝をしたい。
また、過去のろう運動の歴史の知らなかった部分、隠されていた部分が学べたのはもう一つの収穫だった。
記念品の代わりに、氏の活動を記したものが配られるとのことだ。さらに学んだことを難聴者の福祉にも生かそう。
同じ聴覚障害者同士でコミュニケーション出来るのは意識のレベルが高まる。
難聴者の運動は、磁気ループの利用、要約筆記の出現とともに始まった。それは手話を学ぶ機会も意義も知らなかった難聴者が集団的な討議ができるようになったからだ。
同じテーブルの難聴者に、難聴者は話せるし、書けるのに、同じ難聴者同士が話ができない。だから難聴者の手話は話し言葉と同じで、筆談は書き言葉でコミュニケーションするのではと話すと、健聴者に書いて下さいといっても快く思われないのはなぜかと聞かれた。
書くことと話すことは同じ日本語でもモードが違うので負担が重い。話すようには書けないのだ。どうしても書記言語になる。
難聴者のコミュニケーションの綿密な分析は大事だ。間違った理解では社会に広がらない。
ラビット 記
現在の聴覚障害者の福祉、難聴者の福祉も含めてこうした活動の上にあることを実感した。祝賀と感謝をしたい。
また、過去のろう運動の歴史の知らなかった部分、隠されていた部分が学べたのはもう一つの収穫だった。
記念品の代わりに、氏の活動を記したものが配られるとのことだ。さらに学んだことを難聴者の福祉にも生かそう。
同じ聴覚障害者同士でコミュニケーション出来るのは意識のレベルが高まる。
難聴者の運動は、磁気ループの利用、要約筆記の出現とともに始まった。それは手話を学ぶ機会も意義も知らなかった難聴者が集団的な討議ができるようになったからだ。
同じテーブルの難聴者に、難聴者は話せるし、書けるのに、同じ難聴者同士が話ができない。だから難聴者の手話は話し言葉と同じで、筆談は書き言葉でコミュニケーションするのではと話すと、健聴者に書いて下さいといっても快く思われないのはなぜかと聞かれた。
書くことと話すことは同じ日本語でもモードが違うので負担が重い。話すようには書けないのだ。どうしても書記言語になる。
難聴者のコミュニケーションの綿密な分析は大事だ。間違った理解では社会に広がらない。
ラビット 記










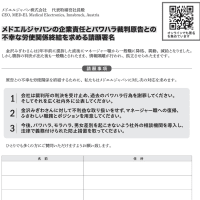

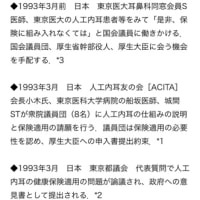






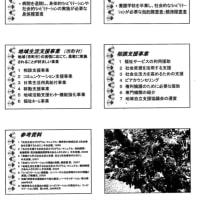
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます