この記事は何を言いたいのかよく分からない。
人工内耳の乳幼児の装用に反対する団体とは?欧米では反対の主張は沈静化しつつあるが日本ではまだ影響があると言うことか?
Googleのアラートは一部分のみ引用するので気をつけないといけない。
Karen Nakamura氏には何度か会ったことがある。
障害者の権利条約を審議していた国連のアドホック委員会で。文化人類学者だ。
ラビット 記
=== 「人工内耳」の Google ウェブ アラート ===
人工内耳@モバウィキ
>乳幼児への人工内耳手術に対する議論とその鎮静化 ...
とはいえ、黒田が報告した日本における事例においては、近年でもなお聴覚障害児の保護者が人工内耳装用について検討する際、乳幼児への人工内耳装用に反対する団体の問題が考慮されているという 黒田、前掲書、142?145ページ 。....
http://www.mbga.jp/.pc/mbkwd_word/%90l%8DH%93%E0%8E%A8?curp=8
※元をたどってみると以下の内容だったが・・・
「人工内耳」とは
[ ▼目次 | ▼関連 ]
→次へ(6 脚注・出典)
←前へ(4 人工内耳の利用状況)
■記事
5 乳幼児への人工内耳手術に対する議論とその鎮静化
アメリカではろう者(Deaf People)の権利獲得運動が公民権運動の影響を受けて展開された為、ろう者集団を一種の少数民族として表象するという戦略が採られたKaren Nakamura, Deaf in Japan, Cornell University Press, 2006, p9。
その為、アメリカのろう運動や、アメリカのろう運動の影響を受けた人々は、ろう者を障害者ではなく「手話という独自の言語とろう文化をもった民族」と位置づけることとなった。
この結果、人工内耳、特に自己決定できない乳幼児への人工内耳手術に対する強力な反発が、「黒人の子供を医学によって白人に変えるようなものである」「文化的民族浄化である」というような論理を伴って生起した。
しかしながら、多くの先進国では聴覚障害児の親の大多数が人工内耳の手術を選択するという現実(医療費の大半が民間の保険で賄われるアメリカでは所得水準の高い親たちが人工内耳の選択を行う割合が大きいと言われる。
とはいえ、黒田が報告した日本における事例においては、近年でもなお聴覚障害児の保護者が人工内耳装用について検討する際、乳幼児への人工内耳装用に反対する団体の問題が考慮されているという黒田、前掲書、142?145ページ。
欧米においては、乳幼児に対する人工内耳手術の定着等に伴い、ここ数年の間で、上記のような議論自体が鎮静化しつつあるとされる。
-----------------
sent from W-ZERO3
人工内耳の乳幼児の装用に反対する団体とは?欧米では反対の主張は沈静化しつつあるが日本ではまだ影響があると言うことか?
Googleのアラートは一部分のみ引用するので気をつけないといけない。
Karen Nakamura氏には何度か会ったことがある。
障害者の権利条約を審議していた国連のアドホック委員会で。文化人類学者だ。
ラビット 記
=== 「人工内耳」の Google ウェブ アラート ===
人工内耳@モバウィキ
>乳幼児への人工内耳手術に対する議論とその鎮静化 ...
とはいえ、黒田が報告した日本における事例においては、近年でもなお聴覚障害児の保護者が人工内耳装用について検討する際、乳幼児への人工内耳装用に反対する団体の問題が考慮されているという 黒田、前掲書、142?145ページ 。....
http://www.mbga.jp/.pc/mbkwd_word/%90l%8DH%93%E0%8E%A8?curp=8
※元をたどってみると以下の内容だったが・・・
「人工内耳」とは
[ ▼目次 | ▼関連 ]
→次へ(6 脚注・出典)
←前へ(4 人工内耳の利用状況)
■記事
5 乳幼児への人工内耳手術に対する議論とその鎮静化
アメリカではろう者(Deaf People)の権利獲得運動が公民権運動の影響を受けて展開された為、ろう者集団を一種の少数民族として表象するという戦略が採られたKaren Nakamura, Deaf in Japan, Cornell University Press, 2006, p9。
その為、アメリカのろう運動や、アメリカのろう運動の影響を受けた人々は、ろう者を障害者ではなく「手話という独自の言語とろう文化をもった民族」と位置づけることとなった。
この結果、人工内耳、特に自己決定できない乳幼児への人工内耳手術に対する強力な反発が、「黒人の子供を医学によって白人に変えるようなものである」「文化的民族浄化である」というような論理を伴って生起した。
しかしながら、多くの先進国では聴覚障害児の親の大多数が人工内耳の手術を選択するという現実(医療費の大半が民間の保険で賄われるアメリカでは所得水準の高い親たちが人工内耳の選択を行う割合が大きいと言われる。
とはいえ、黒田が報告した日本における事例においては、近年でもなお聴覚障害児の保護者が人工内耳装用について検討する際、乳幼児への人工内耳装用に反対する団体の問題が考慮されているという黒田、前掲書、142?145ページ。
欧米においては、乳幼児に対する人工内耳手術の定着等に伴い、ここ数年の間で、上記のような議論自体が鎮静化しつつあるとされる。
-----------------
sent from W-ZERO3










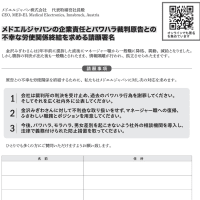

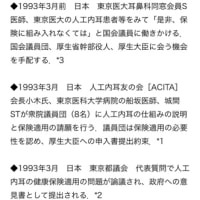






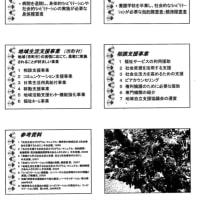
逆にいえば、身体障害者手帳を所持するろう者は、「ろう民族」に属しない、ということになります。
所得税等の控除はできないし、障害基礎年金を受給することもできないというのでは、「ろう民族」は経済的にタイヘンですね。