
難聴者協会の例会で、参加者同士でゲームやおしゃべりタイムなど交流、寺社巡りや施設見学などの野外レクリエーションをが行われる。
これはどこの協会でも行っていて、参加者がみな楽しめるように担当者は内容や情報保障、安全などに神経を使って準備する。
これは、国や行政等への交渉や権利拡大の福祉活動ではない「遊び」、「レク」などして、重要視しない活動かもいるようだが、これは間違っている。
難聴者や中途失聴者の「交流」こそは、リハビリテーションそのものであり、社会参加の重要な場でもある。
集団で交流するには、コミュニケーションが必要だ。一人一人に磁気ループや要約筆記、手話、筆談などでコミュニケーションを確保すること、相手の反応を見ながら対話する。
要約筆記に書かれたものを見て、今の話題をつかみ、自分の話したいことを整理して、言葉を発する。
さらに交流する中でコミュニケーション成就体験を蓄積し、失われた人との関係を復活させる。
介護施設では、レクリエーションが重要な介護技術として一人一人にあったレクリエーションが提供される。たとえ寝た切りであっても部屋に花を飾る、カーテンを変えるなどもレクリエーションとされる。レクリエーションは生活の活性化のことだからだ。
もっと深めたい。
ラビット 記
これはどこの協会でも行っていて、参加者がみな楽しめるように担当者は内容や情報保障、安全などに神経を使って準備する。
これは、国や行政等への交渉や権利拡大の福祉活動ではない「遊び」、「レク」などして、重要視しない活動かもいるようだが、これは間違っている。
難聴者や中途失聴者の「交流」こそは、リハビリテーションそのものであり、社会参加の重要な場でもある。
集団で交流するには、コミュニケーションが必要だ。一人一人に磁気ループや要約筆記、手話、筆談などでコミュニケーションを確保すること、相手の反応を見ながら対話する。
要約筆記に書かれたものを見て、今の話題をつかみ、自分の話したいことを整理して、言葉を発する。
さらに交流する中でコミュニケーション成就体験を蓄積し、失われた人との関係を復活させる。
介護施設では、レクリエーションが重要な介護技術として一人一人にあったレクリエーションが提供される。たとえ寝た切りであっても部屋に花を飾る、カーテンを変えるなどもレクリエーションとされる。レクリエーションは生活の活性化のことだからだ。
もっと深めたい。
ラビット 記










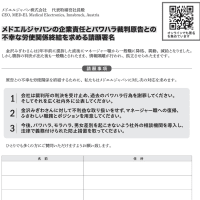

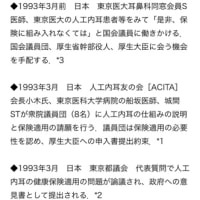






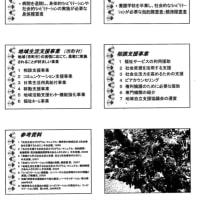
いや、西洋の例を持ちだすまでもなく、日本でも「遊びをせんとや生まれけむ」云々の俗謡がありますしね。
肩肘をはって理論化する前に、何をもって自分の遊びとするか、から出発すると、着実な議論が展開できるでしょうね。
投稿の趣旨は、遊びやレクリエーションを福祉活動より一段と下に見る活動家を諭そうとしたものです。
東京の協会では、高齢難聴者生きがい講座で手話と読話を学びながら、交流しています(交流しながら学んでいるの方が
正しいかも)。おしゃべりタイムも時間たっぷりと取って行っています。
大勢の高齢者が毎週、継続的に参加しています。遠方からも参加されるのですが、ほとんどデイサービス状態です。
また、もっと手話や読話以前の高齢難聴者に対しては「手を動かそう会」も行っており、手と口を動かすゲーム、遊び状態です。
どちらも要約筆記をつけた運営もノウハウが蓄積されています。
参加者は、地域のデイサービスや老人クラブの集まりには参加できない難聴者ばかりです。
これをきちんと事業として位置づけるために、レクリエーションとリハビリテーションの考えを取り入れる必要があるかと考えています。