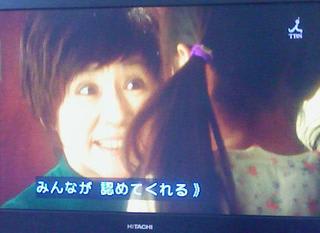「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(「地域主権改革法案」)は、財源の使途、基準も地方に委ねるとしている。
障害者自立支援法の地域生活支援事業は裁量的事業とされていて、コミュニケーション支援事業など地域格差が拡大している。
要約筆記者派遣事業も東京都みたいに市町村事業としてしまっては派遣の対象も範囲も格差が拡大するばかりだ。
5月12日にJDFが開いた「地域主権改革法」の学習会では、「地域主権が地方行政主権であってはならない、今こそ地域住民主権の確立を」が現在の学習の到達点と意志統一した。
「三位一体改革→障害者自立支援法の応益負担など、新自由主義の流れが、大きく障害者分野にもかぶってきています。」
JDF各団体動きは速く、日本障害者協議会(JD)、DPI日本会議、全国脊髄損傷連絡協議会などでは、団体決議に動いています。
JDFで検討中の要望書から。
「4.「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」について、内容をさらに精査し、障害者の人権・尊厳を確保するものとしていただきたい。
障害者自立支援法の改正において、人権に直結する運営基準は「従うべき基準」、その他の運営基準は「参酌基準」となっている。「参酌基準」の中には「居室定員4人以下」など、明らかに人権に直結する項目も含まれており、劣悪処遇への後退が懸念される。人権尊重の観点から、これを担保する仕組みが必要である。障害者施設における人員配置、居室面積、居室定員などについて実態把握のための調査が必要であり、実施を求める。」
ラビット 記
障害者自立支援法の地域生活支援事業は裁量的事業とされていて、コミュニケーション支援事業など地域格差が拡大している。
要約筆記者派遣事業も東京都みたいに市町村事業としてしまっては派遣の対象も範囲も格差が拡大するばかりだ。
5月12日にJDFが開いた「地域主権改革法」の学習会では、「地域主権が地方行政主権であってはならない、今こそ地域住民主権の確立を」が現在の学習の到達点と意志統一した。
「三位一体改革→障害者自立支援法の応益負担など、新自由主義の流れが、大きく障害者分野にもかぶってきています。」
JDF各団体動きは速く、日本障害者協議会(JD)、DPI日本会議、全国脊髄損傷連絡協議会などでは、団体決議に動いています。
JDFで検討中の要望書から。
「4.「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」について、内容をさらに精査し、障害者の人権・尊厳を確保するものとしていただきたい。
障害者自立支援法の改正において、人権に直結する運営基準は「従うべき基準」、その他の運営基準は「参酌基準」となっている。「参酌基準」の中には「居室定員4人以下」など、明らかに人権に直結する項目も含まれており、劣悪処遇への後退が懸念される。人権尊重の観点から、これを担保する仕組みが必要である。障害者施設における人員配置、居室面積、居室定員などについて実態把握のための調査が必要であり、実施を求める。」
ラビット 記