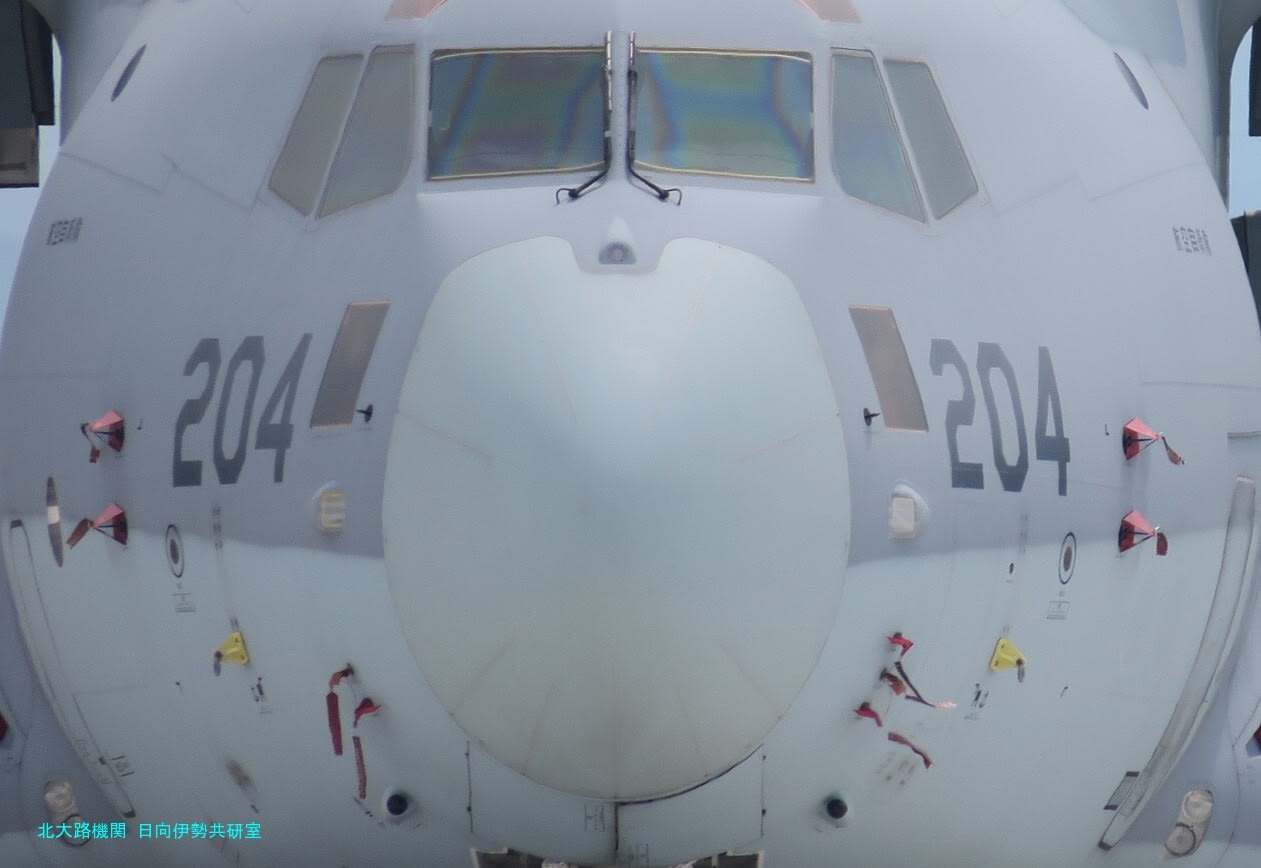■臨時情報-知床沖遭難事故
北海道の知床観光船KAZU-Ⅰが4月23日、遭難しました。これは旅客船の事故では令和時代に入って最大の船舶遭難事故となる懸念があります。なんとか生存者を期待したい。

KAZU-Ⅰは排水量19tの観光船であり定員は30名、乗員乗客26名が乗船していました。小型船である為にAIS船舶位置表示装置はなく救助は難航している。事故は23日、知床半島周遊観光船KAZU-Ⅰが1000時に知床半島のウトロ港を出航しました、当初予定では40km先の知床岬まで航行し往復するという三時間の航路でした。しかし、ここに事故が発生しました。

カシュニの滝、1313時にKAZU-Ⅰより運航会社に対し“沈みかけている”という無線連絡を発しました。そしてその五分後に当る1318時、ウトロ港から25kmほど先のカシュニの滝付近をにおいて、“船首が浸水”“エンジンが使えない”という通信と救助要請が出されました。そして1400時頃、“船体が30度傾斜している”との無線連絡があったとのこと。

船体が30度傾斜している、これが最後の通信となりました。もともとは往復80kmの航路を1300時までに往復する行程だったとのことですが。海上保安庁と警察、そして北海道知事からの要請を受け航空自衛隊が出動しましたが、日没までに遭難位置を確認できず、24日の日曜日に入り10名が心肺停止で救助、死亡が確認されました。現在も生存者はなし。

知床岬、要救助者が心肺停止で発見されたのは遭難信号が発せられたカシュニの滝から、更に14km離れた知床岬付近で発見されたとのこと。国土交通省によれば23日1300時頃の現場は、風が北西の風16.4mと強く、波浪は2mから3m、海水温は2度から3度となっています。生存者を祈りたいものですが、海水温が3度では30分ほどで低体温症になる。

何が在ったのか。原因究明が待たれますが、KAZU-ⅠはFRP製船体であり、気になる情報として2021年に漂流物との衝突により負傷者が出る事故、そして座礁事故を起こしているという情報、また、他の事業者からの目撃情報として船首付近の2m程度の位置に15cmほどの亀裂が在った、という証言です。すると、FRP製船体特有の問題が思い浮かぶのです。

FRP製船体は、亀裂が入りますと補修テープを貼る程度の応急措置以外は亀裂が広がる難点があります、鋼製船体のように破損個所を溶接して塞ぐ事が出来ませんし、木造船体の様に浮力もありません。例えば海上自衛隊も掃海艇を木造船体から最近のFRP船体に切替える際に、このFRPの特性が触雷時のダメージコントロールへ影響が懸念されていました。

原因究明はもとより、船体の沈没位置さえ不明である中で拙速ではありますが、あくまで推測として、高い波浪とともに船体に圧力が加わり、亀裂部分が更に大きくなり大量の浸水が在ったのではないか、事故船舶の規模の船体規模では隔壁は進水を想定していないでしょうし、乗員は船長と甲板員のみ、機関部浸水が始れば航行不能となるのは当然です。

救命胴衣と救助浮器など設置されているのは過去に撮影された写真でも確認できるのですが、低温の海域では救助浮器は溺れないよう掴まる程度のものです、低体温症は免れません、救命艇や自動膨張筏は設置するには小型すぎる船舶ですし、単行で北海道近海にて沈没した場合の安全策には無理があり、唯一の救命手段は一刻も早く水を出て採暖すること。

救助は何故時間がかかるのか。先ず、知床半島全体は国立公園に指定されており、人口希薄な地域となっています。そしてKAZU-Ⅰは出航しましたが、他の事業者は悪天候の予報から運休となっており、波浪の高さから漁船などの出漁も見合わせ、つまり沈没した周辺海域に僚船や漁船などは存在せず、遭難位置が確認できない状態があったといえましょう。

海上保安庁の救助も、近傍の100km圏内に羅臼海上保安署と網走海上保安署はあります、羅臼には巡視船てしお、巡視艇かわぎり。網走には巡視船ゆうばり、が配属されています。他方、海上自衛隊は北海道には札幌に近い余市基地のミサイル艇かはるか離れた函館基地の掃海艇、航空自衛隊は千歳救難隊があるのみ、遭難が陸上ならば第5旅団がいましたが。

しかし、何故出航したのかという点が。乗客としては、特に救命艇のない小型観光船では救命胴衣だけでは一時間以内に他の船舶に救助される状況でもなければ、乗客には自ら安全を確保する方法が思い浮かびません、代金を支払った後で船体の傷を発見してものらないという選択肢は、社会通念上難しいのではないか、まさか、沈まないかとは聞けません。

第一管区海上保安部と北海道警及び自衛隊とともに漁協や別の観光会社も協力して捜索救助を進めていますが、いまのところ26名の乗客乗員の内10名が救助され死亡が確認され、生存者が確認されていません。今日、国土交通省は運航会社へ特別監査をおこなったとのことですが、再発防止よりも、なんとか一人でも陸上に上がり採暖で生存していないか、願うばかりです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
北海道の知床観光船KAZU-Ⅰが4月23日、遭難しました。これは旅客船の事故では令和時代に入って最大の船舶遭難事故となる懸念があります。なんとか生存者を期待したい。

KAZU-Ⅰは排水量19tの観光船であり定員は30名、乗員乗客26名が乗船していました。小型船である為にAIS船舶位置表示装置はなく救助は難航している。事故は23日、知床半島周遊観光船KAZU-Ⅰが1000時に知床半島のウトロ港を出航しました、当初予定では40km先の知床岬まで航行し往復するという三時間の航路でした。しかし、ここに事故が発生しました。

カシュニの滝、1313時にKAZU-Ⅰより運航会社に対し“沈みかけている”という無線連絡を発しました。そしてその五分後に当る1318時、ウトロ港から25kmほど先のカシュニの滝付近をにおいて、“船首が浸水”“エンジンが使えない”という通信と救助要請が出されました。そして1400時頃、“船体が30度傾斜している”との無線連絡があったとのこと。

船体が30度傾斜している、これが最後の通信となりました。もともとは往復80kmの航路を1300時までに往復する行程だったとのことですが。海上保安庁と警察、そして北海道知事からの要請を受け航空自衛隊が出動しましたが、日没までに遭難位置を確認できず、24日の日曜日に入り10名が心肺停止で救助、死亡が確認されました。現在も生存者はなし。

知床岬、要救助者が心肺停止で発見されたのは遭難信号が発せられたカシュニの滝から、更に14km離れた知床岬付近で発見されたとのこと。国土交通省によれば23日1300時頃の現場は、風が北西の風16.4mと強く、波浪は2mから3m、海水温は2度から3度となっています。生存者を祈りたいものですが、海水温が3度では30分ほどで低体温症になる。

何が在ったのか。原因究明が待たれますが、KAZU-ⅠはFRP製船体であり、気になる情報として2021年に漂流物との衝突により負傷者が出る事故、そして座礁事故を起こしているという情報、また、他の事業者からの目撃情報として船首付近の2m程度の位置に15cmほどの亀裂が在った、という証言です。すると、FRP製船体特有の問題が思い浮かぶのです。

FRP製船体は、亀裂が入りますと補修テープを貼る程度の応急措置以外は亀裂が広がる難点があります、鋼製船体のように破損個所を溶接して塞ぐ事が出来ませんし、木造船体の様に浮力もありません。例えば海上自衛隊も掃海艇を木造船体から最近のFRP船体に切替える際に、このFRPの特性が触雷時のダメージコントロールへ影響が懸念されていました。

原因究明はもとより、船体の沈没位置さえ不明である中で拙速ではありますが、あくまで推測として、高い波浪とともに船体に圧力が加わり、亀裂部分が更に大きくなり大量の浸水が在ったのではないか、事故船舶の規模の船体規模では隔壁は進水を想定していないでしょうし、乗員は船長と甲板員のみ、機関部浸水が始れば航行不能となるのは当然です。

救命胴衣と救助浮器など設置されているのは過去に撮影された写真でも確認できるのですが、低温の海域では救助浮器は溺れないよう掴まる程度のものです、低体温症は免れません、救命艇や自動膨張筏は設置するには小型すぎる船舶ですし、単行で北海道近海にて沈没した場合の安全策には無理があり、唯一の救命手段は一刻も早く水を出て採暖すること。

救助は何故時間がかかるのか。先ず、知床半島全体は国立公園に指定されており、人口希薄な地域となっています。そしてKAZU-Ⅰは出航しましたが、他の事業者は悪天候の予報から運休となっており、波浪の高さから漁船などの出漁も見合わせ、つまり沈没した周辺海域に僚船や漁船などは存在せず、遭難位置が確認できない状態があったといえましょう。

海上保安庁の救助も、近傍の100km圏内に羅臼海上保安署と網走海上保安署はあります、羅臼には巡視船てしお、巡視艇かわぎり。網走には巡視船ゆうばり、が配属されています。他方、海上自衛隊は北海道には札幌に近い余市基地のミサイル艇かはるか離れた函館基地の掃海艇、航空自衛隊は千歳救難隊があるのみ、遭難が陸上ならば第5旅団がいましたが。

しかし、何故出航したのかという点が。乗客としては、特に救命艇のない小型観光船では救命胴衣だけでは一時間以内に他の船舶に救助される状況でもなければ、乗客には自ら安全を確保する方法が思い浮かびません、代金を支払った後で船体の傷を発見してものらないという選択肢は、社会通念上難しいのではないか、まさか、沈まないかとは聞けません。

第一管区海上保安部と北海道警及び自衛隊とともに漁協や別の観光会社も協力して捜索救助を進めていますが、いまのところ26名の乗客乗員の内10名が救助され死亡が確認され、生存者が確認されていません。今日、国土交通省は運航会社へ特別監査をおこなったとのことですが、再発防止よりも、なんとか一人でも陸上に上がり採暖で生存していないか、願うばかりです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)