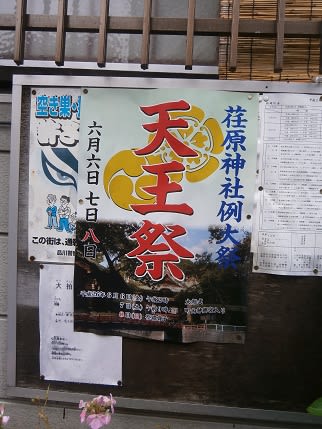京都八坂神社
京都市東山区祇園町

今回は全国の八坂神社の総本社の京都八坂神社。
多忙の折ですが、たまたま大阪に行くことになりましたので、帰りに立ち寄りました。
京都駅からですと、徒歩では1時間くらいかかるでしょう。老人はバス・タクシイーを使われた方がいいでしょう。

「事前学習」として京都八坂神社のホームページを見ました。ホームペ-ジに書かれてある八坂神社の由来について、一部を記しておきます。
「当社は慶応4年(1868)5月30日付の神衹官達により八坂神社と改称するまで、感神院または祇園社と称していた。創祀については諸説あるが、斉明天皇2年(656)に高麗より来朝した使節の伊利之(いりし)が新羅国の牛頭山に座した素戔嗚尊を山城国愛宕郡八坂郷の地に奉斎したことに始まるという。また、一説には貞観18年(876)南都の僧円如が建立、堂に薬師千手等の像を奉安、その年6月14日に天神(祇園神)が東山の麓、祇園林に垂跡したことに始まるともいう。・・・・・」
御祭神については
「中御座 素戔嗚尊(すさのをのみこと)
東御座 櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと)
御同座 神大市比売命(かむおおいちひめのみこと)・佐美良比売命(さみらひめのみこと)
西御座 八柱御子神(やはしらのみこがみ)
八島篠見神(やしまじぬみのかみ)
五十猛神(いたけるのかみ)
大屋比売神(おおやひめのかみ)
抓津比売神(つまつひめのかみ)
大年神(おおとしのかみ)
宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)
大屋毘古神(おおやびこのかみ)
須勢理毘売命(すせりびめのみこと)
傍御座 稲田宮主須賀之八耳神(いなだのみやぬしすがのやつみみのかみ)」と記されています。
由来・祭神では、牛頭天王については一言も触れていません。
すでに、わたしはこのブログで、江戸時代に書かれた『羣書類従』の「二十二社註式」(国立国会図書館蔵、木版原板巻二十二。四十七。 ただし、国立国会図書館デジタル化資料番号では第23冊~25冊[147]の138祇園社)に記されている祇園社と牛頭天王について紹介してあります。(2012年7月6日)そこには
「西間 本御前竒稲田媛垂跡一名婆利女一名少将井脚摩乳手摩乳女
中間 牛頭天皇号大政所進雄尊垂跡
東間 蛇毒氣神龍王女今御前也」
となっているのですが・・・・・・。
そこで、実際に八坂神社に参詣にいってみました。牛頭天王については拝殿の所に由緒書が出されていて
「平安時代以来、祇園精舎の守護神、牛頭天王と付会されました・・・・」と一行書かれてあるのを見ることができました。

さて、一般庶民にとって牛頭天王はどのように思われているのか、地元の人に聞いてみますと、どうやらスサノヲノミコトの「化身」と理解しているようです。
しかしながら、八坂神社側が一行でも牛頭天王について触れていることはうれしいので、全国の八坂神社もこれに倣い、由緒書には牛頭天王の文字を入れていただきたい気持ちでおります。
牛頭天王よりも、もっと「かわいそう」なのは蛇毒気神(だどくけのかみ=女神)で、江戸時代とは変わり「無視」されています。
蘇民将来については境内社としてあります。


参詣に行って思ったのですが、もともとは八坂神社側が言うように、八坂神社は高麗より来朝した使節の伊利之(いりし)が建立したのでしょう。そして、当初は伊利之(いりし)が「八坂大神」として先祖神を祀っていたのでしょう。時代が下り、御霊信仰がさかんになるとそれを勧請し(祇園信仰の盛んな地となり)、さらに牛頭天王信仰と結びついたとわたしは想像しましたが・・・・。


神社側が「八坂大神」の掛け軸を出そうが、仏教徒が「牛頭天王の精神に還れ」と言おうが、とにかくも、地元の人にとっては「祇園さん」。日本三大祭りのひとつ京都祇園祭は健在。そして,今年はさらに盛大にもりあがりそう。
わたしは7月も多忙。京都まで祗園祭を見に行くことはできませんが、今回立ち寄る程度でも参詣できてよかったと思います。

祇園社にやってきた平清盛の「ろうぜき」ぶりについて記した文章の横にある写真。中世の祇園社と思われる絵。



八坂神社から徒歩ですと、2、30分くらい。東大路通りを二条の方に行き、仁王門通りを左に曲がり衣料などを売っている店の道を右に入ると、安産祈願で有名な大連寺があります。八坂神社が祇園社だった頃、仏教信仰の地でしたから当然仏像があったわけです。その仏像を今なお大切に保管しているお寺が大連寺です。きれいなパンフレットを作成してあり、祇園社と大連寺の関係についても述べています。





大連寺 京都市左京区東山二条西入一筋目下ル457