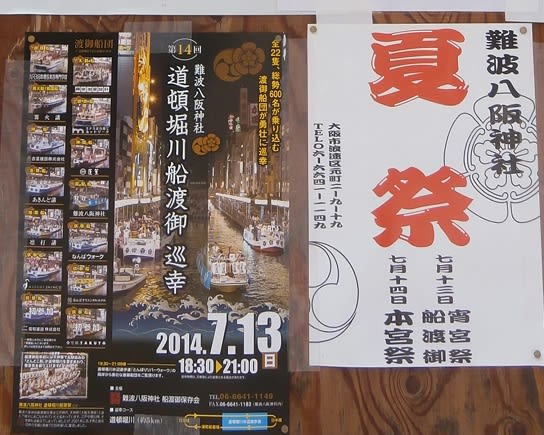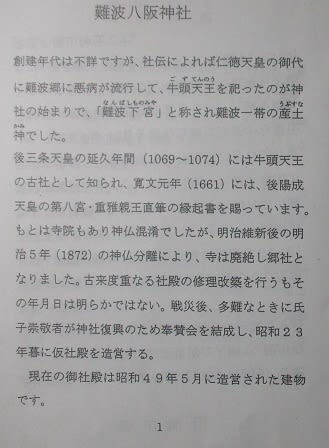忙しい日々が続いていまして、なかなか牛頭天王信仰について調べられない状況にありますが・・・・。たまたま得た情報から、東京世田谷区の代官屋敷跡にある郷土資料館に行くことができ、牛頭天王信仰の存在を確認しました。
世田谷区郷土資料館の中に江戸時代の「年中行事」についての説明があります。これは当時の代官大場弥十郎が『家例年中行事』という文書を残しているため、それに基づいて紹介したもので、6月15日に「祇園牛頭天王」をまつることが書かれています。

「どこの神社でお祭りをしたのか」ということになるのですが、それについては書かれていません。そこで、この資料館にもある、江戸時代に著された『新編武蔵風土記稿』を調べてみたのですが、他郡においては天王社(境内社としての天王社についても)記載がありますが、大場氏の代官屋敷近くには宇佐神社(八幡神社)や天祖神社はあっても、天王社も境内社としての天王社も見当たりませんでした。一番近いのが多磨郡喜多見の天王社(今の須賀神社)です。多磨郡喜多見の祇園牛頭天王社へ行ってお祭りに参加したとは考えにくく、①代官屋敷内に祠をつくってあったので屋敷内で「祇園祭(天王祭)をやったのか、 ②代官屋敷向かいにある天祖神社で「臨時」に祇園牛頭天王を御招きしてお祭りをやったのか、どちらかになろうかと思います。

代官屋敷向かいの天祖神社
関東の多くの神社では6月と12月の「大祓」の儀式の時には、蘇民将来とも武塔神(牛頭天王)とも関係ない神社にあっても「茅の輪くぐり」の神事が行われています。「茅の輪くぐり」を行うのであれば蘇民将来も武塔神(牛頭天王)も祀ればと思うのですが、蘇民将来・武塔神(牛頭天王)の物語に出てくる「茅の輪」を「臨時に利用」させていただいていると言う訳です。
こういった「臨時」発想は「茅の輪くぐり」だけでなく、「臨時」に祇園祭(天王祭)を行うということをも含めて江戸時代には結構あったのではないでしょうか?自分たちの住まいの近くの神社には牛頭天王は祀られていないのだけれども、牛頭天王信仰がはやっているため「臨時に牛頭天王に来ていただく」という儀式が・・・・。そういうことを東京の世田谷郷土資料館にある文書から想像した次第です。

世田谷区郷土資料館(東急世田谷線上町駅下車徒歩5分。代官屋敷内。見学無料)
世田谷区世田谷1-29-18
電話03-3429-4237
世田谷区郷土資料館の中に江戸時代の「年中行事」についての説明があります。これは当時の代官大場弥十郎が『家例年中行事』という文書を残しているため、それに基づいて紹介したもので、6月15日に「祇園牛頭天王」をまつることが書かれています。

「どこの神社でお祭りをしたのか」ということになるのですが、それについては書かれていません。そこで、この資料館にもある、江戸時代に著された『新編武蔵風土記稿』を調べてみたのですが、他郡においては天王社(境内社としての天王社についても)記載がありますが、大場氏の代官屋敷近くには宇佐神社(八幡神社)や天祖神社はあっても、天王社も境内社としての天王社も見当たりませんでした。一番近いのが多磨郡喜多見の天王社(今の須賀神社)です。多磨郡喜多見の祇園牛頭天王社へ行ってお祭りに参加したとは考えにくく、①代官屋敷内に祠をつくってあったので屋敷内で「祇園祭(天王祭)をやったのか、 ②代官屋敷向かいにある天祖神社で「臨時」に祇園牛頭天王を御招きしてお祭りをやったのか、どちらかになろうかと思います。

代官屋敷向かいの天祖神社
関東の多くの神社では6月と12月の「大祓」の儀式の時には、蘇民将来とも武塔神(牛頭天王)とも関係ない神社にあっても「茅の輪くぐり」の神事が行われています。「茅の輪くぐり」を行うのであれば蘇民将来も武塔神(牛頭天王)も祀ればと思うのですが、蘇民将来・武塔神(牛頭天王)の物語に出てくる「茅の輪」を「臨時に利用」させていただいていると言う訳です。
こういった「臨時」発想は「茅の輪くぐり」だけでなく、「臨時」に祇園祭(天王祭)を行うということをも含めて江戸時代には結構あったのではないでしょうか?自分たちの住まいの近くの神社には牛頭天王は祀られていないのだけれども、牛頭天王信仰がはやっているため「臨時に牛頭天王に来ていただく」という儀式が・・・・。そういうことを東京の世田谷郷土資料館にある文書から想像した次第です。

世田谷区郷土資料館(東急世田谷線上町駅下車徒歩5分。代官屋敷内。見学無料)
世田谷区世田谷1-29-18
電話03-3429-4237