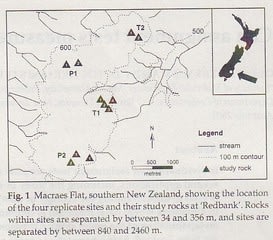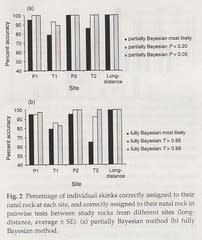・明日からの富良野行きを前に、各種打ち合わせ、準備など。午前中で一区切りしたところで、トドマツ交雑論文の投稿にかかる。Reviewerを4名も指定しないといけない上に、推薦理由が必要!、ということで思いのほか時間がかかる。毎度のことだが、雑誌によって微妙に投稿プロセスが違うのがややこしい。2時過ぎ、どうにかこうにか投稿完了。自分としてはかなりポジティブな印象に変わったと信じているのだが・・・。今度こそ、いい知らせが届いてほしいものである。
・午後から業者との打ち合わせ。最近、何だか妙にバタバタしている。アオキ第二弾の原稿チェック。引用文献として新たに加えられたJohnson and Galloway(2008)Plant Ecolをダウンロードしてみる。これは園芸植物ベニバナサワギキョウの植栽が野生集団に及ぼす影響を、花粉による遺伝子交流を通じて評価するという論文。
・試験設計が複雑で意外と理解しにくい論文である。面白いのは、自生個体の花粉と非自生個体の花粉の混合花粉を割合を75%、50%、25%という3段階に分けて設定し、遺伝マーカーを用いて、自生花粉と非自生花粉のどちらが強いか(選択受精の有無)を調べているところだ。
・1000km以上離れた2つの集団の非自生花粉はほぼ混合割合程度の結実率を示し、自生花粉と非自生花粉のパワーに差がないという結果だった(これはこれで驚きだが・・・)。一方、32km離れた集団の花粉は混合割合よりもむしろ高い結実率を示した(雑種強勢?)。しかし、園芸品種の花粉はいずれの混合割合でもほとんど結実させることができず、自生集団の花粉に負けるという結果となった。
・全体としては、非自生花粉と自生花粉の間で受精パワーに大きな違いはなく、非自生遺伝子が自生集団に交雑を通じて入っていく可能性は十分にあるが、個体によって影響は異なるだろうというのが結論。参考にはなったが、引用の仕方が難しそうだ。
・午後から業者との打ち合わせ。最近、何だか妙にバタバタしている。アオキ第二弾の原稿チェック。引用文献として新たに加えられたJohnson and Galloway(2008)Plant Ecolをダウンロードしてみる。これは園芸植物ベニバナサワギキョウの植栽が野生集団に及ぼす影響を、花粉による遺伝子交流を通じて評価するという論文。
・試験設計が複雑で意外と理解しにくい論文である。面白いのは、自生個体の花粉と非自生個体の花粉の混合花粉を割合を75%、50%、25%という3段階に分けて設定し、遺伝マーカーを用いて、自生花粉と非自生花粉のどちらが強いか(選択受精の有無)を調べているところだ。
・1000km以上離れた2つの集団の非自生花粉はほぼ混合割合程度の結実率を示し、自生花粉と非自生花粉のパワーに差がないという結果だった(これはこれで驚きだが・・・)。一方、32km離れた集団の花粉は混合割合よりもむしろ高い結実率を示した(雑種強勢?)。しかし、園芸品種の花粉はいずれの混合割合でもほとんど結実させることができず、自生集団の花粉に負けるという結果となった。
・全体としては、非自生花粉と自生花粉の間で受精パワーに大きな違いはなく、非自生遺伝子が自生集団に交雑を通じて入っていく可能性は十分にあるが、個体によって影響は異なるだろうというのが結論。参考にはなったが、引用の仕方が難しそうだ。