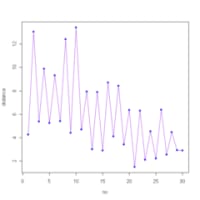・あえなくリジェクトとなったトドマツ交雑論文を修正するということで、Iくんとやりとり。レフリーの指摘のとおり、オープン交配を含めると解釈が難しくなるのは確かにその通りだということで、人工交配家系だけで勝負する、ということで意見が一致。オープンを除いた解析をやってもらったところ、なんと樹高やDBHについてほとんどの場合に遠交弱勢が検出!という結果になった。
・改めて前回の結果と並べて確認してみると、もともとDBHでは95%信頼区間のぎりぎりの値で、惜しくも(?)遠交弱勢検出されずという形になっている。さらによく見ると、NL×オープンの値が妙に低く、これがNL×NLの平均値を押し下げてしまったと見ることができるようだ。このため、親の平均値があたかもF1と有意に違わないという結果になっていたようだ。考えてみると、高標高では個体密度も低く、花粉自体が不足しているために、自然受粉の中に自家受粉や血縁度の高い個体との交配が多くなり、子どものパフォーマンスが低かった、ということなのかもしれない。
・保全に関する全体の論旨は実はあまり変わらないのだが、遠交弱勢が検出されたということになると、論文の流れにも少なからず影響を与えることになる。改めて、Montalvo and Ellstrand 2001の論文を読み返しつつ、考察の展開を考える。木本植物のF1で遠交弱勢が認められているのは、この論文とStacy 2001くらいしかない。また、これほどまでに後期のステージで遠交弱勢が検出されたのは高木種では初めてということで、そういう意味では本研究の結果は”驚き”である。しっかし、どうして今までオープンを除いて解析することを思いつかなかったのか・・・。やっぱり、固定観念に捉われてしまっていたことを痛感。
・といいつつ、北方林業原稿も放置しているとまずい。ということで、カリカリとノートに書き、それを修正する形でパソコンに打ち込む。パラグラフごと書き換えたり、順序を変更しつつ、ようやく落ち着いてきた。プリントアウトして眺めつつ、さらにチョコチョコと修正。
・午後から26日のプレゼン準備。こちらも全面改訂することに。ヒノキ論文のネタを中心にスライドを作成。やはり論文になっていると、流れは頭に入っているので後は図表を貼り付けたり、ポイントを整理するだけで何とかなりそう。後は、Manel et al. 2005の総説を読み返して、アサインメントテストを人に説明できるようにならないと・・・。
・改めて前回の結果と並べて確認してみると、もともとDBHでは95%信頼区間のぎりぎりの値で、惜しくも(?)遠交弱勢検出されずという形になっている。さらによく見ると、NL×オープンの値が妙に低く、これがNL×NLの平均値を押し下げてしまったと見ることができるようだ。このため、親の平均値があたかもF1と有意に違わないという結果になっていたようだ。考えてみると、高標高では個体密度も低く、花粉自体が不足しているために、自然受粉の中に自家受粉や血縁度の高い個体との交配が多くなり、子どものパフォーマンスが低かった、ということなのかもしれない。
・保全に関する全体の論旨は実はあまり変わらないのだが、遠交弱勢が検出されたということになると、論文の流れにも少なからず影響を与えることになる。改めて、Montalvo and Ellstrand 2001の論文を読み返しつつ、考察の展開を考える。木本植物のF1で遠交弱勢が認められているのは、この論文とStacy 2001くらいしかない。また、これほどまでに後期のステージで遠交弱勢が検出されたのは高木種では初めてということで、そういう意味では本研究の結果は”驚き”である。しっかし、どうして今までオープンを除いて解析することを思いつかなかったのか・・・。やっぱり、固定観念に捉われてしまっていたことを痛感。
・といいつつ、北方林業原稿も放置しているとまずい。ということで、カリカリとノートに書き、それを修正する形でパソコンに打ち込む。パラグラフごと書き換えたり、順序を変更しつつ、ようやく落ち着いてきた。プリントアウトして眺めつつ、さらにチョコチョコと修正。
・午後から26日のプレゼン準備。こちらも全面改訂することに。ヒノキ論文のネタを中心にスライドを作成。やはり論文になっていると、流れは頭に入っているので後は図表を貼り付けたり、ポイントを整理するだけで何とかなりそう。後は、Manel et al. 2005の総説を読み返して、アサインメントテストを人に説明できるようにならないと・・・。