今年の春闘は、連合傘下の760組合で2年連続5%超の高い賃上げを獲得し、中小企業に限っても33年ぶりに5%を超えたと報じられた。
デフレ下では賃金の引上げを望む声が多く、韓国にも抜かれたとの嘆きも聞こえてきたが、昨今の物価高騰の原因の一つに「人件費の高騰」を挙げる声を聞けば、「賃上げはインフレの第一歩」と云うことが実感できる。長く公務員であったので、春闘勝利の余慶も人事院の勧告と国会決議を経た年末まで待つのが例であった。
春闘と云えば、父島からの休暇時に国鉄労組の順法闘争の煽りを食った思い出しかないが、今更ながらに春闘を勉強した。
Wikipediaを頼りに春闘の来歴を辿ると
〇1954年 5単産共闘の賃上げ交渉始まる。
〇1955年 3単産が加わり8単産共闘会議結成
〇1959年 総評と中立労連により春闘共闘委員会結成-春闘の言葉が定着?
〇1974年 狂乱物価を背景に物価や税制、社会保障問題なども取り上げられるようになり「国民春闘」と名付けられた。
〇1959年 総評と中立労連により春闘共闘委員会結成-春闘の言葉が定着?
〇1974年 狂乱物価を背景に物価や税制、社会保障問題なども取り上げられるようになり「国民春闘」と名付けられた。
〇1975年 共闘会議の名称も「国民春闘共闘会議」とされ、ストライキ等を伴う実力闘争から労使トップレベルによる交渉が主体となった。
〇1988年 連合の前身となる民間連合が結成され賃上げ闘争は「春季生活改善闘争」と呼ぶようになった。
〇1988年 連合の前身となる民間連合が結成され賃上げ闘争は「春季生活改善闘争」と呼ぶようになった。
〇1989年 連合が結成され春季生活改善闘争を「春季生活闘争」としたが、全労連・純中立労組懇は「国民春闘共闘委員会」を、全労協・全港湾は「けんり春闘全国実行委員会」と銘打っている。
この来歴を眺めると、メディアが現在使用している「今年の春闘・・・云々という表現は必ずしも正しくないように思えるが、まァ1960年頃から使われ始めて半世紀以上も人口に膾炙すれば、歳時記としても認められるであろうように思える。
上記の来歴には出て来ないが、自分では春闘の山場は4月であったように記憶している。何故に4月と思っているかと云うと、かって艦艇には「燃料告知」と云う制度があり、概ね3月には年度当初に与えられた燃料告知量を使い果たし、航海訓練もできない状態に置かれるのが常であった。4月に入ると新年度の燃料告知があって、一斉に個艦・隊・群訓練が行われて母港を留守にするのが通例で、陸上勤務者を除いては順法闘争の余波を受けない暮らしに終始したためである。更には、この燃料告知と訓練に伴って4月初めの年中行事「満開時の花見」ができないことも多かったが。



















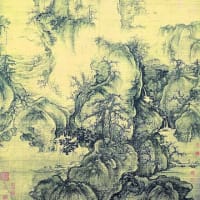
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます