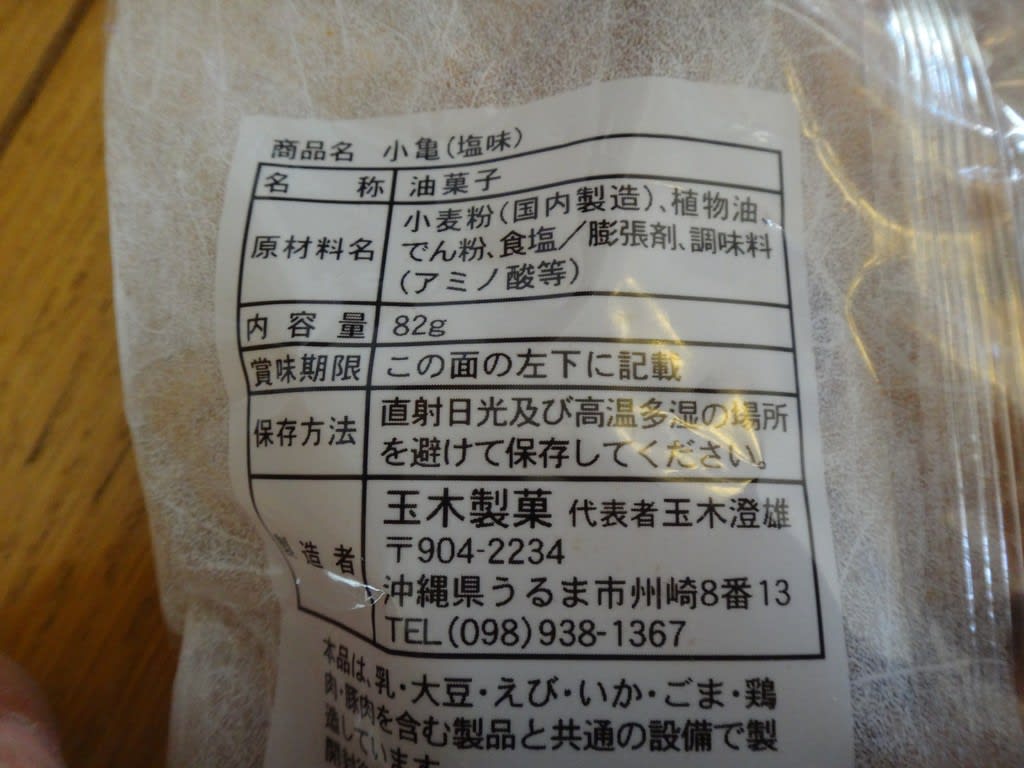ダンナサマは特に甘党ではないのですが、「心のお菓子」がひとつあります。
それが石村萬盛堂の銘菓「鶴乃子」。
小さな子供の頃、お母さんが入院したことがあったそうなのですが、見舞い客がみなこれを持ってきてくれた思い出があるのだそうです。
お母さんがこれが好きだった訳ではなく、
「Kちゃん(←ダンナサマ)が鶴乃子が好きでねえ」という話が広まり、「ぼっちゃんは、これがお好きだそうで」
という感じで、みんなが持ってきてくれたみたい。
大きな卵型の箱を何箱も重ね、抱え込むようにしてひとりじめしていたようです。
で、お気に入りの看護婦さんには一個あげたり。
白くてまあるいたまごの形をしていて、さわるとふわふわ。
しかもたまごの形のふっくらまるい箱入り。
(より高級な、四角い箱入りの献上鶴乃子はイヤだったみたい!)
子供には、魅惑のお菓子ですよね。
もう甘党ではなくなった今でも、このお菓子は好きみたい。
とてもしあわせそうに食べるので、一緒に食べるこちらも幸せになります。
交通会館には、福岡のアンテナショップがあり、この鶴乃子が買えます。
マルシェ出店のあと、いそいそと買ってきました。
今回は、定番のほか、季節限定品もゲット。
「日向夏鶴乃子」です。
ところで、ほかにもフレーバーが?と調べてみると、チョコミントマシュマロやコーヒーマシュマロ、チョコマシュマロなど、各種マシュマロ商品も出していることが分かりました。
ホワイトデーの習慣をはじめたのは、この会社なのですって(1978年)。
ホワイトデーが近くなると、マシュマロを含め、いろいろなお菓子のキャンペーンがあるようです。
なんか、どれも美味しそう。
ホワイトデーは、バレンタインのチョコ商戦に比べると断然つまらない印象でしたが、このマシュマロ菓子は欲しいかも。
関東でも買えるところ、あるかしらん。