2019年2月24日のシンポジウムで話したことを記録しておきます。
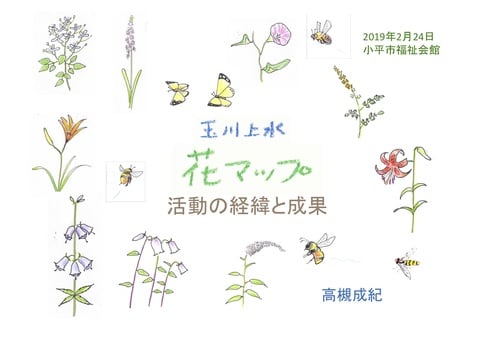
玉川上水と一言で言っても上流、中流、下流でかなり様子が違います。玉川上水の野草は、大きく言って林の野草と草原、茅場の野草に分れます。
玉川上水を上空から見ると、灰色の中にごく細い緑の線のように見えます。

小平上空から見た玉川上水。赤い点が会場の小平市福祉会館
これを羽村の取水堰からかつての「終点」である四谷の大木戸までの玉川上水を緑色で示しました。

玉川上水全域
花マップ作りのきっかけは3年前から始めた玉川上水の観察会で、たくさんの人と作業すると一人ではできないことができることを実感したからです。その例として花のタイプと昆虫のタイプを調べると、皿状の花にはハエなど「舐める」タイプの昆虫が多く訪問することがわかりました。

つまり、「様々な花に様々な昆虫が集まってくる」のではなく、花の形と昆虫の口の関係からある「法則」のようなものがあることがわかったのです。こういう調査は一人では大変ですが、たくさんの人がいれば一気にできます。

花の形と昆虫の口の関係
そこで玉川上水の30kmにあるほぼ100の橋を区分点として区画に分け、そこをメンバーで分担して毎月歩いて、「今月の花」を記録することにしました。私たちの歩いた距離は述べで800kmにもなりましたが、これは東京から来たは札幌近く、西は福岡に達するほどの距離です。
さて、玉川上水の野草を見ていると、玉川上水に何がおきたかが想像できるようになりました。江戸時代から戦前までは武蔵野の田園地帯によくある、雑木林と畑、それに茅場が広がる景観だったと思われます。当時はt玉川上水は水を確保するための運河でしたから、低木類は切りはらわれてススキ群落のような植生だったと思われます。

それが、戦後の経済復興の時代に東京の人口が急増し、都心から広がってきた市街地化が進んできました。

そして現在では市街地が広がって茅場はなくなり、雑木林も少なくなりました。玉川上水は林が発達しました。

花マップの活動としては、マニュアルを作り、毎月「今月の花」を指定して、その記録を取ってもらいました。

その時にお願いしたのは「なになに草がありました」という情報ではなく、必ず写真を撮影してもらったということです。人には思い込みがありますから、そうだと思っていたものが違うこともあります。それを避けるためには写真に写しておくことが一番です。その写真と分布状態のデータが私のところに送られてきて、それを集計して「花マップ」ができました。
そうするうちに「これを冊子にして広く知ってもらいたい」ということになり、去年「夏号」ができました。今回はその続編として「秋号」と「冬号」ができました。
この冊子を作るにあたって次のようなことを心がけました。見開きで2種の花を取り上げ、左ページには解説を書きました。冊子には図鑑的な意義があるので、野外で咲いている花の写真と一般的な特徴を記載したのは当然ですが、そこに必ず玉川上水でどうかということを書きました。また見分け方や特徴がわかるように拡大写真や部分の写真も添えました。そして、右のページには分布マップのほか、花のスケッチとエッセーを添えました。つまり、同類の冊子にはない、オリジナル情報満載のものにしました。もう一つ特記すべきことは、松岡さんという優れたデザイナーがレイアウトなどを考えてくださったことです。これにより、見やすく、楽しく、充実した冊子が出来上がりました。見開きの中央には螺旋のリングが印刷されるなどの工夫もあります。

3冊揃った花マップ冊子
野草のスケッチはこの冊子のポイントの一つなので、私がスケッチをすることろを動画で紹介しました。

スケッチをするところ(当日は動画で紹介)
冊子のオリジナリティの一つとして平安時代の奈良で選ばれた「秋の七草」ではなく、玉川上水のオリジナルな秋の七草を選びました。その結果、つる植物としてセンニンソウ、直立型の双子葉草本としてワレモコウとユウガギク、単子葉植物としてツルボとツユクサ、低木としてヤマハギ、イネ科としてススキと、多様で玉川上水らしい7種がバランスよく選ばれました。奈良のものとの共通種はハギとススキの2種でした。

玉川上水のオリジナル秋の七草
なお、冊子作りについては当日、資料として「玉川上水花マップを作る - 冊子に込めた想い -」という文章を配布しました。
冊子には書きませんでしたが、もう一つ特記すべきことは、昨年の10月1日の未明に関東地方を襲った台風24号による風倒木被害のことです。私はその情報を知った時に「これは花マップのメンバーですべきことだ」と思いました。それで、メンバーに馴染みの区画を歩いてもらい、倒木の実態を記録してもらいました。

風倒木の様子

風倒木の内訳(上)と玉川上水の各区画における倒木密度(/100m)
これにより、倒木はサクラに偏っていたこと、北向きが多かったこと、玉川上水の東側に偏っていたことなどが明らかになりました。これは、日頃その場所をよく歩いている花マップメンバーがいてはじめてできたことです。(詳細はこちら)
最後に玉川上水の未来について触れました。今の玉川上水は杉並の浅間橋よりも下流で暗渠になります。その場に立つと、西側の緑と東側の高速道路が対照的です。

それは戦後の日本社会を象徴しているように見えます。1964年の東京オリンピックの時代、東京を「改造」することに誰も疑問を感じていませんでした。しかしその時代にあっても玉川上水をこれ以上破壊してはならないという英断をし、実行した人がいたということの意味をよく考える必要があります。玉川上水は放っておいても残されるものではありません。現に道路がつけられて破壊されているところがあります。私たちは玉川上水を良い形で次の世代に引き継がなければならないと思います。
そういう考えに至ったのは、私が長年生き物のを眺めていたからということもありますが、レイチェル・カーソンの次の言葉が心の深い部分にあったこともあります。

ささやかな冊子ですが、これが広く読まれて玉川上水の魅力、価値を知ってもらえば嬉しいことです。
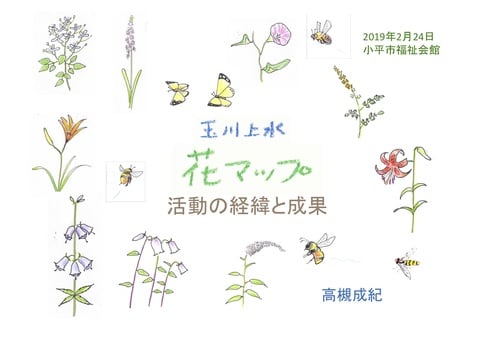
玉川上水と一言で言っても上流、中流、下流でかなり様子が違います。玉川上水の野草は、大きく言って林の野草と草原、茅場の野草に分れます。
玉川上水を上空から見ると、灰色の中にごく細い緑の線のように見えます。

小平上空から見た玉川上水。赤い点が会場の小平市福祉会館
これを羽村の取水堰からかつての「終点」である四谷の大木戸までの玉川上水を緑色で示しました。

玉川上水全域
花マップ作りのきっかけは3年前から始めた玉川上水の観察会で、たくさんの人と作業すると一人ではできないことができることを実感したからです。その例として花のタイプと昆虫のタイプを調べると、皿状の花にはハエなど「舐める」タイプの昆虫が多く訪問することがわかりました。

つまり、「様々な花に様々な昆虫が集まってくる」のではなく、花の形と昆虫の口の関係からある「法則」のようなものがあることがわかったのです。こういう調査は一人では大変ですが、たくさんの人がいれば一気にできます。

花の形と昆虫の口の関係
そこで玉川上水の30kmにあるほぼ100の橋を区分点として区画に分け、そこをメンバーで分担して毎月歩いて、「今月の花」を記録することにしました。私たちの歩いた距離は述べで800kmにもなりましたが、これは東京から来たは札幌近く、西は福岡に達するほどの距離です。
さて、玉川上水の野草を見ていると、玉川上水に何がおきたかが想像できるようになりました。江戸時代から戦前までは武蔵野の田園地帯によくある、雑木林と畑、それに茅場が広がる景観だったと思われます。当時はt玉川上水は水を確保するための運河でしたから、低木類は切りはらわれてススキ群落のような植生だったと思われます。

それが、戦後の経済復興の時代に東京の人口が急増し、都心から広がってきた市街地化が進んできました。

そして現在では市街地が広がって茅場はなくなり、雑木林も少なくなりました。玉川上水は林が発達しました。

花マップの活動としては、マニュアルを作り、毎月「今月の花」を指定して、その記録を取ってもらいました。

その時にお願いしたのは「なになに草がありました」という情報ではなく、必ず写真を撮影してもらったということです。人には思い込みがありますから、そうだと思っていたものが違うこともあります。それを避けるためには写真に写しておくことが一番です。その写真と分布状態のデータが私のところに送られてきて、それを集計して「花マップ」ができました。
そうするうちに「これを冊子にして広く知ってもらいたい」ということになり、去年「夏号」ができました。今回はその続編として「秋号」と「冬号」ができました。
この冊子を作るにあたって次のようなことを心がけました。見開きで2種の花を取り上げ、左ページには解説を書きました。冊子には図鑑的な意義があるので、野外で咲いている花の写真と一般的な特徴を記載したのは当然ですが、そこに必ず玉川上水でどうかということを書きました。また見分け方や特徴がわかるように拡大写真や部分の写真も添えました。そして、右のページには分布マップのほか、花のスケッチとエッセーを添えました。つまり、同類の冊子にはない、オリジナル情報満載のものにしました。もう一つ特記すべきことは、松岡さんという優れたデザイナーがレイアウトなどを考えてくださったことです。これにより、見やすく、楽しく、充実した冊子が出来上がりました。見開きの中央には螺旋のリングが印刷されるなどの工夫もあります。

3冊揃った花マップ冊子
野草のスケッチはこの冊子のポイントの一つなので、私がスケッチをすることろを動画で紹介しました。

スケッチをするところ(当日は動画で紹介)
冊子のオリジナリティの一つとして平安時代の奈良で選ばれた「秋の七草」ではなく、玉川上水のオリジナルな秋の七草を選びました。その結果、つる植物としてセンニンソウ、直立型の双子葉草本としてワレモコウとユウガギク、単子葉植物としてツルボとツユクサ、低木としてヤマハギ、イネ科としてススキと、多様で玉川上水らしい7種がバランスよく選ばれました。奈良のものとの共通種はハギとススキの2種でした。

玉川上水のオリジナル秋の七草
なお、冊子作りについては当日、資料として「玉川上水花マップを作る - 冊子に込めた想い -」という文章を配布しました。
冊子には書きませんでしたが、もう一つ特記すべきことは、昨年の10月1日の未明に関東地方を襲った台風24号による風倒木被害のことです。私はその情報を知った時に「これは花マップのメンバーですべきことだ」と思いました。それで、メンバーに馴染みの区画を歩いてもらい、倒木の実態を記録してもらいました。

風倒木の様子

風倒木の内訳(上)と玉川上水の各区画における倒木密度(/100m)
これにより、倒木はサクラに偏っていたこと、北向きが多かったこと、玉川上水の東側に偏っていたことなどが明らかになりました。これは、日頃その場所をよく歩いている花マップメンバーがいてはじめてできたことです。(詳細はこちら)
最後に玉川上水の未来について触れました。今の玉川上水は杉並の浅間橋よりも下流で暗渠になります。その場に立つと、西側の緑と東側の高速道路が対照的です。

それは戦後の日本社会を象徴しているように見えます。1964年の東京オリンピックの時代、東京を「改造」することに誰も疑問を感じていませんでした。しかしその時代にあっても玉川上水をこれ以上破壊してはならないという英断をし、実行した人がいたということの意味をよく考える必要があります。玉川上水は放っておいても残されるものではありません。現に道路がつけられて破壊されているところがあります。私たちは玉川上水を良い形で次の世代に引き継がなければならないと思います。
そういう考えに至ったのは、私が長年生き物のを眺めていたからということもありますが、レイチェル・カーソンの次の言葉が心の深い部分にあったこともあります。

ささやかな冊子ですが、これが広く読まれて玉川上水の魅力、価値を知ってもらえば嬉しいことです。

































