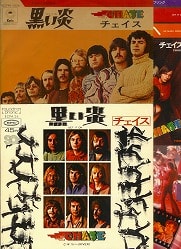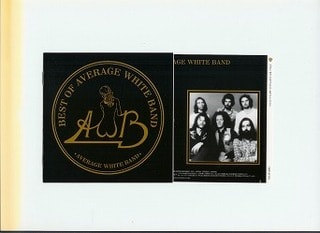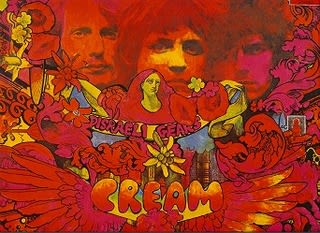2枚組アルバム「シカゴⅢ」からの第2弾シングルヒット曲(3:33)
LPでは2枚目A面2曲目、CDでは12曲目に収録。
全米チャートでは1971年4月最高35位をマーク。
日本では初来日決定の報に合わせて「来日記念盤」として発売(B面は「孤独なんて唯の言葉」 2:37),
ジャケットのロゴ・デザインはベスト盤「栄光のシカゴ」を引用。
当時のシカゴ人気は物凄く何と日本語バージョンまでもが7月に登場しました。訳詞にはあの「帰ってきた酔っ払い」でも有名なフォーク・クルセダーズのメンバー、現在は医師でもある北山修氏(本人の直筆歌詞が見開きジャケット内に印刷されています)。
おもしろいのはオリジナル・コンフィデンス・チャートでは英語バージョンよりも日本語バージョンのほうが上位にライクインしていたことです。(B面は「欲しいのは君だけ」)
日本の音楽専門誌にもそのレコーディング風景が白黒写真で掲載されていました。カラオケにボーカルを録音。リードVOのピーター、コーラスのテリー、ボビーの3人(実際にはリーもコーラス参加)日本語VERのみ最後にピーターが駄目押しで「OHH!」と歌っています。
コンポーザーは珍しくシカゴのリズム・セクション、ピーター・セテラとダニー・セラフィンが担当。
どうりでリズムやアクセントが凝りに凝っています。でもそれを微塵も感じさせないくらいのポップ・ハード・ブラスロック。
ピーターお気に入りのカントリー・フレイバーもちょっぴり加味。
情けないくらいに落ち込んだ男の女々しさを歌わせたら右に出る者なしのピーター節全開。
シカゴには強力なコンポーザーが幾人も在籍しているために、ピーターはセカンド・アルバム最終曲「約束の地へ」が自身にとって最後の曲作りになるだろうと言われていたそう。お呼びじゃあないってわけ。で、ある晩、おとめ座仲間でもあるダニーに会って「ロウダウン」を聞かせたそうです。「実はこういう曲があるんだけど、俺たちの力を見せつけてやろうぜ!」と2人は一念発起。
ピーター本人はとても自信を持っているし誇りにも思っている1曲。でもただ1つ残念なのはテリーが「この曲のギターを弾いているのが俺だとは誰にも言わないでくれ」と言ったこと。
実際、1,2テイクのみのハートが込められていない「俺の知ったことか」といった具合に酷いプレイだったそう。(そうはいっても実際には、さらっと豪快にテクニカルなことワウワウペダルも含めてやっていますが・・・笑)後味が悪く、ピーターもその件に関しては不満だとか。
でも初来日公演では歌詞カードを譜面台に載せ、たどたどしく日本語ボーカルを披露。2度目の来日でも再演。そのテイクは「ライブ・イン・ジャパン」で聞くことができます。
また1995年「ナイト&ディ来日公演」ではジェイソン・シェフがピーター以上に堪能な日本語歌唱を聞かせてくれました。
ちなみに日本企画2枚組ベスト「ギフトパック」には日本語スタジオテイクが収められています。LPではこれのみ。その後、CDでは「ハート・オブ・シカゴ」で日本のみ収録が実現。近年では海外レーベル、フライディ・ミュージック発売の「シカゴⅢ」で遂にワールド・ワイドに「日本語ロウダウン」がボーナス・トラックとして収録されました。
STAは2014年6月22日(日)アート・スペース・ホールでのライブにおいて初演奏。
数ヶ月前からメンバー全員でスタジオにて試行錯誤を繰り返しながらも、タイミングを見計らって本番に臨みました。
もちろん英語と日本語も歌詞を織り交ぜて。(このことに関してはバンド内においても賛否両論飛び交いました)
数年前のシカゴがスタジオでのリハーサル中に日本サイドからのリクエストで「ロウダウン」を求められ、試しに取り組んだのだそうですが、うまくいかずに断念。
本家の分まで頑張ってSTAは機会を見ては大切にレパートリーに加えていきたいと思います。













 原題 PROLOGUE,AUGUST 29,1968~SOMEDAY(AUGUST 29,1968)
原題 PROLOGUE,AUGUST 29,1968~SOMEDAY(AUGUST 29,1968)