「カナダのイヌイットから『ナヌク』と呼ばれるこの動物は、機知に富みアザラシ狩りにかけては抜群の猟師であるがゆえに、イヌイットは過去・現在の、さらには現生のみならず来世につづく自分たちのアイデンティティの力強い象徴としているのだ。イヌイットはホッキョクグマを怖れるよりも、自分の似姿として畏敬の念を抱いている。」エドワード・シュトルジック『北極大異変』(集英社インターナショナル、2016年)p.131
「地球温暖化問題」は最近では「気候危機」という言葉で語られるようになった。なぜ「危機」なのか、本当に「危機」なのか、何がわかっていて何がわかっていないのか。例えば産業革命前に比べて地球の平均気温が1.5℃を超えると、さまざまな場面で深刻な影響が出るとしたIPCCの『1.5℃レポート』を読もうとしても、地球科学の基礎的な知識がなければ理解は難しい。そこでしばらくは「気候危機」についての解説記事を書いてみたい。
日本に暮らしていると「地球温暖化」と言ってもぼんやりしていてよくわからない。今年の夏はとても暑くまた強い台風が次々に襲来したが、これも単なる異常気象なのか、それとも温暖化の影響なのかは、今の時点では科学的には判断できない。何十年か経ってから温暖化の影響だったということになるかもしれない。
しかしながら、地球上には温暖化が誰の目にも明らかなところがある。それが北極圏だ。
温暖化の影響は海洋よりも陸地の方が現れやすい。海より陸の方が温めやすく冷めやすいからだ。一方、地球上の陸と海の分布には偏りがある。地球儀を北から眺めてみてほしい。真ん中にぽっかりと北極海が空いていてその周りは陸地で取り囲まれている。シベリア、スカンジナビア、グリーンランド、カナダ、アラスカである。北半球は陸半球だ。一方地球儀をひっくり返して南から見ると、真ん中に南極大陸、その周りは海で取り囲まれている。南半球は海半球だ。
地球が温暖化し始めると、陸地の集まっている北半球の方が早く温暖化する。さらに北の方に行けば行くほどその影響が早く大きく現れる。つまり、北極圏が地球で一番温暖化が進むことになる。
北極圏において温暖化がどのような現象として現れているのか、地球科学から生態学、人類学まで総合的に捉えようとした国際共同研究がACIA: Arctic Climate Impact Assessmentだ。https://acia.amap.no 2004年に公表されたその報告書を見ると、例えばアラスカのBarrowでは、春になって雪が消える時期が早まっている。年々の早い遅いはあるけれども、1950年頃は6月中だったのが2000年には5月中にと傾向的に50年で1ヶ月早まっている。これは住んでいる人にとっては明らかな変化だろう。
先住民族に聞き取りをすると「私がカリブーだとしたらわけがわらずに途方にくれるだろう」という話が出てくる。カリブーは北極圏を代表するシカである。何十万頭という群れをなして春になると南の方から北極圏の草原にやってきて出産・子育てする。その移動の経路に大きな川を渡るのであるが、例年凍っていた川が解凍する時期が早まり、川岸に到達した時にはとうとうと雪解け水が流れている。右往左往するうちに子どもが生まれるが、親はその川を渡って対岸に行く。しかし、ついていった赤ちゃんカリブーは途中で溺れ死ぬ。先住民たちはその光景を見ていたのだ。
そして何と言っても大きな変化が見られるのは夏の海氷である。北極海では海の表面に氷が浮かんでいる。これは液体よりも個体の方が密度が小さい(軽い)という極めてめずらしい水の物理的性質によるものだ。北極海の海氷は夏に面積が小さく冬に大きくなる。広がったりしぼんだりを1年周期で繰り返している。冬には北極海をはみ出て、アラスカとシベリアを境しているベーリング海峡の少し外まで出てくる。春になるとこれが後退していく。そして9月に最もその面積が小さくなる。
最も小さくなった時の海氷の分布面積が1960年くらいからだんだんと小さくなっている。2000年にはその前に比べて30%程度小さくなっている。その分布を示した衛星写真を見ると、カナダ沿岸やシベリア沿岸では、以前には夏でも氷が海岸にくっついていた場所が、はるか数100km先まで氷が後退しているところが多くみられる。つまり、一年中氷に閉ざされていた場所が、夏になると広大な海が広がるようになっている。この影響はさまざまな場面で大きな変化を生んでいる。
まず、夏に沿岸部で嵐が起きるようになった。氷で閉ざされていればそこは太陽の光を反射するので相対的に冷たい場所になる。つまり空気は重く高気圧となり天気は良い。ところが海が開くとそこが相対的に暖かい場所になり低気圧となる。それで夏に嵐が起こるようになった。高波と高潮が沿岸部に押し寄せ、海岸が侵食されるようになった。
次に動物たちへの影響だ。夏の海氷の上で出産・子育てするのがアザラシだ。海氷がなくなれば子育てができずに絶滅する危険がある。さらに氷上でそのアザラシを捕食するのがホッキョクグマだ。これも絶滅する危険が出てくる。
先住民族の暮らしにも大きな影響が出ている。「天気がまったく昔とちがってしまった。いまでは誰も天気の予測ができなくなってしまった」という声がある。狩りの旅に出るのは、天気が比較的安定していると思われるタイミングだ。その予測が当たらなくなり、狩りの旅が危険なものになっている。また海でクジラを捕る民族は、春になって海氷が後退していく途中に、氷が軋みながら海が口を開けたところにクジラが息継ぎに上がるところを捕っていた。それがあっという間に氷が後退するので、クジラを捕るのが難しくなくなってしまった。
一方、夏の海氷が後退するのをよろこぶ人たちもいる。砕氷船でなくても普通の大きな船が北極海に入っていけるようになったのだ。北極海航路と名付けられ、年々航行可能な期間が延びている。これで北極圏の沿岸部に大量の物資を運ぶことができるようになり、これまでは見向きもされなかった土地で大規模な開発が可能となっている。
このように「地球温暖化」がさまざまな現象として誰の目にも明らかに見えるのが北極圏である。
そのようすをよりリアルに伝えてくれるのがエドワード・シュトルジック『北極大異変』(集英社インターナショナル、2016年)である。著者は北極圏を専門とする科学ジャーナリストで、科学者の調査に同行した豊富なフィールドワークによって、北極圏で起きていることを臨場感たっぷりに伝えてくれる。
夏の嵐は高潮を発生させ、場合によっては海岸から30kmも内陸まで平原が浸水するようになった。そこは野鳥の繁殖地であり、そこが海水をかぶって不毛の地となってしまっているという。
ホッキョクグマは心配された通り、その数を減らしている。薄くなった氷の上を半ば水に浸かりながらさまよう姿が観察されている。そうやって苦労してさまよってもアザラシを捕ることはできず、夏に脂肪を蓄えることができない。それでは厳しい冬を越すことができないのだ。野生のホッキョクグマに人間が日常的に餌を与えることを考えないと絶滅から救えないかもしれないという。
カリブーも数が激減しているという。人間による乱獲の影響もあるようだが、気候変動による影響も無視できないという。気温が上昇して南にいたブヨが北上しカリブーにまとわりつくようになった。虫の集中攻撃を受けて狂ったようになって川で溺れるカリブーの姿が目撃されている。秋に雪が降ったかと思うと雨が降るようになり、地表がカチカチに凍りつく。そうするとカリブーは地面の地衣類を食べることができず餓死することがあるという。
また、南の方からこれまで北極圏に生息していなかった生物が侵入しているという。海のシャチ、陸のハイイログマが北極圏でしばしば観察されるようになった。このことが生態系に与える影響は非常に大きいだろう。
一方、北極圏の温暖化をチャンス到来と活気付く勢力もある。石油・天然ガスの巨大資本と各国政府だ。北極圏の地下や北極海の海底は石油や天然ガスの探査は進んでいなかった。これまでは資源が発見されたとしても掘削しようがなかったからだ。それが、北極海航路が開かれたことで状況が一変、各国はそれぞれの地質探査チームを北極圏に送り込んで資源探査レースが行われている。アメリカの地質調査所は、石油や天然ガスについてこれから発見されるだろうという「未発見量」を推定しているが、それが北極圏には世界全体の20%があるとされている。北極圏は「最後に残されたフロンティア」なのだ。そしてそれは「北極海は誰のものか」という政治的なイシューを作り出した。北極海の境界確定に向けて各国の牽制・駆け引きが続いている。その中には軍事力を動員するキナ臭いものもあるという。
そして、北極圏に眠る石油や天然ガスが実際に開発された時、地球はますます温暖化する。北極圏航路はますます安定したものになり、開発はますます進む。そしてホッキョクグマやカリブーはもう動物園の檻の中でしか見ることができなくなるかもしれない。
北極圏の先住民族の立場は複雑である。農業のできない北極圏では、彼らは動物を狩ることでずっと生きてきた。彼らにとってホッキョクグマやカリブーは今でも生活の糧である。この本の中では、減少するホッキョクグマやカリブーを保護する立場の科学者やNGOの意見に反対する勢力として先住民たちが描かれている。しかしながら、いくら反対しても動物の数が減ってしまえば狩りができなくなるということで、最も痛手を受けるのは彼らたちだ。
この本の著者は冒頭で挙げた文章に続いて以下のように述べている。
「こうした事実のほかさまざまな理由から、ホッキョクグマを救う方途を見出すことは決定的な重要性がある。彼らを失えば北極圏の生態系をゆるがすだけでなく、自分たちが引き起こした気候変動に対処することができなかった人類敗北のあかしとなるだろう。」p131
そして私たちは今日も「敗北」に向かって歩んでいる。
















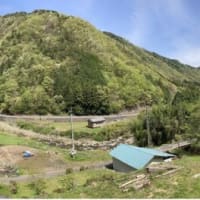


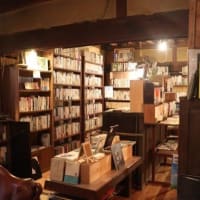
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます