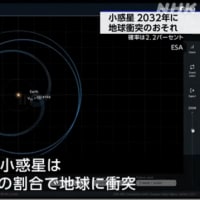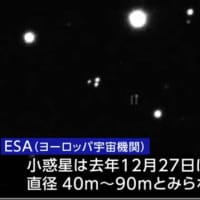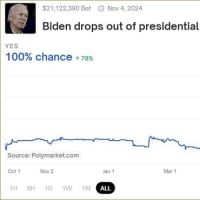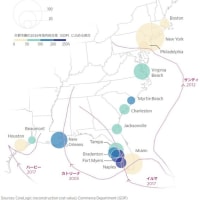宮城県南部で震度6弱を記録した16日の地震について、政府の地震調査委員会は17日、臨時会を開いて検討し、「想定していた宮城県沖地震ではない」とする見解をまとめた。
今後、想定していた地震が起こりやすくなった可能性もあるとして、引き続き警戒が必要だと発表した。
宮城県沖では、平均37年間隔でマグニチュード(M)7.5前後の地震が繰り返し起きており、前回は78年に発生した。
調査委員会はこの地震の震源域周辺で30年以内に同じ規模の地震が発生する確率は99%と発表していた。
今回の地震がこれに相当するなら、当面の地震の確率は減るはずだと関心を集めていた。
調査委員会は、(1)今回の余震分布は78年の余震分布域の南側の一部にかたまっている(2)78年に比べて地震の規模や津波が小さいことなどに注目。今回、想定震源域の一部は破壊したものの、多くは割れ残っていると判断し、想定している地震ではないと結論した。
「今回の地震によって、想定している宮城県沖地震の規模や発生確率は変更しない。いつ起こるかという見通しはむずかしいが、従来と同じように防災対策をとってほしい」と津村建四朗委員長は話した。
朝日新聞 2005年 8月17日 (水) 22:12
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050817/K2005081703030.html?C=S
*************************************
政府の地震調査委員会は、8月16日に発生した宮城県での地震(M7.2)について、想定されていた宮城県沖地震ではないという判断を下しました。
従って「30年以内に99%」の発生確率も変更はありませんでした。
ただ今回の地震によって想定・宮城県沖地震は「どちらかというと発生が早められる」という見方を示しています。
昨日のブログで宮城県沖地震の「単独型」と「連動型」について述べましたが、単独で発生する場合は下記の図の「A1」か「A2」を震源域として発生します。
三陸沖南部海溝寄りの地震(発生確率、30年以内に70%-80%)と連動する場合は、「A1」と「B」、あるいは「A2」と「B」が連動します。
http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_246/html/html/fig2-3-2-3.html
宮城県沖地震が単独で発生する場合、M7.5前後が想定されていますが、「連動型」の場合、次の宮城県沖地震はM8クラスの巨大地震となります。
http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_246/html/html/fig2-3-2-1.html
この図で言いますと「ア」と「オ」の領域が連動するということです。
連動の可能性について政府の地震調査委員会では、「次の活動が単独の場合となるか連動した場合となるかは、現状では判断できない」としています。
ただその可能性は十分ありますので頭の隅に置いておく必要はあると思っています。
新聞報道でも、あまり連動の可能性が指摘されておりませんが、次回の宮城県沖地震は連動型巨大地震の可能性が十分あるのです。
この点、注意を要すると思っています。
ただ東京でも東海でも、また宮城県沖でもそうですが、地震が起こっても、要は犠牲者がほとんど出なければ問題はないわけですから、この点がクリアされていれば大した問題ではないと思っています。
家屋やインフラへの打撃はどうしようもありませんが、犠牲者については、今のところそれほど心配はしていません。
東京や東海等、来ることが、あらかじめ分かっている地震ならば、歪エネルギーの蓄積も少なくて済みますから、むしろ早めに来てくれた方がいいと思っています。
今後、想定していた地震が起こりやすくなった可能性もあるとして、引き続き警戒が必要だと発表した。
宮城県沖では、平均37年間隔でマグニチュード(M)7.5前後の地震が繰り返し起きており、前回は78年に発生した。
調査委員会はこの地震の震源域周辺で30年以内に同じ規模の地震が発生する確率は99%と発表していた。
今回の地震がこれに相当するなら、当面の地震の確率は減るはずだと関心を集めていた。
調査委員会は、(1)今回の余震分布は78年の余震分布域の南側の一部にかたまっている(2)78年に比べて地震の規模や津波が小さいことなどに注目。今回、想定震源域の一部は破壊したものの、多くは割れ残っていると判断し、想定している地震ではないと結論した。
「今回の地震によって、想定している宮城県沖地震の規模や発生確率は変更しない。いつ起こるかという見通しはむずかしいが、従来と同じように防災対策をとってほしい」と津村建四朗委員長は話した。
朝日新聞 2005年 8月17日 (水) 22:12
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050817/K2005081703030.html?C=S
*************************************
政府の地震調査委員会は、8月16日に発生した宮城県での地震(M7.2)について、想定されていた宮城県沖地震ではないという判断を下しました。
従って「30年以内に99%」の発生確率も変更はありませんでした。
ただ今回の地震によって想定・宮城県沖地震は「どちらかというと発生が早められる」という見方を示しています。
昨日のブログで宮城県沖地震の「単独型」と「連動型」について述べましたが、単独で発生する場合は下記の図の「A1」か「A2」を震源域として発生します。
三陸沖南部海溝寄りの地震(発生確率、30年以内に70%-80%)と連動する場合は、「A1」と「B」、あるいは「A2」と「B」が連動します。
http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_246/html/html/fig2-3-2-3.html
宮城県沖地震が単独で発生する場合、M7.5前後が想定されていますが、「連動型」の場合、次の宮城県沖地震はM8クラスの巨大地震となります。
http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_246/html/html/fig2-3-2-1.html
この図で言いますと「ア」と「オ」の領域が連動するということです。
連動の可能性について政府の地震調査委員会では、「次の活動が単独の場合となるか連動した場合となるかは、現状では判断できない」としています。
ただその可能性は十分ありますので頭の隅に置いておく必要はあると思っています。
新聞報道でも、あまり連動の可能性が指摘されておりませんが、次回の宮城県沖地震は連動型巨大地震の可能性が十分あるのです。
この点、注意を要すると思っています。
ただ東京でも東海でも、また宮城県沖でもそうですが、地震が起こっても、要は犠牲者がほとんど出なければ問題はないわけですから、この点がクリアされていれば大した問題ではないと思っています。
家屋やインフラへの打撃はどうしようもありませんが、犠牲者については、今のところそれほど心配はしていません。
東京や東海等、来ることが、あらかじめ分かっている地震ならば、歪エネルギーの蓄積も少なくて済みますから、むしろ早めに来てくれた方がいいと思っています。