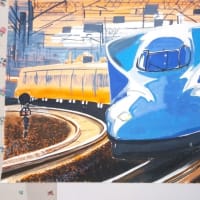想像画が描けない。何を想像してよいのか分からない。と言わせるのは指導者の力不足です。その通りだと思います、ある意味では。そこで考えるのは、ものを考える創造作業は無から有を生むようなものではなく、子どものいろいろな経験や知識の新しい組み合わせで初めて構築されるものではないかと。いわゆる芸術家が言うところの、突然パッとひらめいた、では決してないのです。一人ひとりの子にとって新しいこと、自己表現を目指す行為が創造なのだと思います。そのためには基盤がなくてはなりません。「生活経験」と「関心、感動、記憶」が必要です。
子どもの行動範囲が限られている以上は生活経験は親との同行範囲です。短絡的な例としてお話しますが、苦労してでも公園などへ連れ出すご家庭と、安易に本や映像鑑賞で済ましてしまう家庭とでは、子どもの記憶や感動経験に大きな影響を与えることになります。
ものごとの関心についても、「子どもが関心を示さないから」という理由で親がチャンスを見逃したり、バーチャルといわれる現実を伴わない経験や記憶ほど、頼りないものはありません。実際に「4本足のニワトリの絵」「樹に生る落花生を描く」そんな大人も少なくありません。
ガオー教室の天井に次回課題予定の「天井画」を貼りました。多くの子が気が付かない中で純恋ちゃん(3年生)が「ひげ先生、龍は一匹だよ~!わたし見たもん。」私はとても驚きました。どこで観たの?「お寺さんの天井に描いてあったよ」よほど彼女は強い印象を持ったのでしょう。ご家族に支えられてこその本物の知識が心のポケットに入ったことと思います。
絵は四角いもので、四角形の画用紙に描くものという既成概念を、早くから持ってしまった多くの子にとって、これをほぐすのは大変です。天井を見上げる絵を描く経験は、この先もほとんどないことでしょう。だからこそ今がチャンスです。丸い画用紙を前にして、戸惑うことでしょうが、自由に描いてほしいと考えています。自己表現の方法は限りなくあることを経験してもらいたい。これが今回の目的です。
子どもの行動範囲が限られている以上は生活経験は親との同行範囲です。短絡的な例としてお話しますが、苦労してでも公園などへ連れ出すご家庭と、安易に本や映像鑑賞で済ましてしまう家庭とでは、子どもの記憶や感動経験に大きな影響を与えることになります。
ものごとの関心についても、「子どもが関心を示さないから」という理由で親がチャンスを見逃したり、バーチャルといわれる現実を伴わない経験や記憶ほど、頼りないものはありません。実際に「4本足のニワトリの絵」「樹に生る落花生を描く」そんな大人も少なくありません。
ガオー教室の天井に次回課題予定の「天井画」を貼りました。多くの子が気が付かない中で純恋ちゃん(3年生)が「ひげ先生、龍は一匹だよ~!わたし見たもん。」私はとても驚きました。どこで観たの?「お寺さんの天井に描いてあったよ」よほど彼女は強い印象を持ったのでしょう。ご家族に支えられてこその本物の知識が心のポケットに入ったことと思います。
絵は四角いもので、四角形の画用紙に描くものという既成概念を、早くから持ってしまった多くの子にとって、これをほぐすのは大変です。天井を見上げる絵を描く経験は、この先もほとんどないことでしょう。だからこそ今がチャンスです。丸い画用紙を前にして、戸惑うことでしょうが、自由に描いてほしいと考えています。自己表現の方法は限りなくあることを経験してもらいたい。これが今回の目的です。