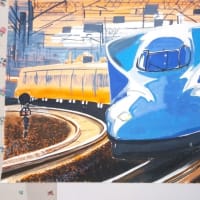「ひまわりを描く」夏の定番テーマなので、子どもたちも つまづくことなく描けるのですが、構図・色調・情景がどれも同じイメージになってしまうことも大いにあるものです。つまりテーマに対してどこまで自分なりのイメージを拡大させ、集約し表現できるか、そうでないかでひまわりの咲き方、インパクトが違ってきます。
児童心理学者などが言われる「本人がテーマの趣旨を自分なりに理解し描くのだから、それを一旦受け入れるのが創作活動の基本である」とする考えがあります。ここで間違えていけないのは、一旦受け入れることは何もしないことではありません。理解だけでは発火しません。物事を真剣に行動に移すには着火が必要です。描くための動機づけ、着火は子どもにも指導者にも同時に行われてこそ、うまく燃え上がると考えます。
手本を鑑賞することも動機づけのひとつですが、今回は子どもたちに「連想ゲーム」を投げかけました。(事前に構想を考えてきた子も多くいましたが、さらに発想の拡大と集約のためにも参加してもらいました)ゲームがはじまり、気になることがおきました。自分が回答できないと心配なのでしょうか「黄色・丸い・大きい、、、。」私がなんとか具体的なイメージに導こうとするのですが、意外な結果となりました。(Sちゃんが「スイカが実る ひまわり!」Goodです!)
一昔前のCMを思い出しました。芸術家の岡本太郎さんのセリフに「グラスの底に顔があってもいいじゃないか!」ひまわりが黄色いライオンになっても、ハートのカタチをしていても、海の中で咲いていてもいいじゃないか。「ひまわりらしく」にとらわれている子に「自分らしく」自由な創作の楽しさへ導くには、連想発想という思考作業を繰り返し、既成概念の殻を破るトレーニングを指導しなくてはいけないと思った課題となりました。
さあ、全員で空の下に大きな自分らしさを咲かせよう!
(もちろんですが、具象画でも抽象画でも今回はOKです。子どもの精いっぱいの描く勇気を励ましてあげるだけで、その子は自分らしく堂々と強くなります、ひまわりのように。 写真は制作途中ですが、ガオー教室のKくんの迫力満点のひまわりライオンなのだ。ガオー!)