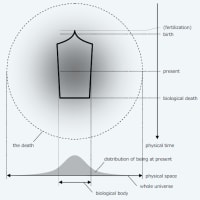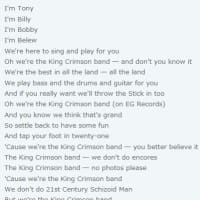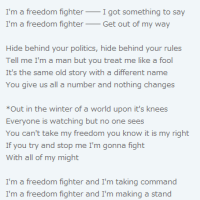謝辞
本書は、わたしがこれまで著してきた他のどんな著書にもまして多くの人からの助力によって成り立っている。これにはふたつの理由がある。まず、この本はわたしが「社会的現実の構築(The Construction of Social Reality, New York: The Free Press, 1995)」で始めた議論の流れの延長線上にあるものである。同書の議論は哲学だけではなく経済学、社会学やその他の社会科学一般の学者から多くのコメントを頂戴した。もうひとつは、わたしはバークレイの社会的存在論研究会(Social Ontology Group)の一員であり、そこでは週1のペースで社会的存在論と関連する諸問題が論じられている。わたしを助けてきた人々のすべてに対してここで感謝を述べることは、[あまりに多すぎて]とてもできそうにないが、少なくともそのうちの何人かのことはここで言及しておかなくてはならない。
わたしは素晴らしい助手達に恵まれてきた。わたしの知的生活に対する彼らの貢献に対して、彼らを「研究助手」と呼んだのでは、適切な概念を与えたことにならないだろう。彼ら全員は言葉のあらゆる意味でわたしの共同研究者である。その中でわたしは特にジェニファ・フディン、アシャ・パシンスキ、ロメリア・ドラガ、ベアトリス・コボウ、マット・ウォルフ、アンダース・ヘドマン、ヴィダ・ヤオ、ダニエル・ヴァサク、ビスキン・リー、フランチェスカ・ラタンツィに感謝している。
彼らはほとんど全員、バークレイの社会的存在論研究会の構成員でもある。同研究会の他の人々の中で特にわたしの助けとなってきたのはサイラス・シアヴォシ、アンドリュー・モアゼイ、マーガ・ヴェガ、クラウス・ストロー、マヤ・クロンフェルド、アスタ・スヴェインドッタ、ディナ・グセイノヴァ、ラファエラ・ギオヴァノリ、アンディ・ワンドである。
「社会的現実の構築」の議論は数多くの学術雑誌や論集の貢献によって成立している。わたしはこれらの貢献の中で特に「アメリカ経済・社会学誌」の特別号*、「社会的現実についてのジョン・サールの考え:拡張・批判・再構築」の編者であるデヴィッド・ケプセルとローレンス・S・モス、寄稿者であるアレックス・ヴィスコヴァトフ、ダン・フィッツパトリック、ハンス・バーナード・シュミド、マリアム・タロス、ライモ・トゥオメロ、W・M・メイヤーズ、フランク・A・ヒンドリクス、レオ・ザイバート、イングヴァー・ヨハンソン、ネナド・ミスチェヴィッチ、フィリップ・ブレイ、バリー・スミスに感謝したい。この号は結局書籍として発行された。
「人類学理論」の特別号*「サールの制度論」の編者および寄稿者ロイ・ダンドレード、寄稿者スティーブン・ルークス、リチャード・A・シュヴェーダ、ナイル・グロス。「意図的行為と制度的事実:ジョン・サールの社会的存在論についての試論集」**の編者兼寄稿者サヴァス・ツォハツィディス、寄稿者マーガレット・ギルバート、カーク・ルードヴィヒ、スーマス・ミラー、アンソニー・メイヤーズ、ハネス・ラコジ、マイケル・トマセロ、ロバート・A・ウィルソン、レオ・ザイバート、バリー・スミス、イグナシオ・サンチェス・クゥエンカ、スティーブン・ルークス。
(中略)
公刊された書籍の中で論じることに加えて、わたしは文字通り世界中で行ってきた講義や講義シリーズの中でわたしの考えを開陳する機会を得てきた。わたしにとって、わたしの考えが検証されたり評価されたり、あるいは攻撃されることでさえ哲学を行うことの本質的な一部である。わたしの得てきた教訓はこうである。「明確に言えないことは理解できていないことであり、公開された論争の場で擁護しきれないような自説はそれを出版すべきではない」。そうした発表の機会のすべてを、あるいは大部分でも、ここで列挙してみるつもりはない。しかしいくつかは特に言及するに値する。
(中略)
その他の友人、同僚、学生達もまたわたしの助けとなり支えとなってきた。ブライアン・バーキー、ベン・ボードレ、マイケル・ブラットマン、グスタヴォ・ファイゲンバウム、マハディ・ガッド、マルチア・ガロッティ、アン・エノ、ジェフリー・ホジソン、ダニエル・モヤル・シャルロック、ラルフ・プレッド、アクセル・シーマン、アヴラム・ストロル、ジム・スウィンドラー。
本書の編集段階で途方もない努力を傾けてくれたロメリア・ドラガ、索引の準備をしてくれたジェニファ・フディンに特に感謝する。
感謝すべき人々がもっとたくさんいることはわかっている。以上は少なくともその始まりではある。わけてもわたしはわが妻ダグマー・サールに感謝したい。彼女はわたしを助け、支え続けてもう52年になる。わたしは本書を彼女に捧げたい。
| ※ | 訳文を作る前に読み直してみたが、結局というか、やっぱり謝辞は謝辞だった。さすがにこれを訳す意味は、訳書を出版しようという人以外にはなさそうである。正直、英文を読んでいるうちにやる気がしなくなってしまった。 ・・・そんなこと、読んでみるまで判らなかったのかと思う人がいるかもしれないが、冗談ではない。英文を目で追って読んだだけでその意味内容が判るというのは、わたしの場合、さっき習ってきたばかりの小中学生でも直ちに読解できるような、よっぽど易しい英語文を読んでいる場合に限られる。 せっかくだから人名や書名誌名がずらずら並んだこの謝辞を訳し、見つかるものはリンクを張って、ということも考えた。実際、今後残りの部分を少しずつ追加して行って、最終的にはそうするつもりである。が、今すぐそれをしなければならない必要を感じない。というわけで、今日のところは主に意味のありそうな箇所の抜粋を中心とした抄訳にとどめる。(Apr.22,2010) |
本書は、わたしがこれまで著してきた他のどんな著書にもまして多くの人からの助力によって成り立っている。これにはふたつの理由がある。まず、この本はわたしが「社会的現実の構築(The Construction of Social Reality, New York: The Free Press, 1995)」で始めた議論の流れの延長線上にあるものである。同書の議論は哲学だけではなく経済学、社会学やその他の社会科学一般の学者から多くのコメントを頂戴した。もうひとつは、わたしはバークレイの社会的存在論研究会(Social Ontology Group)の一員であり、そこでは週1のペースで社会的存在論と関連する諸問題が論じられている。わたしを助けてきた人々のすべてに対してここで感謝を述べることは、[あまりに多すぎて]とてもできそうにないが、少なくともそのうちの何人かのことはここで言及しておかなくてはならない。
わたしは素晴らしい助手達に恵まれてきた。わたしの知的生活に対する彼らの貢献に対して、彼らを「研究助手」と呼んだのでは、適切な概念を与えたことにならないだろう。彼ら全員は言葉のあらゆる意味でわたしの共同研究者である。その中でわたしは特にジェニファ・フディン、アシャ・パシンスキ、ロメリア・ドラガ、ベアトリス・コボウ、マット・ウォルフ、アンダース・ヘドマン、ヴィダ・ヤオ、ダニエル・ヴァサク、ビスキン・リー、フランチェスカ・ラタンツィに感謝している。
彼らはほとんど全員、バークレイの社会的存在論研究会の構成員でもある。同研究会の他の人々の中で特にわたしの助けとなってきたのはサイラス・シアヴォシ、アンドリュー・モアゼイ、マーガ・ヴェガ、クラウス・ストロー、マヤ・クロンフェルド、アスタ・スヴェインドッタ、ディナ・グセイノヴァ、ラファエラ・ギオヴァノリ、アンディ・ワンドである。
「社会的現実の構築」の議論は数多くの学術雑誌や論集の貢献によって成立している。わたしはこれらの貢献の中で特に「アメリカ経済・社会学誌」の特別号*、「社会的現実についてのジョン・サールの考え:拡張・批判・再構築」の編者であるデヴィッド・ケプセルとローレンス・S・モス、寄稿者であるアレックス・ヴィスコヴァトフ、ダン・フィッツパトリック、ハンス・バーナード・シュミド、マリアム・タロス、ライモ・トゥオメロ、W・M・メイヤーズ、フランク・A・ヒンドリクス、レオ・ザイバート、イングヴァー・ヨハンソン、ネナド・ミスチェヴィッチ、フィリップ・ブレイ、バリー・スミスに感謝したい。この号は結局書籍として発行された。
| * | The American Journal of Economics and Sociology 62, no. 1 (January, 2003). また、同号は別冊として再発行された。Koepsell, David and Laurence S. Moss (eds.), John Searle's Ideas about Social Reality: Extension, Criticisms, and Reconstructions, Malden, Mass.: Blackwell, 2003. |
「人類学理論」の特別号*「サールの制度論」の編者および寄稿者ロイ・ダンドレード、寄稿者スティーブン・ルークス、リチャード・A・シュヴェーダ、ナイル・グロス。「意図的行為と制度的事実:ジョン・サールの社会的存在論についての試論集」**の編者兼寄稿者サヴァス・ツォハツィディス、寄稿者マーガレット・ギルバート、カーク・ルードヴィヒ、スーマス・ミラー、アンソニー・メイヤーズ、ハネス・ラコジ、マイケル・トマセロ、ロバート・A・ウィルソン、レオ・ザイバート、バリー・スミス、イグナシオ・サンチェス・クゥエンカ、スティーブン・ルークス。
| * | D'Andrade, Roy (ed.), "Searle on Institution", Anthropological Theory 6, no. 1 (2006) |
| ** | Tsohatzidis, Savas (ed.), "Intentional Acts and Institutional Facts: Essays on John Searle's Social Ontology," Dordrecht: Springer, 2007. |
(中略)
公刊された書籍の中で論じることに加えて、わたしは文字通り世界中で行ってきた講義や講義シリーズの中でわたしの考えを開陳する機会を得てきた。わたしにとって、わたしの考えが検証されたり評価されたり、あるいは攻撃されることでさえ哲学を行うことの本質的な一部である。わたしの得てきた教訓はこうである。「明確に言えないことは理解できていないことであり、公開された論争の場で擁護しきれないような自説はそれを出版すべきではない」。そうした発表の機会のすべてを、あるいは大部分でも、ここで列挙してみるつもりはない。しかしいくつかは特に言及するに値する。
(中略)
その他の友人、同僚、学生達もまたわたしの助けとなり支えとなってきた。ブライアン・バーキー、ベン・ボードレ、マイケル・ブラットマン、グスタヴォ・ファイゲンバウム、マハディ・ガッド、マルチア・ガロッティ、アン・エノ、ジェフリー・ホジソン、ダニエル・モヤル・シャルロック、ラルフ・プレッド、アクセル・シーマン、アヴラム・ストロル、ジム・スウィンドラー。
本書の編集段階で途方もない努力を傾けてくれたロメリア・ドラガ、索引の準備をしてくれたジェニファ・フディンに特に感謝する。
感謝すべき人々がもっとたくさんいることはわかっている。以上は少なくともその始まりではある。わけてもわたしはわが妻ダグマー・サールに感謝したい。彼女はわたしを助け、支え続けてもう52年になる。わたしは本書を彼女に捧げたい。