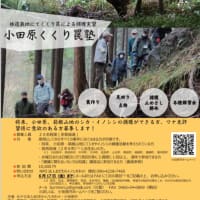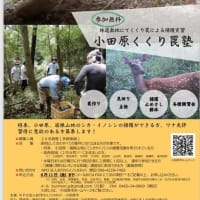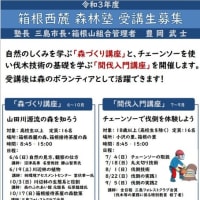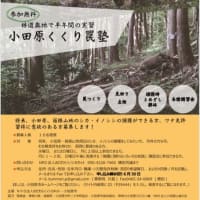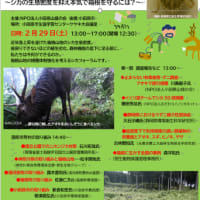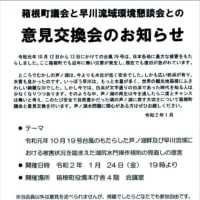小田原のおよそ浜町~本町の海岸近くの松原神社の氏子の地域では、ゴールデンウィーク5/4(土)~5(日)で神輿祭りが行われました。
海岸沿い数kmの範囲が松原神社の各氏子(うじこ)で、その範囲内の各自治会が御輿を持っています。私の地区(浜町4丁目、15区自治会)では北条稲荷の御輿があり、さらに漁の豊漁と安全を祈願した龍宮神社の御輿の2つが同じ町内にあります。
御輿は町内を練り歩くのだが、元漁師町の浜町では名物「お濱めぐり」というのも行いました。「お濱めぐり」は、木遣り歌(♪そ~お~りゃいえ~ええ♪)を歌った後、御輿が威勢良く海に入り、大漁旗が先導して龍宮神社の御輿が先頭になり、各自治体の御輿がそれにつづいて波打ち際を練り歩くというもの(トップの画像)。
地図の中心が浜町の龍宮神社。ちなみに御幸が浜にも龍宮神社があります。

これが浜町4町目に2つある御輿の1つ龍宮神社。地元ではもっぱら「龍宮さん」と呼んでいます。八代龍神ともいう。なんと八代は熊本県八代海のこと。1590年、豊臣秀吉の小田原攻めの際に、八代海からはるばる水軍が来て小田原に上陸しようとしたら台風で難破して浜町海岸に打ち上げられたそうだ。その破船からご神体を取り出して祭ったのがこの神社で、破船した船員さん達は、原住の漁師とともにここに住み着いて代々漁をしたそうです。私が子供の頃まで、地引き網やワカメ漁をしてましたが、漁獲量が減ってしまい、もう漁はやってません。子供の頃の生のシラス(カタクチイワシの稚魚)はうまかった。ちなみにこの辺の昔ながらの家は、写真のように1メートルぐらい土盛りをして家を建ててました。堤防がなかった昔は台風で波がよく来たそうです。

龍宮神社(八代龍神)の御輿

同じ町内の北条稲荷の御輿。この北条稲荷は、小田原に異変があるときは鳴く(伝説)という「蛙石」(かわず石)でも有名。

御輿を担げない子供用として、屋台(山車:だしぐるま)が海岸沿いの道路を練り歩きます。昔はちゃんとした木製の山車だったのですが、壊れてきたりして近年はトラックに飾り付けをしてるところが増えました。綱を子供が引いて練り歩くのですが、少子化時代により、ウチの自治会は山車はもうやってません。これは近所の別の自治会の山車です。中で太鼓、笛などの演奏を子供がしてます。

これが八代龍神の解説立て札。
本記事は、手前味噌ですが、自分のfacebook(下記)から引用しました。
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.639819122710994.1073741830.558435450849362&type=1&l=c40c713839
伊豆川哲也(ブリ森レポーター、野鳥の会西湘ブロック)