今年のゴンクール賞はFrançois Weyergans (ウェイエルガンス?)の?Trois jours chez ma mère?(Grasset)に。ここで写真の右にいる白髪・ヒゲのおじさんが審査員の一人François Nourissierらしい。
馴染みのない作家だが、シムノン生誕百年の折りに書いたEcrivain ou romancier ? (Le Figaro Littéraire, 9/1/03)は覚えている。辛口のもので、
本棚ではいくらでも変な隣りあわせがあり〈決してない〉かは疑問だが、こういうレトリックを尽くした、どうだというような批評文、シムノンには例がない。多少つきあいのある詩人や作家に讃辞を贈るとしても、それは「創造するひと」が同志に向けた軽い会釈のようなもの。ただそれが挨拶程度にとどまっていて、他人の作品に興味がないのではとさえ感じさせるところが問題なのだ。
どんな作家も持つはずの批評家的部分を表に出さない。リンゴの木かもしれないが、着実に小説を産出し続けることのほうが大事なのだ。フランスの知識人が好むpamphlet(論争的小冊子)も、シムノンの著作には見当たらない。『ユダヤ人』のサルトルと、幼い時母の下宿屋にいた留学生の記憶を元に、トルコや東欧生まれのユダヤ人を執拗に描き続けたシムノン。
Weyergansの受賞作?Trois jours chez ma mère?(母の家での三日間)は作者の分身的作家Weyergrafが小説?Trois jours chez ma mère?をどうしても完成させられず、この小説内小説の語り手も・・・と「入れ子」になる。書きあぐむところへプロヴァンスで独り暮らし、まもなく90歳になる母が庭で転び怪我をしたとの知らせ。連想によって次々に脱線が起こる、それが自由自在、優雅で流れるような印象を与える、という本らしい。
("La fluidité Weyergans" http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-693960,0.html)
またまたautofictionではないか。
この言葉の考案者ドゥブロフスキーの作品は芳川泰久『書斎のトリコロール』(自由国民社)に紹介がある。
『断ち切られた書物』では、「作者と等身大」の「私」が書いている、「やがて『断ち切られた書物』という題のもとに本書になるテクスト」に妻が「検閲者」として介入する。

ドニーズはやがて彼と別れ、回想Un oiseau pour le chat(J.-C. Simoën, 1978)を書く。この本でも二人の出会いが語られるが、現実のドニーズはカナダの情報局、次にカナダと連合国の短篇映画を製作・配給するl'Office National du Filmに勤めた、れっきとした職業婦人である。初めてシムノンと会う前、ロンドンに問い合わせ大戦中の彼の行動につき(つまり「対独協力者」でなかったか)確認を取る。答えは"All clear."
速記とタイプは哲学の講義をノートするため覚えた。仕事にやりがいを感じている。けっこう忙しい。強い自尊心、ある経験からもう男は相手にしない、絶対自由でいようと決めたところ。
こういう側面が小説の女性ケイには見られない。ケイは定職を持たず、何やら秘めた過去、虚言癖、といかにもシムノン好みの陰影をつけられ、彼の物語世界にふさわしい女になる。
馴染みのない作家だが、シムノン生誕百年の折りに書いたEcrivain ou romancier ? (Le Figaro Littéraire, 9/1/03)は覚えている。辛口のもので、
Simenon ne voisinera jamais sur les rayons avec Gracq, Mandiargues, Leiris, écrivains de première classe, qui ? donnèrent ? parfois un roman, non pas comme le pommier ses pommes, mais comme la Littérature cette houille produit de loin en loin un diamant. Simenon est resté un mineur de fond. Si son charbon se transmute en diamant, c'est au cours d'un processus mystérieux.(シムノンが本棚でグラックやレリス、マンディアルグと並ぶことは決してないだろう、これら第一級の作家が時には小説を「生んだ」のも、リンゴの木が実をつけるようにではなく、「文学」というこの石炭が時として一個のダイアモンドを生むようにしてなのだ。シムノンは一人の坑夫にとどまった。もし彼の石炭がダイアモンドに変わるとすれば、それは謎の過程を経てである)
本棚ではいくらでも変な隣りあわせがあり〈決してない〉かは疑問だが、こういうレトリックを尽くした、どうだというような批評文、シムノンには例がない。多少つきあいのある詩人や作家に讃辞を贈るとしても、それは「創造するひと」が同志に向けた軽い会釈のようなもの。ただそれが挨拶程度にとどまっていて、他人の作品に興味がないのではとさえ感じさせるところが問題なのだ。
どんな作家も持つはずの批評家的部分を表に出さない。リンゴの木かもしれないが、着実に小説を産出し続けることのほうが大事なのだ。フランスの知識人が好むpamphlet(論争的小冊子)も、シムノンの著作には見当たらない。『ユダヤ人』のサルトルと、幼い時母の下宿屋にいた留学生の記憶を元に、トルコや東欧生まれのユダヤ人を執拗に描き続けたシムノン。
Weyergansの受賞作?Trois jours chez ma mère?(母の家での三日間)は作者の分身的作家Weyergrafが小説?Trois jours chez ma mère?をどうしても完成させられず、この小説内小説の語り手も・・・と「入れ子」になる。書きあぐむところへプロヴァンスで独り暮らし、まもなく90歳になる母が庭で転び怪我をしたとの知らせ。連想によって次々に脱線が起こる、それが自由自在、優雅で流れるような印象を与える、という本らしい。
("La fluidité Weyergans" http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-693960,0.html)
またまたautofictionではないか。
この言葉の考案者ドゥブロフスキーの作品は芳川泰久『書斎のトリコロール』(自由国民社)に紹介がある。
『断ち切られた書物』では、「作者と等身大」の「私」が書いている、「やがて『断ち切られた書物』という題のもとに本書になるテクスト」に妻が「検閲者」として介入する。
本書には、三つの時間が流れている。勝利記念日にわくパリで、妻の不在により生じた孤独な時間。その孤独が誘発する過去への遡行。それはユダヤ人として受けた迫害から、すぐさま戦後の青春時代の体験、それもいつ・どこで・だれと初体験をしたのかという開いへと収赦してゆく。そして最後に、そうした自己の体験を小説に書き、書いた部分を妻に見せて感想をきくという自己言及的な時間が重なる。だから三度目の現在の妻は、かろうじてこの第三の層にしか姿を現わさず、そのことへの妻の不満が爆発したのだ。シムノンの『マンハッタンの三つの部屋』は二番目の妻との出会い・結婚を契機に書かれた。(→要約) 映画俳優フランソワ・コンブにシムノン自身を、ケイには妻ドニーズを重ねることができる。しかしシムノンは語りの構造を錯綜させない。そういうすごさ、面白さはない。

ドニーズはやがて彼と別れ、回想Un oiseau pour le chat(J.-C. Simoën, 1978)を書く。この本でも二人の出会いが語られるが、現実のドニーズはカナダの情報局、次にカナダと連合国の短篇映画を製作・配給するl'Office National du Filmに勤めた、れっきとした職業婦人である。初めてシムノンと会う前、ロンドンに問い合わせ大戦中の彼の行動につき(つまり「対独協力者」でなかったか)確認を取る。答えは"All clear."
速記とタイプは哲学の講義をノートするため覚えた。仕事にやりがいを感じている。けっこう忙しい。強い自尊心、ある経験からもう男は相手にしない、絶対自由でいようと決めたところ。
こういう側面が小説の女性ケイには見られない。ケイは定職を持たず、何やら秘めた過去、虚言癖、といかにもシムノン好みの陰影をつけられ、彼の物語世界にふさわしい女になる。










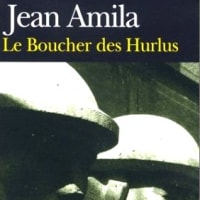
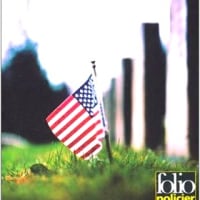
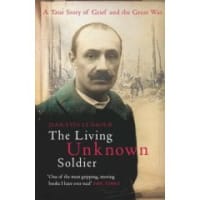







なんとシムノンの記事があり、それもこのような構図の中で語られるのはとても興味深く、楽しみました。今後ともご活躍くださいますよう。
でしたー どうかよろしくお願いします。
ドニーズの回想はゴーストライターの手による「語り下ろし」らしく、シムノンの作品は連鎖して大絵巻になるんだという箇所で「アナトール・フランスの『チボー家の人々』と書いてあると、誰か間違いに気づかなかったのか、とかいちいち余分のことを考えてしまいます。資料としては問題のある本ですが、シムノンの日記や私小説への批評にはなっていると思います。