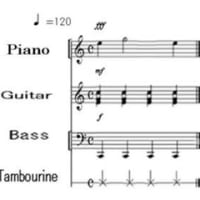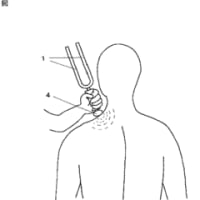今日は、今月の知財勉強会の日。
肌を刺すような酷暑の中、自転車で勉強会会場となっている事務所へ。行きも帰りも汗だくでした。
この知財勉強会の題材は、過去の判例時報(有名な判例雑誌)に掲載された知財判決なのですが、題材がちょっと古いのは否めません。
でも、何人かの弁護士と弁理士が一緒に判例を勉強するというのは貴重な機会で、自分の勉強にもなるので、毎回参加してます。
今回の題材の一つは、「車載ナビゲーション装置事件」(知財高裁平成23年11月30日判決)でした。
名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許権を有していた原告(パイオニア)が、携帯端末を用いたナビゲーションシステムを提供する被告(ナビタイム)に対し、特許権侵害により、システムのサーバ使用やソフト配布の差止めや損害賠償を求めた事件です。
一番の争点は、被告のナビシステムは携帯電話等の端末を用いたものなので、「車載」ナビゲーション装置である本件の特許権を侵害するといえるのかという点です。
結論として、裁判所は、原告の特許権を侵害しないと判断しました。
「車載」という用語の意味を普通に考えれば「車に搭載されている」ということなので、携帯電話等の端末を用いたナビシステムは「車載」といはいえません。そりゃそうだよねという話ですね。
ところで、特許権の侵害うんぬんを検討するときは、文言侵害かどうか、文言侵害でないとしても均等の範囲内かという2点を検討します。
侵害検討の出発点は、特許発明の内容(特許公報の「特許請求の範囲」という欄で、言葉によって説明されています。←知財業界ではクレーム(claim)という。)です。
本件の特許発明の場合はこんな感じで説明されています。
A 目的地を設定しその設定した目的地を示す目的地座標データ及び車両の現在地を示す現在地座標データに基づいて現在地から目的地に至る航行情報を表示する車載ナビゲーション装置であって,
B 目的地座標データを記憶するための記憶位置を複数有するメモリと,
C 目的地が設定される毎にその目的地を示す目的地座標データを前記メモリの少なくとも前回の目的地座標データの記憶位置とは異なる記憶位置に書き込む手段と,
D 目的地の設定の際に前記メモリに記憶された目的地座標データを読み出す読出し手段と,
E 読み出された目的地座標データのうちから1の目的地座標データを操作に応じて選択し前記1の目的地座標データの選択によって目的地を設定する手段とを含むことを特徴とする
F 車載ナビゲーション装置。
発明の内容は抽象的に書かれているため、理解が難しい場合も多いのですが、本件は比較的理解しやすいですね。
特許権侵害となるには、まずはこのA~Fに書かれている構成すべてを満たすことが必要です。そして、そのすべての構成を満たしている場合が「文言侵害」となります。
でも、本件では、AとFには「車載」のナビゲーション装置と書いてあって、発明の説明にも「車に搭載されている」ことしか書かれていません。
そうすると、被告のナビシステムは「車載」されたものではないので、AとFの構成を満たさず、文言侵害ではないと判断されたというわけです。
まあ、裁判所の言うとおりですね。
このように文言侵害ではないとなると、次に、均等の範囲内か(←「均等論」といいます。)という点が問題となります。
要は、発明の要件は満たしていないけど、ちょこっと変えただけで実質的には一緒とみていいかどうか?を判断するのです。
ちょこっと変えただけなのに、文言侵害でない、だから特許権を侵害しない、となっては、特許権者からすればそりゃないよー、という話です。
そんなことなら特許取ってもあまり意味ないし…ってなってしまいますので。
で、本件における均等論というのは、被告のナビシステムは「車載」じゃないかもしれないけれど、ナビゲーションという点では同じなので、一緒とみていいのか?という問題です。
でも、これも裁判所は認めませんでした。なので、最終の結論は特許権を侵害しないということになります。
ネットで述べられている実務家の意見や今日の知財勉強会での意見の中には、この裁判所の均等論に関する判断には批判もあるようです。
本件の特許権が出願されたのは平成3年で、その当時、ナビゲーションといえば車載されたものであったので、携帯端末を使ったナビゲーションシステムが出てくることを予想するのは困難で、特許権者に酷でしょというものや、明細書(発明の説明)に書かれていないことを理由に均等論を判断している、といったものです。
確かに、出願当時は想定できなかったという面もあるかもしれませんが、そもそも、発明の名称にあてはまらないものを、均等により侵害だというのはちょっと違和感があるので、まっとうな判断であったのではないかと私は思います。
均等論成立の要件を示した最高裁の判断では、均等論採用の理由として、
「特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかになった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、…社会正義に反し、衡平の理念にもとる」
として言っていて、発明の名称の一部を「構成の一部」とみるのは無理があるのではないかなあと思います。
クレーム作成では、構成に余分な限定がなされていないかどうかはもちろん、発明の名称についても、そこは均等論の問題にはならないんだと思って、より気を配って考える必要がありますね。
法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!
★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート
★あいぎ特許事務所
商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります