代表の久田です。
本日(2013年2月14日付け)中日新聞社会面に「被災地へ 遠のく足 ~ボランティアが集まらない」という記事が掲載されました。
私はこの見出しに多少の違和感を抱いています。今の愛知ボラセンの状況は、2年を迎える今でもこれだけ現地ボランティアを継続させていることを驚異的に、あるいはすばらしいこととして評価して頂いていいことだと思います。「今も継続 愛知ボラセン 皆さんもどうぞ」というような見出しがいいのになぁと思います。
83回に渡って、参加された6,000人を越える方々が被災者の皆さんと関係を築き、愛知ボラセンの訪問を楽しみにしてくださっていらっしゃる大勢の被災者の皆さんがいらっしゃるから続けてこられました。
確かに、この1ヶ月ほど、現地ボラバスは空席が目立っています。ですが、それでも20人以上の方々が参加されています。また、20人という規模はむしろ適正に近いかもしれないと思われるほど、20人でも充実した活動にボランティアの皆さんはしていらっしゃいます。逆に、今、参加者は100人もいても、それに応えるだけの活動をつくることはできません。
今には今の適正規模と適正期間があるように思います。そろそろほぼ毎週の訪問活動ではなくてもいいのかなと思っています。そろそろ月2回程度の訪問にしていこうかと考えています。なお、仮設住宅がある間は、愛知ボラセンは、月1回は十八成に行きます。これはよほどのことがない限りの決定事項です。仮に私と久世君やスタッフだけになっても続けます。べつにどうということはありません。悲壮感とか、何かの決意ではありません。義務でもありません。自分が訪問したいから、会いたい人がいるから、私たちの訪問を楽しみにしてくださる人がいるから。それだけです。
ただし、自分たちだけでは、たいした力を発揮することもできません。行きたいけど…という方も、まだまだたくさんいらっしゃることも事実です。ですから、できるだけ多くの方々にご参加いただけるような工夫はしていきます。
私は「阪神淡路大震災でお父さんお母さんを亡くした中学生高校生に奨学金を贈る中学生高校生の会」を起ち上げました。18年たった今でも、1月17日には100人を越える中高校生が追悼式を行いました。そして、今月も高校生たちは阪神大震災孤児遺児応援の募金を行います。2011年3月11日の東日本大震災が発生する前の、2010年12月までは、年2回、高校生とともに神戸を訪問し、その時点での「復興」を学び続けました。95年1月~10年12月の16年間で、60~70回くらい神戸を訪問しました。
これをまた18年続けるだけのことです。私にとっては折り返し点をすぎている活動です。
気負わず、無理せず、楽しみながら、でも自分のできることを少しだけ大きくしながら、応援を続けます。
よろしければ、皆さんも、気負わず、無理せず、楽しみながら一緒に応援を続けませんか。













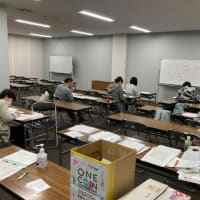











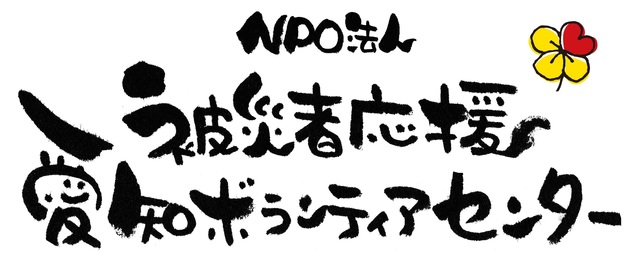

規模の大小ではなく、いま出来ることを自分がやりたいと思うから続ける。
私が好きなアーティストのある歌の歌詞が浮かびます。
『負けたら終わりじゃなくて、やめたらおわりなんだよね。どんな夢でもかなえる魔法、それは続けること』
私も出来ることを出来る範囲で続けたいです。
岐阜のNPO法人KIプロジェクトの鎌倉と申します。
ボク達も月に一回ボラバスを出しています。
新聞記事、読みました。
そしてブログも読ませて頂きました。
ボク達も続けるだけだと思っていますし
続けることの大切さを感じています。
楽しんで続ける。いいですね。
ボク達もそういう想いでやっています。
今後ともよろしくお願いします。
三重県、岐阜県でもボラバスが出ていることが分かり、うれしく思っています。
楽しんで続けていきましょう。ですが、自分だけが楽しい自己満足にならないように自戒しなければならないと思っています。
参加される皆さんが、参加してよかったなと思われ、被災地の皆さんがまた会いたいなと思っていただけるような活動に、自分たちの活動がなっているのかを常に検証し続けることが大切だと思っています。
それを常に意識していれば、自ずと活動は継続していくものだと思います。
私の楽しみは、こうした検証をし続けて、活動を改善し続けることにもあります。また、応援者、被災者それぞれの方々が喜んでいらっしゃる顔を見るのも私の楽しみです。
楽しみとひとくくりにしてしまいましたが、参加される方々、それぞれの楽しみがあり、それを伺うことがまた楽しいですね。
実はこの記事に関して 取材を申しこまれました。と言って愛知からは おいそれと来れるものではなく、電話にてのインタビューをと。
私は「電話では嫌です」と言いました。微妙なことですので。メールにて書かせていただきますと。
★私は、『ボランティアが減って来ているということをメインとした取材ですか? 「ボランティアの人が減って来ている お願いだから募集して」 みたいな おねだりと言うか物欲しげな表現はやめて欲しいな』と。
愛知ボラセンには 毅然としていてほしい が一つの理由。
それとボランティアと言うのは 自らが行きたい!と思ってくれて、そして都合がついた人が参加するものだと それが基本だと思っているから。
いろんな人がいます。お小遣いが少ないので、アルバイトをしてお金がたまった時しか来られないとか、仕事が忙しくて、休みがなかなか取れないとか、お母さんの体調が悪くなって 日帰りならともかく、家を空けにくくなったとか、上司がかわってボランティアに理解がないとか。
でもみなさん、そういった中でもなんとか工夫して、努力して「邦子さん、やっと帰って来られたよ~~」といらしてくれる。
ボランティアが減っています という表現だと そういう人たちの思いや事情をまるで考えてくれていないと 私には思えてしまったのです。
そして今でも 「ボランティアには大きな関心があったけど 自分には何ができるか自信なかったし もう二年たっているから 被災地ではボランティアなんか必要としていないと思っていた、でも紆余曲折して愛知ボランティアの存在を知り、やっと来ることができ、来てよかったと本当に思っている」と言ってくれる人がいるのです。いっぱいいます。
もしかして そういった声を一番聴いている、聞けているのは 後藤文吾さん、阿部恭一(栄悦)氏、そして私なのではないだろうかとふと 思えました。
行き帰りのバスの中で 自己紹介や感想などを話しているそうですけど それはある程度は 他の方の耳を意識しているものです。 私たち被災地の住民に ふっと呟いてくれる言葉を 私はとても大切に受け止めています。
その週によって 心ならずも参加を断らざるを得ないほど 募集があったり 反面バスの中が すかすかなほど 募集が少ないとか 事前のキャンセルが多かったとか。
でもそれは 商売を少しでも知っている人には「そんなこと 当たり前でしょう」なんですよね。
お客さんの都合や気分や体調や そういったことに依存しているのですから。
食べ物商売の場合は 「すたれ」が出て その分は赤字です。 そして 宿泊施設の場合は その日の空室は「赤字」ということになります。
十八成は 以前 この小さな集落に 雑貨屋 7軒 洋品店 1軒 魚屋 1軒 パーマ屋 1軒 床屋 2軒 そして民宿が 6軒ありました。 人口、それと軒数から見て 商売人の確率はけっこう高く、みんなが「赤字補てん」の工夫をして どうすればお客が増えるか また リピーターが増えるかを 精一杯考え続けていました。
その多くは 後継者不足でやむなく閉店となりましたが。
愛知ボラセンは 商売 では決してありませんが どこか共通するところがあると 私は思っています。
そして 参加してくれた人たちが 「また行きたい」 と思ってくれるためには 私たちにも責任があるような気はしています。 ですから 恭一班が生まれました。 阿部邦子の「生きて欲しい」の語りの時間が生まれました。
つまりはやはり 歩み寄りに尽きると思います。
私たち被災者と スタッフの方がもっともっと歩み寄り そしてスタッフの方が 被災者とボランティアのパイプ役となって
ボランティアの人が 「**さんにまた会いたいから帰ってきました」と。
一見 理想論のようですが 基本はそこだと思います。
そして できれば寄付金を戴いてくれるようになれば そんな 「募集してくれる人がいないと 愛知ボラセンは やっていけなくなりますう」 ってことは・・・・。
愛知ボラセンは これから万が一のことがどこかに発生した時の 手本 見本だと思います。 愛知ボラセンが消滅することは 日本の損失です。
そして ボランティアに参加するということは 決して 被災者のためだけのものではありません。 そこを勘違いしないでほしいです。
じかに被災地を見て、 被災者の話を聞いて そこから何かを得て 万が一の時 自分を そして大事な人を守れるように・・・・・そのためのものでもあるのです。 それでこそ 私たちの命をかけた体験を 活かし続けてくれる ということであるということを ここでもう一度 考えていただきたいと思います。
最期に中日新聞さんには 感謝です。
立場が変われば どこに重点を置くか どこを強調するか その視点はかなり変わると思います。
中日さんは 『ボランティアが減っている』 そこに視点を定めなした。 愛知ボラセンのリーダーはじめ多くのボランティアに人たちは 『二年過ぎた今でも毎週ボランティアバスを出せています、皆さん一緒に活動しませんか?』としてほしかったようです。 そして私は 『ボランティアは決して被災者のためだけのものではない 目と耳で被災地に触れ それによって万が一の時 自分と大事な人を守るための何かを得るためにもなっている』ということを伝えたかった。
でも 無視 が一番怖いしむなしい。 中日新聞さん 取り上げてくださって ありがとう。
今度は私の視点による取材をよろしくです♪♪