《創られた賢治から愛すべき真実の賢治に》
賢治昭和2年の上京と三ヶ月間滞京ではどうすればこの矛盾は解消できるかだが、この澤里武治の証言に正しく従えば「現賢治年譜」は成り立たず破綻しているし、その一方で、そのような上京をしたというのは昭和2年の11月頃であるという蓋然性が極めて高くなったのだからこのことと次の二人の証言、
・伊藤清の証言
(「羅須地人協会時代」に)上京されたことがあります。そして冬に、帰って来られました。
〈『宮澤賢治物語』(関登久也著、岩手日報社)〉
・柳原昌悦の証言
一般には澤里一人ということになっているが、あのときは俺も澤里と一緒に賢治を見送ったのです。何にも書かれていていないことだけれども。
〈菊池忠二氏の柳原昌悦からの聞き取り〉を組み合わせればおのずから導かれる仮説が検証できればそれは可能だ。
具体的には、三人の証言を補完し合いながら組み合わせれば次の、
〈仮説☆〉賢治は昭和2年11月頃の霙の降る日に澤里一人に見送られながらチェロを持って上京、しばらくチェロを猛勉強したがその結果病気となり、3ヶ月弱後の昭和3年1月に帰花した。
が定立できるし、それを検証してみたところいろいろと裏付けることはあっても、この仮説に対する明らかな反例は一つもないから検証できる。ちなみに、霙の降る日にチェロを持って上京したのが昭和2年の11月頃であれば、先に掲げた〝「羅須地人協会時代」概観〟を見れば直ぐわかるように、その「三ヶ月間」は大正15年12月上京では到底無理だが、昭和2年11月であれば余裕を持ってすっぽりと当て嵌めることができることが一目瞭然であろう。したがって、この仮説に対する反例が見つかっていない現状では、それに伴って「賢治年譜」は次のような修訂が必要であろう。
・大正15年12月2日:柳原、澤里に見送られて上京。
・昭和2年11月頃:霙の降る寒い夜、「今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する、とにかくおれはやる」と賢治は澤里に言い残して、チェロを持って上京。
・昭和3年1月:滞京しながらチェロの猛勉強をしていたがそれがたたって病気となり、帰花。漸次身体衰弱。
なお、これに関して注目すべき事実がある。前述したように、昭和32年頃を前後して澤里の証言の改竄が何者かによってなされたわけだが、奇しくも同じ昭和32年頃を境にして、かつての「賢治年譜」におしなべてあった、次の2項目が賢治年譜から突如消え去った。・昭和2年11月頃:霙の降る寒い夜、「今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する、とにかくおれはやる」と賢治は澤里に言い残して、チェロを持って上京。
・昭和3年1月:滞京しながらチェロの猛勉強をしていたがそれがたたって病気となり、帰花。漸次身体衰弱。
(ア) 昭和2年:九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。
(イ) 昭和3年:一月 この頃より、過勞と自炊に依る栄養不足にて漸次身體衰弱す。
ちょうどこれは賢治の父政次郎が亡くなった頃である。おそらく、この頃になにか大きな動きがあったであろうことが考えられる。そして、まさにこの〝(イ)〟が、先の〝〈仮説☆〉〟を強力に裏付けてくれる。(イ) 昭和3年:一月 この頃より、過勞と自炊に依る栄養不足にて漸次身體衰弱す。
とまれ、この反例が見つからない限りという限定付きではあるが、今回のトップに掲げた
(3) 賢治は昭和2年の11月頃から約三ヶ月間滞京、チョロの猛練習がたたって病気になった。
は「事実」であるとしてよいことになった。
言い換えれば、現「賢治年譜」は大正15年12月2日の上京の典拠にしている澤里の証言を恣意的に使っているので、そこにはいわば「三か月間問題」という難題が横たわっている。早急にこの難問を解決してほしいものだ。
<注> この項については、拙著『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』において実証的に考察し、それを詳述してある。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “『「羅須地人協会時代」の真実』の目次”
“『「羅須地人協会時代」の真実』の目次””みちのくの山野草”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
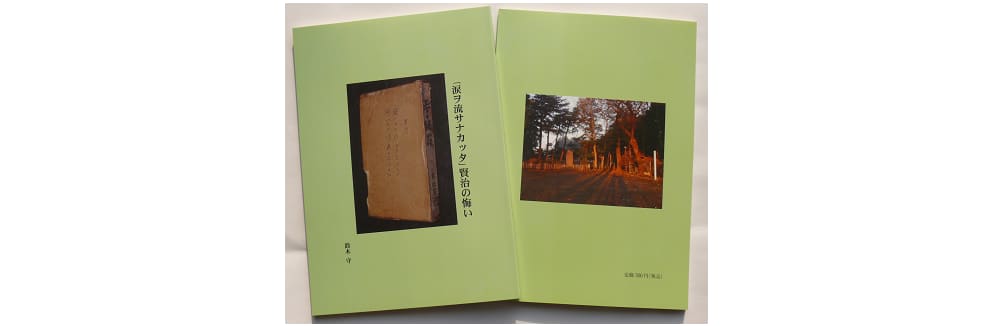
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
◇ 現在、拙ブログ〝検証「羅須地人協会時代」〟において、以下のように、各書の中身をそのまま公開しての連載中です。
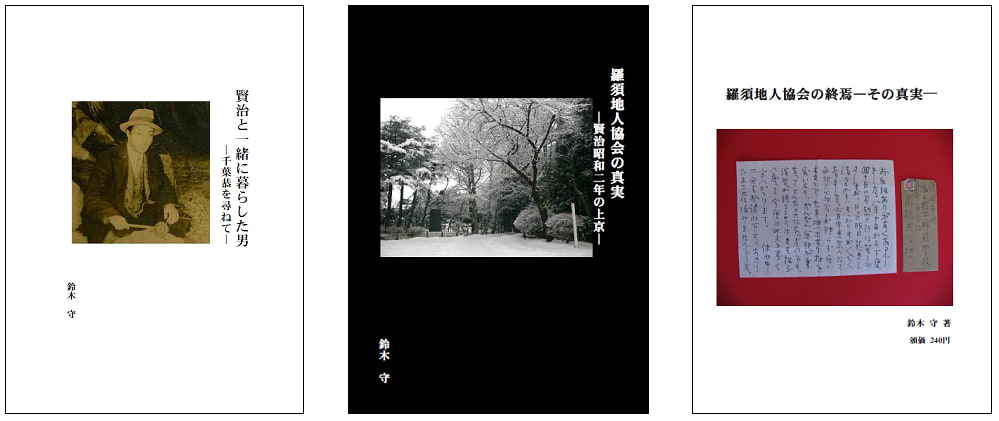
『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 『羅須地人協会の終焉-その真実-』
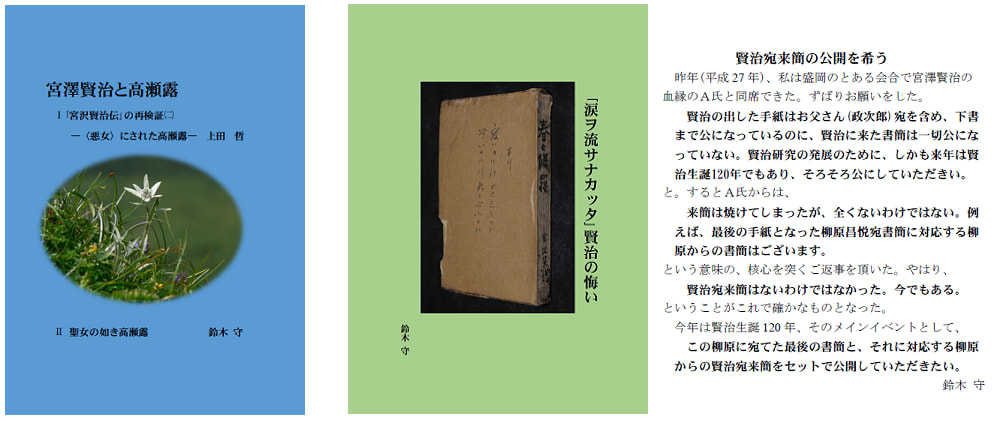
『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) 『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』
















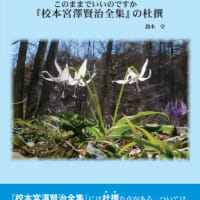
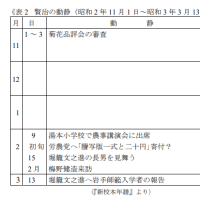






懲りもせず、「復亦如是(マタカクノゴトシ)」なる〈道求道(コトバを求める道)〉、参りますです。小生の〈言語ゲーム(言語使用)〉道樂には辟易とさせられるでしょうが御堪忍御勘弁下さい。
いきなり〈道草道樂〉から始めますがお許し下さい。で、「辟易の辟」という字にも〈辛〉という字が蔵されています。その字面から、この字が、〈癖〉や〈壁〉や〈僻〉あるいは〈避〉などの「あまり吉祥に非ざる文字」を生み出す水源になったのかしらん、などと妄想を広げて遊んありしております。 で、小生が、「辛を蔵している字」の中で最も好しと作しているのは、今日では〈弁〉という全く異質な字に置き換えられている〈辯〉と〈辧〉と〈瓣〉の三字です。どれも、「二つ辛の挟んでいるカタチ」です。先ず、〈瓣〉は「紫苑の花瓣(はなびら)の〈弁〉」で〈言述〉の意ですね、〈辯〉は「辯護人の〈弁〉」。〈辧〉は〈弁別(わきまえる)〉の意ですね。因みに、白川静か師によると、「言という字は、口(サイ)に辛を突き立てたカタチ」だとか。〈口〉は〈クチ・マウス〉ではなく「神の祝詞(のりと)を入れる箱の象形」なんだとか。で、〈辛〉はその蓋を開けるための刀針だったのだとか。そんな因縁があってか、「〈辜・辠(つみ)〉は苦く辛い」という物語(ナラティ―ヴ)が作られたようで。兎も角も、甲骨文字が作られた〈殷(商)〉の時代の昔話という因縁という次第。 という次第で、次の如きヘタレクイズ問題が。道く、「〈弁(辯)〉という字には〈辛〉という字が何個蔵(かく)されているか?しっかりと弁護せよ。」、なんてね。「辛・辛・辛なる口こそが辯なるべし」などと道に楽しむは奇怪(ヲカシ)、などと。
と、斯様な「埒もない〈ことば遊び(戯言)〉」を、「手宮文字です々々々々々々」などと燥ぎまわった「求道すでに道の人人(にん)」はどんな風に受け流すでしょうか吾不識。 因みに、「〈不識〉という道」という辯は、かのダルマさんが、遼の武帝から「如何なるか是仏?」と問われた時のコタエですね。同じ意の公案(禅問道の問題文)に「如何なるか祖師西来之意?」やら「庭前の柏樹子とは如何?」などなどのバリエーションがあるわけですね。
で、譬えば、賢治が作成した公案を小生流に並べてみると、「如何なるか、〈私という現象〉なる〈透明な幽霊の複合体〉とは?」とか、「〈イカリのニガサまた青さ〉なる〈青い照明〉とは如何?」とか、「模範正答も本質も空無なるが故の〈未完成の完成これ完成なり〉ならん乎?」などなどといった塩梅になるのですが、はてさて、「難有い々々々」ということになってしまいました。
ところで、この「難有い(アリガタイ)々々々」という奇妙な日本語表現は、かの送籍者漱石が、その『吾輩は猫である』の結語として用いた〈道得〉もしくは〈道破〉ですね。尤も、それを〈道得(重要テクスト)〉あるいは〈道破(ブレイクスル―的論破)〉とではなく、「単なる戯言」として棄て置くこともデキル訳ですね。尤も、その言述(ディスクール)を「ありがたいありがたい」などと解り易く書き直して了うと、「新しい問い直すや読み直し」は不可能になって仕舞うという次第です。 譬えば、「世界がぜんたい幸福にならないうちは」という道得を、「世界全体が幸福にならないうちは」という道取に変じて、世俗的幸福観を物差しに用いて
〈個人の幸福〉について考えを巡らせ始めたりしたなら、小学生の頭でさえ、「この人は可笑しな奴だ!」と考えるでしょうし、「この文の書き手はトータリタリアニズムの徒なのだ!」と軽蔑するオトナや賞賛するオトナが続出することは避けられないのではないでしょうか。」。ところで、「日本国では主権は国民にはない。」などと平気で発言するオトコを党支部幹事長にしている政党の多数派は、何方の賢治像が広がることを望んでいるんでしょうかシラン。全く、吾不識と呟きたくなってしまいます。 と、〈前置き道取〉だけで、字数が尽きてシマッタようです。何時も何時も、「シマッタ了った閉まって仕舞った」の連続で御免下さい。
2016,3,22 22:05 明日は愈々検査の結果が…
文遊理道樂遊民洞 玄妙に呟き給う
そう言われてみますと、〈辯〉〈辧〉〈瓣〉の三字はいずれも「二つ辛が挟んでいるカタチ」ですね。辛さんが〈弁〉が立つのがこれでよくわかりました。そして、私が辛さんに全く歯が立たないわけもこれでよくわかりました。
そこで教えてもらいたいのですが、「世界がぜんたい幸福にならないうちは」の「ぜんたい幸福」という成語はあるのでしょうか。あったとすればそれはどのように定義されているのでしょうか。残念ながら探し出せずにいますので。
例えば、ベンサムの「最大幸福」であればそれは「the greatest happiness」の直訳だからすんなりと了解できるのですが、「ぜんたい幸福」あるいはそれが「全体幸福」のことであったとしても、このことを考えようとした途端に私の立っている足元では液状化現象が起ってしまいます。定義が確りしていない場合、私はそれ以上のことを考える能力がないということに気付いてしまいます。
鈴木 守
遂に、守先生と文遊理道樂遊民洞なる不埒者との間の、「道(ことば)の道」あるいは「賢治道という現象」についての〈懐疑(コギタンス)〉のヴェクトル、いわば、「実数と虚数との間の因縁関係性の相(カタチ)」の玄妙なる差異性が、…。譬えば、「〈カタチ〉とは言うっても、〈フォルム(フォーム)〉と〈フィジクス〉と〈フェイズ〉、そして〈タイプ〉や〈スタイル〉や〈モード〉との間には如何なる差異性があるのかを明らめ定義してたもれ」、などと請われたならば、吾、如何せん、などと。 で、先ずは、「如何なるか定義とは?」と自問致すに、「或る、〈語や文〉あるいは〈名や概念〉の意味・意義内容を一意的一義的に確定せんと欲す言語行為なる可し」、と。
で、「〈道〉や〈名〉の定義不変化は可能なるか?」と問い質した中国人のハジメビトこそが〈老子〉あるいは〈荘子〉だったのではないか、と。道く、「道嘉s可道、非常之道。名可名、非常之名。」、と。
で、ほぼ同時代の印度のゴータマさんが自問して道く、「言語道に〈自性(じしょう・実体性・不変なる本質本性)〉は実在するのかシラン?」、と。で、自らに応えて道く、「自性実在はなかるべし。生起するのは現象のみ。〈我〉とは千変万化する現象のみなり.諸法無我・諸行無常なるが故に一切皆空にして皆苦なるべし。」、とか。 で、ここで、「言語概念分節以前とそれ以後」という言語宙宇観が。『老子第一章』の術語(ターム)で謂うと、「無名(むみょう)なる〈妙(みょう)〉」と「有名(ゆうみょう)なる〈徼(きょう)〉」との両(ふた)つ。で、この両者が出で来る場としての〈玄(げん・くろ)〉が想定された、と。「〈妙・徼・玄〉 と〈道・名〉 という概念間の因縁関係性」についての小生の明らめ方についてえはまた別の機会に。 因みに、言語哲学としての仏教での〈サッ ダルマ〉に〈妙法〉という「概念(コンセプト)あるいは名辞(ネーム)をあてたのは何という名の個人でしたか、…。〈スートラ(経)〉は〈テクスト(教科書)〉の意ですが、何故、〈フンダリーカ(白蓮華)〉でなければならないのかは。「帝釈天と多他t勝手戦って敗れた非天阿修羅族が蔵(かく)れたのは蓮華の根の孔の中」という昔話が『臨済録』や漱石の『一夜』(『草枕』の先駆形)に書かれています。
で、「諸法無我、諸行無常。」つまり「色即是空、空即是色。受想行識、復亦如是。」という道得でプレゼンされる言語胃身意味観は、「不変普遍なる定義は原理的(本来)に不可能なんじゃ」といった塩梅。それをれが意味する四文字は、〈言語道断〉〈言詮不及〉〈不立文字〉〈直指人心〉〈単伝心印〉などの禅語。尤も、俗語化した言語道断はトンデモナイことに。 で、「私という実存自我」とではなく「私という(因縁関係性としての)現象」と自己規定していたかの如き「賢治の〈言語ゲーム(言語使用)〉法」、小生流に道う「賢治の求道」に話を移します。
で、「〈世界全体が幸福〉ではなく、そうではなく〈世界がぜんたい幸福〉」という道得あるいは道破についてですが。勿論小生も、「世界がぜんたい幸福」という日本語表現は奇怪しくも可笑しいと考えます。で、このヲカシサは賢治自身が企図的に仕掛けた可笑しさだと明らめるに至ったという次第です。世俗の妥当な用法では「世界全体が幸福」にせざるを得ず、そう言語表現するとどう解釈されるかを百も承知の上で、斯様な「玄にして妙なる日本語表現」を用いたのではないか吾不識、というのが小生の辿り着いた「透明な幽霊の複合体なる青い照明なる阿修羅賢治言語宙宇」という因縁です。 で、否応なく、その問いは、「如何なるか、賢治は斯様に玄妙不可思議なる日本語表現を用いたのか?」という懐疑(コギタンス)を自己創出しますよね。というより、この二つの問いは「鶏と卵の関係性」に似て、何方が先で何方が後ということのない両義的な因縁関係性を蔵していると考えて来ました。 で、その懐疑こそが、「如何なるか『一九二七年時点での盛岡中学校生徒諸君へ寄せる』問題?」といった次第です。つまり、小生にとっては、『農民芸術概論綱要・序』と『生徒諸君に寄せる』そして『藤根禁酒会に贈る』とは〈ニ而一一而ニ〉つまり〈不同不二(不一不二)〉という因縁関係性にある、という次第です。解り易く言えば、「切り離して考える訳にはいかない」、と。
またまた長くて晦渋な道取になりつつありますのでこの辺で小休止を。
文遊理道樂遊民洞の道く 2016,3,23 20:22
「一先ずは小休止」と書いて止めたのは、〝「世界がぜんたい幸福に」と「世界全体が幸福に」との間の因縁関係性〟についての小生の考量については、〈承前(こと上げ挙げ以前)〉だったこととの〈因縁果起〉ということに。 念の為に書きますが、おそらくは「世界がぜんたい」という道取がそうであろうと思われるの同様、〈因縁果起〉などという四文字は普通の用語世界(ボキャ宙宇)には有りませんよね。それは、新渡戸稲造の造語である〈温新知故〉や、小生の遊語である〈流石漱石流〉だとか〈流石送籍者漱石〉だとか〈文遊理道樂遊民洞〉などといった〈言語ゲーム(言語使用)〉といったボキャと同様に私人的造語遊戯に過ぎません。 因みに、これまで再三に亘って使って来た〈言語ゲーム〉という概念(コンセプト)は、その論理青年期に、B・ラッセルに激賞され論理実証主義の出発点とも称され、G・フレーゲの思想の感化を強く受けて『論理哲学論考』を書いたL・ウィトゲンシュタインが、前期哲学と二律背反関係にあるかの如き、その後期の言語哲学探究で用いた概念です。ごくあっさりと道うと、「言語の意味作用は言語使用の場によってのみ生成する」といった塩梅の言語胃身意味観と諒解しています。 「言語の意味はその使用状況場によって千変万化する」という言語意味観は、「概念言語分節の固定化」としての〈実体(本質)論的言語意味観〉や〈定義の不可能性〉を否定することになりますね。 で、「前期L・W哲学と後期LW哲学とはアンチノミ―関係にある。」、とい書いた訳ですが、L・W自身は、〈言語ゲームの哲学〉の書とされる『哲学探究』の序に次のような道得を遺しています。
道く、「わたくしは、自分の最初の書物(『論理哲学論考』)を再読し、その思想を解説しなくてはならない機会に見舞われた。そのとき、突然、旧著の思想と新しい思想を一緒にして公刊すべきではないか、新しい思想は、わたくしの古い思想との対比によってのみ、ま
たその背景の下でのみ、その正当な照明がうけられるのではないか、と思ったのである。」、と。 つまり、L・W自身は、世上では二律背反(アンチノミー)と目されていた、「〈『論理哲学論考』の哲学〉と〈言語ゲームの哲学〉との間の因縁関係性」を、「不同不二にして不一不二」と、つまり「相互補完的かつ相互依拠的なるによって不即不離」と見做していたと享受して好いのではないかと考えたという次第です。
尚、小生が白堊校を離れるに際して、研究紀要『自彊』(S63[)に「視えるものを見えるものにするために」と題して書いた〈論文ではないエッセイ〉に引用したL・Wの詞は丘静也訳の『反哲学的断章』の中から、軌感銘を受けた「言語ゲーム哲学的な断章」なのでした。因みに、小生は、その断章と『生徒諸君に寄せる』の断章とを重ねて楽しんでいた気がします。その名可でも特に気に入っていた断章を三つばかり。
「 信じるのだ。だからといって損するわけじゃな い。
だが、「信じる」ということは、権威に服従する
ことである。いったん権威に服従してしまえば、
権威に反抗することなしに、権威を問いなおし、
改めて権威を信じるに足るものと思うわけには
ゆかない。」
「 怖じ気ではなく、怖じ気の克服こそが、称讃に
あたいし、人生に生きがいをもたらす。
器用さではなく、ましてや霊感などでもなく、
勇気こそが辛子種であり、生長して大きな木に
なる。」
「 功名心は、思考の死。 賢さという禿山から。愚かさという緑なす谷間
に、いつも降りて行くことだ。」
譬えが、その頃の小生は、この〈オクシモロン(対義結合的レトリック・撞着語法)〉を用いた「賢さという禿山」という道取を「公理演繹的トップダウン思考法」の、「愚かさという緑なす谷間」という言述を「事象帰納法的ボトムアップ思考法」のメタファーなのではないか、などと。「権威への反抗」ではなく「権威主義への反骨」こそが一大事なるべし、と。されど、それを実践するには、とてつもない勇気が不可欠となるわけで。ヒトラー君臨時代の裕福だった猶太人哲学者L・Wが後世へ語りかけた〈道〉とは。
未だ未だ承前のままですが、再びコビル時
2016,3,24 17:40 文遊理道樂遊民洞のほざく
追伸
昨日、大腸精密検診の結果聞きました。特段
の異常は見つからず、とりあえずホッでした。
今晩は。
この度の検査の結果、異常なしでよかったですね。
これで、今後ますます「辛ワールド」がさらにでっかく構築されてゆくものと期待しております。
ところで、「農民芸術概論綱要」はあくまでも「理論」であるべきだと私自身は思っております。したがって、その意味するところはユニークに決まるものだと思います。ところが、実際には例えば
(1) 世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない
(2) 求道すでに道である
(3) 永久の未完成これ完成である
という記述がその中にあり、これらにはいずれも自家撞着がありそうで、その意味は少なくともユニークには定まりそうにありません。よって、普遍性がないのではなかろうかと思ってしまいます。つまり、「農民芸術概論綱要」は「理論」ではないのかと私は悩んでしまいます。
一方で、「農民芸術概論綱要」そのものが「理論」ではなくて「詩」であるとすれば、私の見方はまた違ってきます。もしそうであれば、前掲の(1)~(3)をあれこれ思索することは楽しそうですし、その意味するところも深いものになり得るということだけは何となくわかります。ただ、それ以上のことは、私にはその鑑賞能力が貧弱なので直ぐ諦めてしまいます。
というわけで、質問いたしましたのにも関わらず、私めには「辛ワールド」が難しくて今回の辛さんからのメールに対して脳味噌が液状化現象を起こしてしまい、まともなご返事ができませんでした。お許しください。
鈴木 守
で、件の提言、改めてその原典なる道得を明らめて観ると、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。」、ですね。そして、この判断文に対応する提言が、「われらは世界のまことの幸福を索(たず)ねよう。求道すでに道である。」ということに。 で、不用意に書き換えられ流通している文が、「世界全体が幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。」ということに。
而して、中学生の頃だったと記憶しますが、小生も最初に読んだのも書換え文の方で、その心象は、「なんて阿呆らしい寝言を言うんジャロ!」ののでした。
固より、この文脈での〈世界〉という語は〈外的ワールド〉の意味に解し、「個人の内的世界」のことなどは全く考えもしませんでしたし、〈幸福〉という名が代理する意味も「俗世間的な意味での幸福「」といった程度で、「人間にとって幸福とは如何?」とか、「個人にとっての幸福とはどういう状態なのだろうか?」などといった、ほんんお一歩を進めた自問など立てはしませんでした。
しかしながら、十四歳になって、「〈或る意味で〉を用いて短文を作れ」という国語授業の宿題に対けて、「或る意味で、日本の敗戦は戦後の日本にとっては幸福だった。」という文を作り、その教師に褒められて不満を感じたヘソマガリ少年期になると、コトはそう単純にはいかなくなった気がします。
というのは、懸命に考えた末に辿り着いた本音は、「あらゆる意味で日本の敗戦は戦後日本にとって幸福だったに違いない。」 といった塩梅だったものですから。
実は小生、小学五年生ぐらいから、第二次大戦中の日米独英の戦闘機や軍用艦船の鉛筆精密描写に請って、いちいち写真など見なくとも、たとえば、零戦の21型、32型、51型などを描き分けることが出来るようになっていました。固より、ムスタング、グラマン、メッサーシュミット、フォッケウルフ、スピットファイアなどを描き分けることなど雑作もない、と。因みに、描画記憶というのは奇妙なもので、小学生時代にインプットしたそれを六十年後近い今再現するのは造作もありません。尚、「機械の形」は、「人の顔の表情のデッサン」と比べたら雑作もないことでしたから、中学生になってからは人物ばかりを描くようになって後に繋がったという次第です。
で、軍用機械を描く為の写真情報はどう手に入れたのというと、戦記雑誌『丸』を三年間ほど購入していたのでした。で、写真以外にも目ぼしい戦記記事は読んでいた訳で、〈『丸』的太平洋戦史〉は頭の中に刷り込まれてシマッタという次第です。
かくして、「学校では教えてくれない史実」なる「ミッドウェー作戦の大失敗」に始まる以後の日本帝国軍の惨めな敗北の連続から「一億玉砕から一総懺悔まで」というあまりにも愚かしい軍国主義国家大日本帝国の醜態を。
小学生の頃は、父親に向かって、「日米開戦の頃、日本はアメリカに勝てると思った?」 というお定まりの質問を何度も対けていたのは、「戦争に勝てるなら真珠湾奇襲もありかな」といった考え方をしていた気がしないでもないですが、中学二年生にもなると、「もし日本が戦争に勝っていたならエライことんみなっていただろうな。」、と。何と言っても軍国主義の維持と徴兵制の継続による日本国民とりわけ若い自分たちが経験せざるを得ない不幸がどんなものかは、と。
そんな、日中米十五年戦争観が十五歳の小生の頭を占有していたが故に、白堊校に入学した四月の、松本竣介画集の巻末に掲載されていたリベラルエッセー『生きている画家』との邂逅が、その後の小生の思想的な歩みの出発点になってしまったという次第です。
という訳で、小生にとっての「国民にとっての幸福と不幸は如何?」という懐疑に対してのイメージはそんな因縁から切り離しては考え難いのでした。
もっと具体的にいうと、「主体的個人にとっての幸福とは如何?」 と問いう前に、「己の自我を尊重せずにはいられない個人にとっての最悪の不幸とは如何?」という設問なのでした。つまり、「不幸から免れることができる幸福」というようなに、〈消極的な幸福〉をしかイメージできないという〈人見知り型対人恐怖症気質の個人〉の内的世界が、オロオロトボトボと歩き廻っていたという次第です。別に、「サムサノナツ」や「ヒデリヒドリノトキ」ではなくとも、「ゲンキニ歩ケ!」と他人様に向かって叫びかけたりは出来ず、「ヒドリトボトボオロオロ歩キ廻ッテ他ノ皆ニ遅レテシマッタ!」といった体でしたので。 譬えば、「行列ノ先頭者型気質」と「行列ノ最後尾者気質」 という両つの喜七気質を背って設定したなら、守先生は、自分は何方側に入るとお考えですか。小生の場合はハッキリと後者です。この問いを、「権力や権威、時勢時流や多数意見などに服従雷同的スナオビトか、それとも懐疑批判的で自分なりに合点納得がゆかなければ動きたくないヘソマガリか?」 といった疑問文と組み合わせたなら、どういうことになるのでしょう。
おそらくは、斯なる相反両気質者の間での幸福観と不幸観は随分と違ったものになるのではないでしょうか。 端的に言えば、小生の〈幸福不幸観〉 は、「個々人の個性や価値観や人間観や世界観などによってまるで違ってしまう。その別異性によって、同一の状況に対しての幸福感と不幸感が楽典逆転してしまうことも大いにあり得る筈だ。」、といった塩梅にならざるを得ない訳です。そんな訳ですから、「国民の最大幸福の為は戦争に撃って出ざるを得ない場合もある訳です。」 といった反知性主義的ヤンキー流の主張には〈批判への意志〉を対けずにはおれないという次第です。
というわけで、小生にとっては、〈ぜんたい幸福〉おいう坐りの宜しくない日本語狂言を、「ベンサム流の最大幸福」という世俗エコノミクス流の生存権との兼ね合いでは考えてみようもないという次第です。
ところで、守先生は、「正義の為の戦争」とか「正義の為の殺人(大量虐殺と個人虐殺とを問いません)」といった観念を受容(じゅよう)や受用(じゅゆう)しますか。『老子・第三十一章』を銘道得と作しているす小生としては、左様な観念は噴飯ものという次第です。その古道に道く、「勝って而も美とせず。之を美とする者は、是れ人を殺すを楽しむなり。夫れ人を殺すを楽しむ者は、則ち以て志を天下に得る可からず。人を殺すこと衆ければ、哀悲を以て之に泣く、戦いに勝てるには葬礼を以て之に処らしむるなり。」、と。敢えて道うなら、「戦勝を美とせず」は、「戦争における戦勝」に限定したくない、とさえ。何しろ、幼いころから、「万歳!」が大嫌いなコドモでしたから。 とまあ、一先ずはこの問題についてはこの辺りで。
尚、小生の、件の賢治の〈ぜんたい幸福〉という提言は、あくまでも「〈ヒドリの個人〉の〈内的世界〉に関しての幸福と不幸」に関するそれだと。で、それは「求道すでに道である。」という提言とも不離不即なる因縁関係性にあるのだろう、と。
書くん瑠斯なる小生の考えは以前にも披露いたした気がしますが思い違いだったでしょうか。 で、小生の受け入れ難い解釈はというと、「『世界全体が幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない』という賢治の幸福観は全体主義的幸福観の主張そのものなんである!」という賢治を八紘一宇主義の狂信者と決めつけたそれ、という次第です。
文遊理道樂遊民洞 閑話休題
2016,3,24 23:04
同じコメントをダブって送ってしまったようですね。後の奴、削除お願いします。
で、〈オクシモロン(対義結合法・撞着語法)〉という文彩(レトリック・修辞法・譬喩)がありますね。〈アイロニー(反語法・漱石の仮対法)〉や〈パラドックス(逆説法)〉と同様、権威や権力と強く結びついている通説や定説あるいは通念への根柢的な懐疑や批判を対けるのに用いる時限爆弾的レトリックなどと表現したのが、『意味の弾性』での佐藤信夫師でした。 その『記号人間』から始めて、レトリックの基礎論として、「一般的には、概念分節言語システムの中で形式論理システムと文彩システムとを同格とする考え方」から「形式論理システムを文彩システムの下位概念に置いた」ところの『レトリック感覚』を経て、〈メタファー(隠喩)〉と〈メトニミー(換喩)〉という基本的レトリックや、その援用形ともいえる〈提喩(シネクドキ)〉や〈直喩(シミリチュード)〉などについて論じた『レトリック認識』に続けて道破したのが『意味の弾性』だったと記憶しています。 『記号人間』が小生三十歳の頃、「中国宋代の修辞別名を〈文則〉と謂った」という記述を見つけて随喜したのが、『意味の弾性』の次に出版した『レトリック消息』だった気がします。時あたかも小生三十六歳の結婚の頃だったように。佐藤氏はその五年ほど後に六十一鎖于歳で亡くなったと記憶しています。 つまり、佐藤信夫という言語哲学者は、小生にとってM・メルロー=ポンティやL・ウィトゲンシュタインと同じくらいの重さの言語哲学者だったということになります。その後に出逢ったのが丸山圭三郎師と井筒俊彦師。小生の場合は、美術を含めて著作や作品を介して出逢った師しかいない、というのが実際です。直接の交流を持てたのは石田洵師ぐらいでしょうか。
さて、守先生は、「概念分節言語システムに含まれる形式論理システムは文彩(譬喩)システムの下位概念である。」というレトリック観に対してどんな深層心象あるいは認識判断をおもちでしょうか。
まあ、「形式論システムと文彩システムとの間に上下位はない。」と「文彩システムは形式論理システムの下位概念なり」からの三者択一ということになるのでしょうが。
こんな、埒もない質問を敢えて向けたのは、先生の、〝「農民芸術概論綱要」は「理論」ではないのかと私は悩んでしまいます。 一方で、「農民芸術概論綱要」そのものが「理論」ではなくて「詩」であるとすれば、私の見方はまた違ってきます。〟という言説に引っかかったものですから。
「『農民芸術概論綱要は理論(セオリー)なるか詩(ポエトリー)なるか?「」という自問に逡巡なされているという次第ですね。同じ〈詩〉でもよりセンチメンタルな〈ポエジー〉ではありませんし、賢治自身は、「森佐一への最初の手紙」で、「これらは詩ではなく科学的な詞文だ」といった塩梅の道破を試みていますから、泣かんかなかなか一筋縄ではつかまりませんね。まがまあ、科学とは言っても自然科学というのではなく心理科学とか社会科学といったほどのニュアンスなんでしょうけれど。 固より、〈論理(ロジック)〉と〈理論(セオリー)〉とは別物な訳ですが、「理論とは厳格な論理的思考によりガッシリと構築された思想体であるべし。」とは言っていいのでしょう。尤も、「芸術論は理論体でなければならない」のかは定かでありませんし、哲学論の場合も同じことが言えるのではないでしょうか。 たとえば、L・Wの「言語ゲームの哲学」を展開している『哲学探究』は断章体で書かれた詞的な道取ですし、どるG・ドルーズとF・ガタリによる『アンチオイディプス』や『ミルプラトー』も断章体の道取です。実は、ドルーズ・ガタリの『ミルプラトー(千の高原)』の翻訳本に眼を通していると、賢治の『小岩井農場』や『青森挽歌』などの如き長編詞を連想したくなり、「私には韻文が書けない」と嘆くL・Wの反哲学的断章を連想しつぃまうのはなぜなんでしょうね。で、例の『生徒諸君に寄せる』と『藤根禁酒会に贈る』とを『農民芸術概論綱要』のダイジェスト版と感じてしまう、小生の〈レトリック感覚〉あるいは〈レトリック認識〉はどう処理したものやら、……。
ところで、前にも書いていたと思うんですが、「未完成の完成、これ完成である。」は自家撞着を引き起こしている文である、というようなことを書いておられたように思うのですが、それは、「批判的ㇾトリックとしてのオクシモロン(撞着語法)「」という意味ではなく、「論理的に破綻しているという意味での自家撞着文である」と読め、「求道すでに道である。」というレトリックについても同様な判断が加えられていると感じられたのですが、それでいいでしょうか、シラン。
というのも、小生から観ると、この二つの修辞は「風とゆききし、雲からエネルギーをとれ」や、華厳経の宙宇観を彷彿とさせる「まずもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばろう」といったレトリックと共に、「流石賢治道」と讃えたいものですから、……。 おっと、小生がこれまでに書いた道取の中で最も妙チキリンでワケノワカラナイ愚癡綺語になってしまったかもしれませんね。お許しの上、お忘れ下さい。
3,25 3:15 辛辯文則流かしらん
「辧辯(ワカチワキマエタル)文則(レトリック)」則ち「道理や論理の通った道(コトバ)の理(コトワリ)」なれば、言語コミュニケーションはスムースにブレイクスル―してくれる筈ですが、慥(まこと)に、〈人間言語という現象〉という〈因縁性起(いんねんしょうき・縁起)〉の〈コンプレックスティ(複雑性)〉なること夥しく、考えれば考えるほど、語れば語るほどワケガワカラナクなってしまいそうです。
それにも関せず、考え続け語り続けずにはいられないという〈性(しょう)の質(たち)〉の持ち主という徒輩は後を絶たないようですね。全くコマッタチャン達です。 小生も守先生ものんなコマッタチャン種に分類される口なんでしょうか吾不識。まあ、「〈口(サイ)〉に〈辛〉を突き立しが〈言〉」とか、「〈辛〉に〈木〉を接ぎ〈斤〉や〈見〉を接したのが〈新〉と〈親〉」などと、「文字の生成因縁」に遊戯(ゆげ)したがる〈性(さが)〉には吾ながら駅駅辟易とさせられるのですが、それが「吾が〈父母未生以前本来の面目〉」とあれば致し方もございません、ね。「時流や時勢への追従や損得勘定」と、「己の父母未生以前本来の面目」との何方を一大事と観るのかという難有い問題に逢着してシマッタとあれば、……。 と道う事で、「吾言ウ字ヤ文ヤ章ト遊ブハ楽樂.」、などと。因みに、〈章〉という字にも〈辛〉が蔵れているんだそうです。白川師の道く「〈章〉の〈日〉は〈墨壺〉なり」、だとか。〈文〉が〈辜人(ツミビト)〉の身体に辛(針刀)で入れる文身(刺青)〉というのですからおそろしい話ではありますが。 呪術的政治を行った〈殷(商)〉の文化が焼いた甲骨の亀裂を整えた道具も〈辛〉なのだとか。ごく初期の甲骨文字に「甲・乙・丙・丁……辛・壬・癸」という十干が含まれ、最後の殷帝紂王の別名が〈帝辛(ていしん)〉だったというのも。「天の帝の言を明らめるのが宰のオシゴト」なんてね。 因みに、「紂は酒池肉林に戯れた悪の権化だった」という『史記』エピソードは、殷を滅ぼした周が捏造したオハナシだったらしいことが考古学的史料から明らめられたそうです。「歴史とは勝者の歴史なるべし」とは、東西古今のリアルということは〈勿忘草紫苑〉ということで。慥(まこと)に、「能ク見聞キシ解リ而モ莫忘.」という自戒をこそ「温故知新而温新知故」の大志大道に致したいものです。 しかしながら、左様な身心態度を堅持せんと欲すると、兎角に、権威主義的かつ反知性主義的ヤンキー連には、「売国奴の木偶之坊め!」という誹謗中傷を浴びせられがち、というのもまた東西古今の習いのようで。而して、逍遥遊を楽しんだ老荘ならぬ律儀な孔孟さんたちでさえ、「和而不同、和而不流にして附和雷同なる莫れ。」、と。 ところで、この〈和而不同〉と〈和而不流〉という四文字、〈不同不二〉や〈不一不二〉あるいは〈不一不異〉ほどではないですが、かなりの程度に〈オクシモロン(対義結合法・撞着語法)〉的な造語構成を蔵していますよね。〈和而合同〉とか〈不和不流〉なら同意結合的で自家撞着は生じに訳でゴクワカリヤスイが故に、自力で深く考えることなく、権威や権力あるいは大勢に追従でくできるわけですが、「大勢への附和雷同は罷りならん」ということになると、……。 で、この、「この両者の間の関係性は、不同(不一)なり、而も同時に、不異(不二)なるべし。」という同異判断の自己矛盾・自家撞着は最高潮という因縁な訳ですね。た、譬えば、三十九歳の漱石が『草枕・1』で、〈三十歳の画工(えかき)〉に語らせている、〝不同不二の乾坤を建立し得るの点に於て、我利私慾の羈絆を掃蕩するの点に於て、―― 千金の子よりも、万乗の君よりも、あらゆる俗界の寵児よりも幸福である。〟という道得の意味するところは、……。
「〈乾(天・明・陽)〉と〈坤(地・暗・陰)〉との両つのものは、不同一である、と同時に而も、不別異なんであり。」というのですから。「Aデナイ、と同時に而も、Aナイデハナイ」はたしか論理基本側の排中律違反ですよね。つまり、同率一律違反でもありかつ矛盾律違反でもあるわけですから、論理的にはノンセンス(無意味)ということに。 実は漱石は三十一歳の時の覚え楽書きノートに〈二而一一而二〉という〈不同不二(不一不二)〉と同意の関係性概念語を書きとめていますし、島地黙雷と島地大等の〈黙雷〉と〈大等〉という名号もそれとほぼ同意を表現する名なのではないか、と考量するに至っています。実際、多少とも禅仏教思想に足を踏みこんでいる人人には、「文殊の不二の法門と維摩の黙雷」という譬喩物語はよく知られているようです。 実は小生は、『志高創立三十周年記念誌』編纂に関わり、「新渡戸稲造と宮澤賢治の思想精神の掘り起し」を試み、『不貪慾戒』などの穿ち読みを試み始めた二十年ほど前から、賢治が二十五歳の国柱会家出の最中にその素案を書き帰花後直ぐに仕上げた『かしわばやしの夜』に登場する「眼の背が高く眼の鋭い変な衣裳を着て靴を履いた絵かき」を、漱石の『草枕』の画工』と重ねて読みたい欲望に抗しきれないまま今に至っています。 実は、そんな読み方は、平成十年度の盛四研究紀要『白楊』に寄稿した「玄妙なるエッセイ」に、「ターナーのサラドの色即是空」問題と並べて書いておきました。勿論、白堊校の『自彊』に寄稿した『視えるものを見えるものにするために』と同様、誰一人、ワルクチの材料にさえして戴けませんでした。つまり、完全無視ということです。 で、「不一不二の乾坤天地陰陽を建立し、我利私慾の羈絆を蕩尽(不羈奔放)できるコト」つまり「禅仏教的な意味での思想的理念的な悟達」が、「千金子や万乗る苦にゃ君や俗界寵児よりも幸福である」という文脈で道う意味での〈幸福〉との何等か間に何等かの因縁関係性が働いていたとしたなら如何、と。
で、「漱石と啄木との間の関係性」というなら、漱石研究者にとっても啄木研究者にとっても常識中の常識ですが、「賢治と漱石との間の因縁」について考量を加えた漱石研究者や賢治研究者はいるのでしょうか。 白堊校史に多少の興味関心のある人なら、「十二歳違いの啄木と賢治の間の因縁」には感心を働かせても、「米内光政と鈴木卓苗と原抱琴と金田一京助と野村胡堂と石川啄木と内田秋皎と橘川眞一郎と長岡擴と小野清一郎と平井直衛との間の因縁関係性「」については考えても見ない筈です。 固より、明治37年4月に盛岡で発行された俳句誌『紫苑』第四号に掲載された、漱石の談話記録『俳句とが外国文学』が、鈴木卓妙苗とともに白堊校生徒文藝活動の先覚となった正岡子規に激賞されたな根岸派の俳人で原敬の嫡養子だった原抱琴から、『紫苑』を編集していた十七歳の白堊校生徒内田秋皎にもたらせたものであることや、明治4,039940年3月発行の盛岡中学校校友会雑誌に掲載された啄木の『林中書』が生徒編集責任者内田秋皎からの原稿依頼に応えたものであり、その雑誌部長が、後に、賢治や金田一他人や阿部孝の担任を務めた橘川眞一郎であったこと、明治45年に母校の英語教師として帰って来て、恩師の橘川から校友会雑誌部長を引き継いだ内田が、賢治や他人や蝦蟇仙こと校友会雑誌生徒編集者阿部孝が卒業した大正3年の10月に長年患った結核のために二十九歳で夭折していることなどのエピソードが反映されることは、……。
ここで、唐突ですし、以前にも書いた気がしますが、小生は、「世界がぜんたい幸福……個人の幸福はありえない」という道得での〈幸福〉とは、「世俗慾の羈絆から自由になれた見性自覚による幸福」 つまり「さとりの願いの成就としての幸福」 と享受しするに至っています。 そう解釈すると、「世界がぜんたい幸福」は、「個人の内的世界の全体性(ホロニティ)が幸福」 つまり、「嫉妬心や瞋恚心や欲求不満や虚栄心や猜疑心に分断されて全体的統合の失調をきたしてシマッタ不安心」という不幸から自由になれなくなるのは必然という訳で。
その点、「我利私慾の充足を幸福と感じるぜ族z世俗的幸福感」はその根柢的性質上、「コチラを立てるとアチラが立たない」という自己矛盾葛藤を克服することは原理的に不可能で全体的な安心立命など期待できないことはオトナの常識ということになるのでは、と。別に論理的整合性の塩梅が宜しくなくともそれなりの筋道は通るのではないのかと。
とまぁ、話が前後滅茶苦茶になってシマッタ気がいたしますが以上で閑話休題です。
辧辯辛新親文則流文遊理道樂遊民が
洞で洞(よ)み申しました
2016,3,06 3:16
お早うございます。
毎度のコメントありがとうございます。ただし、折角内容の濃いコメントをいただきながらも、私の方はその凄さに圧倒されて狼狽えてばかりいて申し訳ございません。
それゆえ、賢治が折角「農民芸術概論」を講義したというのに生徒や協会員はちんぷんかんぷんだったということですが、彼らの心境はまさに今の私の心境と同じだったのではなかろうかと推測しております。辛さんの格調高い論考に頭がくらくらしています。
したがいまして、まともなお返しのコメントは固より書けないのですが、少しだけ弁解したいと思います。
まず、
「未完成の完成、これ完成である。」は自家撞着を引き起こしている文である、というようなことを書いておられたように思うのですが、
につきましては、私はそうは思っておりません。自家撞着を引き起こしている文であると思っているのはあくまでも
(3) 永久の未完成これ完成である
の方です。
それから、これは前にもお話ししたことですが、私にとって「農民藝術概論綱要」はあくまでの「理論」なのであり、そこに書かれている文は、それ自体で完結的に意味が一義に定まるべきものだと思っております。つまり普遍性のある文から構成されねばならないと考えております。
ところが、賢治の「農民藝術概論綱要」は一瞥して眩くて、その絢爛さに圧倒されるのですが、さてじっくり考えてみようとした途端に眩惑、あるいは幻惑されているような状態におかれている自分に気付き、これははたして「芸術論」なのかなと訝ってしまいます。
もしかすると、「農民藝術の概論」とはこういうものだとその骨子を論理的に説明するはずの「概論綱要」そのもの自体が「芸術作品」になっている、と私には思えてしまうのです。
そう言う意味では、曲解しているのだとはわかっているつもりですが 、私からすれば「農民藝術概論綱要」それ自体が自家撞着しているとさえも思ってしまいます。
まあ、これも芸術の何たるかを知りもしない、凡人の繰り言ですので、ご容赦願います。
鈴木 守
「永久の未完成」を「未完成の完成」と誤記したことが、却って、問題の真なる所在を明らめてくれたと「スッキリス」になった気がします。「昏く冥いアイマイなる気遣い方便」が一層事態を「〈渾沌〉ではない〈混沌(カオスモス)〉」に陥らせてしまうのだ、と。
因みに、東洋哲学と現代言語哲学との両方につうしょう通暁していた井筒俊彦師による、「東西古今には、荘子の渾沌、華厳の事事無礙法界、ライプニッツのモナドロジーなど、〈万物万象斉同斉一無差別平等〉」を意味する道得(テクスト)がある。「」という意味の道取は小生の賢治観についての道破(ブレイクスル―)になったのは、丁度二〇年前のことです。それが、「『かしわばやしの夜』は『趙州庭前の柏樹子』エピソードの童話化なのではないかしらん!?」という問題設定(プロブレマティーク)の水源であり吾が発心の起点です。
実は、「万物万象斉同斉一無差別平等」という薄っぺらに読むと、ナチズムやスターリニズムなどの〈全体主義(トータリタリアニズム)〉と附和雷同化を起こしてしまいそうな ― 超国家主義と超社会主義とは雷同化を引き起こすべし。而れば現今のグローバルキャピタリズムや如何? ― 因縁関係性概念として、西田幾太郎哲学や高田博厚(遠野高校蔵『宮澤賢治像』の作者)哲学への長らくの懐疑なのでした。
実際のところ、「有無・肯否・真偽・善悪・美醜・乾坤・天地・陰陽・明暗……」二元論的思考の枠を出ることのなかった時節までは、「高田博厚の道う一元性」に胡散臭さを感じずにはいられませんでした。ところが、高田がその人間性を信頼するch肖像彫刻の対象は皆、その意味での一元性の体得者なのだといいうのですから、小生の自家撞着たるや、……。 「宮澤賢治と新渡戸稲造」を始めとして、西田幾太郎、高村光太郎、内村鑑三、岩波茂雄、志賀直哉、谷川徹三などの日本人だけでなく、R・ロラン、アラン、M・ガンジー、J・ルオーなどの〈人人(にんにん・モナド的個人)〉たちが…。その意味では、小生にとっては、高田博厚は舟越保武以上の損じ存在者だということになります。 因みに、高田師は、南原錫繁の高弟であった工藤巌氏や鈴木實氏(鈴木東蔵の長男,遠野校校長、花北校校長)そして斉藤宗次郎と同じく、内村鑑三が開いた無教会派キリスト者なのでした。「信仰の宗徒」というより「思想実践の宗徒「」という感じです。尚、盛岡市制作委託の『新渡戸稲造像』の実際上の依頼者は、盛岡市長時代の工藤巌氏と遠野高校時代の鈴木實氏のようです。 ただ、内村の無教会派キリスト教は、ゲーテやカーライル、バッハやモーツァルトやベートーヴェンもその会員だったとされ、〈賢者の石〉を象徴のひとつとしていた〈フリーメーソン(自由の石工)〉と同様、その思想信条は非公開、つまり密教であるため、その詳細は明らめられません。「何故に顕教にせず密教性を護持するのか?」という自問への小生なりの見解は、「言語道断・言詮不及なるが故に」、と。 解り易く言うと、「原理的に、一意一義的にその意味や意義、思想内容を確定できないが故に」、と。それは恰も、「唯物論的物理学の世界に、ダークマターやダークエネルギーを想定せずには宇宙の道理が通らない。」という現象と何処かで通じているのか吾不識、と。 で、A・アインシュタインの世界観は、デカルト・ニュートンのそれとボーア・シュレージンガー・ゲーデルのそれに近いのか、などと。相対論的確定性と相補論的不確定性との間の因縁関係性が、……。小生は、言語哲学では、M・メルロー=ポンティの〈両義性の哲学〉や〈L・ウィトゲンシュタインの言語ゲームの哲学〉は、後者のコスモロジーに協和すると考えています。尤も、『論理哲学論考』の前期L・W は前者のコスモロジーに立っていたと考えています。で、L・Wは前者を否定せず、前者と後者との間を相補相依的な関係性で結ぶことをその『哲学探究』の序で提言している、と。実際、相対論(二元論)的画定論確定論に立脚しないことには、客観性と普遍性を保持した思惟や言語表現は不可能になりますし、思惟思索と言語表現とは不離不可分なのですから、「文を書くことによって考えるという乞う意行為の実践が可能になる」のですよね。 しかしながら、そうした思惟表現行為には限界としての壁があるのだ、と。斯なる故の、不立文字・道不得(どうふて)にして直指人心(じきしにんしん)・単伝心印(たんでんしんいん)・以心伝心などという不可解な禅語が。言語の壁(限界)についての思惟思索に没頭したL・Wの覚書にも、「わたしは言語と闘っている。言語ゲームの起源であり、その原初的(プリミティブ)な形式とは、反作用(リアクション)である。反作用があってはじめて、さらに複雑な形式が育つのだ。私は言いたい。言語とは、精密にし洗練することである。〝はじめに行為ありき〟」という道破があります。
といった塩梅に、守先生の、「私にとって〈農民藝術概論綱要〉はあくまでも〈理論〉なのであり、そこに書かれている文は、“それ自体で完結的に意味が一義に定まるべき”ものだと思っております。」という見解言説への対論は収めたいとおもいます。“”を付したけ守先生の見解は「確定論的なる理論は論述的閉鎖系であるべきだ」とでも言い換えることができるでしょうか。固より、「定義とは一意一義的な意味・意義の不変的確定なんである」という思想は、「〈諸法無我・諸行無常〉という道得で表現された〈空観・中観(ちゅうがん)・縁起観・無自性観〉と根柢的に対立する訳ですね。 固より、世俗世間を動かしているコスモロジーは、〈人間的欲望〉を前提土台とした〈素朴実在論〉つまり〈有自性実体論〉ですね。 で、「世間的我利私慾の猛威」への自己批判を働かせない限りは〈空観・中観・中道・無自性〉などという〈イデア(観念)〉や〈コンセプト(概念)〉が生成してくる因縁はないでしょうし、「概念分節言語的思考以前の世界(コスモス)」などというアイデアも生まれてこようはないのでしょう。そして、「文化も文明も進歩(プログレス)し進化(エヴォリューション)すればするほど豊かで幸福になるのだ」という素朴なオプティミスム(楽観主義)が自己崩壊を起こす心配もないのでしょう。
しかしながら、「人間は斯くまで暴虐非道なる戦争という破壊暴力于行動を何故に自己克服できないのだろうか?」という素朴な疑問を棄てることなくトコトン考え抜いて行ったなら、どんな地点に行き着くことになるのでしょうか。 面倒臭くなって、「戦争とは人間性の本質本性であるが故に性悪説が正しいのだ!」といった素朴実在論の枠内に止まっている人々だけが人間存在現象だったとしたなら、老荘思想もゴータマ思想も生まれなかったし、それが継承されることもなかったのでしょうが、幸か不幸か、「ごくマイノリティの人人」が「玄妙不可思議な道取」をぶらさげて、……。
応答はわかりにくくなってしまったようなので、ハジメに戻ります。 定義論や意義確定論についての小生の見解はもう十二分に開示した筈ですから。
で、「〈未完成の完成〉ではなく、そうではなく、〈永久の未完成〉こそが問題なのだ!」、でしたね。
で、まさに、其処の処が落処(かんどころ)つまり「ボツならぬツボ」なのですね。「概念言語分節という言語ゲームの道理は根柢的に不確定にして〝不確実、道可道、非常之道。名可名、非常之名〟(道の理は諸法無我、諸行無常なるべし)」というのなら、〈藝術〉に限らず、「永久の未完成」は避け難いですし、そんな難有いコトを持ち出すまでもなく、アーティスト藝術にとっては、個々の作品についての自分自身のアーティスティック行為についても永久の未完成でしょう。例えば、賢治の全作品はまさにその典型例ではないでしょうか。「賢治に完成作はあるか?「」と改めて問われたなら、何と応えるのが妥当とお考えでしょうか。 で、小生は、二十年ほど前から、「賢治は完成に向けて懸命に努力を続けたのだが、次から次へと思惟が深まり拡大していった為、完成に到らせることが出来ず、題名までも化えざるを得ず、ついには、題名を付すことさえできなくなってしまった。」、と確信するにい到っています。そして、「個々の作品の揺動変遷のプロセスこそからから賢治の思想が浮かび上がってくるのではないのか。」、と考えているという次第です。
で、それは、まさに、禅思想修行に一方法論である〈参禅問道〉の思想でもあるようなのです。世上では〈問道〉とではなく〈問答〉と書きますが、それでは「問いとその正答」ですが、「看話禅修行なる参禅問道には正答(模範解答)は存在しない」というのが実際なのだそうです。で、その問いの根本は「如何なるか是仏?」つまり「仏教思想の根本的な道の理や如何?」ということになるようです。 で、「如何なるか祖師西来の意?」 「父母未生以前本来の面目や如何?」 「趙州の庭前の柏の木とはどういうことなんじゃらほい?などなどは、全て、気の利いた答案を問いに置き換えたものといという次第。」と。 つまり、その根柢には、「言語道断にして言詮不及なるべし!」、つまり概念分節言語では根柢的な真理を表現すること、ましてやそれを不変かつ普遍として確定することなど出来ない相談ナンジャラホイ!「」という〈遊戯三昧(ゆげざんまい・融通無礙自在自由)〉なる思想が働いているのだ、と。
そして、其処に於いてこそ、〈万象同帰・万法帰一〉としての〈万有一如・万物斉同〉なる〈一元性の水源〉なる「玄之又玄、衆妙之門。」が開かれているのだ、と。それを、現代言語哲学的な言語表現を用いると「概念分節言語以前の純粋経験世界」といった塩梅になるようです。因みに、〈大拙〉こと鈴木貞太郎の心友で、〈寸心〉という居士名をもつ西田幾太郎は、その『善の研究』で、漱石や稲造もおおきな感化を受けたA・ベルグソンの〈純粋感覚〉という概念を援用して〈純粋経験〉というタームを提示していますが、要するにmこの「父母未生以前本来の面目」という道得が示唆する内的世界経験の云いということになるようです。
因みに、二十七歳の漱石は、鎌倉エンガク円おn円覚寺の師家住持釈宗演(しゃくそうえん)に参禅した際に与えられた問いが「父母未生以前本来の面目について考えてみたまえ」だあただったということが、『吾輩は猫である』などに書かれてあり、『門』には、何と応え、どんなあしらいを受けたかが書かれています。
固より、その問いは、「庭先の柏林とは如何?」と同様、その問いは、漱石の想定済みだった筈です。さもなければ、当時一番人気の師家であった宗演との問道が許される筈も。因みに、その時点で、漱石の三歳年下だった鈴木貞太郎は宗演の公案が通り〈大拙〉という居士名まで頂戴しており、漱石の参禅時には帰源院に投宿していたというのですから。 さて、二十七歳の金之助の応答は、「物を離れて心無く、心を離れて物無し」。〈物〉は〈身〉と換えても同意で、〈デカルト的心身二元論〉と根柢的に対立する禅哲学の鍵の一つである〈身心一如(しんじんいちにょ)〉を挙げたという訳ですから、模範解答と言って差し支えないわけですが、宗演の対応は「一寸学があるならその位のことは言える。もっとギロリとした所を持ってこないと駄目だ。」、と鮸膠もなかった、と。 負けん