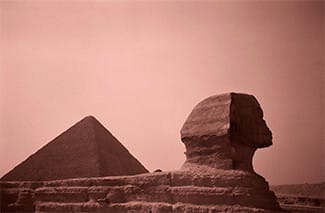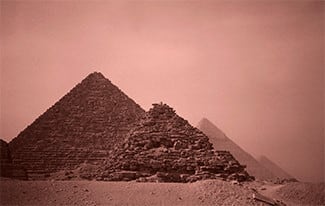※(142)カイロ(後編)(エジプト)のおまけ記事
パチパチおじさんのスーフィーダンス動画を発見したので紹介したい。
動画(スーフィーダンス( Cairo in Egypt 3)はこちら。
興味のある方はこちらもどうぞ。
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 1)
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 2)
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 4)
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 5)
スーフィーダンスとは、回転舞踊(旋舞)を踊るスーフィズム(イスラム神秘主義)の修行の一つ。
スカート状の服を穿(は)き、音楽に併せて回転することで陶酔感を得て神との一体化を求める。
スーフィズムとは、アラビア語で【タサッウフ】と呼ばれる。スーフ(羊毛)で出来た粗末な衣装を身にまとった者という意。
禁欲的で厳しい修行を行い、回旋舞踊の他にも導師の下で修行(マカーマート)を行い、一心に神の事をのみ考え、神と合一したという悟りが訪れるのを待つ。
この境地【ファナー(融合)・バカー(持続)】に至った者は、聖者に認められ、崇拝の対象となった。
ちなみに人名にも用いられる【ダルヴィーシュ】とは、このスーフィズムの修道僧、または托鉢僧のことらしい。
パチパチおじさんのスーフィーダンス動画を発見したので紹介したい。
動画(スーフィーダンス( Cairo in Egypt 3)はこちら。
興味のある方はこちらもどうぞ。
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 1)
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 2)
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 4)
・スーフィーダンス( Cairo in Egypt 5)
スーフィーダンスとは、回転舞踊(旋舞)を踊るスーフィズム(イスラム神秘主義)の修行の一つ。
スカート状の服を穿(は)き、音楽に併せて回転することで陶酔感を得て神との一体化を求める。
スーフィズムとは、アラビア語で【タサッウフ】と呼ばれる。スーフ(羊毛)で出来た粗末な衣装を身にまとった者という意。
禁欲的で厳しい修行を行い、回旋舞踊の他にも導師の下で修行(マカーマート)を行い、一心に神の事をのみ考え、神と合一したという悟りが訪れるのを待つ。
この境地【ファナー(融合)・バカー(持続)】に至った者は、聖者に認められ、崇拝の対象となった。
ちなみに人名にも用いられる【ダルヴィーシュ】とは、このスーフィズムの修道僧、または托鉢僧のことらしい。