知られざる高知人・黒岩恒 その1
黒岩恒(ひさし)といっても、高知県内で名前を知っている人がどれくらいいるだろうか。
私もまったく知らなかった。その名前を初めて知ったのは、沖縄に移住して二年目のことだ。
県立図書館で借りた『沖縄の百年―第一巻近代沖縄の人びと』を読んでいた時だった。沖縄でも北部の山原(やんばる)で農学校の校長を務め、学校で学んだ人々からとても尊敬を集めていたという。
なにしろこの本に見るように、「沖縄近代の人びと一〇四人」の中に数えられるほどである。といっても、沖縄でもいまは、有名とは言えない。知る人ぞ知る人物らしい。
「一〇四人」の中に選ばれているからだけでは、とくに驚くことではない。
読んでいて目が引き付けられたのは、出身地が「高知県高岡郡佐川町立野一〇番地に生まれた」とあることだ。
わが郷里、それも私の生まれた同じ町ではないか。
一八九二年というから、明治二五年にこの沖縄に渡ってきたという。「私より一一三年も前に、高知からはるか離れた南島・沖縄にやってきて、立派な業績を上げた先人がいたとは??」と驚いた。
といっても、何をした人なのかまだよくわからない。いきなりそう言われても、戸惑うのは当然である。そこで、黒岩氏の歩みを『沖縄の百年―第一巻近代沖縄の人びと』を中心にしながら紹介したい。
沖縄北部の農学校の初代校長に
沖縄に来たのは、三四歳の時である。その前の経歴はこちらではわからない。どういう動機からかわからないが、なにか志をもっていたのだろうか。
沖縄師範学校で博物・農業教師をしていたという。来県して一〇年後の一九〇二年(明治三五年)、北部の国頭郡組合立の農学校の初代校長に抜擢されたという。
教師として、それなりに注目される教育を実践していたのだろう。沖縄本島の北部は、農林漁業が主な産業となっているから、そこでの農学校は、その後の地域の発展にとってとても大きな役割を果たしただろう。
この農学校は、戦後の一九四六年、北部農林高等学校と改称し、沖縄返還後の一九七二年に沖縄県に移管され、今日でも農林関係の人材を育てている。
黒岩氏が赴任した当時は、農学校と言っても、地方の組合立の学校だから予算は限られている。教師も少なく、黒岩校長は、博物、地質学、水産学から、倫理、東洋史まで教えた。
その教え方がとても素晴らしかったと、教え子が口をそろえて言っているというから、慕われた校長だったのだろう。
この学校では、生徒を名護の民家に分宿させて寄宿舎としていた。「きみらは農民と学者との中間だから、俗人から尊敬されねばならぬ」「戸外には学問がころがっている」とたえず教えたそうである。
沖縄の風土に根付いた農業教育の伝統が築かれたという。
黒岩氏の業績は、教壇の上からの教育だけにとどまっていない。
博物学者である同氏は、沖縄の動植物から地質、民俗までその関心はとても幅広い。
「博物学上よりみたる琉球」「沖縄の自然界」「沖縄の博物界」「琉球島弧における淡水魚類採集概報」「琉球列島の陸虻類」といった論文・著作を残している。
HN:沢村 月刊誌「高知人からの転載」











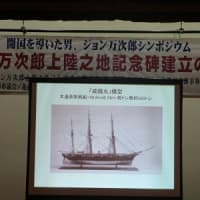







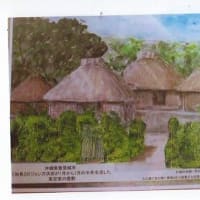
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます