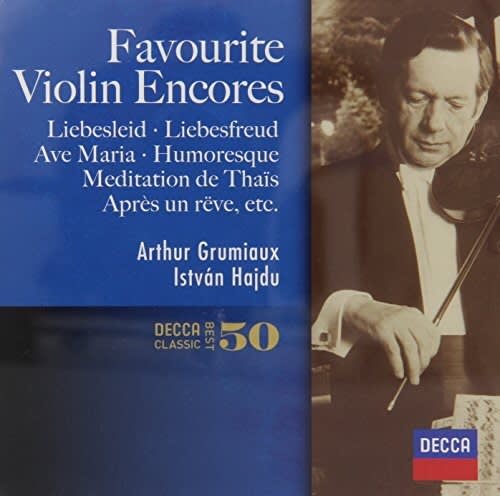【CD3】
1) ナルディーニ:アダージョ・カンタービレ,
2) ショスタコーヴィチ(ツィガーノフ編):4つのプレリュード,
3) メンデルスゾーン(クライスラー編):無言歌 ト長調Op.62-1「五月のそよ風」,
4) クライスラー:ウィーン奇想曲,
5) ハチャトゥリアン:アイシェの踊り(ガイーヌ),
6) ヴュータン:ロンディーノOp.32-2,
7) ドビュッシー(ローレンス編):月の光,
8) プロコフィエフ(ハイフェッツ編):仮面劇(ロメオとジュリエット),
9) ブロッホ:ニーグン,
10) ブラームス:ハンガリー舞曲第1番,
11) グラズノフ:「ライモンダ」より間奏曲,
12) サラサーテ:バスク奇想曲 Op.24
レオニード・コーガン(ヴァイオリン)
アンドレイ・ミトニク(ピアノ)
[録音]1958年2月, ニューヨーク、アカデミー・オブ・アーツ・アンド・レターズ
[原盤]LM-2250 (ステレオ録音だったが初版LPはモノラル盤のみ発売) ※
1924〜1982年ウクライナ
ウィキペディアより
コーガンは、大器晩成型のオイストラフとは対照的に、「魔神と契約した天才」と称される程の早熟の天才であった。公式デビューは1941年、モスクワ音楽院大ホールにおいて、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団との共演によりブラームスのヴァイオリン協奏曲を演奏した。同時期にソ連全土で演奏旅行を行う。学生時代にプラハ世界青年音楽祭で、J・シトコヴェツキー、I・ベズロードニーと共に優勝。また、コーガンはN・パガニーニの全作品演奏に挑み、モスクワで入手可能な作品の全演奏を達成した。奇想曲全24曲を一夜で演奏した演奏会は歴史的な演奏会として伝説となった。1951年には、ブリュッセルのエリザベート王妃国際音楽コンクールにおいて、パガニーニの≪協奏曲 第1番≫で驚異的な演奏を披露、エミール・ソーレ作のカデンツァの解釈にも卓越したところを審査委員長ジャック・ティボーに示し優勝した。また、イザイ・メダルも受賞した。1955年には世界的な楽旅に出発、パリとロンドンに赴き、翌年には南米とアメリカ合衆国にも訪問した。
まだまだ詳しく知らないレオニード・コーガンですが選曲が好きですね。
無駄な力など入ってませんしヴァイオリンのきつめの音は一切なく必要な音量で必要なフレーズを語りかける。
楽器はグァルネリ!
ピアノ演奏で好き嫌いは音色の種類をどれだけ持っているかによることも多いがヴァイオリニストは持ち楽器によってほぼ音色が決まるであろうが選んだ演奏者の責任として聴いたとしても幻想者の好き嫌いはピアノ奏者を選ぶより選択の仕方が多いように思える。
レオニード・コーガン
素敵なヴァイオリニストです。
柿島秀吉