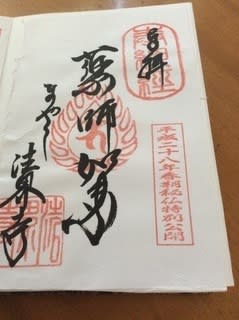写真は、真言宗 東福寺と刻まれた石。この日はアパホテル前橋北口7階に宿泊。窓を開けると眼下に墓場があり、その先にお寺の本堂があるのだが、それが変わっていてとても日本のお寺とは思えない意匠だったので、ホテルを出てお寺に行ってみた。それが東福寺。

寺の屋根の真ん中からまるで鬼の角のような日輪が突き出し、三層の屋根の先端がそれぞれ天に向かってニョキと伸びた様は、東南アジアのお寺のようだ。

インド神話の神鳥ガルーダを模したとされるその先端は、曇天に今すぐ羽ばたいて行きそうだ。

南無大師遍照金剛。

お寺の隣の石屋さんの軒先にいたお地蔵さん。

同じく梟。