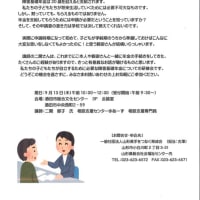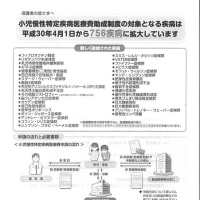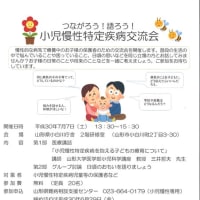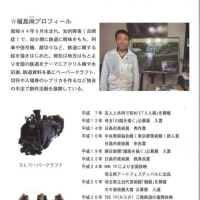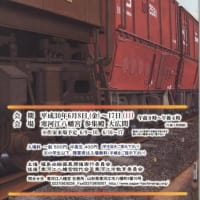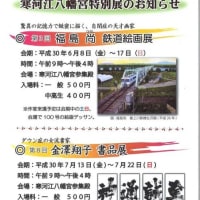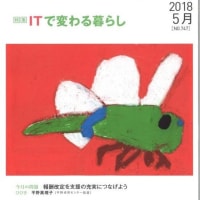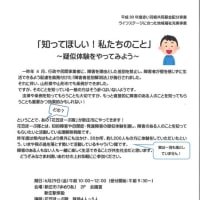本人活動が積極的に実施できるには、本人たちが集まりやすい条件の整備が必要である。そのための福祉サービスの利用等もなければならない。
そして、本人たちが主体的に活動できる態勢を整えられるようにすることだ。
そうした支援のあり方について、展望しているものを紹介する。
以下は、美作大学紀要論文からの引用(2010, Vol. 55,p.99)である。
その第15回目。
これが、最終回である。
*****************************************
【引用始め】
5.まとめと課題及び今後の展望
2)今後の展望
先に述べた課題から、まず、開催日の調整が重要である。
定期的な活動以外にも行事やレクリエーションを行う際に、日程の折り合いをつける必要がある。
また、津山市街地及び周辺地域の交通の便にも配慮する必要がある。
本人活動の取り組みが盛んな主な地域は交通の便がよく、家族や支援者からの送迎の支援はあまり必要ではない。
今後、行動援護や移動支援事業等のサービスを利用して本人活動に参加できるよう地域自立支援協議会や地域の相談支援事業等の協力を得、連携をとっていくことが必要である。
これまで自分の意見を表現する機会の少なかった当事者が力をつけていくためにも。この本人活動はとても重要であると考える。
本人活動を通して、自信を深め、互いの価値を認め、成就観を共有し、社会に働きかけながら、その結びつきをさらに深めていくものである。
そして、相互に支え合い、社会と自分たちの関係を認識し、人間として価値ある人生を生きるために、社会に働きかけ、変革しようと行動する。
こうした活動のプロセス全体が本人に内在する力を強め、彼らの人生の質を変えていくのであり、そのような支援を実践していくことが必要である。
そのためにも、今後は支援者としての学生が支援方法や技術を学び、体得していくことが重要であると考える。
今後、この本人活動が定着し、津山市とその周辺地域の知的障害のある人々が気軽に集え、交流を深め、力を得られる場所になっていくことが望まれる。
参加メンバーが積極的に、意見を出し、「本人の会」を運営していけるように、支援者である学生の支援の力や社会資源とつなぐ力が得られるよう学生、教員共々学びを深めていきたいと考える。
(p.99)
http://www.mimasaka.ac.jp/intro/bulletin/2010/pdf/435510091G.pdf
美作大学・美作大学短期大学部紀要 2010, Vol. 55. 91 ~ 100
知的障害者における本人活動への支援~「本人の会」立ち上げに向けて~
Supporting self-advocacy for people with intellectual disabilities:a report of establishing a self-advocacy group
薬師寺明子、杉谷 理絵*、竹内 瞳*、富澤 真菜*、新延 優子*、真壁かおる*、山本 詠美*、吉元めぐみ*
美作大学生活科学部福祉環境デザイン学科
【引用終わり】
**************************************************
学生たちが本人の会を立ち上げ、本人たちが積極的に活動できるようにするまでのプロセスのレポートを15回にわたって紹介してきた。
学生たちの真摯な取り組みに感謝したい。
これが、次の学生たちにうまくつながっているといいのだが。
サークル活動の一環として、先輩から後輩に引きつながれるシステムになればすばらしい。
本人活動のあり方に関する研究が目的なので、そこまで期待するのは難しい。
大学生有志が集まって、地域に根ざした本人の会支援サークルなんてやってくれるとありがたい。
福祉系の大学には多分あるだろう。
(ケー)
そして、本人たちが主体的に活動できる態勢を整えられるようにすることだ。
そうした支援のあり方について、展望しているものを紹介する。
以下は、美作大学紀要論文からの引用(2010, Vol. 55,p.99)である。
その第15回目。
これが、最終回である。
*****************************************
【引用始め】
5.まとめと課題及び今後の展望
2)今後の展望
先に述べた課題から、まず、開催日の調整が重要である。
定期的な活動以外にも行事やレクリエーションを行う際に、日程の折り合いをつける必要がある。
また、津山市街地及び周辺地域の交通の便にも配慮する必要がある。
本人活動の取り組みが盛んな主な地域は交通の便がよく、家族や支援者からの送迎の支援はあまり必要ではない。
今後、行動援護や移動支援事業等のサービスを利用して本人活動に参加できるよう地域自立支援協議会や地域の相談支援事業等の協力を得、連携をとっていくことが必要である。
これまで自分の意見を表現する機会の少なかった当事者が力をつけていくためにも。この本人活動はとても重要であると考える。
本人活動を通して、自信を深め、互いの価値を認め、成就観を共有し、社会に働きかけながら、その結びつきをさらに深めていくものである。
そして、相互に支え合い、社会と自分たちの関係を認識し、人間として価値ある人生を生きるために、社会に働きかけ、変革しようと行動する。
こうした活動のプロセス全体が本人に内在する力を強め、彼らの人生の質を変えていくのであり、そのような支援を実践していくことが必要である。
そのためにも、今後は支援者としての学生が支援方法や技術を学び、体得していくことが重要であると考える。
今後、この本人活動が定着し、津山市とその周辺地域の知的障害のある人々が気軽に集え、交流を深め、力を得られる場所になっていくことが望まれる。
参加メンバーが積極的に、意見を出し、「本人の会」を運営していけるように、支援者である学生の支援の力や社会資源とつなぐ力が得られるよう学生、教員共々学びを深めていきたいと考える。
(p.99)
http://www.mimasaka.ac.jp/intro/bulletin/2010/pdf/435510091G.pdf
美作大学・美作大学短期大学部紀要 2010, Vol. 55. 91 ~ 100
知的障害者における本人活動への支援~「本人の会」立ち上げに向けて~
Supporting self-advocacy for people with intellectual disabilities:a report of establishing a self-advocacy group
薬師寺明子、杉谷 理絵*、竹内 瞳*、富澤 真菜*、新延 優子*、真壁かおる*、山本 詠美*、吉元めぐみ*
美作大学生活科学部福祉環境デザイン学科
【引用終わり】
**************************************************
学生たちが本人の会を立ち上げ、本人たちが積極的に活動できるようにするまでのプロセスのレポートを15回にわたって紹介してきた。
学生たちの真摯な取り組みに感謝したい。
これが、次の学生たちにうまくつながっているといいのだが。
サークル活動の一環として、先輩から後輩に引きつながれるシステムになればすばらしい。
本人活動のあり方に関する研究が目的なので、そこまで期待するのは難しい。
大学生有志が集まって、地域に根ざした本人の会支援サークルなんてやってくれるとありがたい。
福祉系の大学には多分あるだろう。
(ケー)