杉本彩、動物愛護活動を続けるが「日本は動物福祉後進国」
2018年12月9日(日) NEWSポストセブン
動物愛護活動に長年携わる杉本彩(撮影/田中智久)
なぜ犬たちにとって保護されるべき場所が生き地獄と化したのか。
実態を知る竹中先生と、動物愛護活動に長年携わり、今回の告発に名を連ねる杉本彩(50才)が語った。
ピースワンコは2020年の東京五輪までに、全国の犬の「殺処分ゼロ」をスローガンとしている。
確かに広島県の犬猫を合わせた殺処分数は、かつて全国ワースト1を記録したが、2011年度は2342頭もいた犬の殺処分が、2016年度以降はゼロに。
杉本:行政による動物の「殺処分ゼロ」という目標は、すばらしいことだと思います。しかし、数字だけを追いかけ、ただ生かしておけばいいというスタンスは、あまりにも人間本位です。現に、引き取られた犬たちはストレスにより長期にわたって苦痛を強いられている。
竹中:「殺処分ゼロ」と喧伝すればメディアにも注目され、寄付も集まる。ですが、狂犬病の予防接種すら手薄な状況で、寄付金がきちんと使われているとは到底思えません。
杉本:寄付金について言及するならば、ピースワンコは、本拠地である広島県の神石高原町へのふるさと納税という形で、2017年は5億円以上もの寄付を集めています。自治体への納税として、一民間団体が収入を得ていることにも大きな違和感を覚えます。
──「ピースウィンズ・ジャパン」の役員らは、今回の狂犬病問題に関して「人手不足だった」と話しているという。
ピースワンコのように、少ない人数で多くの動物を飼育し、破綻する“多頭飼育”のケースは後を絶たない。
その背景にはわが国における動物愛護の法整備の問題点がある。
杉本:海外では、保護動物が暮らす施設には、保護に関する規則があり、檻で飼育する場合は、檻の広さなどが決まっています。屋内であれば自然採光の確保と窓の大きさや照明。屋外であれば日陰に小屋を設ける。その小屋は犬がケガをしたり濡れたりしないものにするなど法律に基づいた運営ルールがあります。でも日本においては、「人と動物が共生する社会の実現を図る」ための「動物愛護管理法」が1つしかないうえ、適正な飼養基準となる数値での明確な規制や、ネグレクトの詳細な定義などの文言は一切ないのが現状です。
竹中:動物の避妊・去勢手術や虐待への対策も、遅れています。州によって小さな差はありますが、年に1回しか出産させてはいけないという決まりがある国もあるし、虐待すると法律で裁かれて、動物を飼うことを禁じられるなど厳しい罰則があります。
杉本:ヨーロッパでは、ペットに限らず、畜産動物も含めたすべての動物の健康や幸せを守る「動物福祉」という概念がある。日本ではペットは“愛玩動物”という考えが根強く、動物福祉においては後進国なんです。都合のいいときだけかわいがる人間の気持ちが優先されて、動物がどう感じるか、どんな状況に置かれているかなど、大事なことが置き去りにされています。
竹中:ペットの延命治療も問題です。がんで助かる見込みがなく苦しんでいるのに、毎日点滴をして、体重が半分になってやせこけた状態でも長生きを願う飼い主もいる。つらい治療をやめて、安らかに旅立たせた方がペットにとって苦痛が少なかったとしても、愛するペットを失いたくない、少しでも長く一緒にいたいという人間のエゴで治療を受けさせている人も多い。難しい問題です。
杉本:ペットショップの店員さんの「散歩はさせなくて大丈夫」というセールストークを真に受けて、全く運動させてもらえず、病気になる犬もいると聞きます。ヨーロッパではペットショップで生体が展示販売されていることはほぼないし、保護施設から迎える人が多いので審査をクリアしなければならないため、飼い始めるうえでのハードルが高い。日本ではお金を払えば、簡単に誰でも生き物が手に入ってしまいます。
竹中:海外では、ブリーダーや保護施設から時間をかけて迎え入れるのが基本ですよね。杉本さんは長年犬猫の保護活動をされていますが、現場は変わってきましたか?
杉本:私が保護活動を始めたのは25年前。撮影所の敷地で野良猫を拾ったことがきっかけでした。当時と比べるとずいぶん、保護犬、保護猫の認知度が高まり、地域住民の理解も深まりました。犬や猫も、当時はペットショップで買う人がほとんどでしたが、保護施設から迎える人も増えています。しかしまだ、ペットを飼う覚悟や準備への理解は足りていないように感じます。
──ペットの幸せを考え、よりよい飼い主になるためには、どうすべきか。
杉本:とにかく、飼い主としての責任を全うすることが大事。もちろん、ペットが死ぬまで責任を持って飼う“終生飼育”が原則ですが、飼い主にも予想外の出来事が起きるかもしれない。経済的に厳しくなるかもしれないし、病気や事故に遭うこともありますよね。私は猫9匹と犬3頭と暮らしていますが、万が一のときに面倒を見てもらう人を決めていて、ペット専用の貯金もしています。あらゆることを想定し、準備をしておくことがペットに対する責任だと思います。
竹中:私も、自分に何かあったら愛犬を託す後見人を決めていて、死亡保険金の受取人になってもらっています。だけど残念なことに、このような考えはまだ浸透していない。私たち獣医師が飼い主にきちんと指導できていないことも問題だと痛感しています。
杉本:活動する中で感じるのは、精神的に追い詰められている人がネグレクトしたり、虐待したりすることも多いということ。飼養する能力が不足しているのに飼い続けることに執着しすぎると、かえって動物を不幸にしてしまう。次の飼い主さんに引き継ぐのも1つの選択だと思います。
竹中:最近は、老後のペット飼育が流行っていますが、犬の平均寿命が14年、猫が15年。20年生きる猫もいるから、シニアの動物を迎えてほしい。
杉本:私も年齢を考えると、この先も子犬や子猫を迎えることはないでしょうね。私たちに幸せや喜びをもたらしてくれるペットですが、人もペットも幸せでいるためには準備と覚悟が必要だということを忘れないでほしいです。
※女性セブン2018年12月20日号
この記事のその他の写真
最新の画像[もっと見る]
-
 「迎え入れた保護犬」のお悩み相談
11ヶ月前
「迎え入れた保護犬」のお悩み相談
11ヶ月前
-
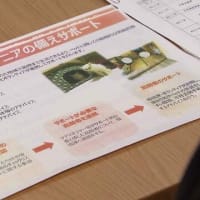 飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
-
 飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
-
 飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
-
 飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
飼い主もペットも老いた時~増える老老介護
11ヶ月前
-
 犬の里親詐欺
11ヶ月前
犬の里親詐欺
11ヶ月前
-
 犬の里親詐欺
11ヶ月前
犬の里親詐欺
11ヶ月前
-
 犬の里親詐欺
11ヶ月前
犬の里親詐欺
11ヶ月前
-
 犬の里親詐欺
11ヶ月前
犬の里親詐欺
11ヶ月前
-
 犬の里親詐欺
11ヶ月前
犬の里親詐欺
11ヶ月前









