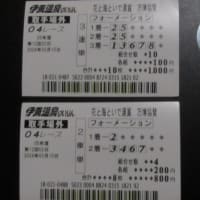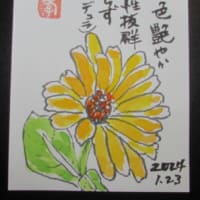▼<花の女王>として咲くバラになぞえ、「どんな場所でも、また、たとえ一人きりでも、一輪のバラのように凛と咲き誇って、周囲を明るく照らしていける」のである。
▼悩みが大きければ大きいほど、偉大な「実証」ができる。
劇的な「使命のドラマ」を演じられる。
▼<生死>という現象にいかなる意味を見いだすか。
宗教本来役割がそもにある。
悲しんでも、落ち込んではならない。
▼生命を洞察する思想的営みから生まれた大乗仏教。
その精髄である法華経から展開した生命尊厳の理念。
死別の悲嘆の中でも、故人との生命の絆を胸に立ち上がり、使命の人生を紡いでいくのである。
▼たとえ若すぎる死や、不慮の死のように見えても、多くの人びとによって、心から惜しまれる姿がある。
そして、残された家族が守られ栄えていく姿がある。
家族が強く生き抜いていく時に、その胸の中に、亡き人は厳然と生き続けていく。
家族は前を向き、故人の分まで使命に生き抜き、幸福になって見せるのだ。
▼大切な人との、思いもよらない死別。
今やそれは特殊な体験ではない。
国内での日本人の年間死亡者数が戦後最多となるなど「多死社会」と言われる昨今。
故人それぞれの傍らには友人・知人など、遺族ではなくとも、別れを嘆き悲しむ人がいる。
死別の悲嘆は「だれもが当事者になりうる体験」―関西大学の坂口幸弘教授が述べている。