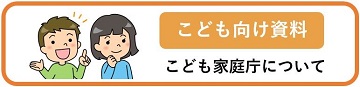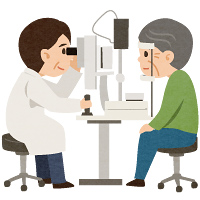D×Pとは?
10代の孤立
わたしたちが取り組む社会課題は、「10代の孤立」です。
「10代の孤立」は、不登校・中退・家庭内不和・経済的困難・いじめ・虐待・進路未定・無業などによって、いくつかの安心できる場や所属先を失ったときに起こります。
全世帯の進学率に比べると、定時制高校・通信制高校に進学する子どもの割合が高くなっています。
経済的に苦しい状況にある10代が、定時制高校や通信制高校に多く在籍しています。
引用:内閣府 平成30年度子供の貧困の状況及び子供の貧困対策の実施状況
定時制高校や通信制高校には、不登校経験のあるなどさまざまな背景によって生きづらさを抱えている10代も在籍しています。
進路未決定で卒業すると所属先を失い、より人とつながりづらい状況になります。
引用:令和2年度学校基本調査(令和2年3月卒業者)
経済的に困難なほど誰かとつながりづらい
内閣府の平成29年版子供・若者白書では、「暮らし向きがよくない」と回答する人ほど、居場所だと思う場所の数が少なくなるという結果が出ています。
それぞれの10代の境遇はさまざまです。
経済的に困難な状況にある人、家庭や学校が安心できる場ではない人、発達障害/学習障害を持っている人など、多様な事情が重なり合っています。
それらの事情によって、孤立しやすい状況が生まれています。
セーフティネットから
抜け落ちやすい10代。
家庭の経済状況は、教育や文化的経験の機会に影響します。居場所だと思える場やコミュニティに出会うきっかけが少ない状況になります。
くわえて、過去の経験によるつながりづらさもあります。
いじめや人間関係のトラブル、家庭での暴力や虐待・無関心など、さまざまな背景からの心理的ハードルです。
これらが重なると、さらに孤立が深まります。
大人のように見える10代。
しかし、未成年であることで本人が自力でとれる選択肢は狭まります。
彼らが頼れる人とのつながりをなくし孤立した状況になると、社会にあるさまざまなセーフティネットへ辿り着くことも難しくなります。
また、危険な大人とつながり事件に巻き込まれてしまうなど、深刻な状況に陥ってしまうこともあります。
学校での取り組みを行なうなかで、スタッフと顔見知りになっていた高校生Aさん。
ある日、顔色の悪いAさんを心配したスタッフが声をかけると、生活に困っていることがわかりました。
学校の先生やソーシャルワーカーとも連携してサポートすることになりました。
生活費を稼がないといけなくなって、最近バイトの掛け持ちをし始めて。アルバイト先は人出が足りないみたいで、今日もこれからバイトやねん。忙しくて全然眠れてない…。
若者がいきる
セーフティネットをつくる。
D×Pは、既存のセーフティネットでは拾い上げられなかった10代と出会い社会につなげていく役割を果たします。
生きづらさを抱えた10代が、この社会で生きて・活きることができる新しいセーフティネットをつくっていきたいと思っています。
「学校」と「インターネット」の2つをフィールドにして生きづらさを抱えた若者と出会います。
若者と関わるときに
“大切にしている姿勢”
10代が抱えている困りごとを聞くときや、10代自身が自分の持っている能力や魅力を発揮するとき、まずはひとりひとりの10代が自己表現ができる環境をつくることが必要だと考えています。
あらゆる可能性を見つめ潰さずに、ひとりひとりと対話するためにわたしたちはこの姿勢を大切にして10代と関わっています。
否定せず関わる
どんな考えや価値観、在り方も否定せずに、なぜそう思うのかと背景に思いを馳せながら関わることです。関わりのなかで生まれる自分の気持ちも否定せず、相手も自分も大切にする姿勢です。
ひとりひとりと向き合い、学ぶ
肩書や性別、年齢に関係のないひとりひとりの考えや特性に目を向け、学ぼうとする姿勢です。たとえば、「LGBTの人」「やんちゃな生徒」のようにひとまとまりにせず関わります。
仕事体験ツアー
働く具体的な
イメージを持てる。
ひとりひとりの希望や状態に合わせた職場見学や仕事体験です。
自分の生き方についての考えや仕事に対する理解を深め、自身が納得のできる進路を選んでゆけることを目的としています。
クレッシェンドや居場所事業で、生徒の希望を聞き、その生徒にあった仕事体験ツアーを実施しています。