10月23日、午前1時30分から、この映画をCSテレビのザシネマで観たのは2度目である。
実話に基づくドラマであるので深みを感じた。
それにしても、120万人もの犠牲者が出たチベットである。
『セブン・イヤーズ・イン・チベット』(Seven Years in Tibet)は、1997年のアメリカ映画。

| 監督 | ジャン=ジャック・アノー |
|---|---|
| 脚本 | ベッキー・ジョンストン |
| 製作 | ジョン・H・ウィリアムズ 他 |
| 製作総指揮 | デヴィッド・ニコルズ 他 |
| 出演者 | ブラッド・ピット デヴィッド・シューリス |
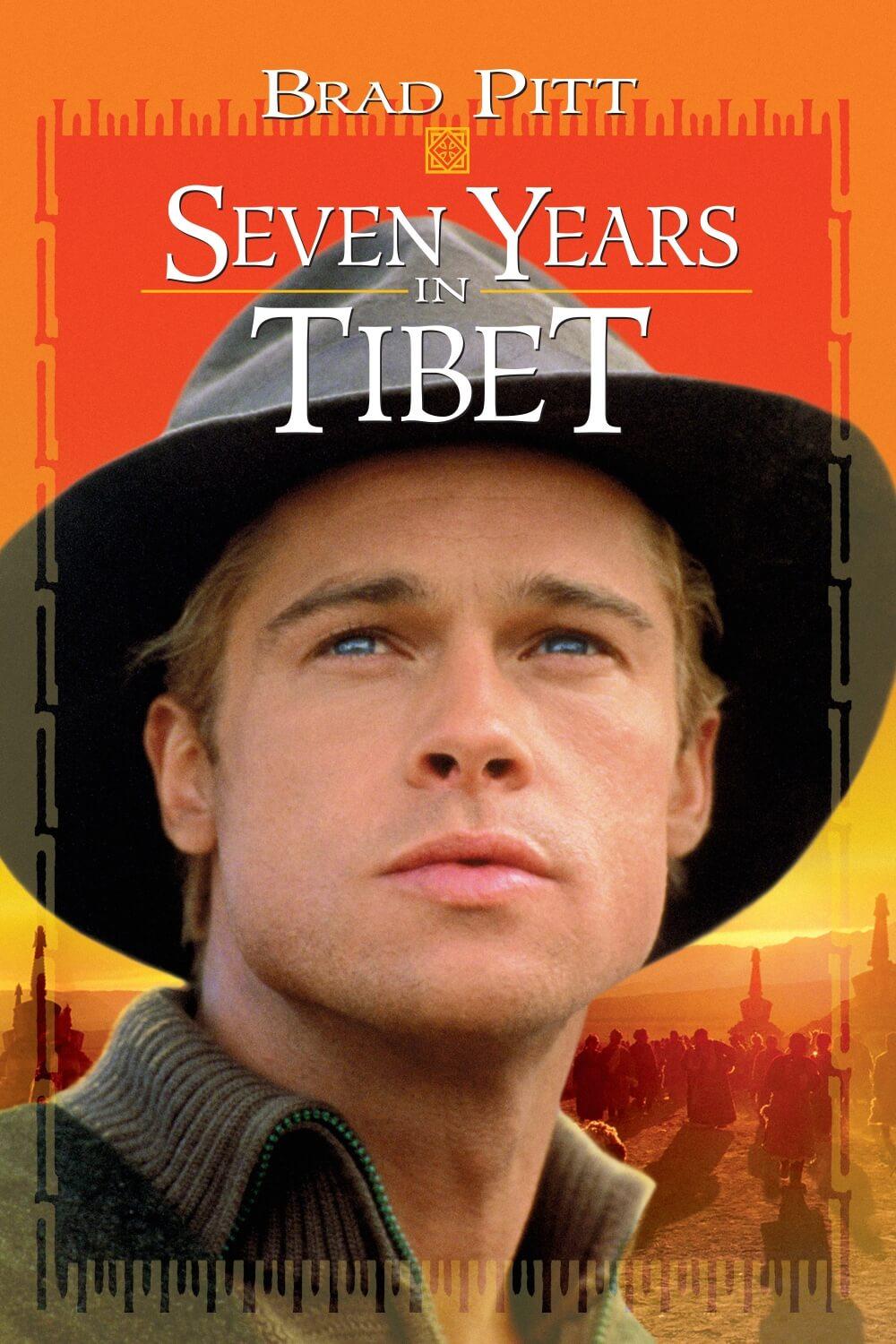
アイガー初登頂で知られるオーストリアの登山家ハインリヒ・ハラーの自伝の映画化。
彼がチベットで過ごした7年間、彼と若きダライ・ラマ14世との交流を描く。
ストーリー
1939年秋、登山家ハインリヒ・ハラーは世界最高峰ヒマラヤ山脈への登山に向かった。
時悪く、第二次世界大戦のためにインドでイギリス軍の捕虜となってしまった彼は脱獄し、
チベットへと行き着く。
チベットの首都ラサで生活をしていたハラーは、当時14歳で好奇心旺盛なダライ・ラマ14世と出会い、
親しく交流する。
ラサでの日々がハラーの荒んだ心に変化をもたらした。
しかし、その生活も中国共産党の人民解放軍によるチベット国への軍事侵略によって終わりを告げることとなるのだった。
この作品の監督は、ラストエンペラーの監督と対照的で、真実を伝えている
今から25年前の映画。 香港返還の年に公開になったアメリカ製の映画。
監督はフランス人。
オーストリアの登山家がチベットに入り、当時若かったダライラマ14世と出会う話である。
内容に関しては、ほぼ真実に間違いない。
中国共産党人民解放軍はチベットに入り問答無用に蹂躙している。チベット仏教で大切にしている絨毯の上を土足で踏み倒す。殺しまくる。毛沢東のでかい写真を一番目立つところに掲げる。
彼らにとっては宗教など関係ない。そういう点をちゃんと我々に伝えてくれているこの映画。
そしてラストエンペラーのバカ監督ベルナルド・ベルトルッチ監督と違い、セブン・イヤーズ・イン・チベットのジャン=ジャック・アノー監督は、常識をわきまえた方だと思う。
チベットは一つの国、ウイグルは一つの国、内モンゴルは元々はモンゴル。
もちろん台湾は国。香港も一つの国だ。中国なんかではない。
・こういうあたりまえのことを日本の教科書にはかかない。
・日教組が牛耳る学校の先生方はそのことを教えない。 ・朝日、毎日という新聞メディアは中国に協力し、偽情報を日本国内に垂れ流す。
・TBS、テレ朝というテレビメディアは全く中国寄り。
・NHKも中国メディアのチェックを受けたようなだらしのない放送ぶり。
・立憲民主党の小沢一郎、2009年12月に総勢626名にもなる訪中団で中国訪問。日本にはこういう中国と関係の深い政党があり、決してこの党は中国の悪口を言わない。
だから、こうやって映画感想文に書いて、見て下さった方々が一人でも真実を知るということをやり続けなければならないと思っている。
日本人よ。特に若い方々。目を覚ませ。気付いてくれ。
これから将来、台湾、尖閣諸島、沖縄、そして最後には日本本土が危なくなる。
自国は自分たちで守らなければならない。アメリカ頼みではダメ。それを怠るとこの映画のチベットの二の舞になる。
チベットの文化や美しい風景が中共に浸食されていく映像に胸が抉られる思いで鑑賞しました。
ストーリーときちんとしており、楽しめた反面、ウイグルや台湾、もしかしたら日本の未来を暗示してるようで辛い気持ちになります。
今のハリウッドじゃ作れない作品でしょうね。 色んな方に見て欲しい作品です。
冒頭のヒマラヤ登頂から始まって、インドの収容所、チベットの大自然、ポタラ宮殿、チベット仏教など場面がどんどん展開するうえに、遠距離離婚、白人とチベット人の結婚、会えない息子への思い、反目しあっていた者の友情などの人間描写がはさまれて、最後は共産主義者のおバカぶりまで出てきて、まあまあ盛りだくさんだこと。
詰め込みすぎの観はありますが、画面もカラフルで話のテンポもいいし、普通に誰にでもオススメできそうです。
中共はずいぶん 怒ったらしいけど微笑ましいですね。
ダライラマ14世のことや、チベットの事を良く知らなかったので、とても勉強になりました。
ハインリヒ・ハラーの人生より、彼がこのチベットの記録を残したことに大きな意味があり、監督が映画にしたことで多くの人々にそれを理解する事ができた、貴重な映画です。香港、ウイグルしかりです。
素晴らしかった!チベットの山々の美しさ、ラサの街や僧院の祈りのシーンなど圧巻。配役も脚本も良く飽きずに観た。 ウイグル、チベット弾圧。
武漢ウイルスの隠蔽など中共の残酷さが世界に知れ渡りつつある現在ではまず作れないであろう貴重な映画。ベースは人間ドラマなので心に響く。
美しい景色と、人と人との関わりと、痛々しい歴史と、よく描かれています。
見終わった後には、長い距離と時間を共に過ごしたような感慨が得られました。
序盤は、ハインリッヒの性格の悪さが気になったりして「面白くなるのかな?」という感じでしたが、 それも後々への伏線となっていました。
チベットを去る時はグッと来ます。
若い頃のダライ・ラマは、こんな好奇心旺盛な少年だったのかな、とか、 実在の人物なのでそう思いながら見ました。
起承転結の分かりやすいエンターテインメントとかではないけれど、 余韻がじわじわと来る良い作品です。












