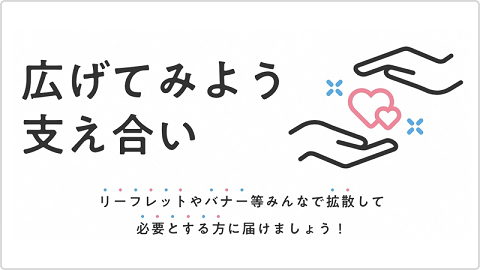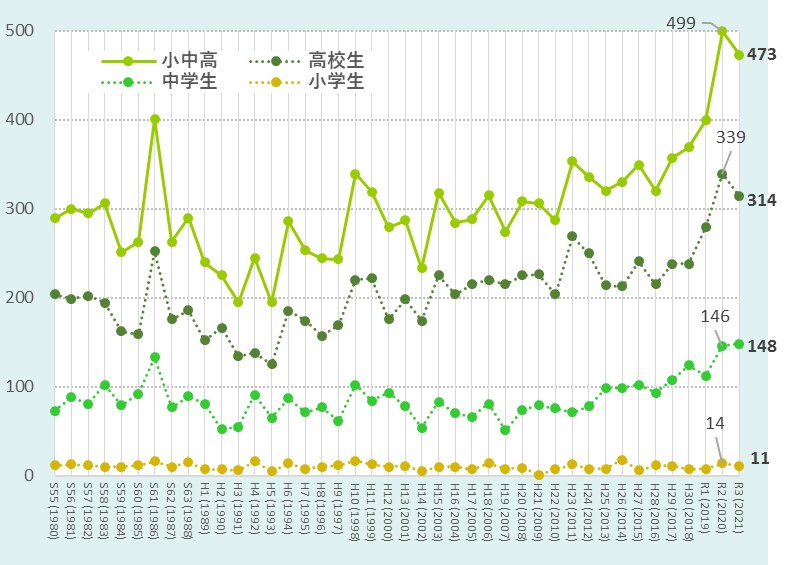▽大事なのは、多様性の対極に「普遍性」をきちんと置くことだ。
普遍性という基盤があってこそ、個々の幸福という多様性を
追求することが、可能になるのではないだろうか。
▽みんなで税金を払い、みんなで恩恵を受ける。
痛みも喜びも、分かち合う。
誰も排除することなく、全ての人々を包摂していくという普遍性である。
▽本来、多様であるはずの人間が、事実として多様な生き方を選び取れるようにする。
その結果、それぞれが抱える生きづらさに、向き合っていくことができると思う。
▽地域の課題や住民の困りごとを解決する力をみんなで育んで営みが必要だ。
▽人間は「人と人の間」に生きる存在である。
「苦楽も共に」という共生の思想。
▽自分自身の生き方を絶えず内面的に問い返し、生きる力を引き出していく宗教的実践には、価値があると思う。
▽みんなが「自分」だけを突き詰めていれけば社会は分断されてしまう。
そこで、その対極に、世界平和や万人の幸福といった「普遍性」を常に掲げていくことが、
大切になると思う。
▽「普遍性」は、人間が人間らしく生きるための土台であるとも言えるだろう。
そうした土台があってこそ、生きる意味は何なのかといった根源的な問いに対する旅が始まる。
▽自己の喜びと他者の喜びを、調和させる力。
苦しみを分かち合い同苦する力。
それが他の動物にはない、人間が人間たるゆえんであると思う。
▽人間は誰もが、自分自身の価値を追求していく存在である。
その一方で、他者の幸せを考えることで、自分の幸せもより深く豊かなものになっていく。
それが可能となる社会の土台をつくる力が、人間にはある。
その意味で、人間にとっての希望は、人間それ自体と言っていいと思う。
未来の希望は、私たち一人一人である。