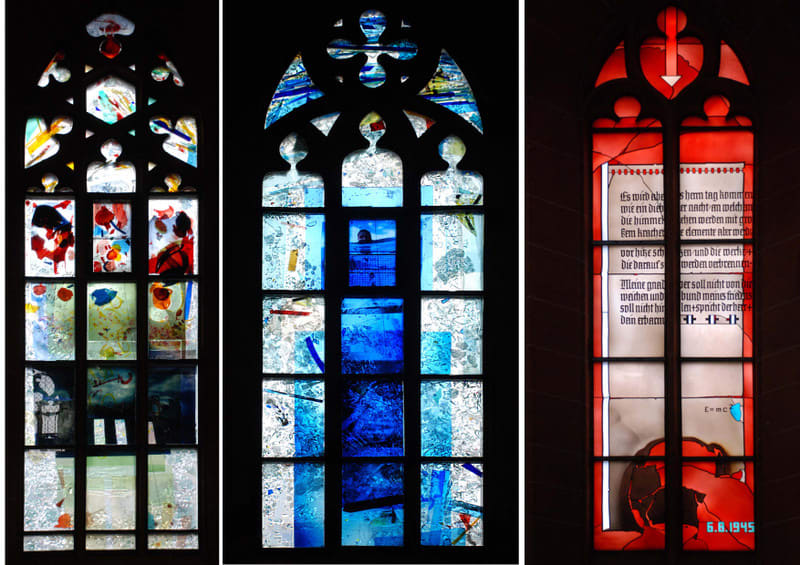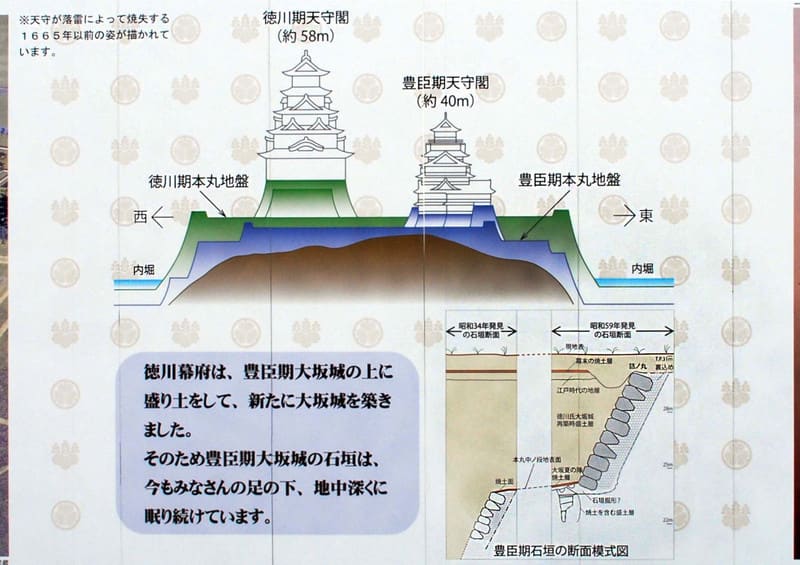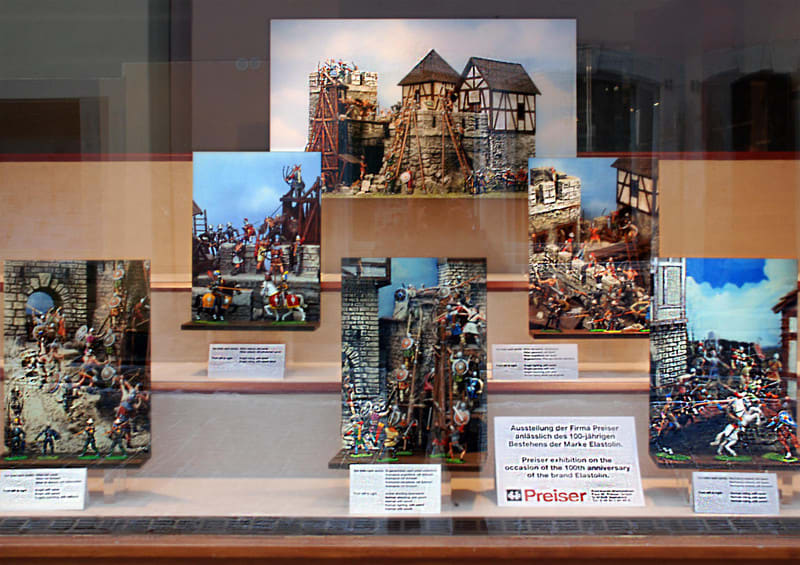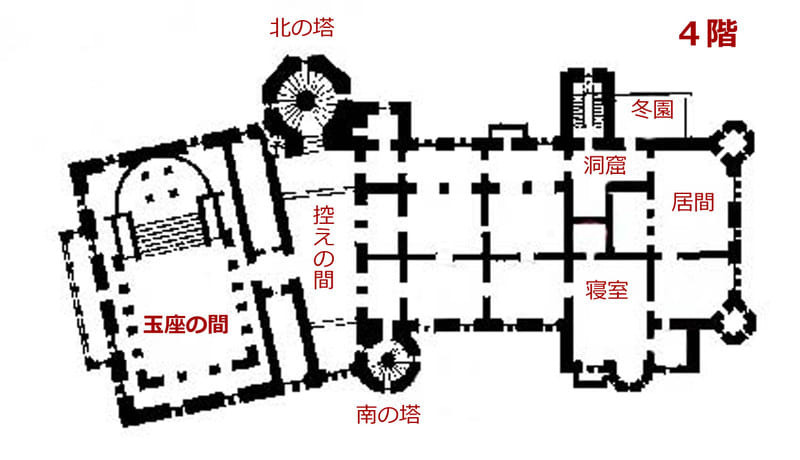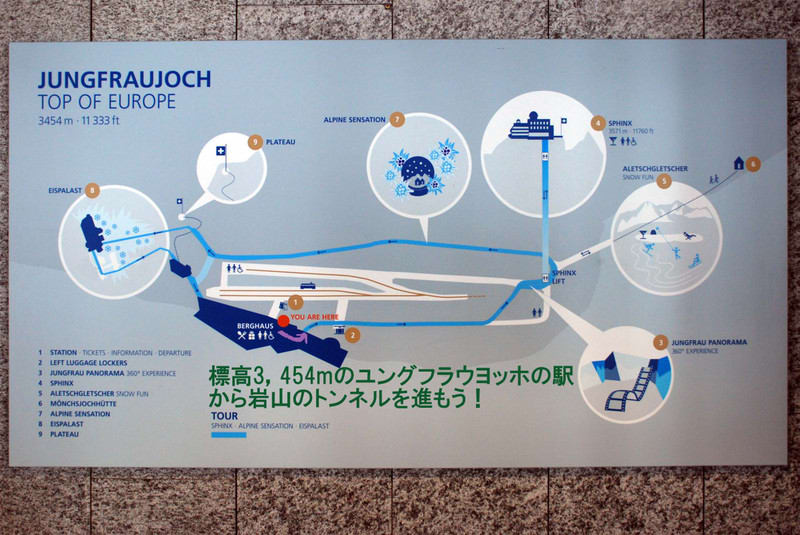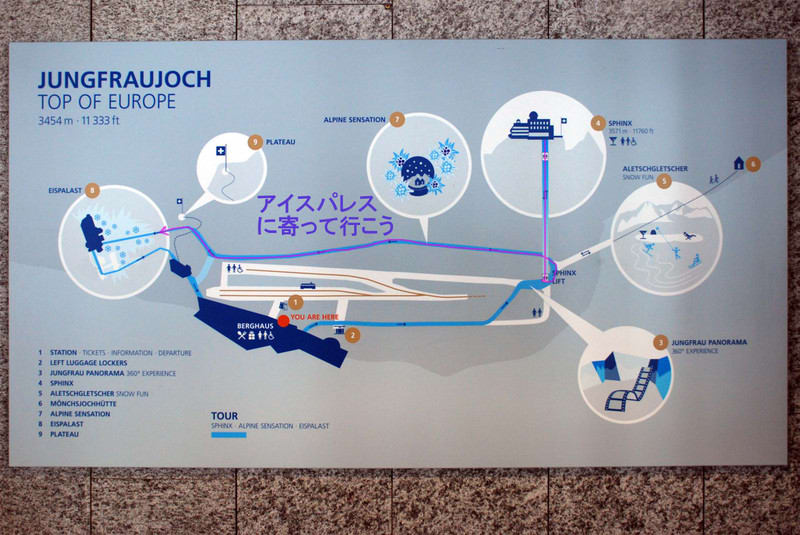高速道路周辺の風景は、・・・わき見運転に興味を持たせないように・・・? こんな風景とトンネルが続く
約60㎞、30分も走ると北陸自動車道と交差する上越ジャンクションに、・・・ここからは西に、日本海に沿って南下する。
日本海を見ながら走れるかな・・・と期待していたが 、トンネル、シェルター、トンネル、トンネルと、この道路も退屈なドライブが続いた。
糸魚川を過ぎ、海岸線に近づいて、多少海が見えたのが 子不知(こしらず)、親不知(おやしらず)地区・・・この付近が、越後と越中を分断していた北陸の箱根峠でしょうか。
地名の由来の一説に、峠越えの難所で子を波にさらわれた悲劇の親子連れがあるそうです・・・ここの人達は郷土の地名をどう思っているのか・・・気になった。
海岸線の断崖絶壁は、国道8号を走れば体感できるのでしょうが、高速道路は海上に張りだす形の高架橋でした。アッという間に通り過ぎてしまう。
今日では、この海岸へ張り出した難所から2~300m先(富山寄り)には、高架の下に駐車場があり、海岸線には親不知海水浴場があります。
1㎞先が親不知IC、ここで一般道に降りてみるのを忘れて、・・・気が付くとまたトンネル。
トンネルが続き、目の前が開けたら・・・富山県、そして黒部川を渡り、上越JCから110km、1時間弱で富山ICで降りる。
国道41号を1㎞くらい走り、右側に海鮮市場があり、市場のショッピングと昼食。
富山駅前付近はかつて散策済みだし、ドラえもんトリムは、隣の高岡市だった・・・
金沢に急ごう・・・再度北陸自動車道で30~40分、金沢森本ICで降り、山側環線(金沢外環状道路)を10分も走り、右折して市内に入り5分、交通整理のお巡りさんが多い。
兼六園下交差点、左折、石川県兼六駐車場に車を入れる。
駐車場の道路反対側に、石川県観光物産館がある
物産館の右横が兼六園交差点、ここを左折した道路に・・・警官が多い、有料観覧席の看板が目立つ。
・・・第63回金沢 百万石まつり 金沢城入城行列 午後2時から・・・
3時少し前だが、行列は城の反対側金沢駅がスタート、先頭がこの地点に来るのは3時半頃かな?
行列の主役はこの人 、加賀藩祖 前田利家
さて、隣の兼六園、庭園を拝見しよう。案内板は左が北、観覧席があったお堀通りを挟んで 金沢城が下側に、兼六園が上に書かれている。
現在地は案内板の中央(上側の兼六園の左端)・・・桂坂口 です
入場券売り場、¥310- 何かうれしい貼り紙が「遠路はるばるご苦労様です。本日は無料開放です。ご自由にお入り下さい」
ありがとうございます。兼六園の横にかわいい桂坂の立札が案内してくれた。
桜の時期に訪れたい桜ヶ岡を抜け眺望台へ、市内が一望できる・・・そして、庭園内を見渡すと、・・・月見橋から霞ヶ池方向
趣のある構成になっている。
ここ兼六園のHP(ホームページ)に
「庭園では六つのすぐれた景観を兼ね備えることはできない。広々とした様子(宏大こうだい)を表そうとすれば、静粛と奥深さ(幽邃ゆうすい)が少なくなってしまう。
人の手が加わったところ(人力じんりょく)には、古びた趣(蒼古そうこ)が乏しい。
また、滝や池など(水泉すいせん)を多くすれば、遠くを眺めることができない」
と中国、宋の時代の書物「洛陽名園記」には六つの景観が共存しているのは湖園だけだと記されている。
・・・「この六勝(ろくしょう)を、兼六園が奥州白河藩主・松平定信によってその名を与えられました」・・・とあります。
この構図の中に 六勝、感じられますね!
大きな池に小島、手前に小さな橋、灯籠があり・・・
徽軫灯籠(ことじとうろう)と名前がついていました。高さは、2.67m
徽軫・・・読めないですね。琴柱(ことじ)に似てるところからついたそうです。
琴柱(ことじ):和琴の場合、胴の上に各弦に「人」の字形の具を立て、弦を支え音の高低を調整するもの。
灯籠の足が二股でこの琴柱に似ていたから・・・和琴では柱を(じ)と読み琴柱(ことじ)と読む。
それで、更に類似の文字を当てたのでしょう・・・
徽も琴の節、弦を押さえる所を示す印、また支える台(ことじ)のこと、軫は琴の弦を巻いて調整する軸木のことを指します。(広辞苑より)
ここ兼六園の中心となる池、霞ヶ池(1837年)広さ5800㎡、池の中の島は、蓬莱島(ほうらいじま)といい、不老長寿をあらわしており、また亀の甲の形をしているので、別名、亀甲島ともいう。(案内板)
先程の 徽軫灯籠(ことじとうろう)の反対側、 内橋亭横からのパノラマです。
右側の大木をアップにしましょう。左下の案内板は、合成です。
「唐崎松(からさきのまつ)13代藩主 前田斉泰(1822~1866)が琵琶湖の松の名所、唐崎から種子を取りよせ育てた」と記されています。
枝ぶりが見事な松で、11月1日から雪吊り作業が始まると、必ずTVで放送されます・・・あの有名な松です。
「蒼古そうこ」・・・時が流れると苔生して、「人力じんりょく」の跡も自然に呑み込まれ・・・いや!
ここは、管理されているからこのような素敵な状態が保たれているのでしょう。
ここは「瓢池ひさごいけ」、池の中程がくびれて、瓢箪(ひょうたん)に似ていることから名づけられた。
池の中には不老長寿の島、神仙島をかたどった大小二つの島がある。
右の六重に重ねた塔が「海石塔」、加藤清正が朝鮮から持ち帰り」秀吉に献上し、秀吉から贈られた石塔と言われています。
中央奥の滝は、翠滝(みどりたき)、霞ヶ池から流れ出てくるので水量も豊富、高さ6.6m、幅1.6m
紅葉時に訪れるのもお勧めで、別名「紅葉滝」とも・・・。
・・・曇天の空に、パレードのにぎやかな音が聞こえてきた。時刻は3時半、・・・最後に噴水を・・・
この噴水も霞ヶ池が水源で、水柱の最高点が霞ヶ池の水面と同じ・・・高低差を利用した自然の水圧で噴出しています。日本で最古の噴水と言われています。
・・・蓮池門通りから、にぎやかな下のお堀通りを
ブラスバンド隊やバトン隊のパレードが進んできました。
オッと、・・・危ない。
大丈夫、危ないシーンはカット。
ミス百万石のパレードに続いて、獅子舞行列(市内5団体)
子供、赤ちゃんが泣き叫び、お母さんが大喜び・・・
加賀とび行列、木遣隊
尾山神社御鳳輦(ごほうれん)・・・(聞きなれない言葉で)・・・つまり、鳳凰が乗っている神輿(みこし)で、利家公の御分霊の渡御(とぎょ)?・・・(神輿が進むこと)、目の前を通り過ぎました。
次々に行列が進み、兼六園下の交差点近くでは、5回目の演技が終了すると兼六園側に大きくUターンして、
写真左端の公園に向かう坂道を上り、写真中央右上の石川橋から、金沢城公園(三の丸広場)のステージへと進みます。
利家公が武者を従え入城し勝ち鬨(どき)をあげる入城祝祭が午後6時まで続きます。
ホテルを6時チェックインにしているので、この辺で散策に行こう。