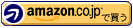6月7日1時35分配信 毎日新聞
訪問介護最大手の「コムスン」に対し、厚生労働省は新規指定禁止など厳しい措置を取った。これに対して同社は、関連会社に全事業を譲渡するという“ウルトラC”で対抗してきた。「量から質へ」とサービス向上のための業界変革を目指す同省と、法令を逆手に介護事業からの撤退を避けようとする同社。同社の訪問介護を受けている6万人はどうなるのか。
◇各自治体、早速対応に乗り出す なかには戸惑う声も
今後の対応について、同省は「一義的にはコムスンが考え計画すべきだ。行政の働きかけでサービスを受けられるようにする」と楽観的だ。一方、同省から「利用者に対するサービス確保に万全を期するよう」と指示された自治体。東京都担当者は「(今回の事態は)自業自得。コムスンが自己責任でやるべきこと」と指摘する。ところが、同社の事業譲渡が明らかになり、衣替えした“新生コムスン”でのサービス継続の可能性が出てきたため、6万人の行方はより不透明になった。
業務ができなくなり始めるのは08年4月。厚労省は他の事業者への円滑な利用移行ができるよう支援を強める。対策本部を設置し、自治体にも対応窓口設置を指示。事業所が廃業届を出す際に、利用者への説明と他事業者への移行計画を作成させる。同社に対しては、7月末までに計画の作成・報告を求めている。
各自治体は早速対応に乗り出したが、なかには戸惑う声も。群馬県は「コムスンには他の事業所などで対応するよう伝えた。県内には多くの訪問介護事業者があるので、介護難民が発生するようなことはない」と説明。岡山県は「県境地域などで支障が出る可能がある」と懸念する。東京都は「突然のことで驚いた。利用者や同業者への影響は極めて大きい」とし、近く、指定切れまでサービスの質を落とさないよう同社に指導する。
しかし、介護の現場での人手不足が指摘される中、最大手が抜けてスムーズな移行ができるか不安視する声もある。栃木県高根沢町で訪問介護などをしているNPO法人「グループたすけあいエプロン」の菅野安子理事長は「利用者やヘルパーさんを引き受けなければならないケースが出てくるかもしれない。コムスンには利用者を守るためにも、なんとか適正な運営をして事業を続けてほしい」と話す。【東海林智、亀田早苗】
| Trackback ( 0 )
|