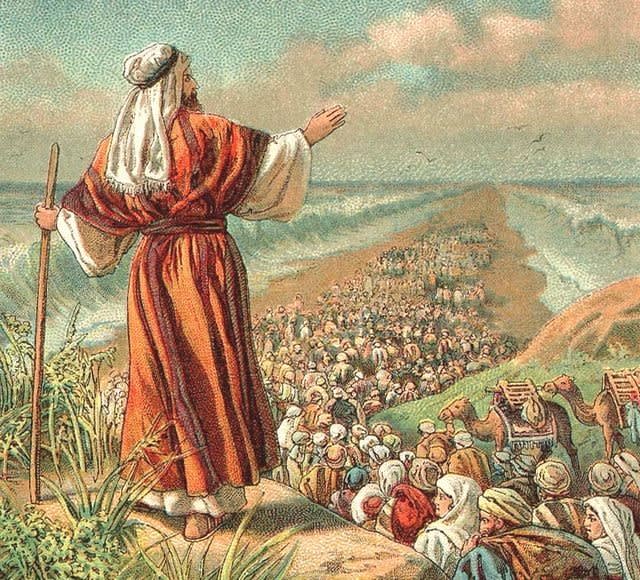🌸『東方見聞録』15(世の中の仕組みを俯瞰する)
☆日本人を「人食い人種」としてレポートしている
*西洋人の偏った日本人観がうかがえる
☆『東方見聞録』は、”世界の記述”の「不都合な真実」である
*西洋人の偏った日本人観がうかがえる
☆『東方見聞録』は、”世界の記述”の「不都合な真実」である
☆著者、マルコ・ポーロ
⛳『東方見聞録』著者マルコポーロのプロフィール
☆「ジパング島は黄金の国」と描いたことで有名な旅行記
⛳『東方見聞録』著者マルコポーロのプロフィール
☆「ジパング島は黄金の国」と描いたことで有名な旅行記
☆「世界の記述」と呼ばれる「東方見聞録」
☆欧州諸国にとり、当時アジア未開の地であった
*アジアが紹介され、人々の探求心を大いにくすぐった
☆ヴェネツィアの商人の子として生まれたマルコ・ポーロ
☆ヴェネツィアの商人の子として生まれたマルコ・ポーロ
☆家族に従い長い旅に出て、中央アジアを経て北京に到着する
☆中国はモンゴル王朝「元」の支配下にあった
☆中国はモンゴル王朝「元」の支配下にあった
☆マルコ・ポーロは約17年皇帝フビライに仕える
☆元の使節で、ビルマ、スリランカ、ベトナムなどの国を訪れた
☆ヴェネツィア帰国後、著述家としたしくなる
*アシアで得た見聞を口述した内容が『東方見聞録』
*多分に誇張も含まれていると考えらる
*多分に誇張も含まれていると考えらる
⛳『東方見聞録』概要
☆商人のマルコ・ポーロは、金の国日本を何故訪れなかった理由
*日本では、金が大量に採掘されているとも記述した
*建物の屋根全体が金で覆われているとも記述した
☆その理由が「東方見聞録」に記述されている
*日本では誘拐ビジネスが横行している
*日本人は「人食い人種」である
☆元王朝は、日本に2度「元寇」を強行したが失敗に終わった
☆元王朝は、日本に2度「元寇」を強行したが失敗に終わった
*巨大な元軍を「神風」で追い返した日本人
*元の人々の間でも、日本人の不可思議さが語り継がれていた
*西洋人の、マルコ・ポーロには一層奇異なものに映った
*西洋人の、マルコ・ポーロには一層奇異なものに映った
☆「東方見聞録」での諸外国の記述内容
*イスラム社会や元社会に対して偏見な内容は少ない
*日本に対しては、偏った日本人観で記述している
⛳『東方見聞録』に記載されている日本人への偏見
☆現在の日本人の『東方見聞録』の認識
*日本を西欧に紹介した書との一側面しか知らない
☆『東方見聞録』日本が記述された内容
*日本人に不都合で不愉快な記述が削除されている
*マルコ・ポーロが紹介した日本像
(ロシア人・イギリス人など正確に知っている)
☆「東方見聞録」は、西洋人が日本人に対して抱いてきた偏見記述内容
☆「東方見聞録」は、西洋人が日本人に対して抱いてきた偏見記述内容
*それを知るうえでも必読の書である
☆人間が、未知のものにどのように向き合うのかも参考になる
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』

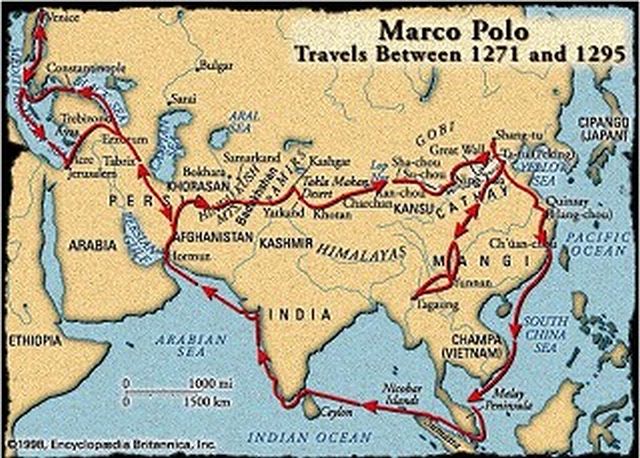
『東方見聞録』15(世の中の仕組みを俯瞰する)
(ネットより画像引用)
















 大坂冬の陣を伝える屏風が復元された
大坂冬の陣を伝える屏風が復元された 復元された大坂冬の陣の屏風
復元された大坂冬の陣の屏風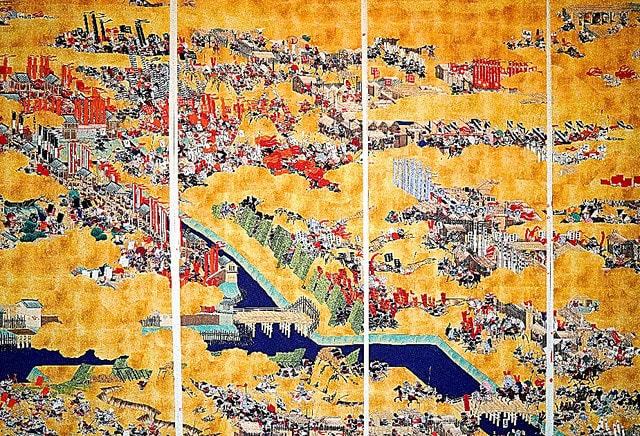



















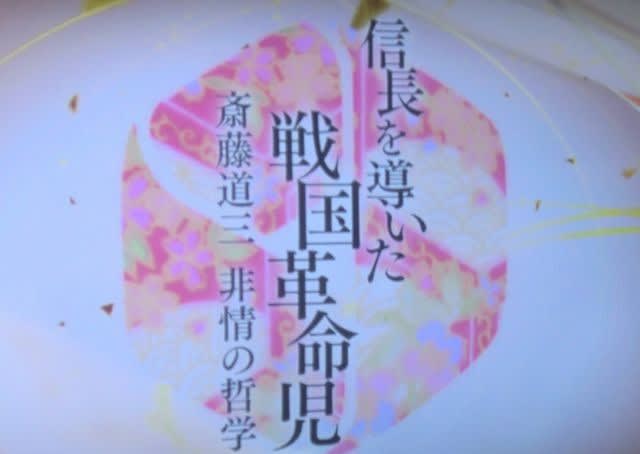














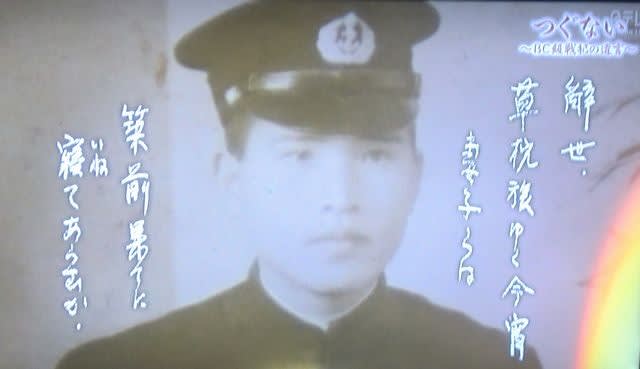

















 世界史のウソと真実の名作3
世界史のウソと真実の名作3