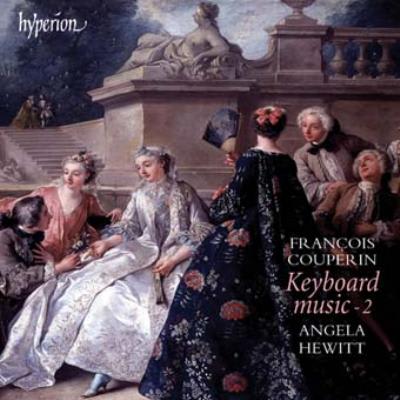(2008.05.04 井の頭公園)
ふと思い立って配偶者を誘って吉祥寺のジャズライブハウス・「サムタイム」に
やってきました。
休日の午後のんびりとビールでも飲みながらリーズナブルなチャージでジャズライブというのは
悪くない休日の過ごし方だと思いませんか?
ジャズライブは「小金井Unit」のとても暖かさの感じられ、それでいてビシッと
締まった演奏でしたが、特にハービー・ハンコック作の「ジ・エッセンス」という曲が最高でした。
洒脱なピアノのお姉さまと芸達者なヴォーカルのナンシーさんがピタリと息が合って、”What's your number ? ”と
ハモるところなど、そのかっこよさに思わずゾクゾクとしましたね。
それから冒頭に演奏されたウェイン・ショーター作の「アウンサン・スーチー」と
いう曲も良かったなあ・・。どちらも私が初めて聴く曲でした。
「サムタイム」の2ステージを観た後でもまだ昼間の名残が残っていました。
井の頭公園は新緑の木々に夕方の陽光がふりそそぎ、長い影を落としています。
さっき聴いたばかりのジャズのせいもあって、私はたちどころにケニー・ドリュー
の「夕暮れの公園」という曲を連想しました。
昼でもない、夜でもない、あと数10分で暗くなる、その寸前の公園です。
一瞬、すべての時間が停まってしまったかのような、安らぎに満ちた時間でした。
落日は池の水面に反射しキラキラと光り、若葉は落ちようとする陽光を受けて
美しいシルエットを演出し、ほんの10分ほど全てが燃え上がるように輝やき
すぐに夜の闇がやって来ました。
なにか憂いのある、メランコリックな、郷愁を誘われる時間でした。
 | パリ北駅着、印象ケニー・ドリュー・トリオエム アンド アイ カンパニーこのアイテムの詳細を見る |