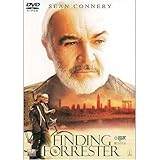渋谷文化村のル・シネマで、念願だった映画「フラメンコ・フラメンコ」を観ました。
一つ一つの画面と映像が、そのまま切り取って永久に残したいくらいに美しい。
もちろん、フラメンコというスペイン独特のダンスと、それを形作るギター、歌、手拍子などの総合されたものを
映画館で鑑賞するので、私の眼と耳に受けたインパクトは強烈なものがあります。
何という凄い映画でしょう。
この映画の監督は、私が20年位前にこの同じル・シネマで観て、感動してボロ泣きしてしまったあのフラメンコの
映画「カルメン」の、カルロス・サウラです。
(ギターのパコ・デ・ルシアはあの「カルメン」の時も、この映画でも、同じく熱演しています)。
フラメンコの持つ哀愁と情念が、カルロス・サウラの心を反映するように、ひしひしとスクリーンから私に
伝わってきました。
映画の中では21曲のフラメンコが演奏されますが、私は個人的に特に心に残ったのは、
・エストレージャ・モレンテの歌う「タンゴス」
・ファルキートの踊るサパテアード「イリュージョンの雨」
・パコ・デ・ルシアがギターをかきならすブレリア・ポル・ソレア「アントニア」
の3曲でしょうかなあ。
それにしても・・・。
もし、人生に意味があり、「美しいものを存分に堪能すること」がそのひとつだとしたら、この映画を
観て感動することで、少しは有意義な時間を過ごした、ということになりましょう。
この映画は3月中旬まではル・シネマで上映されるそうです(当初の2月末までが延長)。
(私がやったように)チケットをオンラインで予約し、開演の直前に現地で受け取ることも出来ます。
仕事も約束もデートも、全てを忘れてでも、今すぐこの映画を観にル・シネマに急行されることを強くお奨めします。