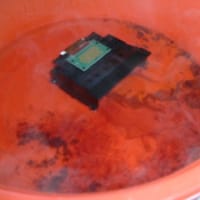サクっと読める本でした
社会全体が「保守化」「右傾化」しているというのは、よく言われること。
その傾向を象徴するのが、犯罪への厳罰化。
特に槍玉に挙げられるのが、少年と精神障害者の犯罪(次点で交通事故か?)。
本書の芹沢一也「ホラーハウス社会」では、この潮流の変化を、過去と現在の状況を活用して語っています。
少年犯罪については、犯罪に対する社会のスタンスを、著者はこのように定義しています。
「決してその時代に多発しているものではない」のは、テレビ以外のメディアでは、けっこう指摘されていることなんですけどね。
著者は、他にもこんな定義をしております。
この前提をもとに、「永山則夫事件」と「酒鬼薔薇事件」を比較します。
「永山則夫事件」
永山則夫については、こちらを、どうぞ。
「確かに、環境によって人は変われるんだ! その環境を提示できない社会こそが、本当の問題だ!」という「作品化」には、うってつけの事件ですな。
「酒鬼薔薇事件」
酒鬼薔薇事件については、こちらを、どうぞ。
著者は、この社会の転換に、メディアが事件の主役を加害者から被害者に移したことを契機の一つにしています(この転換の原因は、少年法の不備があるわけですが、その引用はメンドイので割愛)。
「まぁなるほどなぁ」といった感想を持ちました。
僕個人としての意見としては、特に独創的な意見でもないのですが、やっぱり「死」が社会から遠のいてしまっているのかなぁ…………と思います。
半世紀前までの社会でありますと、日本という社会には、戦争は数十年にいっぺん起こるものだし、不治の病などそこらへんに散見されていたし、権力者の理不尽な横暴は当たり前だし、絶対的な貧困というものは珍しいものではなく、……………つまり、「悲劇」が現実に不即不離で存在していたんですよね。
が、終戦から50年以上経ってしまった現在。
厳密には、「戦争」も「不治の病」も「権力者の横暴」も「貧困」も解決はされていない。
でも、それが現実に不即不離で存在という大げさなものでなくなっているのも事実。
ほとんどのものが、現実の「悲劇」ではなく、物語の「悲劇」と化してしまっている。
そういう社会において、「死」というものが、過大視されてしまう傾向にあるのかなぁ~と漠然と感じます。
結果、神聖化された「死」が大手を振るい、絶対的な論拠として鎮座しているような気がします。
全体としては、「自分の都合の良い事例ばっかり意図的に集めてない?」と言いたくなる箇所もないわけではないですが(そもそも「論」や「主張」など、「自分の都合の良い事例」を集めなくては成り立たないものだろうけどね)、まずまず納得できるものとなっていました。
社会の保守傾向と少年犯罪に興味のある方であれば、読んで損はないと思います。
社会全体が「保守化」「右傾化」しているというのは、よく言われること。
その傾向を象徴するのが、犯罪への厳罰化。
特に槍玉に挙げられるのが、少年と精神障害者の犯罪(次点で交通事故か?)。
本書の芹沢一也「ホラーハウス社会」では、この潮流の変化を、過去と現在の状況を活用して語っています。
少年犯罪については、犯罪に対する社会のスタンスを、著者はこのように定義しています。
| そもそもメディアを騒がすような事件は、実はきわめて特殊な出来事である。決してその時代に多発しているものではない。だが、そうした犯罪が広く関心を呼ぶならば、そのとき社会はそこに自らの姿を映し出そうとしているのだ。それは、このような犯罪を生み出した社会とは、一体どのような社会なのかという自問である。 こうした意味において、時代に選ばれた犯罪は鏡のごときものとなる。とはいえ、この鏡はあくまで、社会が自分の好みに合わせてつくりだされる。必要なのは、自分がそう映ってほしいと願う姿を、はっきりと映し出してくれる鏡なのだ。 芹沢一也「ホラーハウス社会 ―法を犯した「少年」と「異常者」たち」76頁 講談社プラスアルファ新書 |
著者は、他にもこんな定義をしております。
| 世に騒がれる犯罪と社会との間には、こうしたひとつの共犯関係がある。 犯罪の真実があって、それを社会が受け入れるわけではない。社会が事件を素材にして、自画像のような犯罪作品をつくりあげ、そこに自らの姿を「再確認」する。共犯関係とはこうした意味だ。 そして、犯罪に映し出された姿をみて、ときに社会は己を反省する。自らを変えようとすることもある。あたかも、鏡に向かって化粧をするかのようにだ。 芹沢一也「ホラーハウス社会 ―法を犯した「少年」と「異常者」たち」77頁 講談社プラスアルファ新書 |
この前提をもとに、「永山則夫事件」と「酒鬼薔薇事件」を比較します。
「永山則夫事件」
| たとえば、永山則夫の事件。 それは客観的にみれば、利己的で何ら同情の余地のない犯罪だったが、当時の論者たちはこの凶悪犯罪を語るなかで、社会の矛盾や悲惨な貧困を敵に仕立てあげ、その上うな矛盾の噴出や貧困の犠牲として永山事件をつくりあげた。 芹沢一也「ホラーハウス社会 ―法を犯した「少年」と「異常者」たち」75頁 講談社プラスアルファ新書 |
「確かに、環境によって人は変われるんだ! その環境を提示できない社会こそが、本当の問題だ!」という「作品化」には、うってつけの事件ですな。
「酒鬼薔薇事件」
| 費やされた膨大な言葉にもかかわらず、確たる手応えは得られないでいたなかで、少年たちの犯罪は不可解なものだとする感覚が広まっていく。そこにはそもそも、人が理解できるような動機などないのではないか、とする疑問がもちあがる。 そして、「動機なき犯罪」という言葉がつぶやかれはじめた。動機なき犯罪、それは作品化の不可能な犯罪であり、文字通り理解不能な犯罪のことだ。 そのような犯罪者として、少年たちは精神医学の手に委ねられていった。もはや理解できないのならば、それは「異常」でしかないだろうというわけだ。そして、「性的サディズム」や「アスペルガー症候群」「行為障害」などといった異常性のレッテルを貼られ、社会から精神医学の世界に追いやられたのだ。 現在、少年事件について声を大にして語るのは精神科医だちとなっていることも、そんな理解への諦めを表している。そこで語られるのは、もはや悲惨な境遇といったものではなく、少年がいかに異常かということだ。 こうして、あくなき理解への欲望が、皮肉なことに、異常だとして少年の拒絶へと行き着いた。酒鬼薔薇事件以降、一連の異様な少年犯罪によって、社会は作品化への欲望を掻き立てられながらも、結局は少年をまったく不可解なものとして、不気味な存在に仕立て上げていったのである。 芹沢一也「ホラーハウス社会 ―法を犯した「少年」と「異常者」たち」83頁 講談社プラスアルファ新書 |
著者は、この社会の転換に、メディアが事件の主役を加害者から被害者に移したことを契機の一つにしています(この転換の原因は、少年法の不備があるわけですが、その引用はメンドイので割愛)。
| この記事は、妻を失った男性の諦めと怒りで締められている。 「どうしてこうなったか知っても女房の命は戻ってこない。聞いても気が治まるどころか、よけい治まらないかもしれない。それでも残された家族は、カヤの外に置かれることが一番腹立だしいんです」 かつてとは打って変わって、これらの文章における主人公は、理不尽な経験を背負わされた被害者である。少年法の壁によって何も知ることができない、蚊帳の外におかれた被害者のやり場のない怒りと諦めが、否応なしに涜むものの共感を誘う。 そのような被害者の思いを背景にして、少年による無思慮な犯罪の凶悪性がくっきりと浮かび上がる。少年の内面に感情移入することは決してできない。秘密のベールに閉ざされた少年については、読者もまた何も知ることはできないのだ。それゆえ、ただ残酷で不条理な犯行のみが印象づけられる結果となる。 ここで読者は、事件の真相に近づけない被害者の困惑を共有するしか道はない。あるいは、そうした不条理に対する怒りと諦めをともにするほかはない。このような語られ方にあって、読者の感情が移入されるのは、かつての加害者とは違って被害者のほうなのである。 こうした語りとともに、入びとから少年への共感が消えていったのだ。そして、少年は無力で受動的な存在ではなくなり、恐るべき加害者の顔をもって立ち現れるようになった。 かつて、この時期ほど、少年犯罪に人びとの注目が集まったことはなかった。 そうしたなか、論者たちの作品化、被害者たちの異議申し立て、そしてメディアでの語り方、すべての流れが少年犯罪への想像力を枯渇させながら、少年を共感すべき主人公の座から引き摺り下ろしていったのだ。 芹沢一也「ホラーハウス社会 ―法を犯した「少年」と「異常者」たち」90~91頁 講談社プラスアルファ新書 |
「まぁなるほどなぁ」といった感想を持ちました。
僕個人としての意見としては、特に独創的な意見でもないのですが、やっぱり「死」が社会から遠のいてしまっているのかなぁ…………と思います。
半世紀前までの社会でありますと、日本という社会には、戦争は数十年にいっぺん起こるものだし、不治の病などそこらへんに散見されていたし、権力者の理不尽な横暴は当たり前だし、絶対的な貧困というものは珍しいものではなく、……………つまり、「悲劇」が現実に不即不離で存在していたんですよね。
が、終戦から50年以上経ってしまった現在。
厳密には、「戦争」も「不治の病」も「権力者の横暴」も「貧困」も解決はされていない。
でも、それが現実に不即不離で存在という大げさなものでなくなっているのも事実。
ほとんどのものが、現実の「悲劇」ではなく、物語の「悲劇」と化してしまっている。
そういう社会において、「死」というものが、過大視されてしまう傾向にあるのかなぁ~と漠然と感じます。
結果、神聖化された「死」が大手を振るい、絶対的な論拠として鎮座しているような気がします。
全体としては、「自分の都合の良い事例ばっかり意図的に集めてない?」と言いたくなる箇所もないわけではないですが(そもそも「論」や「主張」など、「自分の都合の良い事例」を集めなくては成り立たないものだろうけどね)、まずまず納得できるものとなっていました。
社会の保守傾向と少年犯罪に興味のある方であれば、読んで損はないと思います。
 | ホラーハウス社会―法を犯した「少年」と「異常者」たち講談社このアイテムの詳細を見る |