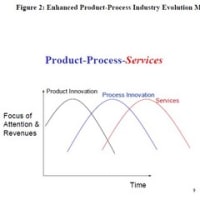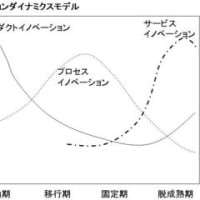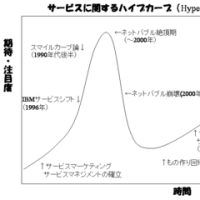中国に「知行合一」という言葉があるが,「実行の伴わない知識は真の知識ではない」という考え方は,「知識経営」や「ナレッジマネジメント」の文脈では共通認識といっても良いと思う.
TV,書籍,セミナー,インターネット等で,様々な情報が容易に入手可能な時代になり,「知っている」ことは確実に多くなっている.しかしながら,「知っていること」が実行に結びつかないケースが多い.逆に,情報の少ない時代のほうが「まずはやってみよう」ということで,実行と結びつくことが多かったかもしれない.これは一種のパラドクスである.
この知識と実行のギャップを取り上げた本が「実行力不全 なぜ知識を行動に活かせないのか」である.
本書では,知識と実行のギャップが生まれる組織的な問題を,(1)計画偏重,(2)前例主義,(3)事なかれ主義,(4)評価の問題,(5)内部競争,の各視点で分析し,これらを解消して知識を実行に結びつける8つのガイドラインを示している.
知識移転,知識継承を推進する場合も,単に知識を伝えるだけでは実行が伴わず失敗する可能性が大きい.上記の「組織的な問題」をステークホルダー間で共通認識した上で,知識移転,知識継承のやり方を考えることが重要であろう.
TV,書籍,セミナー,インターネット等で,様々な情報が容易に入手可能な時代になり,「知っている」ことは確実に多くなっている.しかしながら,「知っていること」が実行に結びつかないケースが多い.逆に,情報の少ない時代のほうが「まずはやってみよう」ということで,実行と結びつくことが多かったかもしれない.これは一種のパラドクスである.
この知識と実行のギャップを取り上げた本が「実行力不全 なぜ知識を行動に活かせないのか」である.
本書では,知識と実行のギャップが生まれる組織的な問題を,(1)計画偏重,(2)前例主義,(3)事なかれ主義,(4)評価の問題,(5)内部競争,の各視点で分析し,これらを解消して知識を実行に結びつける8つのガイドラインを示している.
知識移転,知識継承を推進する場合も,単に知識を伝えるだけでは実行が伴わず失敗する可能性が大きい.上記の「組織的な問題」をステークホルダー間で共通認識した上で,知識移転,知識継承のやり方を考えることが重要であろう.