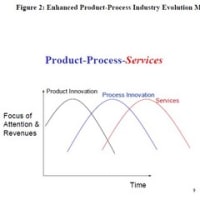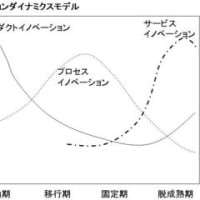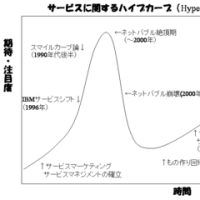MOTのコンテキストで,アナリシス(分析)とシンセシス(統合)の対比はいろいろ論じられてきた.例えば,MBAはアナリシスに主眼に置いているのに対して,MOTはシンセシスを重視しているという言い方もされてきた.ここでは,「分析的」と「統合的」とは別に提言されている3つ目のアプローチ「解釈的」について考察したい.
MITのLester教授は,著書「Innovation--The Missing Dimension」において,イノベーションのコンテキストで,アナリシス(分析)とインタープリテーション(解釈)という対比を行っている.ここで,分析的プロセス(analytical process)が,問題構造を明確にし,要素に分解し,個々の分析結果を還元して,問題を解決することであるのに対し,解釈的プロセス(interpretive process)は,インタラクティブなコミュニケーションを通じてお互いに価値を発見することであるとしている.
これは,IBMのサービスの定義である「顧客と企業が一緒に価値を創造するプロセス」と同じ意味であると思われる.Lester教授の主張は,イノベーションのためには分析的プロセスに加えて解釈的プロセスが重要であるが,解釈的プロセスに関しては十分学問的な蓄積がないので,ぜひ重要性を認識しようということであり,サービスサイエンスの提唱とも重なるとことが大きい.
ここで,統合的プロセスと解釈的プロセスは本質的に何が異なるのかという点は必ずしも明確ではない.実体は同じという見方もあるかもしれない.確かに,統合的を分析的との対比で持ちいる場合は解釈的の意味も含んでいたと思われる.しかし,建築家や芸術家のように1人の頭の中で作品をシンセシス(統合,形成)することと,関係者(顧客と企業)がお互いに気づきあいながら価値を生み出すインタープリテーション(解釈)とは分けて考えた方が良い場合もあるだろう.特に,サービスイノベーションの考察においては解釈的なプロセスが重要であるのは定義から明らかであろう.
MITのLester教授は,著書「Innovation--The Missing Dimension」において,イノベーションのコンテキストで,アナリシス(分析)とインタープリテーション(解釈)という対比を行っている.ここで,分析的プロセス(analytical process)が,問題構造を明確にし,要素に分解し,個々の分析結果を還元して,問題を解決することであるのに対し,解釈的プロセス(interpretive process)は,インタラクティブなコミュニケーションを通じてお互いに価値を発見することであるとしている.
これは,IBMのサービスの定義である「顧客と企業が一緒に価値を創造するプロセス」と同じ意味であると思われる.Lester教授の主張は,イノベーションのためには分析的プロセスに加えて解釈的プロセスが重要であるが,解釈的プロセスに関しては十分学問的な蓄積がないので,ぜひ重要性を認識しようということであり,サービスサイエンスの提唱とも重なるとことが大きい.
ここで,統合的プロセスと解釈的プロセスは本質的に何が異なるのかという点は必ずしも明確ではない.実体は同じという見方もあるかもしれない.確かに,統合的を分析的との対比で持ちいる場合は解釈的の意味も含んでいたと思われる.しかし,建築家や芸術家のように1人の頭の中で作品をシンセシス(統合,形成)することと,関係者(顧客と企業)がお互いに気づきあいながら価値を生み出すインタープリテーション(解釈)とは分けて考えた方が良い場合もあるだろう.特に,サービスイノベーションの考察においては解釈的なプロセスが重要であるのは定義から明らかであろう.