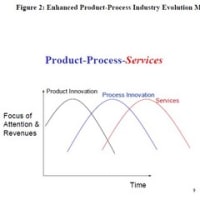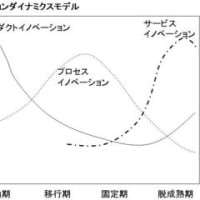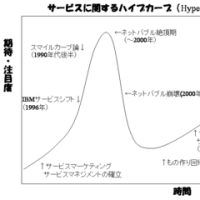九州大学の吉村達彦先生の解説記事「品質問題の未然防止手法GD3」に品質問題と知識創造に関する興味深い指摘がある。
最近の品質問題が、「いくつかの原因が複合して起きており、それに気がつかなかったために問題が起きたというものが多い」とし、「問題に気付く能力(創造性)を上げることが、品質問題の未然防止に役立つ」としている。
これは、従来の品質問題が、分析的・解析的(=アナリシス)なアプローチが主体だったのに対し、創造的・形成的(=シンセシス)なアプローチも重要であるとの指摘として考えると興味深い。
筆者も、「マネジメントの知識継承」とは、結局のところ過去のマネジメント事例を学ぶことで、将来のマネジメントの問題を創造的に発見する能力を育成することであると考えている。
具体的な創造的・形成的(=アナリシス)なアプローチとして、GD3(Good Design, Good Discussion, Good Design Review)およびFMEAをgood discussion向けに改良し、それをベースに創造的問題発見を支援する手法であるDRBFM(Design Review Based Failure Mode)やFMEAをgood design review向けに改良し、それをベースに実験の結果から創造的問題発見を支援する手法であるDRBTR(Design Review Based on Test Result)を提案している。
実際に、DRBFMはトヨタおよびトヨタの関係会社で幅広く使われているらしい。
最近の品質問題が、「いくつかの原因が複合して起きており、それに気がつかなかったために問題が起きたというものが多い」とし、「問題に気付く能力(創造性)を上げることが、品質問題の未然防止に役立つ」としている。
これは、従来の品質問題が、分析的・解析的(=アナリシス)なアプローチが主体だったのに対し、創造的・形成的(=シンセシス)なアプローチも重要であるとの指摘として考えると興味深い。
筆者も、「マネジメントの知識継承」とは、結局のところ過去のマネジメント事例を学ぶことで、将来のマネジメントの問題を創造的に発見する能力を育成することであると考えている。
具体的な創造的・形成的(=アナリシス)なアプローチとして、GD3(Good Design, Good Discussion, Good Design Review)およびFMEAをgood discussion向けに改良し、それをベースに創造的問題発見を支援する手法であるDRBFM(Design Review Based Failure Mode)やFMEAをgood design review向けに改良し、それをベースに実験の結果から創造的問題発見を支援する手法であるDRBTR(Design Review Based on Test Result)を提案している。
実際に、DRBFMはトヨタおよびトヨタの関係会社で幅広く使われているらしい。